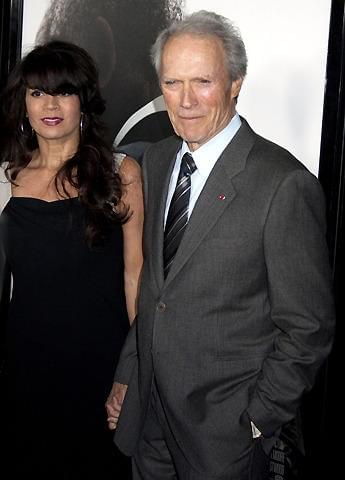インビクタス 負けざる者たち : 特集
【特別対談】芝山幹郎×サトウムツオ その4

Photo:Everett Collection/アフロ
■「許されざる者」で巨匠に
ムツオ:この間「キネマ旬報」のベストテンが発表されましたけど、1位が「グラン・トリノ」、3位が「チェンジリング」でしたね。そういう意味で、隔世の感があるというか、僕なんか映画専門のライターになったのは遅いですけど、「ホワイトハンター ブラックハート」から書いていますが、あの当時はそこまで巨匠じゃなかった。一生懸命、イーストウッド映画はすごいぞと書いていた感じだったですから。

芝山:やっぱり「許されざる者」から、別の次元に入っていった感じがありますよね。堂々たる作家という印象が表に出てきたんです。振り返ってみると、「ブロンコ・ビリー」にしても「センチメンタル・アドベンチャー」にしても素晴らしい映画なんですけど、圧倒的な大きさを感じさせるようになったのは、「許されざる者」からですよね。それまでも面白い作家だったんだけれども、あれから、グレートという言葉がつくような作家になりましたね。あれは92年くらいでしょ。それから約20年、堂々たる歩みですよね。
ムツオ:僕は2000年のベネチア映画祭でイーストウッドのシンポジウムを聞いたんですけど、それは「カイエ・デュ・シネマ」主催だったんですが、ヨーロッパでは大先生というすごい持ち上げ方だったんですね。
芝山:カイエ・デュ・シネマは評価がけっこう早かったですからね。
ムツオ:その時の新作は「スペース・カウボーイ」ですよ。それでも映画評論家たちはああでもないこうでもないと熱狂しているんです。
芝山:お茶目で、大変分かりやすい映画だったと思うけど、それこそ小林信彦さんがよく言うように、日本人のほうが昔から落語などに親しんでいるから、娯楽映画に関しては感度が鋭いんです。フランス人の場合、娯楽に対してちょっとつんのめりがあってね。たとえば、ジェリー・ルイスをあんなに面白がるのは過大評価でしょう。イーストウッドの娯楽映画に関しては、日本人はけっこう早い時期から面白さに気づいていたという気がしますね。「ブラッド・ワーク」とか「目撃」なんかも、アメリカでは批評家の点が辛かったけど、日本人はけっこう楽しんでましたよね。「目撃」なんて可笑しかったよね。煙のように消える怪盗なんて(笑)。「ブラッド・ワーク」では上半身裸になってたし。
ムツオ:ああいうB級のノリは、10年くらい前まではあったんですよね。
芝山:だけど、「グラン・トリノ」でもそういうテイストが少しあった。「グラン・トリノ」のあの軽さというか、さくっと撮った感じ、あれは彼がいまだにB級テイストを持ち続けていることの証明じゃないかなと思うんですけど。
■導入部のうまさ
ムツオ:今回の映画もいつも通り、本当に導入部がいい。いつの間にか引き込まれてましたね。かつてマーティン・スコセッシ監督が、地図を使って30秒足らずで一気にパリからアフリカのカサブランカへと話を持っていく「カサブランカ」のオープニングを絶賛してましたが、あれをやったのがワーナーの編集マン時代のドン・シーゲルで、いわゆるB級のプログラムピクチャー的な手さばきでパッパッと状況を分からせてしまう技術は弟子のイーストウッドにも伝わっていると思いますね。

芝山:イーストウッドの場合は、最初のエスタブリッシュメント・ショットが実に上手いですよね。今回の「インビクタス」でもそうだったけど、どこに話の中心があるのかを一発で見せてしまう。最初に、整備されたグラウンドでラグビーの練習をしているところが出てきたあと、道を一本隔てたところの空き地で黒人の子供たちがサッカーに興じているというところが映し出される。そこをワンシーンで見せてしまうんですよね。
ムツオ:左パンひとつだけですよね。
芝山:映像を切っていないんです。そして、間の道を通る車が、ちゃんと1990年頃のちょっとボロい車なんですね。そうすると、南アの経済状況や政治状況もわかるんです。マンデラが牢屋から解放されたときの南アの状況を、無駄なくワンショットで見せていますよね。
ムツオ:やっぱりベストショットを選ぶ嗅覚というのが凄いなと思うんですよね。例えば、日本映画のセットビジットなんて何度も行ってますけど、まあ、ビジコンを見ながら、監督、助監督たちがあーでもないこーでもないとやってるんですが、最後はなんだかんだで切り返しのショットを撮るか撮らないかで悩んでいるんですよね。押さえとして。
芝山:まあ、自信がないんでしょうね。イーストウッドの場合は、本当に劇的なショットというのは少しで、めったに刀を抜かないでしょう。切り返しも少ないし。