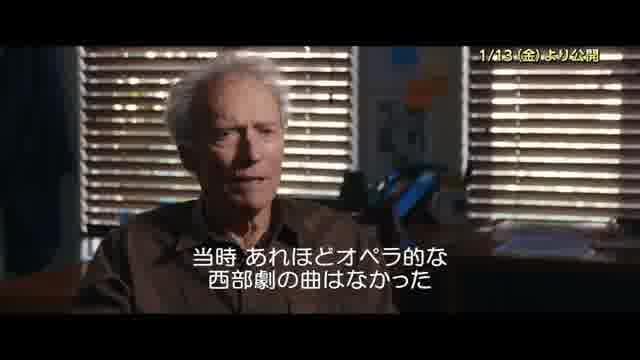モリコーネ 映画が恋した音楽家 : 映画評論・批評
2023年1月10日更新
2023年1月13日よりTOHOシネマズシャンテ、Bunkamuraル・シネマほかにてロードショー
映画音楽のマエストロ、モリコーネ自らが語る“我が映画人生”
メトロノームがテンポを刻む。膨大な本や資料が並ぶ書斎に体操着を着たエンニオ・モリコーネが現れ、おもむろにストレッチを始める。ふたつの反復運動によって映画の語り口が伝わる。音楽とは一小節ごとに異なる音を連ねて人々の感情を揺らす反復の芸術だ。その連鎖が世界共通の言語となって人の心を動かす。モリコーネにとって大いなる反復運動である音楽は、単に繰り返すことではなく、常に新しいときめきに満ちた出会いであり挑戦である。

(C)2021 Piano b produzioni, gaga, potemkino, terras
ジュゼッペ・トルナトーレ監督が、心の師であり、映画音楽のパートナーである作曲家エンニオ・モリコーネのドキュメンタリーを撮った。まさに教養に満ち溢れた、豊穣なる映画の旅が堪能できる。映画の教養、その本質を裏付けるのが、唯一無二のマエストロ、モリコーネその人となれば尚更だ。
千載一遇。キャメラの前でモリコーネが自らを語るただ一度の機会が訪れた。「語る」と決めた巨匠は、まるで昨日作曲したかのように自身が生み出した映画音楽創作の秘密を明かし、その裏側を余すところなく伝えようとする。息せき切って話し始めると瞳が輝き眼光に力が漲る。言葉だけでは足りないとばかりに、オーケストラを指揮するかのように身振り手振りを交え、創作渦中の鮮明な記憶を語っていく。
この映画は過去を疎かにしない。父に命じられて若くしてトランペッターとなった過程で作曲を学んだこと、生涯の師となるゴッフレード・パトラッシとの出会い、編曲者として大胆なアレンジによってヒットメーカーとなった音楽武者修行時代など、モリコーネの礎、原点となった音楽体験談に耳を傾ける。
音楽とは何かを学び、自分だけの編曲センスで頭角を現したモリコーネは、出会うべくして映画と邂逅し、音楽技法をロジカルに構築し、製作者の意図を汲みとりながら感性に裏打ちされた独自の音階を創造した。ある時は撮影された映像を観て、ある時は無名の監督から託された脚本を読み、またある時は音楽を拒絶する監督の撮影現場を訪れて依頼を受けた。
盟友セルジオ・レオーネとは「荒野の用心棒」(1964)「夕陽のガンマン」(65)「続・夕陽のガンマン」(66)へと続き、傑作「ウェスタン」(68)を経て、1984年の集大成「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」まで続いた。
「革命前夜」(64)のベルナルド・ベルトルッチとは、「ベルトルッチの分身」「ルナ」と続き、四時間の大作「1900年」(76)へと結実する。1988年のアカデミー賞で3度目の作曲賞ノミネートを果たすが、奇しくも同監督の「ラストエンペラー」によって受賞を逃すことになる。
更に、ダリオ・アルジェント、P・P・パゾリーニ、ジッロ・ポンテコルボ、テレンス・マリック、ローランド・ジョフィ、ブライアン・デ・パルマなど、世界的な映画監督の作品に音楽を提供した。
引退をほのめかしながらも、88年の「ニュー・シネマ・パラダイス」では、当時全く無名だったトルナトーレの脚本を読んで即決、息子と共に名曲を生んだ。クエンティン・タランティーノとは、「ジャンゴ 繋がれざる者」(2012)のオープニング曲を提供した後、「ヘイトフル・エイト」(15)でアカデミー賞作曲賞を受賞した。2007年の名誉賞に対する物言わぬ回答である。
音楽の決め手を問われた巨匠は、曲が完成すると「ある時から妻のマリアに聴いてもらうことにした」と答えている。若き日に出会い、生涯を共にした妻のマリアさんはモリコーネにとって世界で最初の聴衆であり、どんなことも話せる観客であった。青年時代に押しつけられたトランペットは、父が吹けなくなった頃から逝去するまで使わなかったとも。
そんなモリコーネが生涯唯一の心残りは、「時計じかけのオレンジ」(1971)製作中のスタンリー・キューブリックからの依頼を盟友レオーネに反対されて、知らぬ間に断られたことだと笑う。
作曲するためにピアノもギターも必要とせず、湧き上がる音を譜面に記していく。国境を越えて活躍する優れた映画監督のために、観客の心をより豊かにするために、一作ごとに教養に感性を注いで作曲し続けたエンニオ・モリコーネ。その映画人生こそ「我が生涯に悔いなし」と呼べるものではないだろうか。「教養」とは何か、ひと言で表すなら“精神の豊かさ”である。
(髙橋直樹)