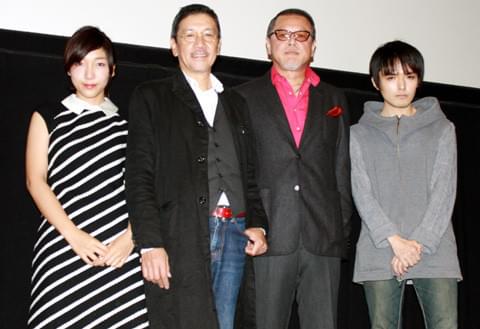奥田瑛二監督作品
物語の中で交わることのない二人の物語を、東日本大震災を題材に描いている。
英語で書かれた「case of Kouko,case of syuichi」
この二人のケースとは、未曽有の大災害が起きたにもかかわらず、しばらくそれを無視し続け、ようやく重い腰を上げた二人の違いのことだろう。
過去に犯した父殺しの罪
収監中に起きた大震災
行方不明のままの母
本当にすべてを失った修一は、帰ったところで仕方がないことを理由に働き続ける。
あれは確かに、行方不明という意味を、死んだと考えるに十分な災害だった。
大学受験を再開し見事合格、好きになったミキに「ひょっとしたらひとりじゃないのかも」と言葉にする。
何もかもなくなっているから、行っても仕方ない。
そんな虚無からの再生。
母が死んだという覚悟はできている。
しかし、修一は大人への通過点、通過儀式として実家を見ておく必要があると考えたのだろう。
母の死は覚悟した。それは受け入れるしかない。でも、心にけじめをつけなければならない。
これが修一のケースだろう。
一方、夫と息子がいる身でありながら枕営業に流され、勘当された今日子。
ホテトル嬢のような仕事と素性のわからないトオルとの同棲。
小遣いをねだるヒモ その時起きた地震 そして2度目の大きな地震で包丁が刺さって死んだ。
この時の今日子の心情は正直よくわからなかったが、今日子は呆然としながら勘当された過去を思い出している。
そう言ったのは義理の父で、夫は何も話さない。
トオルが誤って死に、ニュースでは津波の様子が流れている。
家族は誰も生きているはずはない。
今日子はそう思ったのだろうか?
彼女はトオルの死体を切り刻むと、スーツケースに詰め線路脇の空き地に埋めた。
「あなたは本当は誰なの?」
この言葉はおそらく、自分自身に言ったのだと思う。
切り刻んでいたものは、自分自身の心だったのかもしれない。
何もかもが無意味に通り過ぎてゆく。
そんな寂しさが彼女自身を包んでいるかのようだ。
今日子の両親や兄弟はすでにいないのだろう。
実家などはなく、元居た家だけが唯一の故郷と言える場所だったが、おそらく何もかも流されたと思ったのだろうか? そう思うことに決めたのかもしれない。
トオルなのかタケシなのか知らないが、「私もキョウコか何者かわからない」
定食屋で見た津波の様子と、定食屋の息子が自分の息子に被ったとき、みな死んだのか確認したくなった。
息子にだけは会いたい。もう一度この目で見ておきたい。
彼女はそう思ったに違いない。
義父と夫は死んだようだが、義母と息子は元気よく生きていた。
息子はもう母の顔を忘れてしまったのだろうか? 祖母に隠れながら今日子を見ている。
それは遠い記憶を思い出さない方がいいと頭のどこかで感じているのと、どうしても見ずにはいられない葛藤のようなものを、あの子から感じてしまう。
涙だけを残し、今日子は去った。
彼女は戻れない。
ただ一目見たかった。
これが彼女の人生に対するけじめだろう。
これが今日子のケースだ。
さて、
この作品は人生と同居せざるを得ない大災害をミックスしている。
ただその震災被害そのものはこの二人に大きな影響を与えているわけではなく、二人の心の虚無として描かれている。
そして震災以上に犯した事件と誤った認識によった転落の方がよりウェイトが大きい。
この二人にとっては、震災よりも心の傷が深いことになる。
虚無感という大きな落とし穴に落ちてしまったかのようだ。
あんなに重大な出来事があったとしても、いまの自分自身との折り合いをどうしてもつけることができない理由がこの虚無感だ。
それにようやく折り合いをつけらるようになるのがこの物語。
二人にとってあの大震災とは、どうにもならない虚無感に等しいのだろう。
若干長ったらしい作品ではあるが、余白に残る虚無感が良く描かれていた。










 万引き家族
万引き家族 怪物
怪物 アルキメデスの大戦
アルキメデスの大戦 ある男
ある男 百円の恋
百円の恋 きみの鳥はうたえる
きみの鳥はうたえる 先生、私の隣に座っていただけませんか?
先生、私の隣に座っていただけませんか? 火口のふたり
火口のふたり 0.5ミリ
0.5ミリ 花腐し
花腐し