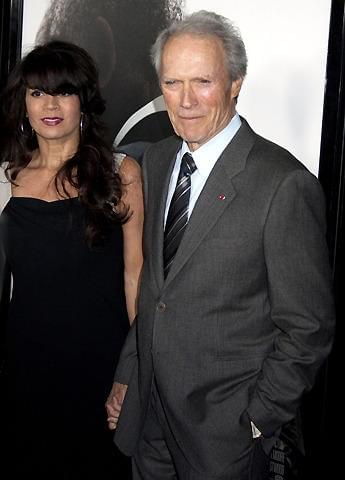インビクタス 負けざる者たち : 特集
【特別対談】芝山幹郎×サトウムツオ その2

■不屈の戦い
芝山:そうですね。あのフレーズは2回出てくるでしょ。「我はわが運命の支配者、我はわが魂の指導者」という一節。本来なら復讐に走ってもおかしくないところで、和解と赦しの話にしたということは、しっかりと伝えておきたかったんでしょう。イーストウッドという人は、そう簡単に許したりする人じゃないから(笑)。ジェームズ・ファーゴみたいに、妙に舞い上がって、ずっと許されなかった人もいますからね。それを思うと、マンデラの赦しの心の大きさには俺も納得したんだ、ということを、駄目押し的に言っておきたかったのかもしれないですね。
ムツオ:「負け犬」が勇気を取り戻す話でもありますよね。
芝山:イーストウッドって、例えば「硫黄島からの手紙」を見れば分かるけど、「あらゆる人生はすべて負け戦である」という意識を持ってますよね。となると、負け犬とかアンダードッグという観念には、足を取られている暇がない。イーストウッドから見れば、マンデラの人生も負け戦を戦い続けた人生であり、ボクスの主将のピナールもまた負け戦を続けた一人であり、結果として勝利に結びついたけれども、それはたまたまの結果ですよね。孤独でハードな戦いが果てしなく続くというのは、イーストウッドにとっては永遠のテーマでしょうね。復讐というテーマは今回消したけど、不屈の戦いというテーマに関しては、しかもそれをライオンのハートで撮るという彼の方法に関しては、やっぱり毎回一貫している。そこに関してはブレがないなと思いました。

だから、話はね、マンデラという偉人が私怨を捨てて、乗り越えて、国を治め、民を救い、天下を平和にするために、そういう心の広い決断をしたという話で、歴史上の話だからみんな知っているわけです。だけど、そういった予定調和は承知の上で、あの高みに持っていけたというのは、やっぱりイーストウッドのハートが素晴らしいということの証明だと思う。それに最後の20分は「和解のための戦い」でしょ。ここでは戦いというご馳走をドーンと出してきた感じがあって、それまでちょっともどかしい思いをしていた人も、あの20分で納得するんじゃないかなと思うんです。
ムツオ:まさにワールドカップの決勝戦で、あるいはあのワールドカップの全試合を通じて、マンデラが提唱した「虹の国」というものが少しずつ実現されていくところを目の当たりにするんですよね。
芝山:たとえば、セキュリティの人たちが中庭でラグビーを始めるところとか、警官とその辺の小僧が一緒になってラジオに耳を傾けるところとか、そういった場面は全部ありきたりなんです。ただ、ありきたりであるにもかかわらず説得力があるというのは、やはりイーストウッド自身が「マスター・オブ・ザ・ハート」であることの証明だったのではないかと思うんです。
ムツオ:本当に上手い。
芝山:それとね、私が意外に思ったのが、イーストウッドという人はもちろん大映画作家であるんだけれども、それと同時に大常識人なんですね。それでね、彼から見るとマンデラという人は、政治家の、そして大常識人のひとつの典型なんです。これは死語に近いけど「経世済民」とか「治国平天下」という言葉があって、先ほどもちらっと言ったけど、国を治め、民を救い、天下を平和にするという意味なんですね。これは本来の政治家だったら、誰もが目的とすべき言葉なのに、今の現実はほとんどがそれに反している。共和党も民主党もそうだし、日本なんてもっとすごいでしょう。
そういったことから考えると、イーストウッドという大常識人は、ネルソン・マンデラという人物を通して、そういった思いを述べたかったのかなと思いましたね。イデオロギーの問題などではなくて、とにかく国を治め、民を救い、天下を平和にするということはすごく難しい。うっかり口に出すとすごく馬鹿馬鹿しく聞こえるかもしれないんだけど、馬鹿馬鹿しいからこそ、改めて発言したんじゃないかなという気がしたんですよね。
■悠揚迫らざる語り口
──イーストウッドは今年5月31日で80歳になるんですが、少し遺言めいた感じになっているんですかね。

芝山:というか、ちょっと丸くなってきたのはたしかでしょうね。「グラン・トリノ」にはちょっと悪役がいたけど、とにかく今回は一人も悪役がいないんですよ。誰も悪い人が出てこない、イヤなヤツも出てこない。
ムツオ:ほのめかしだけですもんね。その悪役も……。
芝山:ネルソン・マンデラは、偉人ではあるけれども、私生活においては不幸というか、グレーの部分があった人ですよね。映画のなかでも妻と別居していたけど、たしかあのワールドカップの後に離婚するんですよね。で、1998年かな、80歳でまた結婚する。モザンビークの大統領未亡人と3度目の結婚をするんですよ。イーストウッドは、そういうところでもニヤリとしてるかもしれない。映画のなかにも「父が羨ましい」なんて一夫多妻制にあこがれる話が出てくるでしょ(笑)。ああいうところは、イーストウッドらしいユーモアですね。ただ、私がこの映画で一番ホロッとしそうになったのは、決勝戦の前のセレモニーでニュージーランドの主将のロムーに「I am a little afraid of you(君のことがちょっと恐いんだ)」って言う場面。ああいうところにイーストウッドのセンスの良さが出ていると思いますね。
──画づくりの面においても、何というか、ある種のおおらかさがありますよね。今回のようにラグビーを撮るのは初めてでも、気負いみたいなものは感じられず、いつものペースで撮ったという印象を受けます。やはり、これがマルパソ(イーストウッドの製作プロダクション)のチームワークの成せる業なんでしょうか。
芝山:イーストウッドがどういう画をほしがっているか、ちゃんと分かっているんでしょうね。でも、(画自体は)いわゆる綿密という印象は与えないんですよね。ザックリ撮っているんだろうけど、そのザックリが的確。そういう印象を与えますよね。だから、計算じゃないんですよ。やっぱり、学習してきたことがいろんな意味で身体に染みついているんでしょうね。
それから、語り口に悠揚迫らざるところがあって、これ、若い監督が見たら嫉妬するだろうなあと思うんです。とにかく、こう動かしてこう撮ればこうなる、という流れを完全に把握しているんですよね。しかも、それがマンネリズムにならない。いつもの手で撮っているなあとは思うんだけど、それが実に安定したペースなんで、こちらもゆっくりと彼のペースに身を委ねることが出来るんです。
──そういったイーストウッド独特の語り口がないと、今回の映画はドラマが弱いぶん、辛かったかもしれませんね。

芝山:この映画に関しては、さっきも言ったけど、不安があったんですよね。話があまりにも予定調和だということと、あと偉い人の話というのは退屈になりがちでしょう。「バード」の場合はチャーリー・パーカーという実在の人物を題材にしていたけど、あれは破滅派の話でしょう。だから、イーストウッドの手の内に入ると思うんですが、今度は「パストゥール伝」とかそっちのほうでしょう。それをこういう風に仕上げたというのは驚きですね。ただ、偉人伝の匂いとかタッチは残しているんです。イーストウッドは子供の時にああいう映画を見ているわけだから、そのペースは頭や身体に入っているんですよね。でも嫌味ではないし、鈍重でもない。たしかに年齢的な問題はあって、さすがのイーストウッドもエッジは鈍くなったかなという気はしますけど。
ムツオ:まあ、昔から「ピンク・キャデラック」とかその辺のゆるい映画も撮ってましたからね。監督はバディ・バン・ホーンとかに任せて。
芝山:最近だと「ブラッド・ワーク」みたいのも監督・主演で撮ってますよね。イーストウッドには、けっこうゆるいことを平気でやってしまうようなところがあるんですよね。そして、それを恐れない(笑)。度胸がいいというか、不思議な人なんだなあ。自信があるというか、ゆるくて何が悪いんだ、みたいなところがあるんですよね。今回も少しそういうところがありましたよね。
これは多分いろんな人が言うだろうけど、私はこの映画に対して重層的な感想を持ったんです。こんな話でよく持ったなということと、にもかかわらず、見終わった後に一種の高揚感を覚えるんです。これはたぶん、最大公約数的な感想だと思うんですよ。だけどそれは、最初にぽろっと言ったけれども、イーストウッドというハートの達人にのみ可能な一種のマジックなんですね。細部の端々に、イーストウッド・マジックと言わざるを得ないような何かがあるんです。あんまりそういう言い方をしちゃうと、批評家の端くれとしていかがなものかと思うんだけど。