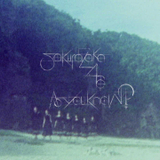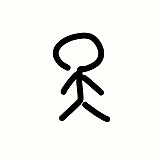アバター(2009)のレビュー・感想・評価
全366件中、81~100件目を表示
4DXにピッタリの映画
はじめての4DX3Dで観ましたが、
映像の綺麗さと迫力が、4DXに
ピッタリマッチしていて
とても楽しめました。
物語は人間とナビィ達が戦争を
して殺しあうので、あまり好きでは
ないですが、映像の綺麗さと
4DXの素晴らしさで星4つ。
まさに革命
DVDで鑑賞(吹替)。
嗚呼、何故映画館へ観に行かなかったのか!
⋯と、未だに悔いているのが本作だ。
長尺なのにダレず、ずっと引きつけられる脚本の面白さもさることながら、ジェームズ・キャメロン監督が極めようとした映画芸術、映像表現のすごさに圧倒されっぱなし。本作以降、画面の奥行きに特化した3Dは新たなスタンダードとなり、今日に至っているのは本当にすごいと思う。
高精細のCGで表現されたパンドラの風景はとても美しく、本当にどこかに存在しているのではないかと錯覚しそうになるリアリティだ。繰り広げられる地球人とナビィの戦いの壮大さは比類無きスケールで、まさに革命的な映画であると感じた。
これまで3Dで観たことがないので、2作目公開を記念した再上映が本当に楽しみだ。遅ればせながら、革命的映像をスクリーンで体感したい。
[鑑賞記録]
2010/??/??:DVD(吹替)
2012/02/17:金曜特別ロードショー
2016/??/??:Blu-ray(字幕)
2023/02/08:地上波放送(テレビ大阪)
*修正(2025/12/17)
映像美、ストーリーにアクションが良いです
原題も邦題も同じ「アバター」です。
アバターとは、人とナヴィのDNAを合成して作った、ナヴィのような体で、人と神経システムが同調し、人が遠隔で操作できます。
友人、カップル、夫婦、親子または一人で鑑賞しても、楽しめる映画です。
映画では、人類の単語とナヴィの単語が入り乱れて、混乱させられます。
高所恐怖症の人には、お勧めできません。
キャッチコピーは「観るのではない。そこにいるのだ」です。
IMAX3Dの吹き替え版で見ましたが、没入感がすごかったです。
再上映されるなら、IMAX3Dの吹き替え版をお勧めします。
2150年頃の物語で、この頃の地球とパンドラの状況を理解できないと、映画も理解できません。
映画では、軽く触れられるだけなので、補足します。
人類は、地球の資源を使い果たし、地球の環境を汚染し、他の惑星から資源を輸入せざる得ず、地球に未来はなく、地球は人が死に行く場所でしかありません。
パンドラは、人類は生活することさえできませんが、ナヴィにとっては、資源は豊富で、環境は綺麗で、活動的で、未来があり、生きて行くに相応しい場所です。
人類は、圧倒的な武力を持っています。
ナヴィは、原始的な武力しかありません。
ナヴィが、ジェイク・サリーとグレイス・オーガスティン博士を受け入れたのは、人類への恐怖心です。
人類になりたいですか、ナヴィになりたいですかということです。
簡単に分かりやすく例えるなら、不便となった都会で生活したいか、自活できる田舎で生活したいかという感じです。
自分は、空を自由に飛んでみたいです。
映画を鑑賞しても、分かりにくい部分を私見ですが、説明します。
ジェイク・サリーに、聖なる木の種子である聖なる木の精のお告げがあり、エイワがジェイク・サリーについて何らかの意思を伝える意味があり、ツァヒクが何のエイワの意志があるのかを読み説くということ必要があるので、ツァヒクに引き合わせられます。
ジェイク・サリーが、オマティカヤ部族に受け入れられた理由は、何も知らない、戦士だからで、パンドラについて教えれば、パンドラのために戦う戦士になると思ったからです。
主人公のジェイク・サリーの視点で映画を鑑賞すると感情移入しやすいです。
ジェイク・サリーは、鑑賞する人と同じで、パンドラについて何も知りません。
色々な人が、ジェイク・サリーに、パンドラについて教えてくれます。
それでも、パンドラについて映画を鑑賞するだけで理解するのは困難です。
パンドラについて理解したいなら「アバター 公式完全ガイド 単行本」という本が出版されているので、読むことをお勧めします。
脇役の人々が意志が強くブレないので、魅力的でもあり、主人公のジェイク・サリーを引き立てています。
「ナヴィは二度生まれる」と「エイワはどちらの味方もしない。この世界、命のバランス守るだけ」というセリフが伏線になっています。
人類の利益のために、地球の環境破壊は進み、宇宙への進出も計画され、将来はこの映画のようになるのかもしれないと感じました。
これぞエンターテイメント!
続編が公開されるようなので、復習のため観ました(笑)。やはり、面白いですね!公開時のような感動がなかったらどうしようかとちょっとだけ不安でしたが、全く杞憂でした。主人公ジェイク・サリー(サム・ワーシントン)が優秀な科学者の兄の代役とか足を負傷して歩けないとか、地球が環境破壊で住みにくくなっているとか、惑星パンドラに莫大な資源があるとか…、様々な設定がうまく噛み合っていてぐいぐい引き込まれました。ネイティブアメリカンの地に移民がきて先住民族たちの土地を奪っていく合衆国の歴史や、身分の違いを乗り越えて結ばれる「タイタニック」(97)的なエッセンスもうまく融合して、独自の世界観が楽しめました。公開当時も話題になっていましたが、自然崇拝の思想や森や生物の描写などで「もののけ姫」(97)や「天空の城ラピュタ」(86)と類似しているところも多々ありますが、ジェームズ・キャメロン監督も宮崎アニメのファンのようなので、なるほどと思います。映画公開から13年、リアルな世界でアバターが出現していることに衝撃を受けてしまいます。
これは初めて3Dを観た作品でした。 映像の壮大さ、綺麗さに圧巻して...
新ジャンルを開拓する意欲作ではある
こんなにも映像美で惹きつけられる作品はSFでも少ないのは確かでしょう。展開としては何かジュラシック・パークと似たようなノリがあったりするし、無機質で人間味が感じないのが欠点ではある。 お互い平和に生きようで一件落着。
人間が演技してる場面が少ないから、これはこれで新しいジャンルとして確立する可能性があるわけで、興行収入の凄さからも今後この手の才能に長けた製作者が次々と出てくる気はする。
個人的には人間のままで良いのでは?と思ったりしました。ただ役者さんへのコストを考えると、今後こういった方法を取る映画が増えそうと冷静に観ちゃいました。
とにかく映像美の数々を満喫できる映画ですが、物語としては特に面白みは感じなかったので退屈に思えました。長いので途中で飽きてしまった。ジャンルは違いますが「キングスマン」辺りにも感じた作り過ぎ・凝り過ぎた映像で、私自身は返って印象に残らなかった。
どんなに優れた作品でもヒットが伴わなければ「隠れた名作」として片付けられてしまう風潮があるけど、これは新しいジャンルを確立する意味でも気合が違う! 娯楽作として価値あるヒットだったんでしょう。
とにかく綺麗☆
タイトルなし(ネタバレ)
12年ぶりに視聴。当時は大学生で映画館で3Dで鑑賞し、そのファンタジー感に感動したのは覚えている。
SFとファンタジーのハイブリッドという様子で地球上の話ではないが、リアリティを持って鑑賞することができた。最初、ジェイクがアバターに乗り込む所から始まり、徐々にファンタジー感あふれる世界で新たな事を次々に体験していく様子にワクワクしながら視聴していく。その中で①主人公の成長②主人公とヒロインの恋愛③先住民と征服者の問題という課題を体験していく様が違和感なく盛り込まれており、どのような視点の視聴者でも楽しめる作品となっている。
インディアンとウラン鉱山を彷彿とさせる内容。
革新的映像美
マンガをお金かけて実写化した
映像美が素晴らしい
没入
表現力はさすがです!!
ジェームズ・キャメロン監督の最新作。
キャメロン監督といえば「タイタニック」。
この映画も「タイタニック」から12年ぶりの新作とのこと。「タイタニック」は長作でスケールは大きい映画だった。ただし、脚本に面白さを見出す自分としては、スケールだけでかくて中身の無い映画はあまり好きじゃない。ってことで「タイタニック」も一度観たが正直たいして評価してない。
そんな監督の作品、行こうかどうかしばらく迷ってた。。ただ、世間的な評判は随分良い。昔一時期流行った3Dメガネがどう変わったのかも気になる。。これだけ時間経ってればさすがに3Dメガネも進化してるはずだし。。「うーーーん、どうしよう」とこの1~2週間悩んでたけど、悩んでる時間がもったいないので、さっさと行くことに決めた(笑)
場所は梅田の「TOHOシネマズ」。
もちろんレイトショー。けど、レイトショーなのに1500円。普通は1200円なのに…何故?どうやら3D付きだと料金が少し高くなるみたい。
3Dメガネはかなり大きく丈夫な感じで、昔の紙で作られたようなペラペラな代物とは一味違う。メガネは劇場へ入る前に手渡される。こりゃ、期待できるかな?とスタートから期待度上げさせるイントロとしては効果十分。で、実際の作品前の予告編でも3Dの作品があって、かなり面白かった。映画を3D化すると、奥行きができて表現の幅が広がるねー。
さて、作品の「アバター」。
まずは最初の宇宙空間の3Dでの表現力に驚いた。すごく立体的。3Dは想像以上に良いツールかも。。
で、最初に結論言うと、「アバター」は結構楽しめた。
とは言え、脚本(ストーリー)自体はたいして中身は無い(笑)これは「タイタニック」と同じ。「ポカホンタス」かいな?と思っちゃったし。。。
しかし、表現が素晴らしかった。パンドラに住む様々な生き物達、木々や環境、この舞台設定が凄かった。ほんとに細部まで考えられてる。空を飛ぶシーンもかなり爽快感があった。また、ナヴィと呼ばれる生き物も最初は違和感あったけど、最後はヒロインのネイティリが可愛く見えてきたもんね(笑)
それと、3Dも一味スパイス加えてくれた。表現力が間違いなくUPしてる。しかし3Dメガネは、普段メガネかけない自分としては2時間以上も付けてると頭が痛くなる。最近は3D有りの映画が多くなってるので、この辺どうにか改善してもらいたいな。
もう1回観たいか?と言われるとNOなんだけど、1回観る分には十分楽しめた。
まだ観てない人はぜひ「映画館」で観る(体験する)ことをお薦めする。
キャメロン監督、さすがです!!
全366件中、81~100件目を表示