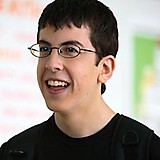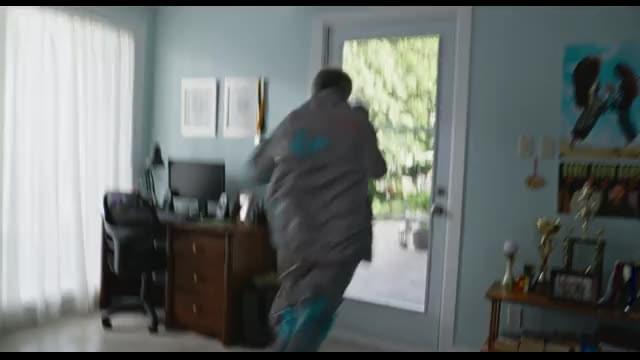ボーはおそれているのレビュー・感想・評価
全364件中、241~260件目を表示
途中で寝た
この映画、彼氏・彼女や親御さんと見に行った場合は猛烈に気まずいから要注意だよ。
私はというと、冒頭1時間で飽きてしまい、中盤は少し寝た。(ちなみにレビューで「寝ました」という感想は最高に面白くない映画にしか使わない表現です。)
さすがに上映時間が三時間は長すぎるんだよ。実験的な妄想映画なら、それならそれでもっと内容をまとめて観やすくしないと。もしこれが一時間くらいの短編だったらもうちょっと高評価だったかな?
途中ポップコーン食べることしか楽しみがなくなって困った。
あー、でも最後の水上での裁判は少し面白かったかな。あれはラスト、沈んでいったあとにボーが生まれたときの音声っぽいのが流れてたから、また生まれて話がループしてるってこと?
いや、もう知らん。考えるのがめんどくさい。あのお父さん一体何なの?本当に意味わからん。あとお父さんと戦ってたやつも誰?怖っ。
監督はペンキでも飲んでいてください。
本当は星0個だけど、裁判シーンと音楽がうるさいっていう隣人からの苦情のお手紙がちょっと笑えたのと、TOHOシネマズのバターしょうゆポップコーンが美味しかったので星1.5個追加しとくね。
なんだこれ
『ガープの世界』かと思ったら、
『俺の空』みたいでもあったし、
最後なんか『555 パラダイス・ロスト』みたいだった。
ホアキン・フェニックスの演技はさすが。
不安を誘う絵作りや間もよい。
だが映画通を気取って褒め上げることもできなくないけど、
絢爛すぎてというかケレン味がありすぎて
整合性をあえて無視して男の主観の悪夢に終始したため
とっちらかっている感のほうが強く、ノリ切れない。
なぜ路上の全員があの部屋を目指すのか。
MW社の差し金?
タトゥーの男の死因はなんだ? 蜘蛛?
天井の男は何をしていた?
外科医夫妻のテストってなんだ?
親父だったのがチンコになっているのはなんなんだ?
ぜんぶ妄想や悪夢なんだといわれれば
ああそうですかと答えるだけだし、
劇中でつぶさに語るようなものではなく、
シチュエーションのインパクトや異常性を楽しむもんなんだ
と言われればそうなんだけど。
そういう「解れよ」的なシークエンスを
知ったような顔して褒めそやす気にもなれず、
観るほどに没入感とは真逆のほうへ向かうばかり。
楽しんではいたんですよ。
179分とかいうアホみたいな長さも退屈はしなかったし。
でも受け入れられないところが多すぎた。
思えば『ヘレデタリー』もダメだった。
『ミッドサマー』は楽しんだけど。
もしかしたら監督と相性が悪いのかもしれない。
パンフを読んで2度目を観たら変わるかな…。
悪夢を観た
途中までは最高
理解を超えた展開で、演劇パートまではすごく面白く観てました。この後どうなるんだろう?!と。
演劇パートはボーの別の生き方、選択肢だったと思いますが、もう訳が分からず何故だかつまらなくなって、時間だけが長く感じました。ロジャー、グレース、トニはモナに雇われていたと思いますが、トニはどういう立場だったのか?なんでペンキを飲んだのか?それすらも妄想?
そもそもあの薬は手下のカウンセラーはなんで処方した?
そもそもチャンネル78で未来も決まってるらしいけど、冒頭の薬を飲むシーンで、ラストまでの流れが出てきているので、ボーは最後は飛び降りて自殺したのかな。
よくわからない系の映画ですが、割と好きなタイプの映画で、もう一回くらいは見ても良いかなと思いました。
【やっぱり癖凄、でもテーマは普遍的かも】
『ヘレディタリー/継承』『ミッドサマー』のアリ・アスター監督&Hollywood指折りの性格俳優ホアキン・フェニックスときたら観ないわけにはいかない。ホアキン出演作はとりあえず逃さず鑑賞。
終始現実か妄想か?の境界線が漠然とした支離滅裂な早い展開に面食らう。アニメーションや舞台装置を演出に取り入れたり、ワサワサさせる画角映像に音響音楽と、アスター監督独自の世界観に加えて、冷静と狂気の狭間で混乱するホアキンの演技で長尺を感じなかった。
よくもまぁこんな脚本作ったものだと賛否両論あるだろう癖凄作品だが、アスター監督の過去作品同様に“家族との葛藤”がテーマ。主人公がどんなナンセンスエピソードに遭遇しても只管に受動的なのも家族、とりわけ母親のとの関係がそうさせるのだと妙な納得感アリ。
色々なフリにしっかりオチがあって、現代社会へのアンチテーゼも落とし込んで、呆気に取られるエンディングも含めこれら全てが如何にもアスター監督ぽい。
ポスターに油断していた。
ポスターを見てポップな映画を想像していたら、不安神経症の内なる世界の様な物語で、先々不安になる怖いものでした。
それでも、映像は綺麗でとても丁寧に作られています。
ホアキン・フェニックス見事過ぎて疲れました。
30分単位で分けて見れば消化できる映画ですが、179分通して見るとヘビーです。
「わからない」と拒否した方が安全で、食いついて見てしまうと気持ちが沈みます。
気持ち的には評価ー5.0ですが、作り手の情熱を感じる見応えのある映画なので、評価3.5としました。
日曜日13:25 観客3名、がんばれー。
封切り3日目で123レビュー、感心はあつめてるぞー。
成功体験てんこ盛りの「フォレストガンプ」見て、精神の安定を取り戻そうと思います。
最後の裁きの場合
これは結局のところ最後の妄想シーンで、ボー自体、自分が母親を殺めてしまったことの後悔があの妄想を呼び、自殺に至ったのだろう。でないと、いきなり池でボートを出して裁きの場に行こうとしたとは思えないし、そこが死者の集まった場所とするならば、あのカウンセラーの姿もあったからだ。あの場には、彼がこれまで母親との絡みで接してきた全ての人がいたと考えるのが妥当なんだろうな。
そしてボートが転覆してボーは水の中に。この映画の冒頭は、ボーが堕胎で外に出てくるところから始まるが、それがまた母親の胎内に戻っていくように確かに捉えることができる。その転覆といえば、ボートの転覆は、ボーがカウンセラーのところに行った帰り、屋台でさまざまなものを売っているが、その中で水槽の中でおもちゃのボートが転覆するが、確かにあのシーンは最終のシーンの暗示なんだろうな。
昨日、今日と立て続けに見てしまったが、もちろん上のような考察は面白いが、アリアスター監督の作品は、一回だけ見て、自分の胸の内で色々と考える方が本当はいいのかもしれないと感じてもいる。今年のベストに入る作品と言ってもいいように思う。
旅路の果ては安堵ではなかった、、、
ジョーカーからの、ナポレオンからの、ホアキン・フェニックスの変貌っぷりを見たい!で観に行った。体張ってました。すごい満身創痍っぷり。一番ちゃんとした服着てたのは森で出会った謎劇団からあてがわれた衣装だった。
隅々まで手抜きなしの、サービス精神溢れた、全然ホッとさせてくれない映画。全てが虚飾の美、もしくは圧倒的カオス二択二重の世界。
振り返ってみると既視感のあるようなエピソードや映像の切り貼りぽく見えないこともないんだけど。同じ夢が何度も出てきたり。なぜかゾワゾワする人たちにしか出会えないポーの人生、本当につらそうだった。でもお人柄がなんだかチャーミングで。そしてこれは夢なのかなんなのか、何かから覚めないうちに急なエンディング、なのでした。置いてきぼりはもはや快感、脱力。
大きな意味で上映中の「哀れなるものたち」とリンクした世界観感も感じた。
いずれにしてもハリウッドでも発達障害主人公モノは一つのジャンルになってると思う。
観客は戸惑っている
非支持の理由。
家族とは万人を不快にさせるテーマらしい
普段ホラーは見ないが、ああこういうのもホラーなんだと思った。違う形で人を恐怖、不安そして不快な気持ちにさせる映画だ。もっとも監督はanxiety comedy (不安コメディ?)と呼んでいるらしいけど。なるほどね。
昔大学でabnormal psychology, 異常心理学というのを勉強した時、ああ自分だって異常と正常の境目にいるんだなと感じたことがある。鬱や恐怖症はじめ、誰でもどちらにでも振れることがあるんだと。
この映画はそんな自分の負の部分が出てきそうな、不安になる映画だった。精神衛生上非常に良くない。悪夢を見た後みたいで、早く何かで上書きしたい。。もう2度と見たくないけど強烈な印象残したのも確か。最後だけもう一度見てみたい気もする。。アリアスターよく正気でこんな映画撮れるよね。。皆どん底に落ちるが良いという監督の言葉がまた怖い。
強迫性障害の心象風景を描いた感じ。不安になる人ってこういうこと心配して生きてるのよ、と。
そして悪夢ってこんな感じだよね、という半分妄想も。
ひたすら連鎖的に悪いことが起きて追われ続ける。常に走ってる。
周りはみんな気狂いで隙あらば殺される。
途中病院や互助会的な救いが出てくるけど安心はできない。誤解されて糾弾されて、常に狙ってくるヤツがいる。
家族にも大きな秘密がある。
そして自分のしたことは全て罪として裁かれる。
主人公ボーは後半で発達障害と出てくるので実際不安なだけでなくこういう幻覚に近いものを見ているということなのかもしれない。でも前半はともかくママのくだりはどこまでリアルなのか?これも虚構なのか実際に起きてしまったのか?怖くなる。最後の裁判は自分が責められているような気にもなってくる。
「家族は万人に通じる最も身近な存在であり、それはつまり万人を不快にさせることができるテーマ」とアリアスターがwiredのインタビューで言っていた。
わかるとはいえないけど、自分の家族との関係を思い起こしむずむずさせられたという意味ではまんまと不快になったということだ。やられた。
一晩寝て、これだけ長文吐き出して、ようやく気持ちが落ち着いた気がする。ああ、気持ち悪かった!
A24✕アリ・アスターにしてはソフトな作品
相変わらず色々分からないまま終わる、そりゃこの組み合わせならそうだろう。でもヘレディタリーやミッドサマーよりは過激な描写は少ないので、色んな人が見られるかなと(年齢制限あるし理解できるかどうかは別だけど)。
とりあえず何が現実で何が夢なのか判然とせず、言ってしまえば『劇団mw』にひと芝居うたれたボーなのだが、あまりに謎が多すぎる。(たぶん)無意味にフルチンの殺人鬼も、ボーの部屋になだれ込んだ街の連中も、看病してくれた医者一家も、森の中の謎の劇団も、ヒッチハイクで拾ってくれた男も、みんなみんな母親の指示のもとに動いた存在だったのだろうか。屋根裏にいた『父親』を語るマーラ様は幻なのか?最後の裁判シーンはどういうことなのか?少なくともまともな現実世界ではないのだろうなと。
経営者として優秀ながら抑圧的な母親、対してADHD(示唆するシーンあり)で自己決定が苦手で周囲に判断を委ねてばかりの息子、その対立が終盤のテーマになるが、ここがまぁ見ていてしんどくなるほど。親子間でそういった出来事があった人には結構キツイかもしれない。
とりあえずホアキン・フェニックスは『ナポレオン』に引き続き体張って怪演してます。お見事です。
誰だよ
3時間の苦行とか言ったヤツ。
クソオモロかったやんけ、前半7回くらい声上げて笑ったぞ、そこでそう思うんかーい!とか。
そのリアクションかーい!とか。
近くで見ると喜劇のチャップリン論にグイグイ笑っちゃったよ、そこにjokerホアキン重ねたりも出来たし
まあホアキンの気弱で良いヤツ感の芝居が素晴らしいよな、俺常に悪いことしてるんじゃ無いか?に自己疑心に心当たり弄るわ。
まあ、ボーは基本的に良いヤツなんだろうな、不安に駆られる人生は非暴力者だろうし、まあ最後はアレだったけど、聖書に人生預けるのも怖いね。
映画の魅力としては今敏夫重ねちゃったなー、実写でコレ出来るヤツ居たのかーーー!!って。
もうどっからどこまでが事実で、どっからがボーの脳内か解んないじゃん。
もう3時間凄えの見たわ。
我慢不能でラスト5分トイレ離席したけど。
入場前コンビニビールも不安産むんだな。
後からじわじわくる
心配症を患った為に不安が不安を煽り、そしてさらに様々なあり得ないことが次から次へと起こってしまう。
前半は現実、後半は母親に囚われている心の中の状況、もしくは夢の中。母親との電話で普段は優しい母親の声が低くなる一言からが本題の入り口のような気がする。
最後のシーンは悪夢でうなされているボーに対して、現実の世界からの母親の声が聞こえてくる。
誰もが持っている不安を描写した映画だと思った。
追記
2回目観てきました。感覚も変わりますね。
1回目には気が付かなかったこと。チャンネル74の早送りの画像内容。そしていつもボウを監視している謎のおじさん。誰よwwwマジ。
。新しい発見。スッキリしたい(笑)
この映画、字幕を気にしていたら気が付かないことたくさんあるような気がします。
3回目あるな。
ミッドサマーは良心的
狂っているのはだれか
3時間ポカーン( ゚д゚)
こんな母子、日本の社会に多いんじゃないか
職場の同僚(♀)が、一人息子(高校3年生)を溺愛しており、息子の話ばかり。
幼児のような世話焼きぶり、干渉ぶり、ほとんど残業なしとはいえフルタイム勤務のワーママなのに、生活は彼が快適に過ごせるように細部まで気を配って、夫は空気かむしろ邪魔、ひたすらむしゅこラブでカワイイかわいいって、話聞かされるたびにドン引き。
高校3年生の息子のほうもこういう母に反発ないみたい。
正直、キモチ悪い。
うちは息子ふたりだが、ずっとフルタイムの共働きなのでそこまで世話焼いてないし、男の子はある年令になったら母親をウザがるもんで(そして理不尽なことしか言わない反抗期がある)、それも自立へのステップなんじゃないかと思っている。言わないけど。
気持ち悪すぎてリアクションに困り、彼女とふたりでランチするのは避けています。
人に世話されて当たり前、自己中で自立できない、大人になれないオトコ、こんな感じでできあがるんだろうと想像しました。
母のワンオペ育児に少子化で一人っ子が多い日本は、この同僚や、ボーの母子みたいな家庭が結構あるのでは。
ボーは、多分発達障害。富豪のママは、多分、製薬も含んだ多角的事業を手掛けている。
この母が猛毒。
自己中で息子は所有物、とことん支配する。
息子に自分以外のオンナを近寄らせない気持ち悪いオンナでもある。
息子が自分の意に沿わないことをすれば、一般的観点からなら十分理由があることでも、捻じ曲げてボーに罪悪感をもたせる方向で責め立てる。
常に強迫観念を持って、自分の行動全部が高みにいる神(と母)に見張られて「悪いこと」をすべて把握されている感覚があり、人に合わせるだけで自分がない、とか、いつも謝っているとか、そうやって育ってきたコドモらしいところがてんこ盛り。妄想(多分)の内容もいちいち毒母に支配されてきた男児らしい感じ。クスリのせいもあるでしょうが。
多分、ボーはコドモの頃から精神系のクスリを飲まされており、現在は精神科医付きで母の手の中で一人暮らしなんでしょう
色々出てくるエピソードは多分、ほとんどがボーの極端に偏った妄想だろうがクスリのせいかも。
結局、母の支配から抜け出せずに沈んでしまったようだけど、ヒトらしさも手放すくらいの本格的精神疾患になってしまったということなんだろうか。
現実にこういう人はいると思う。気の毒です。
とにかく長い。
妄想らしく筋が通らん訳の分からないエピソードばかりでストレス溜まって、早く終わらないかばかり思っていました。
ボーが恐れている理由
ヘレディタリー、ミッドサマーに続く怪作で、制作費3500万ドルという前作の4倍近くの予算規模となる本作。
アリアスターの短編映画BEAU(2011)が元になった作品で、冒頭の『自宅の鍵をかける途中でフロスを忘れて取りにいって戻ってきたら鍵が盗まれている』というプロットはこの時の着想が元になっていることが分かる。
今回も「母性」がテーマとして描かれ、聖母の置物や銅像のモチーフは、まるで母が神のような立ち位置なのだ。途中で ”Jesus sees your abominations”と出てくるのも、チャンネル78で過去現在未来が監視されているのも、まるで母親が神となって、「あなたの悪事を監視している」かのようだ。これはエンディングにも大きく関わるので注目しておきたい。
もう一つの要素として見過ごせないのが「水」の描かれ方だ。冒頭の羊水、アパートの水が止まる、薬のための水(クレジットカードを止められ、買えないため通報される)、浴槽の水(水浸しになる)、大洪水、回想シーンでの船、浴槽、そしてエンディングに繋がるわけだが、モナ・ワッサーマンのwasserman はドイツ語で『水の精』を表すため、母親が絶対的な権力者であることも示唆している。
本作は4つのセクションでできており、最初の3つはそれぞれボウが気絶して終了する。①車に撥ねられる②森の木に激突する③脚のGPS装置が爆破する(劇中の大洪水のシーンでも気絶しているので、それを含めると4回気絶している)
ボウはパラノイア的で、強迫観念や被害妄想がひどく(もしくは薬の副作用)、母親に依存し、極めて優柔不断な性格なのだ。母親という足枷を外して自らの人生を歩もうとするボウの建設的妄想も描かれるが、最終的には親子の葛藤・軋轢に帰結する4部構成となっている。
アリアスターならではのゾッとするサイコスリラー描写が散りばめられ、展開の移り変わりも早いので、間延び感はさほどない。
ボウの一人称視点のため、現実と妄想の境目がなく、付いていけない観客は、最後まで真相分からず愕然とするだろうが、世界観に入り込める人なら、ボウの内面に穿ちいって、心地よささえ感じるだろう。
ホアキンは当時アカデミー賞を獲ったばかりだったのもあり、出演を渋っていたそうだが、アリが説き伏せて、形になったそうだ。次回作の西部劇がテーマのeddingtonの出演も決まっているらしいので、今から楽しみである。
アリアスターの交響曲とも言うべき音色に、身を委ねてほしい。
全364件中、241~260件目を表示