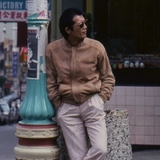きっと、うまくいくのレビュー・感想・評価
全366件中、41~60件目を表示
学歴を買うことができたら
なんだか音楽とか乗っていて楽しくテンポ良く進むので、見やすい。
でも、カースト制の下お金持ちが財力を言わせて
子供の学歴を作ったってお話し。
その裏で身代わりになっている男の子の奮闘ぶりに
応援したくなるなぁとなった。
やっぱり頑張ればなんとかなる日本って恵まれている。
自分の人生は自分で決めよう。
一言「おてんこ盛りなのに、あっという間」。
インド映画というと、尺が長くて突如歌う。
そうなんだけど、そんなのカンケーない面白さ。
冒頭の、飛行機を無理やり止めるシーンから、もうこれは!と確信。
工科大学のルームメイト三人達が、10年後に再会を約束する。
大学時代が7割、現在が3割くらいの内容。
時間軸は行ったり来たりするけど、わかりやすかったし。
インドの学歴社会を、めっちゃdisってます。
大学を出ていれば、幸せになれるのか。学ぶって何よ?。
暗記ではなく、応用力。大切だよね。そして友は大切な宝。
いろんな伏線があります。
ルームメイトを訪ねて行ったら、同名の別人だったとか。
どれも「ああそういえば!」と膝を叩き、笑っちゃったし。
セリフ「ALL IS WELL♪」(きっとうまくいく)、耳から離れない音階ですよ。
⭐️今日のマーカーワード⭐️
「お前は好きなものになれ」
インドの趣たっぷり
ALL IS WELL
ドローンを発明したロボ・ジョイの自殺。学長、サイレンサー、ミリ坊主などの特異なキャラクターも印象に残った。学長相手に無茶苦茶なことをやったりするのはやり過ぎだろうと思いつつも、親が息子ファランを工学者にする願いに逆らったり、ラジューの父親の命を助けたり、感動的なエピソードでたたみかけてくる内容。もっともランチョーとピアとの恋物語がクライマックスとなったが、ピアが惚れてしまったエピソードが終盤にあるので、恋愛面での感情移入がしにくかった。
インド映画のミュージカル部分はもう定番なので驚くこともなかったのに、ラジューの弾くギターが音楽に全然合ってなかったのが気になってしまった。医学生から医者になったピアというヒロイン。ちょっと大人の魅力がありすぎて、学生の恋愛ものとしては似合ってなかったかな~などという欠点も。
点数制の学力社会に対するアンチテーゼ。真に学問を学びたいとする受験生に対するメッセージともとれる。何しろ40万人の中の200人のエリートなんだから、落ちこぼれであっても頭がいいはず。そして、学長息子の悲劇、ロボ・ジョイの悲劇を後追いするようなラジュー。彼の行動は痛々しかった。コメディ部分が吹っ飛んでしまうくらいの衝撃!まぁ、10年後の姿があるので無事だとわかるが・・・魔法の言葉”Allis well”が効いた!
アミールカーン万歳!!
きっとうまくいく
All is well
心躍らせ一流工科大学に入学してきた学生たち。
インドのキャンパスライフ
ウイルス学長の人生は競争、偏狭な結果主義、競争に負けることは死を意味するほどのこの考えのもと、学生たちが命をたつ、学長のむすこでさえも。、
エンジニアになるべく夢を持ってこの大学に入ってきた,と思いきや、三人三様の事情があった。冒頭のインド航空?機内シーンからつかみは最高で、やがてアミールカーンさまが登場してからは、アミールの一挙手一投足、顔の表情、首の動き全てに気持ちが集中する。
2007年作品?え?アミールカーン何歳??学生役??驚きしかない彼の若さオーラ存在感。
原題3人のバカ,3人のバカもそれぞれ事情あれど、社会制度社会通念を変えようと最初から素朴な疑問や自論を恐れも忖度もなく学長につくつけれランチョ(アミール)
学長家では男子が生まれたらエンジニア女子が生まれたら医師と出生前からの決めつけ
学長がいうには、ランチョの実家は大富豪ファルハーンの実家は中流ラジュの実家は貧困層、、ランチョが富豪の息子??と引っかかりながらもみていくことになるが、
インドの学歴社会
男女差別
その入口にも立てない貧困問題と今も残るカースト
そもそも職業なんて選べない前提が当てはまる人も多い社会
ランチョが社会の仕組み,人々の社会既成概念を変えようとする、なんとかなる,うまくいく、突破できる,人生を楽し,という、彼もあり得ない這い上がりの人生を諦めない心で歩んでいる自分だけではない、周りを巻き込んでいく明快なすがた。アミールがそれを体現するさまは圧巻。
歌と踊りあり、爽やかで男女平等感溢れる恋愛(と反対に親に決められた権威主義拝金主義女性蔑視に基づく結婚)あり、もちろんインターバルあり,とインド映画のお作法もバッチリ。
2回ある結婚式,結婚パーティーのシーンも、ピアの姉であり学長の娘の出産も、瀕死のラジュの父親をバイクで救急搬送するシーンもラジュが救急搬送されアミールカーンがバイクで先導するシーンも、そして、おそらくロケ地ハ地名通りかと思うがらマナリ、シムラー、ラダックと車で旅していく旅の景色も最後のランチョの社会貢献,工学を学び社会に還元していくところまで、インド映画ベタな展開の中で丁寧に話を繋げ拾い物語をつないでいく、そしてインドの人のみならず世界中の人が人生に希望や価値を見出し勇気をもらえるベタさが絶妙。なんといってもこの明快明朗氏を実現できるアミールカーンの力。もう一度言うけどアミールカーンこの映画時違和感なく躍動する学生なるお年ではないよね、、、
泣いて笑って泣いて笑って自宅でみたので、ティッシュ一箱くらい泣き笑い笑い泣きさせてもらいました。
ドタバタだがしっかり感動できる
俗世間に挑む主人公達の奮闘は、素直に笑って泣ける。勧善懲悪のストーリーと言うべきか、観終えてスッキリ。
あと、インドの素晴らしい景色の中、赤のボルボのSUVは映えた。ラストシーンの湖も幻想的で、インドのイメージが変わった。
合言葉は「うまーく いーく」、元気のおまじないだ。使わせていただこう!
長いが楽しめる。
DVD で試聴。半分のところで休憩時間もあるほど長い。でも、DVDで少しずつ見たが、それでちょうどいいかんじ。
難関大学に入学した3人。
本当は写真家になりたい。
家が貧しい。
金持ちの使用人だが勉強できるから金持ちの名前で入学。
それぞれに背景がありつつも学生生活を満喫する。
10年後、その1人に会いに行くも、田舎の教師と科学者になっていた。
友情と愛情と絆。それを感じることができる作品。
学長の教育方針と学びたくて来ている学生の方向性も考えさせられる。
戦略的愚直
(偏見や憶測があります。この映画やインド映画を好きなかたは読まないでください。)
何年も、いや何十年もまえからつぎはインドがくると言われていてインドのファンドや関連ETFを試したり検討したひとは多いだろう。
インドは00年来経済成長を維持している。数年で日本のGDP(世界3位)を追い越すと言われ、人口においても中国の14.3億人に対しインドは14.1億人(2022)で、はやければ来年(2023)にも中国を抜いて世界一になると言われている。
ざっぱくな感慨だが、国の興廃は国民の性格にあらわれる。たとえば毎日SNSに日本人は堕落したという趣旨の発言が多数あがり、個人的にはそれに賛同してしまえるが、その法則を適用するなら勃興を続けるインドは健全になっていかなければならない。
が、伝わってくるインド社会はいつも壊乱している。むろんインドへ行ったことも住んだこともないにんげんが限られた情報にもとづいて言っているに過ぎないがロイターでも共同でもAFPでもインドの話題といえばいつもすべてがrape。どうなってんだ──っていうくらいrape事件とその抗議運動の報道しかない。
またインド映画にはアートハウスやカウンターカルチャーに属する映画がまったくない。すべてが“盛った”設定のブロックバスター映画になっている。むろん政情ゆえの理由もあるだろうがわたしたちはインド人の“盛っていない”市井の生活環境をほぼ知らない。ボリウッド内の景観とプリヤンカチョープラーをインドだと思っている輩だっているかもしれない。
カウンターに属する映画がないということは(簡単にいえば)自国民を悪く描く映画がないということだ。主人公は無垢で女たちは清らかで勧善懲悪が為される。
だから(悪く言えば)「おまえらこんな善良なにんげんじゃねえだろ」と思うのである。
わたしは日本人が善良なにんげんではないことを充分知っている。それは日本映画の品質と内容に如実にあらわれている。だがボリウッド映画はインドの内実をまったく伝えてくれない。ボリウッドはいつでもどこでも正義の男と心の清らかな女が勧善懲悪をおこなう映画になっている。
だからボリウッドはうさんくさい。
じぶんとて踊るマハラジャのようになにがなんでも踊り倒して圧倒するボリウッドパワーが解らないわけではない。だが一方に内省的な映画があっていい。冷静に自国を見つめ直している映画があっていい。上位GDPの文化圏にはかならず独立orリベラルな自主製作が存在する。中央と逆の意見を持った創作がある。
──というわけで多数の人々の共感をえてベストにもあがる『きっと、うまくいく』だが、個人的には全編がうさんくさかった。
とはいえ本作も他のボリウッド映画も基本的に熱意や良心によってつくられていて、がんらい扱き下ろされるような映画ではない。
見識の分かれ目は“愚直”をどう見るか──による。
世界中に旋風を巻き起こしている「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」。グッドドクターの弁護士版という感じ。良質なドラマだが個人的には演技者が演じる“愚直”や“障害”には白ける。
日毎SNSやTiktokにヨンウとグラミの挨拶がかわいいとの声や動画があがる。が、わたしにとってパクウンビンは充分すぎるほどわざとらしい。なんならグッドドクターのFreddie Highmoreもチュウォンも山崎賢人もわざとらしい。スリングブレイドのソーントンも7番房の奇跡のスンリョンもわざとらしい。マラソンのチョスンウもそれだけが僕の世界のジョンミンもわざとらしい。
絶対的愚直や知的障害は座頭市の勝新太郎やI Am Samのショーンペンみたいにものすごくうまくないとぜったいムリ。──だと(個人的には)見ている。
そもそも世界は上面ではわからない。
たとえば、戦争で打ちひしがれた気分を慰めてあげたかったのでウクライナ人を招いてパーティーを開いた──という表向きの体裁にたいして、じっさい呼ばれたのは未成年をふくむ女性だけで、日本側の参加者は全員年配の社長や重役たち。パーティーの真の目的は愛人契約や体を引き換えにした仕事の斡旋などだった。
──そのパーティーの模様を撮った映像には泣いているウクライナ女性を励ましてあげる日本人の様子しか映っていなかった。ので、戦争で傷ついたウクライナ人を慰めているのだろう──と好意的に解釈できますか?
リテラシーとは疑い深さやひねくれ度のことだ。
わたしは疑い深くひねくれたにんげんなのでインドで工学をめざす学生たちがこれほどまでに愚直で純朴とは思えなかった。笑いがグーグルアシスタントの駄洒落レベル。高揚と転落がないたあかおにのように童話的。なりふりかまわない圧倒的クサさ。
──
日本の「かわいい」とは自愛と“同調を誘う身悶え”のことだ。まいにちまいにちSNSやTiktokにかわいいが並ぶ。かわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいい・・・並ぶとじぶんが好きになれ共感も得られる。
純粋なもの、たとえば猫を好きなとき、かわいい発言者の健やかな人間性も伝わる。かわいいと言ったときの“好ましさの醸成”に無自覚なにんげんはいない。猫動画にかわいいと言い野良に同情を寄せると発言者は完全にいい人になれる。逆張りをするような奴でも「猫なんか大っ嫌い、蹴っ飛ばしたいわ」とは言わない。そんな猫のような雰囲気がこの映画にはある。つまり『きっと、うまくいく』を嫌いと言ってしまうとレビュアーにマイナスイメージがもたらされる──のである。
そんなこの映画の気配がきらい。
・・・とはいえ、ひねくれ者のこまっしゃくれた見識を乗り越えるばかばかしいほどの熱量があったのは確かですw。
All is well!
アマプラにて初めての鑑賞。社会の中に隠れてる問題をコミカルにリズミカルに訴えている素晴らしい作品だと思った。インド映画とあって3時間の長時間映画だったが山場が多くあっという間だった。
All is well〜すべてはうまくいく〜前向きになれる不思議な呪文♪是非子どもにも見せたい映画だと思う。
All is well〜うま〜くいく〜。呪文♪
内容は、舞台はインド国内随一のICE工科大学時のクラスメート3人を主体とした思い出話と10年後再び会う事を約束した事で現在の関係も再び取り戻そうと3人の内の1人(ランチョルダース・シャマルダース・チャンチャル)を探す話を全体の物語として青春、勉強、仕事、社会に対して問題を突きつける映画作品。好きな言葉は『うま〜くいく』映画🎬の中で終始唱えられている呪文の様な言葉で、言葉による具現化効果としての安心する言葉としての表現が爽やかで効果的でした。『映画と違うんだぞ!』この言葉も映画の中で印象に残った。宿敵の学校長が娘に忠告する言葉。映画の中での映画批判は思い切った台詞回しをするなぁと驚いた。好きなシーンでは、冒頭の飛行機を仮病を使って緊急着陸させる場面。2回観ると親友との出逢いによって価値観が変わって影響されたんだなぁと思わされる所が良かった。人生は競争だ!といわれる社会問題にアンチテーゼとして楽しく生きる事を伝えたいのだろうと思いました。やれば出来るとの根底を流れるメッセージでは、絶望感を払拭する事は出来ないので残酷な現実を見る事を解決できる視点の表現が少しでもあれば深みが出で良かった様に感じます。本作品はインド映画🎞特有のダンスが濃すぎる事もなく物語の流れを遮らないので非常に見やすく、喜怒哀楽を随所に織り混ぜ観客を飽きさせない様に魅せる3時間の末の大団円!この手法は素晴らしい。随所に流れる心象表現のピアノの音がうまい具合に物語盛り込まれていた所も良かった。絶望の音はやっぱ『ガーン』ですねぇ。それにしても3時間という長時間を感じさせない山場がとても良かった。何か凄いものを見せられた様な気になる映画でした。
競争社会の片隅の天才
全くの初鑑賞です。広島市映像文化ライブラリーは、今度は週末のみインド映画大会。
インド映画らしく長い。と、海外上映を前提とした配慮に乏しく、各国の「意識高い系」の方々からはクレームがつきそうなエピソードや表現も連発の前半戦です。
コレがコレがコレが。
ランチョーの正体の謎。以降は、やたら盛り上がる気分。前半戦では、ちょっとやり過ぎだよ、等と共感出来なかった3人のアホさ加減も忘れてしまい。
で、ラスト一時間の破壊力ですよ。インドですよ。前振り回収の連発でフルスイング演出。いかにもインドですよ。出産シーンから mm→cm あたりまでは、涙を誘うシーンを畳み掛けて来ます。
コレがあってのバジュランギでありパッドマンなんですね。最近は今ひとつですが、また泣かすベタな物語り、期待してます。
わかりやすく 良い映画だと思う。 学生の時の親友を探し出して、 オ...
全366件中、41~60件目を表示