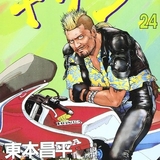グリーンブックのレビュー・感想・評価
全946件中、1~20件目を表示
何もかも正反対な2人が人種差別を乗り越えながら変化していく実話を基にしたロードムービー
必死に理性を保ちながら生きている
孤独な天才ピアニストと
そのピアニストのコンサートツアーに
用心棒兼運転手を任されることになった
必死に今をありのまま生きている主人公。
性格、人種、生活すら正反対な2人が本気でぶつかり合い
人種差別を乗り越え、固い友情が芽生えていくお話し。
笑えるところもあり、じんと心が温まる
素晴らしい友情を実話を基に描いている。
人種差別の問題は本当に辛い。
奴隷制度、アメリカ南部の黒人差別問題。
グリーンブックというものがあったことは知らなかった。
そんな真っ只中
敢えて人種差別に立ち向かう
彼ら(先人)のとてつもなく強い勇気と行動が
現在に繋がっているのだとわかり
とても考えさせられた。
勇気ある行動は人の心を動かす。
差別は会社やコミュニティなど小さなところから地域や国など大きなところまで、
なくなることは難しいかもしれない。
黒人だから、白人だから、イタリア系だから
〇〇なんだと決めつけることは
差別している事と同じだと気づかされた。
私自身も知らぬ間に、偏見や決めつけるような凝り固まった思考になっているところがあると思う。
個人、1人の人として、向き合い理解を深め、尊重できる人になりたいと思った。
人は何かがあって心を閉ざすことがある。
常に冷静でいて、楽しそうではなかった天才ピアニストだが、
主人公と心に触れ、段々距離が縮まり
感情を出せるようになっていった。
そして最後、楽しそうに演奏する姿はいつにも増して素敵で輝いていた。
人は人との心の交流を通じて閉ざされた心も開くことができる。相手を想う行動は相手の心に伝わる。
音楽は差別も関係なく人の心に伝わり、素晴らしいと感じさせてくれた。
最後のシーンは色んな愛に溢れていた。
人種差別を考えさせながら
友情や愛に心温まる映画。
ヴィゴ・モーテンセンか!??
車内の前後の位置関係が、まったく異なる二人を優しく近づける。
〇作品全体
生まれも育ちも、人種も、性的嗜好も、何もかもが異なるトニーとシャーリー。旅の序盤、すでにトニーは妻ドロレス宛の手紙で「シャーリーとはウマが合いそうだ」と綴っている。しかし、黒人に対して差別意識を持つトニーにとって、シャーリーと長時間同じ空間に身を置くというのは、やはり簡単なことではなかったはずだ。
そんな中で、ひとつ印象的なアクセントとなっていたのが、車内での“前後”の位置関係だった。
旅の大半を車内で過ごす二人の会話は、必然的に前席と後部座席という“前後”の構図になる。この位置関係では、肌の色や所作といった“育ち”の違いが、視界に入らないぶん薄れていく。たとえば、膝掛けを上品にかけるシャーリーと、人の分のサンドイッチまで食べてしまうトニーの「育ち方の違い」は、カメラを通せば一目瞭然だが、二人にとってはお互いの視界に入らない。後部座席のシャーリーから見れば、トニーが「不衛生」に食べるフライドチキンの姿も直接目に入ることはない。
視線を合わせないからこそ、真正面で対峙する緊張感が和らぐ。相手の許容できる部分はそのまま受け入れ、許容できない部分については本音を出して衝突することもできる。行く先々で「黒人であること」を突きつけられる世界で生きるシャーリーにとって、その空間は肌の色に囚われず、しかも一人ではないという点で、初めて心を開ける場所になったのではないかと思う。
トニーにとっても、見えているのは前方の景色とバックミラーだけ。話すとき、人種を意識するような視線のぶつかり合いはほとんどない。すぐ頭に血がのぼる性格だが、用心棒としての働きぶりや、家族との関係を見る限り、自分勝手な人物ではないことは明らかだ。
少し主観になるが、映画作品において「嫌々仕事を引き受ける」動機は、ネガティブな事情に基づくことが多い。家庭に問題がある、過去に過ちを犯した、などだ。本作でもトニーが「やりすぎた」ことで仕事を失ったという背景はあるが、最終的に旅に出る決断をしたのは、ドロレスの承諾があったからだ。順調な夫婦仲をより強くする、というポジティブな物語線が存在する点が好ましい。そして、トニーがただの乱暴者ではなく、“家庭に責任を持つ男”であるという描き方にも好感が持てる。
話がやや逸れたが、トニーが「2時と10時でハンドルを握る」と語る姿勢には、責任感と、それを時折裏切るようなユーモアが込められている。この運転席という位置こそが、彼のキャラクターと物語のバランスをとっていたように思う。
そもそも二人が対面で視線を合わせるシーンは、車外でさえ稀だ。レストランではシャーリーが新聞に目を落とし、手紙の書き方を教える場面でも、シャーリーは横を向いているか、トニーの周囲を歩いている。宿泊時の会話も、ベッドに横たわりながらのものだった。
このように“ひとつクッションを置いた”距離感のある会話が積み重なっているからこそ、真正面から視線を合わせて交わす言葉には、大きな意味が宿る。たとえば、石を盗んだトニーをシャーリーが咎めるシーン、あるいは浴場で警察を買収した後の駐車場のやりとりがそれにあたる。心の距離を縮めるときは目線を外して柔らかく、ぶつかり合うときは真正面から――。この映像的な緩急が、二人の関係の構築に欠かせない要素になっていた。
Wikipediaを覗いてみたら、この映画が「白人の救世主」ものの典型だとする意見があった。確かに、その指摘も理解できる。ただ、そう断じきれない感覚もある。なぜなら、二人が車内で“前後”に位置し、肌の色や所作が直接的な意味を持たない空間に身を置いていたからだ。その空間においては、“誰が救うか”ではなく、“どう向き合うか”が主軸となっていた。だからこそ、自分はこの映画にただの感動以上の何か――静かで強い友情の物語として、強く惹かれたのだと思う。
〇その他
・終盤、黒人が集まるレストランでシャーリーがピアノを弾くシーンがすごく良かった。孤独から脱却する一歩、みたいに映るし、今までシャーリーがやってきたことは間違いじゃなかった、といような肯定感もある。
理解し合う映画と、理解し合える関係になれた、そんな気がした映画でした。
おっさんには、オスカーの凋落と打算しか本作には見いだせなかったよ。
去年のアカデミー賞はマイノリティ、ダイバーシティヨイショの極端な過敏反応のせいで、クソみたいな同人誌映画「シェイプ・オブ・ウォーター」が受賞した。
もちろん前向きに見ると、「初の怪獣映画のオスカー受賞、イエイ」といえなくもないが、ただ単に、オタクが会員層の大部分を締め、「難しい」映画を理解できなくなったとも言えなくない。
そんなこんなのアカデミー賞の今年の結果はどうかと言うと、案の定の、会員があたかも全員一斉に集まって、消去法で決めたかのような、各部門の受賞結果。
もはや映画の内容、映画のデキには目を向けず、マイノリティ、ダイバーシティヨイショだけが選考理由。
結果、あげるべき人にあげてないくせに「ダイバーシティ」だとほざきやがる。
アカデミー賞は、業界人による、内輪の賞だが、もはやこんなももらって嬉しいか?というほどに、権威は失墜したと思う。
そんなことがはっきり見えたのが、この
「グリーンブック」
・
・
・
「既視感」というには、あまりにも退屈すぎる。ここで繰り広げられる物語は、表面上で起こったことしか見えない。というより、見せていない。想像力の欠如とでも言おうか、登場するキャラクターの背景が全くと言っていいほど、表面的だ。
ああ、脚本家の一人に、主人公の息子がいるからか。
もちろん、彼にとって父親である主人公は「ヒーロー」である。だがあまりにも物分りが良すぎる。まるで、事の流れに逆らわないように。
ドクに、「自分にしかデキないことをしろ」、というが、そんなキャラだったか?
そもそもドクが天才なのは誰でもわかるかもしれないが、彼がそこまでドクに「仕事以上」に心を通わせるのがわからない。
手紙?手紙の反応がトニーに戻ってきた描写はない。
plainとplaneのしょうもない話はともかく、主人公の「美しい平原広がる南部ツアー」の結果が黒人と仲良くなっただけなのも、ロードムービーの体をとってるくせに、つまらなすぎ。
ドクのほうも、全くと言っていいほど、ペラペラのキャラクター。
ちょっとだけホモネタ入れちゃう?とか、どうせ、そんなノリだろ?
南部に行く理由も、「勇気ある行動」で片付けられる。
勇気を示す理由は何よ?そして、そもそも散々引っ張った兄貴の件はどうなったんだよ?
つまり、こういう設定だったら、オスカー取れんじゃね?こういうシーン入れときゃオスカー取れんじゃね?ということしか考えていない映画。
グリーンブックというタイトルも、止まった場所に何かあるわけでもなく、地域性だって、ケンタッキー・フライド・チキンだあ?子供の映画か。(当時のクソ不味いアメリカのKFCをニコニコ食べる二人をギャグにしているのかもしれないが)
「グリーンブック」ってタイトルつけときゃ、アイロニックな感じが出るでしょうみたいなのりだったんだろうが、全く機能していない。
クライマックスに、黒人で溢れるBARでドクの演奏するシーンが有る。トニーが黒人限定BARに入るところこそが、本当は一番ドラマなはずなのだが、そこはお前ら、スルーかよ。
トニーが黒人限定なBARに入る、これこそまさに「『逆』グリーンブック」。
これで評価されるならまだ分かる。
追記
唯一の笑いどころは、銃を実際に持っていたところだけ。だが、これだって相当やばい「ネタ」なのに、もっと高いレベルの笑いにまで昇華できたはずだ。
結果、黒人をダシにして、主人公がお金を稼いで、物分かりのいい性格になり、手紙を書くのが上手になりました、っていうだけの映画。
それでも、僕たちは手紙を出さなければいけない。
初めて鑑賞したとき、あまりの“良さ”にやられ、その日のうちに2度目の鑑賞をキメた。それくらい好きな作品だ。
改めて再鑑賞したので、僕の心のうちをうまく説明できるかどうかわからないが、とにかく感想をつらつらと書いてみる。
おじさん2人の珍道中ともいうべき物語は、どこかハートフルで、どこかコミカルで、どこかデカダンス。個人的に心に残るのは、「手紙」というモチーフを通じて描かれる“コミュニケーションの郵便的不安”だった。
“郵便的”とは何か。フランスの哲学者ジャック・デリダによる概念だ。ここでは「意図したものが届くかどうかわからない」という意味で使用していく(概念として間違ってるかもしれないけど…細かいことは置いておく)。
郵便は差出人が郵便局を預ければ、それは局を通じて受取人に届けられる。しかし、郵便は確実に届くのだろうか? 誤配の可能性は確かに存在し、郵便が届くかどうかはわからない。そして何かの行き違いでどこかに行ってしまえば、永久に失われるのである。
それは手紙などの郵便物だけでなく、コミュニケーションも同様である。僕すなわち主体が発する言葉を、受け手である客体は、主体が意図した正しい意味で受け取るだろうか。
言葉という媒介を通している以上、主体の意図した意味から大きく外れ、誤解が生じることは珍しくない。というか宿命とすら言える。コミュニケーションは非常に脆いシステムの上に成り立っている、極めて紛失されやすい郵便なのだ。
本作ではトニーが妻に、旅の無事を知らせる手紙を出す。それは単なる手紙ではなく、物語のテーマを内包する“装置”でもある。つまり本作の手紙は、コミュニケーションの郵便的不安、すなわち“届くかどうか、伝わるかどうか”という主題を象徴している。
トニーがドクターにフライドチキンを勧め、「黒人のソウルフードだろ?」と語りかける。ドクターは苦虫を噛み潰したように顔をしかめる。トニーに悪気があったわけではない。無自覚に、本当に単純に、美味いからチキンを食えと言っている。しかし、差別に敏感なドクターには、その意図は届かない。
こうして、トニーとドクターはいささか、コミュニケーションの郵便的不安に翻弄され、すれ違いを見せつつ、誤解と理解を繰り返しながら旅を続けていく。ところが、その誤解と理解を繰り返す、という点に、僕たちがこの修羅のような世界で健やかに生きるためのヒントが現れているように思える。
トニーとドクターが対話するうちにお互いを知り、友情を芽生えさせていく。コミュニケーションは届くかどうかわからない不安定な手紙だ。でも、差し出してみなければ絶対に届かない。痛みが伴うかもしれない。溝ができるかもしれない。それでも、僕たちは手紙を出さなければいけないのだ。スクリーンに映る2人は、観客にそんなことを語りかけてくれる。
「寂しいときは自分から手を打たなきゃ」「才能だけでは不十分だ。勇気が人を変える」「黒人でも白人でも人間でもない。教えてくれトニー。私はなんなんだ」
監督のピーター・ファレリーやキャストたちが差し出した手紙は、僕にしっかりと届いた、と思う。このレビューという手紙も、誰かに届くだろうか。
複雑に入り組む人種差別
粗野なイタリア系白人と知的な黒人のロードムービー。あえて黒人差別の激しい南部へコンサートツアーに行くシャーリーの決断は、それもまた偏見をなくす一歩であるからだが、そのコンサートに来るのは、「先進的」だと思っている白人ばかり。黒人の音楽に理解を示す自分は差別主義者などではないと彼らは思っている。しかし、地元の黒人にはめもくれず、この構造自体が差別を温存してもいる。(スパイク・リーが過激な発言をよくするのは、そういう構造に利用されたくないという思惑もあるのだろう)
白人であっても貧困で被差別的な扱いのイタリア系のトニーは黒人に仕えるということに複雑な感情を抱き、黒人であっても知的で裕福に暮らすシャーリーは黒人コミュニティでも馴染めない。人種差別がとても複雑に入り組んでいるのである。
その複雑に対して、やや安直すぎる結末ではないかとも思うが、気持ちよく観られる作品だ。ただ、気持ちよくなっただけでは、「先進的」だと思いこんでいる南部の白人と変わらない。差別の複雑な背景を理解するよう努めなければならない。
祝作品賞。旅が育む友情、笑い、音楽すべて最高!
よく指摘されるように、仏映画「最強のふたり」を観た人なら多くの共通項をこの「グリーンブック」に見出せるだろう。白人と黒人、教養も資産もかけ離れた2人が、カルチャーショックを経て確かな友情を築いていく。どちらも実話ベースだが、創作したかのように好対照な凸凹コンビだし、だからこそ奇跡的に生まれた絆が一層輝く。
ロードムービー、バディもの、喜劇、音楽といった王道のジャンルと素材に、人種問題やLGBTという社会派の味も加わり、しかもそれぞれの要素が邪魔しあうことなく、絶妙なハーモニーで口当たりの良い逸品料理に仕上がった。アカデミー賞の作品賞も納得だし、ピーター・ファレリー監督の手腕も見事と言うしかない。
車中でトニーがドクにフライドチキンを強引に薦める場面。ラスト近くでトニーの妻ドロレスがドクに伝える言葉。思い出すだけで頬が緩み、同時に胸がじんわりと温かくなる。
この映画は観客を選ばない。分かりやすく楽しく、魂のうねりに触れられる傑作
この映画は観客を選ばない。誰もがハードルなく楽しめて、10人中9人が「本当にいい映画だったね」と胸を熱くさせて映画館を後にすることができる。そんなわかりやすさと可笑しさ、そして観客の心をグッと引き寄せる魂のうねりを併せ持った作品なのだ。
冒頭ではちょっと強面なオヤジに見えた太鼓っぱらのヴィゴ・モーテンセンと、それとは正反対の気高さを持つ黒人ピアニスト役のマハーシャラ・アリ。肌の色も性格も育ちも正反対の彼らが、旅の過程で徐々に互いへの敬意と友情を結んでいく。そこに折り重なるエピソード一つ一つがまた、なんとも言えない輝きを放ち、胸いっぱいに余韻を広げていく。
このロードムービーは二人の目線の高さを同じくして、互いの立場に立って物事を見つめることの尊さを我々に教えてくれる。60年代を舞台にしながら、分断の顕著な現代世界に、普遍的であり微塵のブレもない力強いメッセージをもたらしてくれる傑作だ。
最強のふたりみたいなんかなってみてみたら
直接的な言葉や説明ではなく、シチュエーション、表情や演技で心情を表すことが多いこの時代の映画が好きです。
黒人の輪の中にも入れず、白人からは差別の中認めてもらうこともできないコウモリのようなドクを、モーテルで1人お酒を飲んでるシーンからも感じれました。
黒人は黒人のコミュニティで、楽しそうにしてるそうな姿をどう感じ、どう思いながら見てたんかなぁって。羨ましい気持ちか、差別を憎みながらも自分はこの人らとは違うって気持ちもあったんかなぁって。
なによりリップのキャラクターが、人間らしくてこの映画の魅力でした。
やんちゃな少年がそのまま大人になったような。
粗暴で口先はうまいけど嘘はつかないし、
本来プライドも高く人に媚びるのが大嫌いな性格だろうに、家族のためにはそのプライドも置いておけるような家族愛の強さも
まるで子供がみんながそうゆってるからってなんとなくしていた差別を、初めて自分が関わってみてその考えを改めれるとこも、
きっと教養はないのにいいものをいいと思える感性や素直さが、本当に魅力的だなぁって見ていて飽きず、リップのキャラクターを好きになっていけました。
奥さんもそのリップの良さも悪さも含めて、
愛してるんだなぁってのがわかるのがいいなと。
最後のドクと抱き合いながらした手紙のお礼がそれを物語ってるなと思います。
本人がうまくしてるように思っていても
ちゃんと見抜いてるとこや、
愛する人の未熟な部分も理解しながら
その成長や変化を嬉しく思ってる様子がみえて
恋人であり、パートナーであり、母親のような愛情は、きっと女性ならではですね。
いい奥様です。
長期での旅の仕事の承諾をして、寂しそうにそっぽむく姿なんか、すごく愛してることが伝わってきました。
最後にこの脚本が実話だと知って、
余計に心が温まりました。
いい映画をありがとうございます。
互いを知ることって大切ちゃなァ
差別の時代を走る二人の旅路
差別という重いテーマを軸にしながらも、物語の中心にあるのは不器用な友情の芽生えだ。
アングロサクソン社会の中で最下層と見なされてきたイタリア系の用心棒トニーと、卓越した才能を持ちながらも黒人であるがゆえに居場所を奪われ続けてきたピアニスト、ドクター・シャーリー。
生まれも価値観も立場も正反対の二人が、旅を通して少しずつ距離を縮めていく過程は、観ていて自然と頬が緩む。
特に印象的なのは、「スタインウェイでしか演奏しない」という強いこだわりを持つシャーリーが、トニーの勧めでバーのピアノに向かい、上流階級ではない黒人客の前で楽しそうに演奏する場面だ。
それは彼が自分の殻を破り、他者と向き合う覚悟を決めた瞬間でもある。
人と信頼関係を築くためには、相手に理解を求めるだけでなく、自分自身もまた変わる必要がある——そのことを、このシーンは静かに、しかし強く教えてくれる。
重苦しくなりがちなテーマを扱いながらも、温かさとユーモアを失わない。
『グリーンブック』は、違いを乗り越えることの難しさと尊さを、肩肘張らずに伝えてくれる良作だ。
クリスマスに観たくなるヒューマンドラマ
旧き良き80年代のアメリカと黒人差別を扱った実在人物のドキュメンタリー映画。
対照的な移民白人用心棒と黒人ピアニストのロードムービー。
当時のアメリカの世相や移民や同性愛に黒人への差別などが知ることが出来る。
「グリーン・ブック」という”黒人専用宿泊ガイドブック”はこの映画で初めて知った。
テンポ良く物語は進み、なぜカーネギー・ホールに居住する著名ピアニストが人種差別が強い州にツアーに出向くのか?
物語が進むうちに2人の価値観の違いから相手を尊重し、価値観を受け入れて(白人側が)変わっていくのが良い。
白人主人公の粗暴な振る舞いを諫める知的な黒人ピアニスト。
かなり好きなシーンが多い。
各州で全くそこに居住するアメリカ人の気質が違うことに「日本国土並みに州が広く、州がの集合体=アメリカ」がよくわかる。
半分は移動シーンだが、スパイスとして様々なトラブルに遭遇する。
ピアノ演奏シーンは神秘的でもあり、ミュージック映画としても秀逸。
クライマックスのJAZZ演奏者とのセッションでは楽しそうに演奏するシーンは音楽の素晴らしさを再認識させられる。
また白人主人公が愛する妻への手紙に黒人ピアノマンが代筆(口述)して、淋しさを癒す素敵なシーンがある。
視聴後「最高の人生の見つけ方」と同じ気持ちになるのは「お金持ちだけど孤独な黒人ピアノマン」と「親族多数でクリスマスを祝う白人主人公」の場面に黒人ピアニストが現れて妻の心からの御持て成しのシーンがグッとくる(知的で魅力的な手紙の相手だと理解しているから)
最期は両主人公がハッピーエンドで〆るのが視聴後暖かく誰かに親切にしたいという気持ちになる。
一度見てBlu-rayを買ってしまった。
身を守るための人種差別
差別する側の主張が聞けて斬新でした。いじめてやろうとかそういう単純な話ではなくて、コンサートで呼んだホテルの主張としてはお客様に配慮して差別しておかないと、今度はホテルの評判が下がるので、仕方なく差別してるとのことのようでした。黒人の方は長いこと戦って、犠牲を払ってやっと今の地位を手に入れたんですね。我々東洋人はまだこれから戦って、血を流して犠牲をたくさん出しながら戦い切るまでは差別され続けて当然というふうに思われてるのかもしれないと気づきました。終盤主人公たちもおまわりさんは不当な仕打ちをしてくる生き物だと学習し、会ってすぐ見た目でそう判断していたし、、、差別や偏見は人間の身を守るための防御反応と結びついているんだとしみじみ感じました。
肩の力を抜いて観賞すれば良質なコメディ
事前情報から、伝記映画として観るには難があるような印象を受けたが、実際に観賞してみれば、娯楽映画として十分に楽しめた。対称的な二人が旅を通じて変化していく様が痛快に描かれている。緊張の場面と緩和の場面がテンポよく切り替わり、飽きることなく最後の最後まで楽しめた。アカデミー賞という権威的な看板はこの作品には不要だったのかもしれない。
粗野と優雅の完璧なハーモニー
一言で言うとタイトルの通り、二人が少しずつ調和していく旅と友情の物語だ。
二人を演じたヴィゴ・モーテンセンとマハーシャラ・アリが最高で、「粗野なトニーと優雅なドン」のコントラストから繰り出されるスットコドッコイなコミカル・ロードムービー。
で、非常に満足したわけだけど、なんか変に黒人差別の描き方に苦言を呈してるレビューを見かけて逆に驚いた。
もちろん、ベースとして人種差別が描かれるわけだけど、「可哀想な黒人を白人が助ける話」みたいな見方しか出来ないのは勿体ないとしか言いようがない。
という訳で長くなっちゃうけど解説めいた事を書く。
作中でドン・シャーリーが抱える思いは複雑だ。ドンは小さな頃からピアノに親しみ、才能を開花させて一流のピアニストになった。
彼が住むNYはリベラルの最先端で、街には黒人以外にもあらゆる人種が往き来し、アジア系の姿も目立つ。
カーネギー・ホールの上でインド系のサーバントにかしずかれ、王のような椅子に座るドンは物腰柔らかく優雅で、知的で、「ザ・上流階級」。
そんな彼が、南部へコンサートツアーに出るという。リベラルで清潔で安全なNYから、差別の色濃く残る南部へ。黒人だ、という以外に彼を定義する尺度を持たない土地へ。
それは一体何故なのか?それこそがドン・シャーリーの抱える複雑な思いに直結する。
一方、橋を渡ったブルックリンに住むトニーはイタリア系移民で、都心郊外の治安の悪い地域出身らしく、腕力と小狡さを活かしたその日暮らし。嘘ではないが真っ当でもない巧みな知恵で金を稼ぐ。ボクシングやってないロッキー、喋りが達者なロッキーである。
ガッツォさんみたいな、イタリア系を仕切ってるオッサンも勿論いる。なんてことを考えてたら、ホットドッグ早食い競争の相手の名前が「ポーリー」でちょっと笑ってしまった。
イタリア人街の結束は強く、何かあるとすぐ集まる。その中心はトニーだ。もちろんお昼はミートボールスパゲティ。
ブルックリンで生まれ、ブルックリンで育ち、「イタ公」と呼ばれ、気に入らなければ殴り、同じ境遇の仲間とつるむ。きっと息子たちも自分と同じように生きていく。その事に何の疑問も違和感もない。それがトニー・リップだ。
そんなちぐはぐで対照的なな二人が、「旅」という密接な時間を共にすることで生まれていくお互いへの理解が面白いのだ。
「黒人」も「イタ公」も差別を受ける側だが、二人は全く違う。ドンは知的で冷静な振る舞いを通して、一人の真っ当な人間として扱われることを期待し、トニーはある程度の事には目をつぶりつつ、限界を超えれば暴力で解決する。
「黒人の好物はフライドチキン」に抵抗するドン。「イタ公はミートボールスパゲティ。その通りだ」と開き直るトニー。
「旅」は予期しない一面も覗かせる。危ないから一人で出歩くな、とトニーに言われていたドンが一人で向かった先は、今風に言うならハッテン場だ。
見た目は黒人、だから白人世界には溶け込みきれず、中身はリベラルのインテリ、だから黒人世界では居場所がないと感じ、性的マイノリティ、だから「私は男だ」という帰属さえ脆い(当時の感覚ですよ。あくまでも)。兄と疎遠になった真の原因もその辺りにありそうだ。
自分は一体何者なのかと問うドン。自分はこういう人間だと説明できるトニー。
魂の安らげる国を目指して、この国を変えようとしている大統領に望みを託して、自分もその変化に貢献するために、あえて南部へと旅立つ。勇気だけが世界を変えられる、それがドンの旅の理由だ。
心を映し出したような土砂降りの雨の中、理性の下に隠してきたドンの叫びは、ドンにとってあまりにカッコ悪く、本当だったら誰にも見せたくない姿だっただろう。だが、「旅」はそれを許さない。
一夜明け、不用意な外出を謝るドンにトニーがかけた一言がシンプルなだけに心に響く。
「人間は複雑だからな」
多分この一言が、二人の絆を更に強める切っ掛けになったのだと思う。「ありのままで良いよ」という態度が、弱っているときどんなに有り難いか。
クリスマス前に家に戻るべく、雪道を走る車を警官に停められる。この旅二度目の出来事で、トニーも辟易している。
この警官が優しかったことをご都合主義だ、と思う?これはクリスマスの奇跡。パワーストーンの力と合わさって、二人に舞い降りた祝福なのだ。
最後に。トニーの家族の前に姿を現したドンは、世界を変える為ではなく自分の為に、勇気を出して行動した。「淋しいと思った時は自分から行動しなくちゃ」というトニーの言葉を信じて。
そしてその勇気は、旅の間送り続けた「交響曲とブリキ太鼓のハーモニー」を心待ちにしてくれていた人の感謝の言葉、という最高のクリスマスのプレゼントを与えてくれたのである。
みんなに見て欲しい映画…トニー好きだなあ
すごく良かった…
トニーがいいのよ…ドクとの友情があったかいんだよね。
久しぶりに涙腺こわれたなあ。
レストランのピアノのシーンとか、最後にドクが訪ねてくるシーンとか、自分史上最高にジーンときました。
道徳の授業で流してほしいなー
全946件中、1~20件目を表示