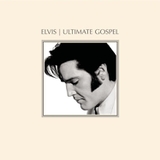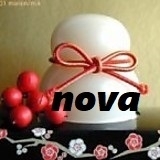邦題にある「身終い」を辞書で引いてみたが、見当たらない。「身仕舞」「身じまい」であれば、身なりをつくろうこと。また、化粧して美しく着飾ること。身支度 (みじたく) とある。転じて「人生の身じまい」であれば葬儀会社のキャッチコピーなどに見いだせる。原題の直訳は「春の数時間」。本作を観れば、その意味するところも伝わるのだが、邦題が伝えたいことは、人生の最期をどのように迎えたいのか、何かを成し遂げておきたいことはあるまいか。そうした、人生の旅を終えるときへの身支度、身近な者の想いは、この邦題の語感と文字遣いなればこそ心に響いてくる。
47年間連れ添った夫は先だち、自宅に独り暮らすイヴェット(エレーヌ・ヴァンサン)。48歳になる一人息子のアラン(ヴァンサン・ランドン)は、長距離トラックの運転手だったが麻薬運搬に関わり18か月の刑期を終えたばかり。いまはイヴェットの家に同居し失業中の身だ。
イヴェットの暮らしぶりは、ある意味坦々としている。家の掃除、洗濯、食事づくり、ゆとりのある時間はジグソーパズルなどに興じたり、ジャムを作って親しい隣人のラルエット(オリビエ・ペリエ)にお裾分けする。アランが帰ってきてからは、家で食事をするがリビングとキッチンに分かれて座り、飼い犬が呼ばれる度に二人の間を行き来して食べ物をもらう。
その打ち解けあえていない空気感が、みごとなまでに漂う。テーブルのゴミをかき集めるイヴェットの仕草にも、失業中の息子へのちょっとした苛立ちが垣間見られる。そんなある日。アランは、イヴェットがスイスの尊厳死を仲介するNPOからの書類を見てしまう。がん細胞が脳にまで転移していて治癒の可能性はない。ターミナルケアの勧めを拒否して、自殺ほう助による尊厳死を選択していることを主治医から確認したアラン。
どうにか仕事に就いたが、張り合いのない毎日。見つけた仕事も辞めてしまったことで母子は激しく口論し、アランは家を出て隣家のラルエットの所に隠れてしまう。
イヴェットとアランの少ない会話のなかに、二人がどのような家庭の中で暮らしてきたのか。夫が亡くなった後、イヴェットはなぜ自殺ほう助での尊厳死を選択し、意固地なまでに遂行しようとするのか。母親の自死への決意を知ったアランの心の動きは?。その人情の機微が静謐(せいひつ)なときの流れの中で、不思議な体温を感じさせながら語られていく。
スイスの尊厳死を援助する団体の責任者が、イヴェットの意思を確認するため自宅を訪問した時の会話が印象深い。「あなたの人生は幸せでしたか?」と問う責任者に、イヴェットは、「人生は人生ですから」とだけ答える。投げやりな答え方ではない。亡き夫との関わり、アランとの関係、それらすべてを受け入れて歩んできて「いま」があるという誇り。
イヴェットの選択と決意に、賛否両論が生まれることだろう。だが、彼女の自律した選択と方法論を超えて、二人が最期の‟とき”に臨んでどうありたかったのか。人生を捨てたのではないことが、静かに深く心に伝わってくる作品だ。
監督:ステファヌ・ブリゼ 2012年/フランス/108分/映倫:PG12/原題:Quelques heures de printemps 配給:ドマ/ミモザフィルムズ 2013年11月30日(土)よりシネスイッチ銀座ほか全国順次ロードショー。






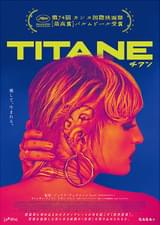 TITANE/チタン
TITANE/チタン 秋が来るとき
秋が来るとき ロダン カミーユと永遠のアトリエ
ロダン カミーユと永遠のアトリエ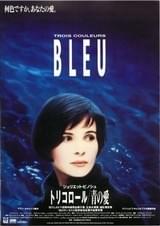 トリコロール/青の愛
トリコロール/青の愛 カサノバ ~最期の恋~
カサノバ ~最期の恋~ 愛と激しさをもって
愛と激しさをもって シャンボンの背中
シャンボンの背中 女の一生
女の一生 ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド