ドライブ・マイ・カー : インタビュー
西島秀俊、濱口竜介監督との対話で封印を解く カンヌ4冠「ドライブ・マイ・カー」を語る

例えば、映画を見終わった後、こんな思いに駆られることがある。「すぐに帰りたくない」。スクリーンから放たれた力を反芻しながら、ひとり当て所もなく歩いてしまったり、同行者がいるのであれば、時間を忘れて話し合ってしまう(往々にして、興奮のあまり立ち話となる)。そういう作品が、世の中には存在する。
濱口竜介監督作「ドライブ・マイ・カー」(原作:村上春樹)は、その例に漏れなかった。主演・西島秀俊へのインタビューを申し込んだ際、その吉報はもたらされてはいなかったが、妙な予感があったことは確かだ。7月17日(日本時間:7月18日)、第74回カンヌ国際映画祭授賞式において、日本映画初となる脚本賞、そして国際映画批評家連盟賞、AFCAE賞、エキュメニカル審査員賞といった独立賞の受賞が発表された。思わず拳を握る。いち早く同作と出合えたことの幸せを噛みしめていた。
西島へのインタビューは、7月4日に実施されたカンヌ国際映画祭壮行会イベント後に実施したものだ。無論、この時点では輝かしい未来を知る由もない。しかし、西島と対峙しているうちに「受賞」への期待が一層高まったことを、今でもはっきりと覚えている。(取材・文/編集部、写真/間庭裕基)

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
まずは映像化の経緯を簡単に説明しておこう。当初、プロデューサーの山本晃久氏は、濱口監督に「ドライブ・マイ・カー」とは異なる村上氏の短編小説の映画化を提案。しかし、濱口監督は方向性に悩んだ結果、かつて読んでいた1作を思い出した。それが「ドライブ・マイ・カー」(短編小説集「女のいない男たち」収録)だ。同作のテキストは「ハッピーアワー」製作時におけるワークショップの参考テキストとしても使用され「“声”について非常に真実とも思えることが書いてあった」という。濱口監督の「『ドライブ・マイ・カー』であれば、映画化をしたい」という思いのもと、企画が始動している。
「女のいない男たち」に収録された「シェエラザード」「木野」もモチーフとなって完成した“濱口流の物語”。西島は「1冊の台本を読んだ時の密度が、他の本とは全く違いました。気持ちの流れ、言葉の量――当然、演じる側は大変なことになる。でも、挑戦したくなるような本でした」と振り返る。
西島「『PASSION』『寝ても覚めても』など、濱口監督の作品は見続けていました。これまでの作品には『一見軽薄に見えるような人物が、実は深い事を考えている』『少し汚れているように見える人物が、純粋なものを持っている』『突然立ち上がる、人の計り知れなさ』『人と人が徹底的に話し合うことで人生の第一歩を迎える』といったものを感じていたので、今回の作品にも、それらは組み込まれる要素だろうと思っていたんです。村上春樹さんの原作にも、先入観が覆されるような瞬間がいくつも出てきましたし、それが濱口監督の作品になれば、もっと密度が深まり、強度を持った形で描かれていくのだろうなと思っていました」

そもそも西島は「中学、高校時代だったと思いますが、当時から爆発的な人気がありましたし、そこからずっと読んでいます」と語るほどの“村上春樹ファン”である。「イスタンブールの映画祭に行った時、そこで出会ったおばあさんに『村上春樹の新作は読んだ? どう思う?』って聞かれたことがあるんですよ。国も、年齢も超えていく普遍性と共感。その力を持った作家なんだなと実感しました」とエピソードを披露しつつ、濱口監督(共同脚本:大江崇允)の脚色について語りだした。
西島「濱口監督は、今まで近しい人間関係における『得体の知れないもの』『人が繋がれずに断絶するさま』を描いてきたと思うんです。村上春樹さんの原作にも、喪失感や、肉体的に繋がっていても心の部分で繋がることが出来ないというものがある。ここが濱口監督のテーマにも通じる部分だと思いました。でも、濱口監督ならではの部分があるんですよ。不思議なことに(原作から)全く外れているわけではないのに、きちんと濱口監督のモノになっています。断絶した先の希望なのか、喪失のまま終わらせないことが出来るのかということへの模索が感じられる。だからこそ、濱口監督が『ドライブ・マイ・カー』という原作を選んだことに納得がいくんです」

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
稀有な監督が日本に生まれた――濱口監督への尊敬の念はたえない。「2000年に『カサヴェテス2000』という特集上映があったんですが、僕はそこで人生が変わるほどの衝撃を受けました。その場にいらっしゃった濱口監督も同様の衝撃を受けたと仰られていましたね。年齢は僕の方が上ですが、映画館で会う機会が何度もありましたし、同じような映像体験を同時にしてきているという感覚があるんです。そんな方と再び出会い、一緒に映画を作れているというのが運命的ですよね」
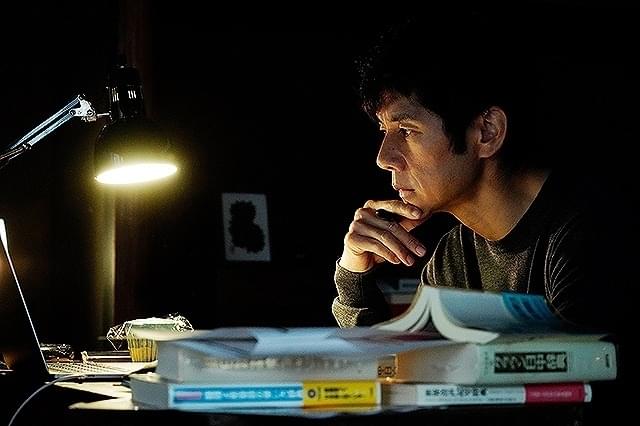
(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
念願の現場で挑むことになったのは、舞台俳優で演出家の家福悠介役。脚本家の妻・音(霧島れいか)が秘密を残したまま他界したことで、喪失感を抱えながら生きている人物だ。空き時間の全てを本読みに費やし、宿泊場所に戻ってからは、重要な要素となる“音”を聴き続ける日々を送った。
西島「脚本は常に変わっていました。でも、本読みの段階では非常に厳密なんです。『、』が『。』に変わると、それだけで間(ま)が変化する。楽譜のように、厳密なスピードも決められている。本番は変化してもよかったのですが、そこまでの過程では、常に更新をしていかなくてはならない。それをずっとやっていました。きつかった……と言ってはいけないのかもしれませんが、全ての時間とエネルギーを、作品のために注がなくてはいけない現場でした」

ブラッシュアップされ続けるテキストと向き合うなかで、濱口監督流の演出にも触れていく。繰り返される本読み、劇中では描写されない過去の光景に関してのリハーサル、質問に対してキャラクターとして答える作業――西島は「今後参加していく現場でも活かす」と語るほどの感銘を受けた。
西島「例えば『この質問に、家福はどう答えるか』というものについて。これに関しては(“西島秀俊”として)正直に答えなくてもいいんです。自分の考えではなく、質問に対する家福の答えですから。自分も考え続けていましたし、同じく濱口監督も考えてくれました。劇団の演出家の方々ともお話をさせて頂きました。劇中では舞台の公演が描かれますが『カメラで撮る舞台』というのは、いわゆる『中継映像』とは異なりますよね? そういうことに関する話し合いを、濱口監督は常に付き合ってくれたんです。自分ひとりで役を想像して、形作っていたら、もっと違う点からのアプローチになっていたはず。きっと“掴み切れなかった”と思います」

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
西島が言及した「舞台」は、特筆すべき手法で描かれている。それが「多言語演劇」だ。韓国、台湾、フィリピン、インドネシア、ドイツ、マレーシアからオーディションで選ばれたキャストが参加している本作では、9つの言語が飛び交っているのだ。
西島「本読みは『相手の“声”、テキストに注意を払って聞く』ということを繰り返していきます。それが多言語になると、脚本には各言語のセリフが記載されています。まずは話者の(きっかけとなる)“音”を確認して、その後に意味をチェックして翻訳、再構成してから頭の中に入れ込みます。それをひたすら続けるわけですから、日本語で本読みを行う以上に、相手の言葉を注意深く聞き続けるという作業になっていました。言葉を発する、聞くというプロセスで、最も手間がかかるやり方です。大変な作業でしたが、皆楽しんでやっていたと思いますよ。演じている側は、作品のテーマに繋がっているものを感じていたと思います」

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
劇中では、全俳優の一挙手一投足に見入ってしまう。なかでも、手話を用いるユナ役のパク・ユリムの芝居は圧巻だ。「ここまで感情が揺さぶられるとは思ってもいなかった」と打ち明けると、西島も嬉々として同調してくれた。
西島「ユリムさんは、相当練習されたようで、当然本読みも手話で行うわけです。そこでは感情を込めずに、セリフを手話で表現していく。やがて、ここに感情を込めていくと、ものすごくセリフが伝わってくるんですよ。(手話では)表情も大事な情報ではありますが、機械的に行っていたものが、ここまで変わってしまうものなのかと。とあるシーンでは、相対する形ではなく、僕が本人の目線で“手話を見る”場面があるのですが……これは一体何なのだろうなと。(意味の)伝わり方がすごかったんですよね。本当に素晴らしかったです」

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
話題はキャスティングへと転じていく。家福の愛車サーブを運転する寡黙なドライバー・みさき役の三浦透子、キーパーソンとなる俳優・高槻役の岡田将生、秘密を抱えたままこの世を去る家福の妻・音役の霧島――それぞれの思いを述べつつ、西島はある答えを導き出した。
西島「三浦さんはお若いですが、とても聡明で真っ直ぐな方。会話をしていても、下の世代と話しているという感覚がありません。岡田君は、とても純粋な人ですよね。(芸能界において)これほど純粋な心の持ち主がいるのだろうかと驚くほど(笑)。この映画の中で、個人的に印象深いのが、岡田君の独白シーンです。そこには彼の根っこにある“本当の純粋さ”というものが出ている。撮影に立ち会いながら『すごいことが起きている』と思っていました。霧島さんは、やはりミステリアスですね。女優さんは前に出て表現されている印象の方が多いのですが、彼女は感じられたことを心の中に1度留め置いて、そこから再び外へ出していくようなイメージがあります。撮影前から色々なことをお話させていただきましたが、ミステリアスな部分は失われないまま。そう考えると“役柄の根っこ”と近しい部分のある方がキャスティングされているのかもしれません」

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
やがて、西島は作品を支え続けたスタッフへの思いを打ち明けてくれた。
西島「通常は、照明の光が目に入ってしまうことがあります。それによって、目の前にいる相手の顔が見えなくなることも。車中での会話であれば、もう少し大きな声で話す必要性があったりもする。それは当たり前の話で、どうしても技術的に不可能な場合があるんです。でも『ドライブ・マイ・カー』では、そういうことが一切なかった。照明の高井大樹さんは、俳優の視界を遮るようなことはされませんでしたし、撮影の四宮秀俊さんは『本番、行きます』と言われれば、すぐに対応ができる。録音部からは『もう少し大きな声で』と言われたことは1度もなかった。小さな嘘の積み重ねを無くしていく。その結果、真実が映り込む。現場全体に『嘘をつくのをやめていこう』という意識がありました。演技の範囲が決まっていないのに、どこに移動してもいいんですよ。この点には非常に驚きました。美術、技術パートの方々には、頭が下がるばかりです。本当にすごい現場でした」
「ドライブ・マイ・カー」は「演技についての映画」といっても過言ではない。改めて、演技そのものについて思考することはあったのだろうか。
西島「『演技についての映画』というのは、(俳優が)非常に厳しいさらされ方をするものだと思っています。自分自身を断罪しなくてはならなくなる。僕は自己評価が高くないので、非常に辛らつな意見になってしまいがちですが……。自分自身への不安というものは、本来は自分で消化しなくてはならないものです。でも、濱口監督はそういうことに関しても付き合ってくれるような方でした」

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
濱口監督とのタッグは、ある封印を解くきっかけにもなり、俳優としての転換期を迎えることになったようだ。
西島「『ジョン・カサヴェテスは語る』『シネマトグラフ覚書 映画監督のノート』という本がありますが、濱口監督が読んでいらっしゃったんです。『西島さんは読みましたか?』と聞かれたんですが『僕はもう封印しました。もう読むことはないと思う』と答えました。でも、濱口監督は『読んでください』と。そう言われて十数年ぶりに奥底から引っ張り出したんですが、やっぱり素晴らしいんですよね。『カサヴェテス2000』を経て、20年ぶりに色々なことができたことが、僕にとっては本当に大きなことなんです。(本作への参加を契機に)昔はやろうとしてもできなかったこと、自分の好きな演技を、他の仕事でもチャレンジしてみようと思えるようになりました。求められていない場所でも、何か表現ができるのかもしれない――これは、僕のなかでは“既に始まったこと”です」

本作は、大部分の撮影を広島で敢行。東京、北海道、韓国もロケ地となり、物語は広がりを見せていく。カンヌでの称賛を経て、日本凱旋を果たすことになった「ドライブ・マイ・カー」。西島は「“今”の日本人が抱える気持ち、心の在り方というものが映っている」と説明し、その魅力を分析してくれた。
西島「コロナによる自粛期間、これはたまたまですが、役とリンクするものがありました。本作は、ある出来事をきっかけに人生が断絶してしまった男の話。僕たちが日本で経験したことが映し出されていると思います。それと、日本の最北端まで実際に車を走らせていることで“今の日本”というものをとらえています。『風の電話』(諏訪敦彦監督)も同様ですが、現実の風景がしっかりと映っているということは大きいことだと思うんです。海外の方が見れば“今の日本”を感じとることができますし、もっと先に視線を移せば、普遍的な感覚を得られることだってできるはず。過剰に何かを表現したり、フィクション度がものすごく高いというわけではないですから、実際に人々が感じていることを伝えられているのではないでしょうか。広島で撮影ができたことも重要なことです。悲劇が起き、世界中からたくさんの人が学びに訪れている国際的な場所。そこでロケができたということは、この作品が成立する大事な要素だったと思っています」


