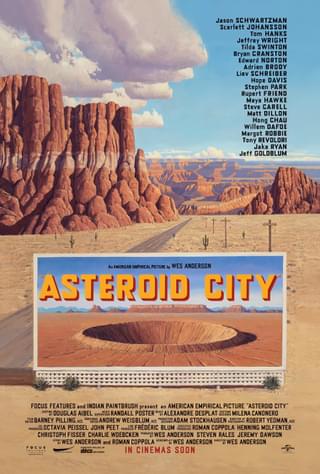犬ヶ島 : 映画評論・批評
2018年5月15日更新
2018年5月25日よりTOHOシネマズシャンテほかにてロードショー
ウェスの色彩センスが日本でいっそう花開いた “犬ヶ島”の背景が鮮烈!
日本が舞台だと聞いていたから、いったいどんな異形日本カルチャーが展開するのかと、わくわくしながら客席に座っていたら、細部までことごとく想像を裏切る仕上げになっていた。ウェス・アンダーソンの「ファンタスティック Mr.FOX」(09)以来になるストップモーションアニメは、端から日本文化のごった煮で始まる。例えば、こんな風に。
今から20年後の日本のメガ崎市(巨大化した川崎か?)では、犬のインフル“ドッグ病”が蔓延し、感染拡大を恐れた小林市長(白のスーツが何か右翼っぽい)がすべての犬を“犬ヶ島”(多分東京湾の埋め立て地)に流刑。そこで、市長の養子、アタリが愛犬スポッツを探して小型飛行機で“犬ヶ島”に舞い降り、5匹の犬たちと協力して捜索を開始する。
メガ崎の舞台では「乱」の秀虎みたいな白髪の武将が能を舞い、相撲取りが四股を踏み、バックには和太鼓にサックスやクラリネットをフィーチャーした不思議なパーカッションが鳴り響く。英語訛りの日本語を話す日本人の台詞はすべて、話し終わらないうちに通訳と機械で英語に翻訳される設定になっているから、言語のすみ分けは終始あやふや。それが意図的であることがはっきり分かるのは、ネタの下ではなく上にわさびを乗っけたにぎり寿司が登場する場面。監督はハリウッド映画が今も平気で冒す間違った日本文化を茶化しつつ、自らの日本通ぶりを逆説的に表現しているのだった。

何よりも、パンデミックを連呼して民衆の恐怖を煽り、罪もない犬たちを孤島に隔離してしまう市長の暴走政治は、現実の日本を否応なくイメージさせて説得力があり過ぎる。
顔に297個のそばかすがある少女トレイシーのために、1人のペインターが複数作られた顔のパーツをすべて手作業でコピーし、犬たちには本物のアルパカの毛を植毛する等、ストップモーションアニメならではの手間のかかる作業が、作品にアーティスティックな味わいを加えていることは言うまでもない。
でも、視覚的に最も鮮烈なのは確信犯的似非日本や凝ったキャラクターの造形ではなく、主な舞台になる“犬ヶ島”の背景だ。アタリや犬たちの後ろの積み上げられたラベルがブルーのペットボトルの山、キューブ状に圧縮されたアルミの壁、茶色い土を被ったゴミの山。それら、彩度の低い中間色のグラデーションは、前作「グランド・ブダペスト・ホテル」(14)のピンクやパープル以上に絵画的。ウェス・アンダーソンの色彩センスが日本でいっそう花開いた最新作なのである。
(清藤秀人)