ロマンティック・コメディ。小学生~高校生くらいまでの、少女漫画の世界。
なんでこういう邦題?
当時はこの方が客入りが良かったのかな?今では、この邦題で敬遠する人もいるだろう。私もその一人だった。オードリーさんでこの邦題?オードリーさんのイメージと違うけれど、新境地を開くつもりの映画なのかな?と。
鑑賞中は、オードリーさんを売り出すために(一発屋ではなく、人気や映画界における価値を不動のものにするために)、大物人気俳優と組んで『ローマの休日』『麗しのサブリナ』の二(三)匹目の泥鰌を狙ったのかと思ってしまった。
それぞれの映画の粗筋や、オードリーさんの役どころはまったく違うけれど。
正直、筋だけ追えば、90分くらいにまとめて欲しかった。
スキャンダル多き富豪と、初恋もまだの、恋に恋する乙女の駆け引き。乙女の、富豪の気をひく方法がかわいくもくすくす笑える。それに対する富豪の反応も笑える。よい年をした大人が振り回される様。余裕を見せながらも、思っていた反応と違う反応を返された時の表情が見事。だが、似たようなシーンが繰り返されるので、ちょっと飽きてしまう。
とはいえ、掛け合いが秀逸。
警察の言葉を繰り返し、知的なウィットに仕立て上げるとか。警察の言葉を知らない富豪は、その観点を面白がる。やり手の経営者に対して、具体的な数字を出してというところが気に入ったのかな?他にも、富豪の質問へのはぐらかし方とか。映画の中で出てくる元ネタを知らなければ、知的な女に見える。否、あの場で、とっさにあの言葉だから、頭の回転は速い。
愛溢れる父と娘の会話は心が温まる。
そんな筋に挟まれるエピソードも面白い。
富豪と楽団の関係。ワゴン。サウナ。”END”の文字に掛かる楽団の面々。
コメディにはつきものの、繰り返しの間。ルームサービス。隣の部屋の飼い犬。勿論、楽団。
鍵のかかっているはずの金庫。見事なすれ違い。…。くすくす笑える。
映像も見事。
鏡に映る姿。鏡化した窓に映る姿。…。
なんだかんだ、いつの間にか、見続けてしまう。
そして、そんな綱渡りの恋は…。
2度目の別れ。
同じように富豪に対して強がる娘。でも、その表情は…。改めて、オードリーさんの演技力の高さを堪能しながら、いつの間にか共感してしまう。
そんな娘を見守る富豪の逡巡。
ラスト、二人を見守る父の姿。楽団。
ああ、このシーンを見るための映画だったかと目が開かれる。
最後のテロップは、ヨーロッパ版にはなく、USA版に後から付けたものと、解説者から聞く。白黒はっきりさせないと気が済まないUSA。そんな国民性も面白い。
(原作未読。他国で映画化された作品はすべて未鑑賞)
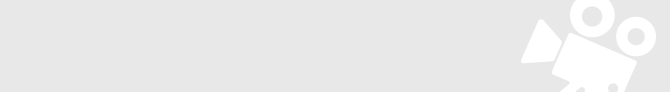




 ローマの休日
ローマの休日 オードリー・ヘプバーン
オードリー・ヘプバーン ティファニーで朝食を
ティファニーで朝食を マイ・フェア・レディ
マイ・フェア・レディ 麗しのサブリナ
麗しのサブリナ パリの恋人
パリの恋人 シャレード
シャレード 暗くなるまで待って
暗くなるまで待って アパートの鍵貸します
アパートの鍵貸します お熱いのがお好き
お熱いのがお好き














