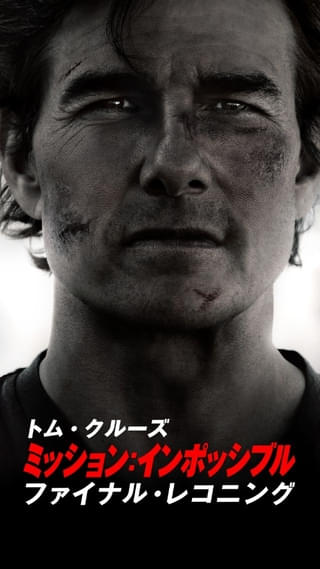コラム:清水節のメディア・シンクタンク - 第11回
2014年11月21日更新

第11回:地球時間とデジタルに抗え!時空を超える「インターステラー」創作の秘密
なんという気宇壮大な映画的挑戦なのだろう。制約なきインディペンデント映画出身の実験精神を、ハリウッド・メジャーになっても貫き通すクリストファー・ノーラン監督作品が、さらなるバージョン・アップを遂げた。「インセプション」で「夢」を精密に建築設計し、その中に侵入して前代未聞のアクションで魅せたノーランが、「宇宙」の構造に挑みかかり、星間旅行を科学的に解き明かしながら、未知なる体験へといざなうのだ。
思弁的でやや難解な方向へ傾きがちなノーラン映画だが、宇宙SFに1億6500万ドルを投じて取り組むにあたり、ドラマに太い幹を用意している。父と娘の絆だ。科学に基づく冷徹な冒険の中核にあるのは、最もプリミティブな人間的情感。マクロな視野とミクロな物語のクロス・カッティングが、切なく厳かなハーモニーを奏で、マシュー・マコノヒーの人間味あふれる存在感は、哲学や宗教性を超えて観る者をぐいぐいと牽引する。

(C) 2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved.
物語が分かりやすくなっても、濃厚なサイエンスや深遠な世界観にアレルギー反応を示す者は少なくないだろう。本作への冷めた反応を目にする度に、「2001年宇宙の旅」に対する公開直後のニューヨーク・タイムズの映画評を思い出す――「完全に独りよがり」「ディテールにこだわりすぎ」。あの作品が歳月をかけて勝ち得た映画史的な位置づけへの道を、「インターステラー」も歩む可能性は十分に秘めている。それを決めるのは、科学の発展と未来の観客であることは間違いない。「コンタクト」はもとより、日本のアニメーション「トップをねらえ!」や「ほしのこえ」に親しんだ世代には既知の世界の側面もある。かつて天文少年だった筆者にとって本作は、脳内を攪乱され、宇宙で起きる事象に瞠目し、もう一度夜空を仰ぐ想いに駆られる至福の2時間49分だった。
■「2001年宇宙の旅」を敬い・挑み・捉え直し・更新する
“引き裂かれる親子”といえば、劇場デビュー作以来、スティーブン・スピルバーグが繰り返し描いてきたモチーフだ。実は「インターステラー」は、当初スピルバーグが撮る予定だった。もちろんノーランは脚本に大幅な改変を加え自らの作品に引き寄せたが、本作と同じ制作会社レジェンダリー・ピクチャーズによる「GODZILLA」のギャレス・エドワーズもまた、このモチーフを活用しヒットに導いたことを併せて考えれば、興行的リスクの伴うジャンルにビッグバジェットで取り組む際、親子のドラマは、成功を担保するために不可欠なファクターになりつつある。さらに付け加えるなら、今年のレジェンダリーの2本の大作は、物語が作動し秘匿されたプロジェクトへと向かうプロットにおいて、いずれも「未知との遭遇」の導入部を大胆に引用している。
舞台は、地球上の生命が維持できなくなり、移住先を宇宙に求める必要性に迫られた人類のありうべき近未来。精神的な意味での救済ではなく、物理的に世界を救うべく主人公は暗黒の海へと向かう。つまり宇宙探査はロマンではなく、切実なサバイバルの手段だ。クリストファー・ノーランは、本作を「人類の限界を超える極限の体験」と捉え、「人間の存在意義を見極める旅」だとする。一言で言うならば、暗澹たる未来を覚悟せざるを得なくなった“21世紀の「2001年宇宙の旅」”。いや、あらゆる側面から「2001年宇宙の旅」を生み出したスタンリー・キューブリックの思考と話法に対し、敬い・挑み・捉え直し・更新する、野心作と言うべきかもしれない。

(C) 2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved.
■「地球時間」と「デジタル」に抗うノーランの孤高の闘い
万人向けのドラマを中心に据えた安心感からか、ノーランの冒険はより一層過激になったともいえる。主人公が闘うべき相手は、子供たちの世代の生命のゆくえを懸け切迫する「時間」だ。一刻の猶予も許されない地球のクライシスと、遠大な星間飛行を現実のものとする時空間のセオリー。ノーランと時間といえば「メメント」である。それは、映画とはエンドマークへ向け、時間経過に従って進んでいくものという通念を覆し、時間を逆行させる構成によって、記憶障害に陥った主人公のアイデンティティを明確にしていく試みだった。映画編集は逆転可能でも、実時間の時計の針は止められない。では一体、どのようなアプローチでノーランは闘ったのか。
「インターステラー」とは、2つの「時間」に抗う映画だ。ひとつは、破滅的な未来へ向かってしか流れていかない、ストーリー上の地球時間。もうひとつは、過去の技術を捨て去ってデジタル化へ突き進む、映画技術の趨勢。これらに抵抗する挑戦こそが、星間飛行にリアリティを与えるための2本柱である。常人ならば呑み込まれ、あるいは従うしかない、時の流れに対するチャレンジを読み解いていこう。
コラム