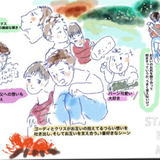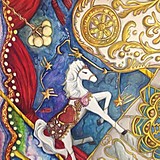怪物のレビュー・感想・評価
全1009件中、241~260件目を表示
良い意味で裏切られた
やだ、私だけっぽい
somewhere
ウエストサイドストーリーの秀逸なナンバーのひとつにsomewhereがある。スピルバーグ版ではオリジナル版のアニタ役のリタ・モレノが唄うが、マリアとトニーがデュエットする前作のナンバーの方が、行き場のない愛する二人の切なさに涙せずいられない程、感動的だ。このナンバーは、実は男女になぞらえて、当時はひた隠しにしなければならなかった同性愛者の心情を表現したと言う逸話がまことしやかに語られていた。しかし、スピルバーグ版の新作のメイキングでスピルバーグはこの映画に携わった主要スタッフが同性愛者だったことを公言した。ウエストサイドストーリーが、半世紀経っても今なお色褪せないのは、人間そのもののアイデンティティーの問題と言う永遠のテーマを訴えているからだ。(映画の中でジェット団に入りたがるボーイッシュな女の子の存在は、今なら多くの人が理解出来る)
怪物のラスト、二人の少年が台風一過の清々しい晴天の中を閉鎖されていた線路を駆け抜けて行く。これはあくまで自分の解釈だが、やはりこの二人の少年はこの世にはいない。台風の日に自宅の浴室で自殺しようとした少年を助けて、二人が唯一呼吸の出来る森の中の廃車へと逃げ込む。映画では、二人の少年が死の覚悟をしながら亡くなったのか、そんな暇もなく死んでしまったのかは、観客に委ねれている。
この映画が多くの人に評価されたのは、「怪物だれーだ」と言う問いかけに、単純な回答を用意しなかったからだろう。人間は誰しもその中にモンスターの要素を内蔵していると言うことなのか、それとももっと究極を極めれば、そんな人は誰もいないと言う事なのか?後者を信じたい自分がいるが、昨今の世の中を見ると、前者なのかと疑ってしまう自分がいるのも否定出来ない。
切ない
片方の靴がこんなに切なく感じるなんて…
終始ヒリヒリする感覚で見ていました。
結局本当のことなんてどうやったらわかるんだろ。
何事もなくスクスク育ったと思ってるのは、単に分かってないだけなのかもな。とてつもない悩みを抱えてたら、きっと母には話してくれると思ってるのは母親だけで、何にもひとつも分かってないのかもしれない。片方だけなくなった靴がいじめを表してるかと思ったら、実は二人の仲を表してた描写は秀悦だと思った。
次々と視点が変わる描写に、どんどん自分の中のそれぞれのキャラに対する想いが変わっていって、その度に一つの視点から物事を捉えることの危うさを感じ…
でも…どうしたらいい?だってみんな全部なんてわかりきれないじゃない?日本がもっと性に寛容なら二人は悩まなかったの?ヨリの父親がヨリを病気だと言ってるのは、ヨリが同性が好きだからだけなのか、発達障害がある(鏡文字を5年生で書いてるとか、教科書読んでるところとかでそう思ったんだけど)ということなのか、そこがいまいちよくわからず…だってヨリがあのお父さんにそんなに自分の事を話してるとは思えなくて。
色々後から考えると?な事は多いですが、とにかく子供二人のシーンが可愛くて美しくて切なくて…そして子育てした身にはどうやったって子供の全部なんてわかり得ないというのを感じ、自分の子育てを振り返ってしまう、そしてより切なくなってしまう…
整理が必要
なかなか鑑賞後星をつける気分になれなかったが、色々な足跡を頭に残し、疑問と闘っていた当時のメモを一旦整理する。
---
小学生のこどもがいる人は平常心ではみられないかも?
最初から生まれ変わりの話が出てきたから都度ブラッシュアップライフがよぎって邪魔だった
クィアパルム賞は忘れてたけど、それが主題なのか?やや疑問。そんな賞があること自体がまだ多様性を阻んでる気もするし、それが主テーマだと思われるのは違う気もする。
◆怪物誰だ?
- 隠蔽体質の校長と教師陣
- 伝聞と噂を真実と決めつけ子どもに結婚の圧をかける母親
- 男らしさを強要し、真実を見極められない先生
- イジメをする子どもたち
- イジメを傍観し、嘘をつき、なぜかホリ先生になすりつけることにしたクラスメート
- 子どもを豚の脳と呼び虐待する父親
- 自分は病気だと思い火をつけた?星川くん
- イジメを止められず自分の想いも認められない湊
◆謎
星川くんは本当に火をつけたのか
校長は本当に孫をひいたのか
湊の父は本当に不倫してたのか(ホリ先生のガールズバー通いが嘘だったことを考えるとまだ分からない?)
湊が猫を殺したと伝えた女子生徒の意図 (ただの勘違い?)
アンケートで皆ホリ先生暴力を振るったって答えることにしたのはなぜ。それとも書いてないのか
校長は一体何を考えているのか
◆無理を感じたところ
教育委員会に言うとなぜ言わないんだろう?
ホリ先生もさすがにあそこまでは不自然?
(途中までは言わされ感と納得したが、飴のくだりとか、片親批判とか(自分もなのに)、もっとしっかりしてそうだったのに)
母親も最初は決めつけて作文で名前の隠し文字を見ただけで優しい子だったんですまで分かるのか?
◆気づけなかったこと
湊の身体が反応してしまったこと
校長が走り回る子どもに足をかけたこと
結構重要なポイントだけど人のレビューを見るまで気づいてなかった。
---
こうして色々考えるに至るのが是枝作品の好きなところ。最後の笑顔が切ない。
とんでもないものを見てしまった
鑑賞後しばらく、すごいものを見た…とんでもないものを見てしまった…という感情の渦の中で、動きが鈍くなった。
序盤から中盤にかけて、予告で流れていた「怪物だーれだ?」という無邪気で空恐ろしい子供の声が頭の中に渦巻き、「この物語の怪物はいったい誰なんだろう、こいつか?いやそいつか?あ、こいつかもしれない…」などと考えながら見ていた、そんな自分の中に確かにある、悪意のない独断や偏見をまざまざと見せつけられ、苦しくなった。
或る怪物
色々と考えさせてくれる映画
わんわん泣かされた。 周囲の無理解と自分は”普通”だと思い込みたい...
わんわん泣かされた。
周囲の無理解と自分は”普通”だと思い込みたい主人公の男の子。
つらい。
そして幼少期に無自覚に人を傷つけてしまっていた自分を恥じた。
物語の構成。
ミステリのような楽しさ。
役者さんたちの鬼気迫る演技。
神経質すぎるcorrector
長野県諏訪市のとある公立小学校で起きたパワハラ事件を巡る三者(母親、教師、生徒)の視点。“クィア”な存在に対する社会の偏見はどのようにして生まれるのか、という問いがそこから浮かび上がってくる、なかなか巧妙なシナリオだ。かつてオーストリアの巨匠ミハエル・ハネケは、ファシズムの精神的起源を宗教的不寛容にあることを『白いリボン』の中で暴露して見せた。是枝裕和と坂元裕二が、さらに遡ってその不寛容の起源について考察してみた映画といえるのだろう。
「人間の脳を移植された豚は人間といえるのか」科学の進歩とともに人間と動物の境界がどんどんあいまいになってくると、逆に倫理規程が取り沙汰されるように、LGBTQに対する差別偏見をなくそうと上から圧力がかかればかかるほど、末端の小学校ではクィアの子供に対するイジメが激化する。私たちが社会のあらゆる境界を無くそうと努力しているのだから、その末端の組織でも差別が少なくなっているはずだ、と良識的な大人たちは思っているのかもしれない。それって逆じゃないすか、と是枝✕坂元コンビは疑問を投げ掛けているのだ。
豚の脳、鏡文字、誤植、転覆病にかかった金魚、お菓子泥棒(万引き癖)、不協和音を奏でる楽器.....それらはクィア=風変わりなもののメタファーであるとともに、登場人物たちの目にはなにかしら別の意味を持った得体のしれないもの=“怪物”として映るために、(『白いリボン』の牧師のように)“矯正しなくてはならないもの”のように思えるだ。(汚れを落とす)クリーニング屋のモンスターマザー、出版物の誤植探しが趣味の教師、消しゴムで何かを必死に消そうとする生徒、床の汚れ落としに一生懸命な校長先生は、神経質すぎるcorrectorとして描かれるのである。
しかし、観客はそれら“風変わりなもの”の中に隠された別の意味があったことを、『羅生門』演出によって知ることになるのである。冒頭の火事が実は放火で、パワハラ教師は実は優しい先生で、死んだ父親は不倫していて、イジメッ子だと思った子供は無二の親友だったのである。依里に対して友達以上の感情を持っていることに気づいた湊は、その感情の正体が自分では理解できずに、“怪物ゲーム”という『禁じられた遊び』によって、相手に教えてもらおうとするのである。
生まれもった人間の瑕疵というのは、瑕疵ではなく個性だと思ってもいない嘘をつくのではなく、ましてや人工的に無くそうとしたり消し去ろうとするべきものではない。ラスト湊と依里が泥だらけの姿のまま、いつのまにかフェンスが消え去っていた鉄橋をわたろうとしたように、(人間の事実認識に限界がある以上)本来的には瑕疵は瑕疵のまま、自然にまかせて放任すべきものではないのだろうか、そんな寓意が伝わってくるのである。ちょっとした歪みをみつけると、すぐに矯正排除しようとするせっかちな現実社会の中で、救われることは決してないのだけれど.....
まったく情報を入れずに見に行きました。是枝作品は合うものと合わない...
全1009件中、241~260件目を表示