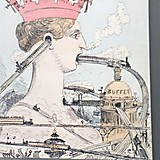メッセージのレビュー・感想・評価
全692件中、61~80件目を表示
ばかうけの出オチじゃないぞ。
前評判がいいのと「ばかうけ」なのは知っていて、お気に入りに入れながらも、なかなか手が出なかった本作。ここ最近マーヴェルとホラー三昧で胃もたれ気味だったので、やっと手に取れた。
とにかく、「ばかうけ」の存在感すごい。日常風景にこれが映り込むだけで、一気に違和感が強調させる。
話は静かに始まり、静かな緊張の中進んでいくが、淡々とした中に散りばめられた伏線とその回収、「そうきたかー」って言葉が漏れますね。観た人があのエンディングをどう捉えるかで感じ方は大きく変わる作品。
一度もスマホに手を伸ばす事ないくらい集中して観られた。
それにしてもヘプタポッドに話しかける時、どこ見ていいかわからない感じ、スッゲェわかる。
何これ?さっぱりわからん
フラッシュバックで登場する女の子は誰なのか?
ドゥニ・ビルヌーブ監督(ボーダーライン等)により2016年製作の米国映画。
原題Arrival、配給ソニー・ピクチャーズエンタテインメント。
フラッシュバック的に挿入されている映像が、実は未来の映像というのは実に斬新で、凄く面白く感じた。そして、フラッシュバックの謎が完全に分かり、未来には不幸があると分かっていても、今この時の幸せを重視し、プロポーズを受け入れたヒロインの重い決断。一人一人の人生の意味の様なものを考えさせられた。そして、映画のラストにおいて、あのフラッシュバックの原点に辿り着いたという大きな感慨があり、映画タイトルは自分的には原題の方が良かったかなとは思った。
異星人が12ヶ所におり、断片的な情報をもたらす。タコの様な異性人ヘプタポッドの造形はありきたりだが、墨の様に描かれるループ状の表意文字の造形は素晴らしかった。宇宙船の形もシュールで気に入った。
ヒロインの活躍で最も好戦的であった中国将軍を説得し、12の断片的情報を繋ぎからのわせることに成功し、異性人からのメッセージを解読することができた。この流れ、ありがち感は有るが、ヒロインが観る未来映像の賜物という要素が入れられて上手いストーリー展開と思わされた。また12カ国のノンゼロサムゲーム、win-win の関係性が現実にあり得るということを、具体的に示していたことに、メッセージ性は感じた。
製作ショーン・レビ ダン・レビン、アーロン・ライダー デビッド・リンド、製作総指揮スタン・ブロドコウスキー、エリック・ハイセラー ダン・コーエン、カレン・ランダー トーリー・メッツガー、ミラン・ポペルカ。
原作テッド・チャン「あなたの人生の物語」、脚本エリック・ハイセラー(遊星からの物体X ファーストコンタクト等)、撮影ブラッドフォード・ヤング、美術パトリス・バーメット。衣装レネー・エイプリル、編集ジョー・ウォーカー、音楽ヨハン・ヨハンソン、視覚効果監修ルイ・モラン。
出演はエイミー・アダムス(バイス等)、ジェレミー・レナー(ハート・ロッカー等)、フォレスト・ウィテカー、マイケル・スタールバーグ、マーク・オブライエン、ツィ・マー。
久々のハードSF映画はおもしろかった。
伏線もちゃんと回収できており、最後はなるほどと思った。少々説明が足らず難解か。「他の言語を覚えれば思考の方法も変わってくる」というような台詞が映画の中にあったが、主人公が時間の概念のない異星人の言語を学ぶことによって、時間の制約を超えて未来を見ることを段々できるようになってくるといったくだりが上手に描かれていなく、ちょっと分かりにくくなってしまったかもしれない。それでもエンターテインメント映画でなく、久々のハードSF映画を観られてよかった。楽しめた。
09-049
上位者系エイリアン
主人公は言語学者の女性。突如世界中に現れたエイリアンの宇宙船(?)のひとつに足繁く通い、「彼ら」との対話を重ねて、エイリアン語の解読を試みる。
彼らの目的は?
もし侵略なら、なぜ攻撃してこない?
エイリアンは明らかに高い知性と技術を持っているが、いきなり人類の言葉で話してきたりはしない。しかしこちらの言葉や意図はすぐに理解し、問いには素早く答えてくれる。
まるで人類の能動的・主体的な成長を、はるかな高みからゆったりと待っているかのよう。
そのレベルに近づくべく、主人公たちが研究と対話を重ねていく過程に、心地よい知的興奮を感じる。キャラクターと同じように好奇心と恐怖心が刺激される。彼らを信じて知識を得るべきか、それとも打ち払うべきか。そんなことを考えながら、どんどん映画に入り込んでしまった。
そして終盤に明かされる驚きの真実。観客の常識と先入観を利用した叙述トリックは「やられた!」の一言。エイリアンの描き方も、どちらかといえば典型的なデザインの中に独自の特徴がしっかりあって、ちょうどいい案配。
こういうSF、好きだなあ。面白かった。
彼らからのメッセージ
娘との未来の記憶が彼らからのギフトだったとは、、
過去の記憶とばかり思っていてその仕掛けに
気づいたときには切なさと愛しさが込み上げてくる
今を生きる自分は得体の知れない彼らとは
一生懸命に意思疎通を図ろうと歩み寄るのに
未来の自分は言語というツールに怠けて
娘とのコミュニケーションさえ疎かにして
かけがえのない一瞬を手放している
手にした言語にありがたみもなければ
言葉に乗せて気持ちを伝えることの大切さも忘れている
彼らからの記憶のギフトを貰い
家族とのその瞬間をいつか後悔することなく
大切にすると心に刻んだのではないかと思う
それは人類も同じで言語があるのに歩み寄らず
分からないから怖いから攻撃する
私たちの時間軸の3000年後
自滅してバラバラになっている運命だった私たちに
助けの手を差し伸べてくれたのが彼だったという理解で
友好的な国際関係が分かる未来の記憶の中で
真ん中に彼らの旗が掲げられていたのが感動的であった
テンポが
言語と時間の関係、主体性と運命を考えさせられる素晴らしいSF作品
英語の文法で主語、動詞、目的語、補語、前置詞等々習いますが、これは誰が何を何に対して何するという行動の方向性です。つまり、言葉に因果関係が組み込まれているということでしょう。
言葉に因果関係が含まれれば、我々の思考は因果関係に縛られる、つまり、現時点から未来は因果の先ですから見ることができません。時間の経過通りにしか物が見えません。
対して、ヘプタポッドの言葉は線形ではなく円形が象徴するとおり因果関係に縛られません。意味内容が恐らく誰が何をした、みたいなものでなく、もっといろんな含意がある状態あるいは状況を表しているのかもしれません。映像的なものかもしれません。それは過去、現在、未来を等価に表現したものだ、というのが映画からは読み取れます。明言はないですけど。
日本でも神狩りのような秀逸な言語をモチーフにしたSFはありますが、本作はは単なるモチーフやギミックではなく、言語の在り方が物語の中枢の哲学的なテーマになっていると思います。ここが非常にSFマインド…センスオブワンダーでした。
ヘプタポットは未来が見えるということになるのでしょう。としたときに、途中のアクシデントで死ぬことをヘプタポッドは自分の運命としてあらかじめ知っていることになります。
このとき、ルイーズの子供の問題が出てきます。子供を作るか作らないかという選択は主体的に見えて、実は運命なのだと言う風に見えます。これは死んだヘプタポットの覚悟の仕方の別の見方になります。子供が死ぬことがわかっているルイーズに選択の余地はあったのか無かったのか。
実存主義的な人間の選択つまり「予知できない未来と」いうのは実は無いと取るのか、分かっていても運命を逍遥と受け入れるとつらい選択を自ら行うのが主体性だと取るのか。それが問われている映画ではないでしょうか。
とってつけたような世界平和の話はかの国への忖度でしょう。むしろ、因果関係にしばられず、運命をそれぞれが受け入れたとき、本当の協力が生まれると取ればいいのでしょうか。ヘプタポットとの未来の協調関係も想起させます。そして人類の未来も。その辺はオープンエンディングですので、それぞれが考えればいいと思います。
なお、いまさらこの作品のレビューを書いたのはアニメ「地球外少年少女」を見たからです。内容は言いませんけど。
多分、村上春樹のファンにウケる
私の友人に村上春樹のファンがいる。 彼を見ていると何が楽しみで生きているのかわからない。 趣味があるわけでもなく 生きがいがあるわけでもなく ただただ働いている・・と言うか働いていた。 彼は正月も盆もなく年がら年中夜遅くまで働いていた。 私に入れば言わせれば彼は働いていたのではなく、することがなかっただけだ。 そんな彼は今、引退して介護が必要な母親と二人で暮らしている。 もしその母親が死んだら彼は一体何を楽しみに生きていくのだろう? 私には分からない・・
・・・そして、そのようなわからない主人公を書き続けているのが村上春樹だ。 彼の描く主人公たちは一様にして生きる気力が弱いように見える。 彼らは色々とおかしなことに没頭する知人を見て羨ましがっているって言うか不思議がっていると言うか・・・理解できないようだ。理解できないことを面白がっているようだ。そんな主人公たちは生きる活力が少ないものだから 女性に対してのワクワクドキドキもなくそれが為に簡単に口説けてしまう。 かと言って彼女ができたことを喜ぶでもなく セックスを楽しんでいる様子も見られない。 何があっても彼らは生きる活力を見いだせないようなのだ。 私の中にはそういったものは欠片もないので全く共感することはできない。しかし村上春樹の小説とそのファンである友達 そして今回この映画を見て、初めてそういう人たちがいるのだと理解することができた。 普通の活力のある人に(もし)こんなことが起こったら生きる活力がなくなるだろう・・・ というその究極の「こんなこと」というのは 未来が見えてしまうことだろう。特に未来の悲劇が。・・・「 私達、生まれつき生きる活力の少ない人間は 、こういう世界に生きているのよ」・・・ ということを、 活力の豊かな普通の人々に伝えた映画 ・・・私はこの映画を見てそんなことを思った。
普通の映画として見ると、難病物の名作劇場。退屈でつまらない。
まぁついでに書いてしまおう。
そういう人々というのはおそらく多くはいわゆるマイナージェンダーの方々ではないかと思うのだ。 この世に男と女がいるのは何故か?オスとメスがいるのはなぜか? 遺伝子をシャッフルするためだと生物学者は言うけど私は違うと思う。「 いつか交尾するのだ!いい女をゲットするのだ!いい男をゲットするのだ!」というのが生きる活力の元になっている。 生きる活力をアップさせるために男と女がいるのだと思う。 中間ジェンダー人にはそういうものがないので 生きる活力が少ないのではないだろうか?今までそういう人々はあまりクローズアップされてこなかった。今、けっこう話題にあげられることが多くなっている、これからの時代の大問題だ。・・・ そういうことを考えると村上春樹氏がノーベル賞を受賞する日もいつかやってくるかもしれない
12と7の古代聖数
映画「メッセージ」は、2001年宇宙の旅や惑星ソラリス並みの衝撃だった。
何の予備知識もなく、できるだけ早めに見ておこうと思った。
気になるのは「12」と「7」の聖数。
突如、日本を含む世界12ヶ所の上空に現れた巨大なシェル。
12の国それぞれがエイリアンとコンタクトを取り、何の目的でやってきたのかを探ることで協力し合う。
7本足で7本指のエイリアンは、ヘプタポッド(ギリシャ語で7本足)と呼ばれる。
なぜ奇数なのか?
その前に、なぜ地上の生物が2本4本8本とすべて偶数かといえば左右対称となるため。
宇宙空間では7でも不都合はない。
映画のクライマックスで、足並みを揃えていたはずの12の国の中からエイリアンに不信感を抱き中国が宣戦布告するも、主人公の言語学者ルイーズ・バンクスはヘプタボッド語を習得し未来からのメッセージを受け取って世界を和解させる。
ここでも中国がキーとなるし、ヘプタポッドのサークル状の文字も墨絵だし、映画化の原作「あなたの人生の物語」のSF作家は中国系アメリカ人。
ヘプタポッドとの接触で誤解を招いた「武器」の意味は、時系列のない「言語」のことだった。
映画ではチラッとしか見せないが、この後世界はヘプタポッド語が採用され、共通言語でひとつとなる。
言語による文化の違いで、国同士の戦争をくり返してきた歴史。
元はといえば、バビロンのころまで世界はひとつの言語だった。
その当時、人々は協力し合って天にも届く勢いのバビロンの塔(バベルの塔)を築こうとした。
カミはその傲慢な人間に対し、言語をバラバラにして遮断したのだった。
数字のことを含め、その辺りもテッド・チャンの原作をしっかり読んでみようと思う。
追記:
ヘプタポッドは原作で7本足に7つ目とどこかに書いてあった。
映画では霞みがかってよく見えなかったけど、目の代わりに7本指だったのかも。
いずれにしても「7」も「12」も聖書からの暗示を感じる。
古代イスラエルの12支族。
ヨハネの黙示録には7つ目の子羊=イエスが出てくる。
好みの映画ですありがとうございました
序盤〜中盤まで超ミステリアスでエイリアンが何してくるかめっちゃ気になったし、シリアスな雰囲気がさいこーう
米軍テントの雰囲気、上官の雰囲気すき、そしてなによりエイリアンとの対話ルームのあの感じ!
墨?で〇書いてるだけかと思ったらそれが言葉かい!
ほんで最後がさ、別の映画か?っていうくらい感動した!バイオリンのBGMって卑怯だね
あと中国の将軍と会話するシーンとか展開えぐい
いい映画、人も死んで無いし
不思議な魅力に溢れる奥深いSF
本作は、“2001年宇宙の旅”を彷彿とさせる作品である。難解ではあるが、作品の世界観を重視した作風で、総合芸術と言われる映画の本質を感じることができる。本作は、地球に飛来した宇宙船をめぐるSFであり、派手な展開はなく、映像表現主体の不思議な魅力に溢れた作品である。
何の前触れもなく、突如、12隻の宇宙船が地球に飛来する。異星人たちの目的は地球征服なのか否か騒然とする中、アメリカ軍の依頼を受けた言語学者ルイーズ(エイミー・アダムス)は、異星人たちの真意を知るために、彼らとの言語によるコミュニケーションに挑んでいく。そして、試行錯誤を繰り返しながらも、ついに主人公は彼らの言語を解読し、彼らが地球にきた目的が明かされるが・・・。
ハッキリ言って、生易しい作品ではない。分かり易いナレーション(言語表現)はない。時折、主人公のフラッシュバックとして挿入される主人公と子供のやり取りは何を意味するのか説明はない。映像表現から、我々観客が想像するしかない。本来、映画には、映像表現という手法があり、それを最大限に活かした作品である。最近、言語表現を多用した観客に分かり易い作品が多い中では出色であるが、観客の想像力に挑むような作風は刺激的あり、往年の名作SF“2001年宇宙の旅”を彷彿とさせる出来映えである。
宇宙服のような厳重な装備、異星人との接触準備中に手を震わせる主人公など、異星人との接触シーンは極めてリアルであり、敵か味方か全くわからない異星人への恐怖がヒシヒシと伝わってくる。主人公の自己紹介から始まる、異星人との接触による、彼らの言語を解読するプロセスは泥臭く、手探り感が上手に表現されていて面白い。満身創痍状態になりながらも懸命に未知なる言語を解析する主人公の姿は知的好奇心に溢れていて、逞しさすら感じられた。
異星人の地球飛来の目的が明かされると、それまで、一致団結していた世界の国々が分裂してしまうシーンは、非常事態においても、自分のことしか考えられない人間のエゴが丸出しになっている。この先、物語の結末はどうなるかと思っていたら、伏線の回収とともに、作品のイメージ通りのラストに落ち着いた。
観終わって、久し振りに、何か不思議な世界を観たという独特の浮遊感を感じた。作品の世界観を完全に掴みきれず、幻惑された感じがした。全てが納得できる作品も良いが、本作のような、卓越した映像表現で我々の想像力を試すような難攻不落の作品も面白い。本作の不思議な世界観にまた挑んで完全解読してみたい。難問である程、解いてみたくなる。そんな気持ちにさせられる作品である。
始まりと終わりがないということ
未知とコミュニケーションをとるということの難しさ。
同じ星の同じ人間同士ですらコミュニケーションを上手く取れない。
ヘプタポッドたちの概念では始まりと終わりがない。
始点と終点がない。
線があるだけだ。
因果論と目的論が同時存在するならば、どちらの理論も使えて使えない。
ルイーズが事象を見た後に選択ができるならばハンナの未来は違うかもしれない。
変わるのではなく、そもそも違うものとしてあるはず。
若くして死ぬかもしれないし天寿を全うするかもしれない。結果は同じだ。
その時ルイーズはまた「見る」のではないだろうか。
おそらく「結果」の意味は違う。
ルイーズは「使える」。
そしていつか、最長でも3000年後には人類が「使える」のだろう。
そして「武器」になり得る。
おおよそ120分の枠の中では、因果論のみ理解し体感できない我々が、結論の出ないループに入るという隙を作ることでしか表現できないのお話だと思う。
レビューを書きながらも端々に矛盾を感じている僕もまたループに入っているのでしょう。
イカ星人は墨を吐く
放射能汚染も心配されることから完全防備態勢で内部に入る面々。とにかく、ルイーズ(アダムス)の息苦しさが伝わってきて、こちらまで苦しくなってくるほどだ。下から入ると、重力がいきなり変わる。地球上ではあり得ない!と、『ゼロ・グラビティ』みたいに吐き気をもよおしそうになるのだ。
ガラス面を境にして7本足のイカみたいな異星人と対峙。しかし、相手はちゃんと質問には答えているみたいけど、聞いたことのないノイズを発するのみ。18時間に一度しか扉が開かない浮遊殻物体。二日目にはホワイトボードで言葉(HUMAN)を書いてみるという手段にでた。すると、イカスミをガラス面に吹きかけ、文字みたいなものを描く異星人。それをつぶさに観察して、古代語を解読するように文字を解析しようとするルイーズたち言語学者チーム。
18時間ごとにUFO内部でコンタクトをとるルイーズとイアン(レナー)。円形を基本とした文字を見ていると途端に眠くなってくる。どちらがコステロで、どちらがアボット?・・・zzz
冒頭では、シングルマザーとして娘ハンナを育てる数カット。成長するカットを繋げていくのだが、ハンナは20歳くらい?で病死してしまうのだ。本編でもそのフラッシュバックが何度も織り込まれているが、これは未来のことではないのか?と、なんとなく思えるようになった。時間軸をわざとずらしてあるのだと。終盤、異星人たちが飛来してきた目的をいきなり読めるようになったため、救ってほしいとか3000年後の未来を救うためとか・・・よく理解できなかったが、UFOを攻撃しようとしていた国の一つ中国のシャン将軍に未来で知った言葉を電話で伝え、宇宙人との全面戦争を回避したのだ。異星人に未来を教えてもらい、自分の悲しい未来も聞いてしまう・・・それでも子どもを生みますか?と、試練を与えられたルイーズ。夫になるのはもちろん・・・という展開。見終わってからじわーっと感動させられる。
ルイーズだけはイカ星人と同じく線形時間軸がなくなってる様子。それも彼らと直接対峙したためかもしれない。侵略者には武力でもって立ち向かうという地球人の性質も理解していたイカ星人。12の地域での紛争を無くし、3千年後には地球人の力を借りに来るという極めて平和的な宇宙人だったわけだ。ルイーズがいなくても他の地域に未来を読める人を作り出したかもしれないし、世界の歴史を多角的にとらえるために大きく貢献した形だ。で、シーナ・イーストンの曲は何?
HANNNAHという名前は特別。前から読んでも後ろから読んでも同じ回文になっている。過去から見ても未来から見てもルイーズにとっては愛する娘に違いない。愛という真実があればいいのだから・・・この作品が与えてくれる言語学のテーマ、多言語交流、人類みな兄弟!戦争はやめよう!といったこと以外に愛は永遠なんだとメッセージを貰った。私負けましたわ・・・
【2017年6月映画館にて】
全692件中、61~80件目を表示