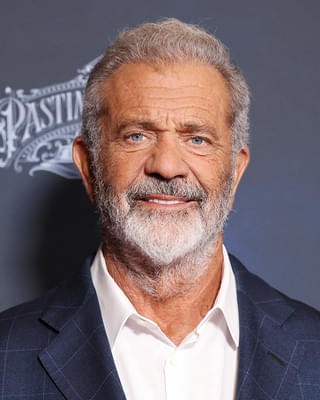パッション : 映画評論・批評
2013年10月1日更新
2013年10月4日よりTOHOシネマズみゆき座ほかにてロードショー
デ・パルマ好きなら楽しめる「愚直な悪夢」

ブライアン・デ・パルマは、もしかしたらあまり頭がよくないのではないだろうか。
あるとき私は、失礼ながらそんな疑念を抱いたことがある。話は緻密さに欠けるし、恐るべき真実や辛辣な知恵を感じさせることも少ない。
にもかかわらず、若いころの私は、彼の映画が大好きだった。悪夢が現実を侵犯していく瞬間の怪力が、なんともスリリングだったからだ。「ファントム・オブ・パラダイス」も「キャリー」も「愛のメモリー」も。
「パッション」は、そんな思い出を誘発する映画だ。見ている間、私は数回、馬鹿じゃないのか、とつぶやきそうになった。ベルリンの広告代理店を舞台に、強欲で陰険でケバい女たちが悪だくみの限りを尽くして共食いをはじめるのだから、なにが起こってもべつに不思議ではない。
ケバい女は3人出てくる。ブロンドのレイチェル・マクアダムスは若い役員。その下に黒髪のノオミ・ラパスがいて、ラパスの助手が赤毛のカロリーネ・ヘルフルトだ。もうひとり、軽薄な男の同僚も話にからむが、存在感はきわめて薄い。
3人の行動は、ほとんどすべてが出世欲と性欲に由来している。つまり、なにもかもが嘘と裏切りと罠に直結する。馬鹿馬鹿しいといったのはそのためだが、デ・パルマは舌なめずりしながら彼女たちの悪行を追う。
面白いのは、妄執に近い監督の確信だ。正直なところ、「パッション」はスリラーとしてそんなによくできているわけではないし、型破りのエロスが発露されるわけでもない。にもかかわらず、この映画には愛嬌がある。よくもまあ、と感心したくなる愚直さで悪夢に迫っている。愚直な悪夢だなんて形容矛盾もはなはだしいが、デ・パルマ好きならきっとその矛盾を楽しむことができるはずだ。
(芝山幹郎)