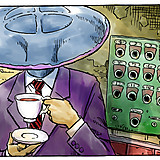舟を編むのレビュー・感想・評価
全258件中、201~220件目を表示
心が温かくなる作品です
●のだめカンタービレのシュトレーゼマン(as竹中直人)曰く・・『音楽に向き合ってますか?』『半端は許しません!』
いまから・・
映画好きで読書好きな俺が・・長くて変態的なレビューを書く!
引かれてもお構いなし!
それくらい感動したから(@_@;)(@_@;)(@_@;)
①名作・・●のだめカンタービレで、主人公千秋の師シュトレーゼマンが言ってる・・
『大事なのは・・どれだけ向き合ったか?です!』
そう・・
どれだけ仕事に?言葉に?向き合ったか?
本作にに出てくるすべての人物は・・きちんと自身の仕事や言葉に向き合ってるよネ?
俺・・涙止まらず見ました!
同時に・・
公開時、劇場に行けなかった事・・激しく後悔しました(+_+)(+_+)(+_+)
②原作/三浦しをんさん・・は俺的に好き嫌い有る作者さんです。
本作は素敵でしたが・・
●星間商事社史編纂室・・他、は最悪でした(*^^)v
でも・・
本作の原作は・・俺後半涙止まりませんでしたヽ(^o^)丿
これはすばらしい作品です(原作も・映画も!)。
③書籍を映画化する時・・
●百回泣く事や●リアル完全なる首長竜の日・・みたく原作レイプするPTと・・
●本作みたく・・原作に寄り添うパターンと・・
●ガンツや●冷静と情熱のあいだ・・みたく、原作から離れるけど・・それはそれで有り!みたいなPTが有ります。
これは素晴らしかったヽ(^o^)丿
原作はもう少し西岡(asオダギリジョー)とかぐや(as宮崎あおい)を掘り下げてるんですがね?
そうすると・・
前後編や三時間ものになるから・・これはこれで良いのでしょう?
④俺的には・・
かぐやは『黒谷友香さん』のイメージだったし・・
西岡のカノは『安藤サクラさん』のイメージだった・・
でも・・
宮崎さんはもちろん良かったし・・
劣化が騒がれてるけど・・池脇さんは●ジョゼと虎と魚たち以来の輝きだった・・
そして・・
松田龍平さん・加藤剛さん・小林薫さん・・
黒木華さん・鶴見新吾さん・・
みなさん良かったけど・・
一番良かったのが・・
オダギリジョーさんだった!!!
仮面ライダークウガ以来のオダジョーさんの代表作に思う・・。
つくづく・・原作のCUTが残念!
池脇さんとオダジョーさんの化学変化・・もっと見たかった⌒(^O^)⌒♪
星☆評価は・・
劇場公開1800円基準で(*^^)v⑤
DVD買う度 ◎◎◎◎◎
モ1回見たい度 ◆◆◆◆◆
おすすめ度 *****
デートで見る度 ◇◇◇◇◇
観た後の行きたいお店】
料亭や割烹や小料理屋!
観た後の飲みたいお酒】
ビール・焼酎・シャンパン・・アルコールならなんでもござれ!
観た後の食べたい一品】
月の裏・・特性ゴマ豆腐!!!
もう一度記するが・・↓
本作、原作のが千倍素晴らしい!
でもコチラも十二分に&ぶっちぎりに素晴らしい!
伯爵・・
品質保証作品!!!
すばらしい!日本人なら見るべし(V)o¥o(V)
期待してたほどでは
辞書づくりという私の日常生活では全く想像できない仕事というものが当たり前だが存在していて傍から見たらそんな仕事面白いの?みたいなものも続けていくうちに自分の中で誇りが生まれていく
特に私は単純作業が非常に苦手なので淡々と熱中して仕事に取り組む松田龍平演じる馬締の姿はとてもかっこよかった(馬締はぱっとみコミュ障だし社会に出ても仕事とかでうまくいかなそうなんだけどそんな人が仕事できる時のヤンキー理論みたいなかっこよさ)
またオダギリジョー演じる同僚の西原も最初は軽薄そうな人だったのに馬締に感化されて仕事に誇りを持ち始めて尚且つ西原のキャラクターのまま辞書づくりで必要不可欠な人になっていくところ、西原と池脇千鶴の実在しそうな仲いいカップル感とかも好印象でした
ただかぐや(宮崎あおい)の恋愛がまぁいらない
だいたいコミュ障で全然アプローチしたりしない馬締の告白を受け容れるとか現実離れしすぎていて現実はそんな甘くないんやで...と思ってしまった
その後の結婚した後も献身的な妻過ぎてもうかぐやが馬締の妄想なんじゃないかと思えたくらい
原作は女の方でしたかどうなんでしょう?変わっていたなら監督の趣味ですね(笑)
あと辞書づくりに年月がかかるので時間が一度に飛ぶシーンがあったがイマイチ前後の描写の細かな変化を入れられていないように感じた
そこは映画の娯楽的要素に大きく関わるのに
また一つのミスが見つかりみんな総出で泊まり込みしなきゃいけなくなった時に人数が増えてからそんなに時間が経たずまたエピソードも弱いためみんなが一致団結するシーンに違和感を感じた
最優秀アカデミーは
作品→そして父になる
主演男優→松田龍平or福山雅治になってほしいなぁ
ほろりと
小説も好きだけど、また違ったよさがある
基本、小説が原作の映画って、小説の方が世界が深くて映画は勝てないなと思っていました。
でも、この映画に関しては、小説も大好きだけど、映画は映画の良さがある。
真締さんの描き方は、映画でなければできないものになっている。
僕が一番好きなのは西岡の異動のシーン。
志半ばで、仲間のために自分の身を切らなければいけない悔しさ。
僕はそのシーンで完全に感情移入してぼろなきでした。
もう一回見たいな。
誇らしい
働いてる人におすすめ
主人公の名前通り、馬締(まじめ)な作品でした。舞台が1990年頃?辞書制作を追ったお話ですが、辞書中の言葉がルーズソックス、チョベリグーなど古い。対象年齢は30才~。
恋愛模様は描かれず、仕事(辞書制作)の話がメインです。地味な作業で、面白くはないです。作中では辞書が完成するまでに13年かかります。それもひとつひとつ手作業で、大変な仕事だと思いました。
もともと雑誌の営業部に所属していた主人公でしたが、本が好きで無口な性格で友達もいないため、周りからは疎んじられていました。そんな時、人手が必要な辞書部に、主人公が引き抜かれるのです。営業に向いていない主人公にはいい出会いだったと思います。
そしてグッときたのが、終盤の「ありがとう」のセリフ。黙々と辞書制作に取り組んできた地味な主人公だけど、ちゃんと見てくれている人はいて、感謝されている所に惹かれました。
仕事関係で悩んでいる人は、見ると心が軽くなるような作品。
厚い辞書にはアツい情熱を!
この物語は、ある出版社のお荷物部署だった辞書編集部が、新しい辞書『大渡海』という辞書を作るというお話。
コミュニケーションを取るのが苦手で、下宿屋のおばさんにしか心を開けなかったマジメ君(松田龍平)が、辞書作りを通して自分の仕事に生き甲斐を見つけたり、かぐやさん(宮崎あおい)と恋に落ちたりするエピソードを辞書が完成するまでの13年間と共にゆっくり描かれる。
この映画が好感が持てるのは『日の当たらない仕事をしている人にも等しくやり甲斐や光が当てられている』からなのかもしれないな。
他人から『お荷物部署』と白い目で見られようと、地味な繰り返して気の遠くなるような作業だとしても、そこには必ず面白味もやり甲斐も存在し、情熱を傾けるだけの価値はあるのだ。
そんなメッセージがほんわか伝わってくるようで、見終わった後の印象は不思議なほど温かかったな。
『当たり前なんだけど、なかなか語られない』部分に焦点をあてたこの映画は、先の見えない仕事を抱えている人や仕事に意義を見いだせない人にとって、優しい応援歌なのかもしれないな。
すくなくてもオイラにはそう思えたんだ。
純粋すぎてなかなか人と分かり会えない主人公(名前もマジメ君w)や下宿屋の娘のかぐやさんなど、人物の深みにやや物足りなさも感じないわけでもないけど、それでもあえてセリフで語るのではなく雰囲気で関係性や心情を語るという手法は「これは映画なんだ」って思えるような演出で満足。
チャラいんだけどマジメ君の熱意に感化されて、部署を離れてもサポートし続けるオダギリジョーや、一般部署から配属されて変人だらけの仕事場にとまどいながらもちょっとづつやり甲斐を見つけだす新人女性社員といったキャストもすげー適役だった。
特に新人社員は「むしろこの子の目線の方が観客に一番近い目線を持っている」感じがして好感を持てたことも、話の作りとして感心した部分だったりした。
もうちょっと辞書づくりならではのニッチな知識を見たかったような気もしたけれど、語られるのは『辞書がどう作られるか』ではなくて『そこに携わる人々の想いや熱意』だと考えれば納得もつく。
「今の仕事がつまらない」と思う人や、抱え込みすぎた宿題を前に途方に暮れている人にこそ見て欲しい映画だと思うんだ。
『厚い辞書を作るには熱い情熱が必須』
熱意こそが世界を動かす、
のかもしれないな(笑)。
あたたかい気持ちになりました。
・ひとつのことに情熱を持って長年打ち込める人は、魅力的だし凄いと改めて思った。辞書編集という一見地味な仕事を通して、湧き上がる喜びや達成感、それを通じて出会った仲間。素晴らしいです。
・営業にいたときは「できない」レッテルを貼られていた彼。でも一方で辞書編集の仕事を営業で件数を取ってる人間が成し遂げられるかといえばそうでもない。適材適所の良き例でもある。
・大きな展開はなく、驚くようなことも起きない。海外に行ったりめちゃくちゃ有名になったり億万長者になったわけでもない。そんな静かな、一見すると同じ事の繰り返しに見える毎日が、いかに本当はエキサイティングで素晴らしいものか。改めて教えられた気がします。
日本の良さが缶詰めのように詰まっている
普段シドニーで邦画がタイムリーにみられることはあまりない。でも今回はシドニー日本文化交流フイルムフェステイバルのこけら落としに、この映画が上映されて、幸運にも観ることができた。日本では70万人もの視聴者を映画館に動員し、興行成績をあげたそうだ。本当に良い映画だ。
ふだん何げなく使ってきた辞書というものを作る人々が居て、何十年もの時間をかけて、地道に「言葉集め」をして、意味の解釈だけでなく用例集めや使用例を他社の辞書と比較しながら コツコツと編集する、その仕事ぶりに驚かされた。また流行語を含めた新しい言葉を常に探し求めて、新たに辞書に解釈を加えるだけでなく誤用例もあげていく。そんな編集部の苦労する様子が実に興味深かった。20数万語の言葉を収録するために15年間文字通り、一目一目を編んでいくような地道な歩みに目を見張る。
公演された当時、石井裕也監督と馬締を演じた松田龍平とは、共に30歳だったという。若い監督だが、実力がある。上質の落語のような会話の呼吸、間合いの良さが秀逸。誰かが何かを言う。その瞬間にガラリとその場の空気が変わり、居合わせた人がそれぞれその人なりの反応をする。その間合いと、変化の仕方をしっかり演技で見せてくれる役者たちがとても生きている。見ている人が自分の体験を思い起こしてその場にすんなり納得できて 深く共感できる。
香具矢に一目ぼれをして腑抜けになった馬締が出勤してきたところを、松田が後からふざけて脅かしただけなのに、その場に崩れ落ちて腰をぬかして立ち上がれないシーン。人とうまく話ができない馬締にちょっとした冗談やおふざけが通じなくて、かえって慌てる人の良い西岡がおかしくて笑える。西岡は一見軽薄に見えるが実は情のある、良くできた男だ。私は映画の登場人物の中でこの西岡が一番好き。社の予算が足りなくなって、馬締か西岡かどちらかが辞書編纂部から広報部に移動しなければならなくなって、それを誰にも知らせずに自分から潔く部を去っていく。後からそれを知らされて、馬締が必死で西岡を追うが突き返されて言葉を失い茫然と佇むシーンも印象的だ。どっちもいい奴なんだ。
編集部の面々が馬締が恋の病に陥ると すかさず香具矢の勤める料理屋に予約をとる、その息のあったチームワークの良さには笑いを誘い人の心をなごませる。編集長松本の人柄の良さゆえだ。仕事の後で居酒屋に皆を連れて行き、本音で部下との交流を図る。部下たちは熱い親父には勝てない、と文句を言いながらその親父を慕っている。こんな職場で働きたいと思う人も多いだろう。家族のようだ。
役者がみんな良い。西岡を演じたオダギリジョーがとても良い。この役者、個性の強い役柄を演じることが多いが、この映画のような普通の男を演じると、すごく光っていて魅力的だ。加藤剛と八千草薫の夫婦も良い。本当の仲の良い夫婦が一緒に年を取ったみたいな穏やかで心地良い空気を作っている。
主役の松田龍平と宮崎あおいは、難しい役を上手に演じている。
馬締は軽度のアスペルガー症であるらしい。これは 自閉症の一種でオーストリアの小児精神病医ハンス アスペルガーによって命名された症候群。対人関係に障害をもち、特定分野に強いこだわりを持ち、軽度の運動障害をもつ。知的水準は高く、言語障害も持たない。子供の時に「b」と「d」、「つ」と「て」、「わ」と「ね」の区別ができず、鏡文字を書いたりして発見されることが多い。ふつうに学校生活た社会生活ができ、「ちょっと変な人」くらいに認識されて何の問題もなく、家庭を持つ人も多いが、社会適応ができず ひきこもりやうつ病を併発する人も多い。ひとつのことに偏執狂のように異常な興味を持つ特性を生かして、芸術分野で優れた結果を出す人も居るが、自分の興味ない分野には、きわめて冷淡になる。そういった難しい役を松田龍平は、若いのによく演じていた。お父さんは松田優作だそうだが強い役者遺伝子を受け継いだみたいだ。1988年バリー レヴィンソンの「レインマン」で、トム クルーズと共演したダステイン ホフマンが重度の自閉症を演じている。きっと松田龍平は役作りの過程でこのダステイン ホフマンを100回くらい見たのではないだろうか。
この作品、日本映画製作者連盟から、アカデミー賞外国語映画部門に出品されたそうだが、欧米で評価されるだろうか ちょっと心配。「仕事人間、過労死、残業クレイジーニッポン」の典型みたいに見られないといいけど、、。個が確立していて、個人生活重視、公私混同を嫌い、時間がきても仕事が終わらなくて残業すると自己管理ができない無能者とされ、残業どころか休暇は締切だろうが何だろうが、きっちり取る、、、他人の個人生活に介入しないことが礼儀とされて、職場ではどんなに信頼できる仲間でも互いの私生活には関心を持たない、、、そういった欧米型社会で育った人達に、この映画の良さがわかるだろうか。
編集長の部下に対する父親のような愛情、家庭よりも仕事への情熱、苦労を分かち合うことによって育つ職場での結束、仲間の犠牲になって自分から移動になる潔い部員、ボスへの敬愛、自己主張の強かった新人が職場の空気に染まっていく様子、夫を思いやり自分を決して主張しない謙虚な妻、家族の理解、愛情の示し方が下手だが心から妻を愛する夫。個を超えた共同体の中でこそ自分たちの達成感、満足感を充足させる日本人特性。日本人の優しい労わり合い。あうんの呼吸で仲間が育っていく環境のやさしさ。謙虚と潔さ。熱すぎず、ぬるすぎない、ぬくくて温泉みたいに心地よい映画だ。。映画を観ていると、日本人って、何て良いんだろうと思う。
さて、外国人はこれをどう観るか。作品は、アカデミー賞に輝くだろうか。結構、高く評価されて、「シャル ウィー ダンス」みたいに、この映画の欧米版「オックスフォード辞典を編む人々」なんていうコピー映画を、エデイー レッドメインみたいなハンサムな役者が主演して大成功するかもしれない。わくわくする。
辞書作りも人生も一つ一つ丁寧に紡ぎ出していく
評判も非常に良く、本当ならば劇場で観に行きたかったのだが、近くの映画館でやってなかった事もあり、レンタルになるまで待つしかなかった(泣)
そうこうしている内に来年のアカデミー賞外国語映画賞の日本代表にも選出。期待は高まるばかり。
ようやくレンタルリリースされ、鑑賞。
メチャメチャ好きなタイプの映画。去年の「わが母の記」もそうだが、クスッとさせられしみじみとさせられる、日本映画の良心とも言うべき作風は、どうしても自分の心に直球ストライクなのだ。
辞書作り。
こんな地味そうな話が映画になるの?
なるんです!
むしろ、映画向きの話だと思う。
こういう知られざる世界を描いた作品は邦画の名作に多々あるし、主人公の姿や恋と絡め、言葉への敬意に溢れ、人と人の交流の尊さも描き、素晴らしき人間讃歌&職業讃歌になっている。
主人公、馬締光也のキャラクターがいい。
名前の通り真面目だが、口下手、コミュニケーション下手、内気、不器用、ちょっと変人さん。
何だか自分を見ているようで共感せずにはいられなかった。
そんな馬締が、密やかながらも殻を破り、ひたむきに情熱を傾ける姿に、誰が文句をつけられるだろう?
元々個性的な演技が光っていた松田龍平がまた巧い。ホント、何をやらせても器用な演技派である。
新旧実力派のアンサンブルも極上。
一人一人挙げていったらとてもじゃないけど文字数が足りないので泣く泣く割愛するが、特に、映画にいいメリハリをつけてくれたオダギリジョーの妙演と、穏やかで優しい加藤剛の存在感が特筆。
下宿のタケおばあさんと契約社員の佐々木さんの好サポートもナイス。
石井裕也監督、グッジョブ!
企画から完成、辞書が出来上がるまで、実に十数年。
言葉を収集し、意味を調べ、校正を重ね、かつオリジナリティも出す。気の遠くなるような作業。
そのなかで幾つものドラマも生まれる。
あわや発行中止になった時は、続行の為奔走。
発行直前にミスが発覚した時は、皆で泊まり込みで再確認。
十数年という歳月の中で、出会いもあれば別れもあり、友情や団結力も育まれ、次第に主人公も成長していく。
辞書作りという作業に留まらない、人生そのもの。
仕事も恋も一つ一つ丁寧に紡ぎ出していき、自分だけの人生という名の辞書が完成する。
言葉は生きている。
熱中出来る天職があるって素晴らしい。
「大渡海」が欲しい。
人生って面白い。
原作のキャラが足引っ張ってる気が
原作は読んでいる。それの映像化として期待される辞書編纂作業をしっかり映像化してヘェ~って感じにはなる。ここは小説より断然上。映像向き。ただ、原作にあるほとんどファンタジー(メインふたりの名前が既にそう)なキャラクターがひとつ抜けてこない感じ。テレビ的な平面さというか、テレビみたい、と思った。
いい話ではあるけれども、松田龍平、宮崎あおい、そして素晴らしかった加藤剛も、書き割りの先にいけてないというか物足りない。唯一オダギリジョーだけが完全にキャラクターをすいすい演じていた。ということで、多分、監督もこのキャラクターだけが救いだったのではないか。面白みがないので端正にやらざる得ない。思えば、原作がなんとか大賞をとっているというのだが、そんなにたいした内容ではなく、辞書編纂をネタに石井裕也監督が、伊丹十三くらいに取材効かせて描きあげたほうが良かったんじゃないかという気がしてくる。それくらい原作のキャラクターに足を引っ張られていた気がする。いい映画かもしれないが、突き抜けてこない。完全に物足りない。
「まじめ」に生きる
観終わってすぐ、「用例採集したいね~!」と友人と言い合いながら映画館を後にした。
そのくらい、辞書編纂に携わる人達の生き方に魅了された。
不器用で真面目な馬締を演じた松田龍平さん、
チャラ男風な同僚・西岡を演じたオダギリジョーさん、
このお二人の演技は素晴らしいの一言に尽きる。
クスっと笑えて、静かだけど温かさが画面から伝わってくるような。
馬締を取り巻く人々も、味があって良かった。
個人的には、契約社員の佐々木さんのナイスフォローがツボだった。
作品を貫かれる、辞書を作り上げるという過程の中で起こる事は
決して派手ではないが、ひたひたと感動が広がるものだった。
いやぁ、良い作品だったな~。
静かに燃え続ける炎のような情熱
辞書編纂の仕事への情熱は、静かに燃え続ける炎のようでした。面白かったです。
大きな会社の人事のシステムはよく知らないけれど、馬締さんを営業に配属するセンスって分からない。会社が辛くなる前に、天職のような仕事に出会えて良かった良かった。
馬締さんの時間は手巻きの柱時計のように、秒針に煩わされず、着実に丁寧に過ぎているのでしょう。いつの間にか背中で人を引っ張る編集者に成長している馬締さんが頼もしいです。
キャスティングはみんな気持ちよくハマっていました。若い編集者役の黒木華、可愛いらしかったです。
加藤剛の健在ぶりが嬉しかったです。松田龍平演じる馬締さんの師匠、情熱的に辞書に向き合う松本先生を熱演でした。
昔、新○○国語辞典の第○版が、編者の色が出ていてユニークだと聞いて古本屋にあたってみたけど、愛好家が大事にしていて手放すことは稀なんだそうです。愛され使い込まれる辞書は素敵。
馬締さんの「大渡海」はとても信頼できそう、それが彼の色です。
いつも、ああやって言葉集めしてるの?
映画「舟を編む」(石井裕也監督)から。
「三浦しをん」さん原作の小説と今回の映画、
共通している部分とオリジナル部分の比較は、
書籍と映画、両方を楽しむ私のライフスタイルには
ピッタリの題材であった気がする。
読書後のメモと、鑑賞後のメモを比べると、映画の方が、
宮崎あおいさん演じる「林香具矢」さんが輝いていた。
松田龍平さん演じる主人公・馬締光也さんが、下宿で
可愛がっている猫に「迎えにきたよ」と声を掛けたら、
香具矢さんが「迎えにきてくれたんだ」と登場するシーン、
昔話「かぐや姫」で月からのお迎えがくる場面とダブった。
また2人が出会った頃、料理人として修行をしていた
「梅の実」から彼女が独立したお店の名前が「月の裏」。(笑)
彼女が「みっちゃん」と呼ぶ「光也」という名前も、
「月の光」に関係しているのかな、なんて想像してみたり。
(「満月」をもじって「満也」も面白かったけれど・・)
こんなことをメモして楽しんでいるなんて私くらいかな。
ところで、どんな場面でも「用例採集カード」を欠かさない
馬締に、香具矢さんが笑いながら問いかける。
「みっちゃんて、いつも、ああやって言葉集めしてるの?」
私も宮崎あおいさんに言われてみたいな。
「しもさんって、いつも、ああやって言葉集めしてるの?」
全258件中、201~220件目を表示