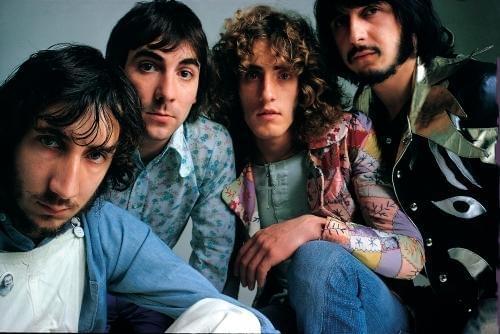ザ・フー:アメイジング・ジャーニー
劇場公開日:2008年11月22日
- 予告編を見る
- U-NEXTで
関連作品を見る PR

解説・あらすじ
英国が誇るロック・バンド“The Who”の栄光と軌跡を総括するドキュメンタリー。フー初期の幻のライブ映像などがスクリーンに蘇る。また、スティング、エディ・べダー(パール・ジャム)、ノエル・ギャラガー(オアシス)、エッジ(U2)ら現在のポップ・ミュージック界のトップ・スターたちがカメラの前に登場し、伝説のバンド“The Who”を熱く語る。監督は「毛沢東からモーツァルトへ/中国のアイザック・スターン」のマーレイ・ラーナー。
2007年製作/237分/イギリス
原題または英題:Amazing Journey: The Story of The Who
配給:ヘキサゴン・ピクチャーズ
劇場公開日:2008年11月22日
スタッフ・キャスト
- 監督
- マーレイ・ラーナー
- 製作
- ナイジェル・シンクレア
- ロバート・ローゼンバーグ
- 製作総指揮
- ビル・カービシュリー
- ガイ・イースト
- 脚本
- マーク・モンロー
- 編集
- ポール・クラウダー






 ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド セッション
セッション アリー/ スター誕生
アリー/ スター誕生 レ・ミゼラブル
レ・ミゼラブル SING/シング
SING/シング はじまりのうた
はじまりのうた ウィキッド ふたりの魔女
ウィキッド ふたりの魔女 ウォンカとチョコレート工場のはじまり
ウォンカとチョコレート工場のはじまり 蜜蜂と遠雷
蜜蜂と遠雷 BLUE GIANT
BLUE GIANT