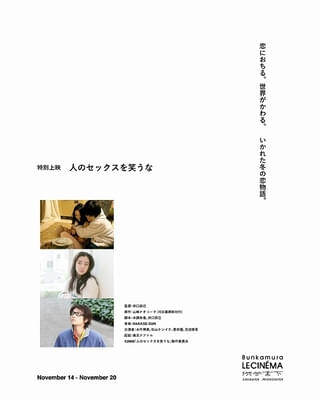ネタバレ! クリックして本文を読む
桐生と玉ノ井テアトルが私で接続される。
その喜びはきっと私だけだと思うが、チベットに見間違えられる荒涼の地であんなドラマが起こっていたとは…感動です。
さて、小津なんです。私も意味が分からない。世俗的な恋愛映画(のようにみえる)でなぜこんなことを言わなければならないのか。でも間違いない。松山ケンイチ演じるみるめが、ユリの前で始めて衣服を脱ぐとき、そこには赤いヤカンが置いてある。これは完全に意図的だ。ではなぜやるか。
それは小津作品を語る主題系「着換えること」「階段」「見ること」をリフレインさせながら、小津にあった儀式による成長を批判的に描くためだ。
本作では以下のエピローグが語られる。
「会えなければ終わるなんてそんなもんじゃないだろう」
これは明らかに後期小津作品に対するアンチテーゼだ。後期小津では、父娘の物語が主に展開される。そして娘が花嫁衣装に着換え、嫁ぎにいくことで二人の関係が終わることが語られてきたことだろう。極めて単線的な人生観。しかしこの「結婚」という儀式が人々を嫌が応にも変化させ、人生を前に進ませたのだ。
しかし現代はそうではない。単線的に人生は進まない。そうではなくラストシーン近くで、みるめとえんちゃんが原付の二人乗りでロータリーをぐるぐる回るように円環的な人生構造だ。セックスをしてもみるめとユリは、夫婦にはなれない。セックスができなくてもみるめとえんちゃんは関係を変えていく。そしてユリの人物像がはじめ朝帰りをした未熟な女子大生から、先輩の女子大生、研究者の独身女性、別の男の妻へと変化し、放浪によりはじめに戻るようにとても円環的だ。
それでは儀式ではなくて何が人物を変化させるのか。それは着換えである。そこは小津を踏襲している。しかし本作で主に着換えられる場面は、セックスの時であるのだが。
さらに階段でも人物は変化する。玉ノ井テアトルで階段を昇ってみるめとユリが出会い、えんちゃんが目撃するように。キャンパスで階段を昇るように。しかしそれもまた円環構造に回収されるかのように、ユリはセックスでの着換えの場面で階段昇降をして「不在の階段」を立ち現せてみせる。そこにはどこか円環構造の閉塞感が見受けられる。
「見ること」に伴う人物の位置は周到に考えられている。対面にするのか、横位置につくのか。またユリの家での夫とユリとみるめの座り位置と、みるめの家でのみるめと父とえんちゃんの座り位置が対比になっており、そこでの人物のずれが関係のずれを描いてもいる。ショットにおける人物の位置と運動の方向はまだ自分の中で判然としない。けれどきっと法則があるし、意味がある。ひとつ思うことは横位置から対面になり、その距離を零にするためにキスのアクションが導入されているし、ならないときは人物が移動せざるを得ないということだ。他にも出血する出来事がどのような意味を生じさせているのか、まだ分かっていない。
本作はまだちゃんと「見られていない」。だからかの老人が小津作品のよさを発見したように、私も本作のよさを発見し、記述するためにこれからも見続けていきたいと思う。











 ロストケア
ロストケア 朝が来る
朝が来る ノイズ
ノイズ プロメア
プロメア 聖の青春
聖の青春 八日目の蝉
八日目の蝉 大河への道
大河への道 聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団
聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団 GANTZ
GANTZ ホテルローヤル
ホテルローヤル