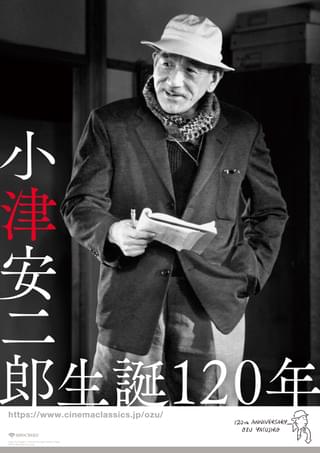小早川家の秋
劇場公開日:1961年10月29日
解説
他社進出三本目として小津安二郎がメガホンをとるホームドラマ。脚本は「秋日和」につづいて野田高梧と小津安二郎のコンビが執筆。撮影は「女ばかりの夜」の中井朝一。宝塚映画創立十周年記念作品でもある。昭和36年度芸術祭参加作品。
1961年製作/103分/G/日本
原題または英題:The End of Summer/Early Autumn
配給:東宝
劇場公開日:1961年10月29日
あらすじ
秋子は小早川家の長男に嫁いだが、一人の男の子を残して夫に死なれてからは御堂筋の画廊に勤めている。代々、造り酒屋で手広い商売をしてきた小早川家も、万兵衛が六十五になり今は娘の文子のつれあい久夫に仕事が渡り、万兵衛は末娘の紀子と秋子をかたづけるのに頭をつかっていた。文子たち夫婦も、店の番頭信吉、六太郎も、この頃、万兵衛の妙に落着かない様子に不審を抱いていた。或る日、六太郎は掛取りを口実に万兵衛の後をつけた。万兵衛は、素人旅館「佐々木」に入っていった。女道楽ばかりしてきた万兵衛で、競輪の帰り十九年振りにバッタリ逢った焼け棒杭がつねだった。つねは百合子と二人で暮らしていて、百合子は万兵衛をお父ちゃんとよんでいる。秋子には、万兵衛の義弟に当る弥之助の世話で磯村との話が進んでいた。磯村は一生懸命であるが、秋子の気持はどうもふんぎりがつかない。一方、紀子もお見合いをしたもののこれも仲々決めようとしない。紀子は、札幌に行った大学助教授寺本に秘かな愛情を寄せていた。亡妻の法事の日、嵐山で一晩楽しく過ごした小早川家一族は、万兵衛の病気で大騒ぎとなった。心臓が痛いというのである。が、翌朝になって万兵衛は、ケロリとして起き上り皆を驚かした。万兵衛はその日にまた佐々木の家に行った。万兵衛はつねと一緒に競輪を楽しみ、その晩佐々木の家で心臓の発作を起して息を引き取った。お骨ひろいに一家は集った。久夫はいよいよ合併が近いことを洩らした。小早川家の商売も、大資本の波におしまくられ企業整理のキッカケが、万兵衛という柱が亡くなって一遍にやって来たのだ。文子は「小早川の家が何とかもったのも、お父ちゃんのお蔭やったんや」とつくづく思った。紀子は札幌に行く決心をした。秋子も心から賛成したが、自分は再婚しないで今のままでいようと思った。火葬場の煙は一族の者にそれぞれの思いをしのばせながら秋めいた空に消えていくのだった。





 東京物語 ニューデジタルリマスター
東京物語 ニューデジタルリマスター 晩春
晩春 秋日和
秋日和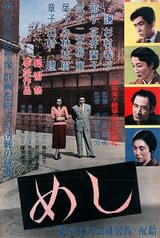 めし
めし 秋刀魚の味 ニューデジタルリマスター
秋刀魚の味 ニューデジタルリマスター 麦秋
麦秋 お早よう
お早よう 東京暮色
東京暮色 彼岸花
彼岸花 早春
早春