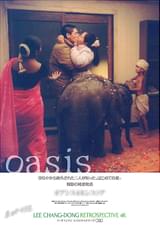巨匠イ・チャンドンを形成したものとは?「“苦しい”という体験が、私に大きな影響を与えていた」
2023年8月25日 09:00

韓国を代表する巨匠イ・チャンドンの全作品を初の4Kレストアで一挙上映する特集「イ・チャンドン レトロスペクティヴ4K」が、8月25日から開催されている。初期の傑作「ペパーミント・キャンディー」に加え、「バーニング 劇場版」「ポエトリー アグネスの詩」「シークレット・サンシャイン」「オアシス」「グリーンフィッシュ」をラインナップ。さらに、上映プログラム作品と呼応するようなドキュメンタリー映画「イ・チャンドン アイロニーの芸術」も披露される。
日本初のレトロスペクティブ上映の開催――イ・チャンドン監督は、情報解禁時に、このようなコメントを寄せている。
映画を保存するため、過去の映画と新たな観客と出会い結び付けるためにも、必須だと思います。元々のクオリティを維持するための綿密な作業には時間と費用を要し、その映画に関わった監督やスタッフが作業に携われない場合もありますが、幸いなことに、私は今回その機会を得ることができました。当時の映像の雰囲気や印象、そして感情を味わえることに努めてアップグレードしましたので、そこに注目して観てもらえたらと思います。
とても嬉しく、大きな期待を寄せています。私はいつも韓国のほか日本、欧米など遠くにいて違う文化圏にいる観客であっても、人間であれば、根本的に共有や理解、意思の疎通ができると思っています。今回のレトロスペクティヴを通して、私たち人間について、人生について、皆さんと分かち合えればと思います。新しい日本の観客の皆さんとお会い出来ることを楽しみにしています。

イ・チャンドン監督は、8月上旬に来日を果たし、日本のファンと交流を深めていた。映画.comでは、同タイミングでインタビューを実施。「イ・チャンドン アイロニーの芸術」にフォーカスし、これまでの“歩み”について語ってもらった。
 (C)MOVIE DA PRODUCTIONS & PINEHOUSE FILM CO., LTD., 2022
(C)MOVIE DA PRODUCTIONS & PINEHOUSE FILM CO., LTD., 2022韓国の名匠イ・チャンドンの創作の原点と人生に迫るドキュメンタリー。イ・チャンドンが自ら水先案内人を務め、作品のロケ地や幼少期に過ごした場所などゆかりの地を訪れながら、43歳にして小説家から映画監督に転身した異色の経歴や、自身の芸術に対する思い、創作の原点について率直に語る。さらに、ムン・ソングン、ソル・ギョング、ソン・ガンホ、チョン・ドヨン、ムン・ソリ、ユ・アインら、これまでイ・チャンドン監督作を彩ってきた豪華俳優陣や制作スタッフも登場し、撮影当時を振り返っている。
監督を務めたのは、フランスのドキュメンタリー映画監督アラン・マザール。イ・チャンドン作品に魅了されたマザール監督の発案でプロジェクトがスタート。コロナ禍での困難を逆手に取る形で当初被写体であったはずのイ・チャンドン監督が、彼の制作会社パインハウス・フィルム全面協力のもと水先案内人として深く携わっている。
 (C)MOVIE DA PRODUCTIONS & PINEHOUSE FILM CO., LTD., 2022
(C)MOVIE DA PRODUCTIONS & PINEHOUSE FILM CO., LTD., 2022「イ・チャンドン アイロニーの芸術」は、まず最初にアラン・マザール監督の方から「あなたに関するドキュメンタリーを作りたい」という提案があったことから始まっています。私自身も改めて考えてみたところ、ある映画を観た時に“監督について気になることが生じる”ということが、よくあったのです。もちろん作品として受け入れますが、その次に「これを作った人はどんな人なのだろうか」と、監督の人間性を含めて知りたいという気持ちになりました。ですから、監督や芸術家に関するドキュメンタリーは必要なのではないかと思いました。
アラン・マザール監督は、私について色々気になっていることがあったようで「直接会って話がしたい」と言ってくれましたが、当初はそれが私にとってのプレッシャーになっていました。例えば、日本で作品が公開される時、宣伝のためにインタビューを受けることがあります。日本だけでなく、他の国を訪れたり――(その動きは)韓国でも同様です。宣伝の時期が終わると、可能な限り、メディアと接触しないようにしてきていました。講義もなるべくしない方がいいとも思っていました。なぜかと言えば“作品だけを通して観客と触れ合いたい”という思いがあったからです。それ以外の話をするということは、ある意味、観客に対して干渉するようなことになるのではないかと感じていたのです。
ですから、今回のお話をいただいた際、やるべきか、やらないべきか……と考えました。その葛藤を経て「観客のために、このようなドキュメンタリーも必要だろう」という考えに至り、参加をすることにしました。
「ペパーミント・キャンディー」のような構造でドキュメンタリーを撮るというアイデアは、最初の段階から知らされていました。そのような構成にすると、私の人生を振り返ることになりますし、素敵なものを見出せるような気がしていたんです。
「ペパーミント・キャンディー」は“時間をさかのぼる”という構造を選択して作品を生み出したわけですが、当時、こんなことを考えていました。原因があり、それに伴って結果というものがある。時間というものは、そのように流れていくわけです。それが逆になるということは、結果を先に知り、原因に辿り着くということになります。すると、より“時間の意味”を知ることができるのではないかと考え、「ペパーミント・キャンディー」の構造に採用しました。

私たちはどのような未来が待ち受けているかわからないまま生きていますよね。でも、未来がわかっていて、過去を振り返るということになれば“時間の意味”について考えることができます。この時間にこのような選択をしていた――そこに生じる意味もわかるのではないかと思っていました。
今回、同じような提案をいただいたので、私の人生を振り返るきっかけにもなりました。人生を振り返りながら、色々なものを感じとることができたのですが……新しく感じたもの、新しく知ったものは何かと問われると、答えることが難しいですね。でも、たくさんの選択、たくさんの失敗、たくさんの努力によって、これまでの時間を過ごしてきたのだなということを改めて実感しました。
どうして映画監督になったのか――これはかなり長い話になってしまうので、なかなか簡潔に言い表すことができません。個人的かつ、さまざまな問題が生じたうえ、映画監督という職業に辿り着くことになりました。当時の韓国は、複雑な時代でもありました。そういう状況の中にありましたが、実は“小説家を辞め、映画監督にならなければならない”といった強い決心や意志を持って、映画界に入ったわけではなかったんです。ある意味、偶然のきっかけがあって、映画界に入ることになりました。
 (C)MOVIE DA PRODUCTIONS & PINEHOUSE FILM CO., LTD., 2022
(C)MOVIE DA PRODUCTIONS & PINEHOUSE FILM CO., LTD., 2022私の友人に、映画監督のパク・クァンスという方がいます。ある日、彼から電話がかかってきました。「『あの島に行きたい』という小説を映画化したい。作者として話をしてくれないか」という内容でした。私は、同作の作者イム・チョルさんを知っていましたし、友人でもありました。そのような流れで、3人で会う機会を設けることになったんです。映画化するにあたり、その場でプロットのアイデアを少し話すと、パク監督が「シナリオを書いてみないか?」と提案してきました。そこからシナリオを書き、さらに助監督としても参加することになりました。
助監督については、監督になるための修行の一環というよりも、当時の自分は人生の転機を求めており「何か辛いことをやってみたい」という気持ちだったんですね。助監督の仕事は、非常に辛いもの。だからこそ、助監督をやってみたくなり、さまざまなことを経て、結果的には映画を作ることになっていきました。
書いてみたいという考えはあります。そして、書きたいと思っている題材もあります。でも、それは一種の夢のようなものです。それが叶うかどうかはわかりません。

とても大きな影響があったと思っています。ドキュメンタリーの中では、主に姉や兄の話をしていますが、父や母も含めて、家族全員が、私に大きな影響を与えていました。子どもの頃の経験が“私”を形成してくれたとも言えるでしょう。
その時の経験で味わったのは「人生の苦しみ」です。当時は朝鮮戦争の直後でもありましたので、全ての人たちが“苦しい”という状況の中で時代を生きていました。「苦しみを味わう」というのが、基本的な条件だったのです。
とはいえ、家庭によっては状況は少しずつ違っていたとは思います。トルストイが「幸福な家庭はどれも似ているが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである」ということを言っています。私たちの家庭には“不幸なこと”がたくさんありました。不幸だということは、すなわち苦しいということです。“苦しい”という体験が、私に大きな影響を与えていました。
特に内面に対して、大きな影響が生まれていたと思います。だからこそ、小説を書いたり、映画を作った時に、その作品を通して、それが滲み出ているような気がしていますね。小説でも、映画でも“人生の苦しみ”が描かれている。その苦しみをどう乗り越えて、どのように癒していくのか――そういう問いかけがある部分にも、影響が表れていると思っています。
関連ニュース





Netflix、今年の韓国ラインナップ33本発表 BLACKPINKジス、チョン・ヘイン、パク・ウンビン、チャ・ウヌ、永山瑛太、ソン・ヘギョら豪華俳優陣が勢揃い!【あらすじ・キャスト一覧】
2026年1月21日 17:00

映画.com注目特集をチェック
 注目特集
注目特集 メラニア
世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?
提供:イオンエンターテイメント
 注目特集
注目特集 神の雫 Drops of God
【今、この作品にハマりにハマってます】人間ドラマとミステリーがとんでもなく面白い!!
提供:Hulu Japan
 注目特集
注目特集 “超怪作”が最速配信!!
【“それ”に踏み込んではいけなかった――】2025年で個人的に最も“混乱&ゾクッ&快感”きた注目作
提供:JCOM株式会社
 注目特集
注目特集 ブゴニア
【事件です】あり得ないほどすごい映画がくる――ヤバいエグいの類の言葉じゃ“追いつかない”異常事態
提供:ギャガ
 注目特集
注目特集 映画.com編集長もドハマり“極限スリラー”
【大傑作「ヒート」級】規格外の“演技力”と“魂の殴り合い”が生み出す、ヒリヒリとした緊迫感
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント