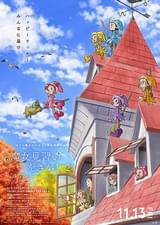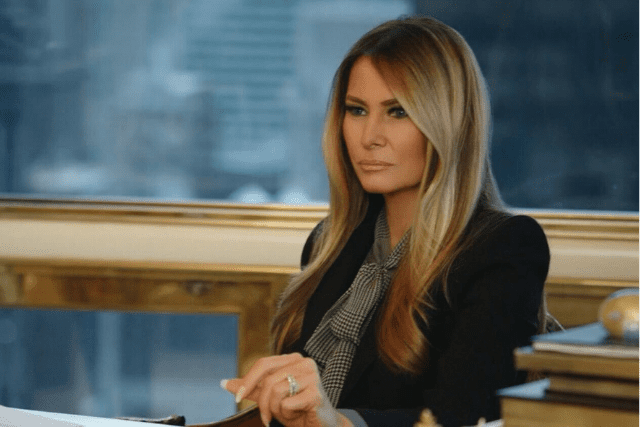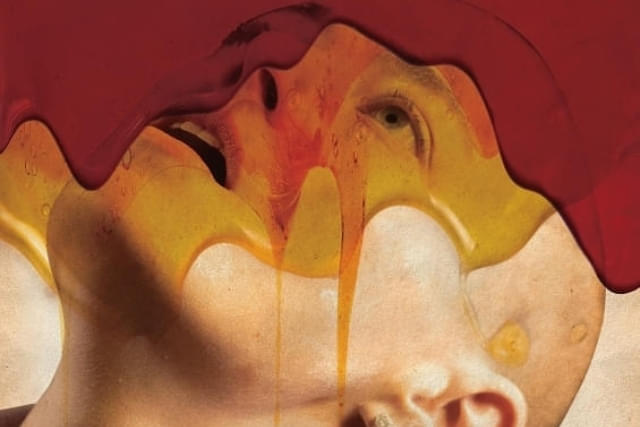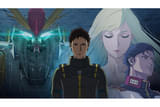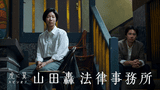我々にはミュウツーとピカチュウの両方が必要 映画「ポケモン」から紐解くキャラクターの歴史と効用
2020年11月4日 19:00

第33回東京国際映画祭のジャパニーズ・アニメーション部門マスタークラス(シンポジウム)「ジャパニーズ・アニメーションの立脚点 キャラクターと映画」が11月3日に開催され、アニメ評論家の藤津亮太氏、SF評論家の藤田直哉氏、相模女子大学教授(マンガ研究・メディア論)の岩下朋世氏がトークを繰り広げた。
今年のアニメーション部門のテーマは“キャラクター”。同部門のプログラミング・アドバイザーを務める藤津氏は「劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲」を上映作品に選んだ裏の理由に、「ポケモン」の世界観を成立させるルールに深く切り込む批評的な映画であったことを挙げる。
人工的につくられたミュウツーというキャラクターは、ポケモンが人間といる理由を問う存在で、「命はどこからくるのか」といった根源的なテーマにも触れられている。藤津氏は「ポケモンの本質を暴露するミュウツーの存在はユニーク」と述べ、藤田氏は、科学が生み出したクリーチャーが人類に牙をむく構造を「ゴジラ」「AKIRA」のタイトルを挙げながら戦後サブカルチャーの系譜に位置づける。
マンガ研究が専門の岩下氏は、マンガにおける先行研究や批評を紹介しながら、キャラクターにはメディアを越えていろいろなところに表れることができる越境性があると語る。メディアを横断し、商品としては複数存在しながらも、受け手にとっては唯一無二の存在として認識される固有性があるのがキャラクターの特徴で、昨今のキャラクターとの関係の結び方についてはポジティブな面とネガティブな面があると指摘する。親しみがもてない物事を“キャラ化”することで寛容性をもってうけとめることができる一方、自分と異なるリアリティをもつ物事を安易に“キャラ化”し、消費の対象にしてしまう危うさもある。藤田氏も、現実を分かりやすく形にするキャラクターには、人を励ましたり勇気づけたりする素晴らしい機能がありつつも、現実を覆いかくしてポジティブなものに錯覚させる危険性もあると語った。
3氏とも「ミュウツーの逆襲」の批評性と物語構造の見事さを称えながら、キャラクターについての議論を深めていった。最後に藤津氏から、ミュウツーのような世界の欺瞞を暴くキャラクターと、この世界で楽しく生きていくための“同居人”としてのピカチュウのようなキャラクターの両方がいることが、これからの我々には必要でないかとまとめられた。
11月7日には、「魔女見習いをさがして」の佐藤順一監督らが登壇するマスタークラス「2020年、アニメが描く風景」が六本木アカデミーヒルズで行われる。第33回東京国際映画祭は、11月9日まで開催中。
関連ニュース






映画.com注目特集をチェック
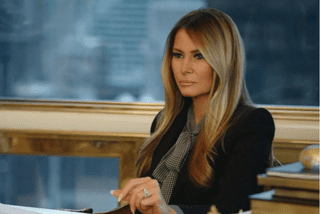 注目特集
注目特集 メラニア
世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?
提供:イオンエンターテイメント
 注目特集
注目特集 今、この作品にハマりにハマってます
人間ドラマとミステリーが…とんでもなく面白い!!
提供:Hulu Japan
 注目特集
注目特集 ネタバレ厳禁どんでん返し衝撃ラスト
【個人的に最も“ゾクッ”とした注目作】このゾクゾク、むしろ快感――ぜひご堪能あれ。
提供:JCOM株式会社
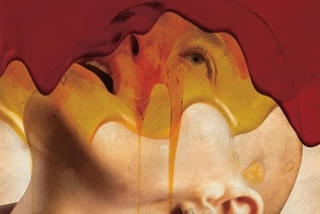 注目特集
注目特集 あり得ないほど“すごい映画”
【とんでもない、事件的な、想像を絶する異常さで…】これはヤバいエグいの類の言葉じゃ“追いつかない”
提供:ギャガ
 注目特集
注目特集 あの“伝説の傑作”級との噂を聞きつけて…
【映画.com編集長が観に行ったら】心の底からドハマりでした…規格外の“物語”と“死闘”に唸った
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
 特別企画
特別企画 アマギフ5000円が当たるX投稿キャンペーン実施中!
【最新作公開記念!】あなただけの“本作との思い出”を教えて下さい! (提供:東宝、CHIMNEY TOWN)