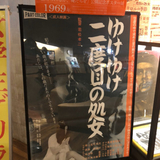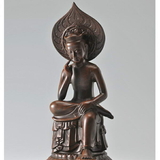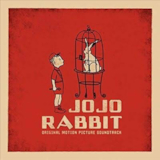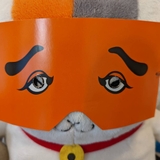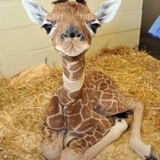ザリガニの鳴くところのレビュー・感想・評価
全296件中、101~120件目を表示
映画という総合芸術の高みを堪能できる名作
封切り当時、チラシ&ポスターのビジュアルやちらほら見ていたレビュー、コメントからなんとなくホラー色を感じてしまい、迷っている間に終わってしまいました。
それでも、映画仲間の人たちにも評判がよく、中には2022ベストムービーと言う人もいたので、ようやく下北沢トリウッドで。
2/11〜すでに上映していたのに気が付かず、3/10(金)で終わるところ、週末駆け込みで。
これは、観れてよかった!
ミステリー要素も映像美の要素も、普遍的な偏見や差別への警鐘も、自然(そのものも、それを体現する主人公という存在)への畏敬も全部入っていてあの完成度は凄い!
ストーリーや映像から芸術への昇華のさせ方などいろんな意味で実に「ビックリ」なクオリティ。
あまりの余韻にパンフレットを求め、映画館のスタッフさんに話しかけ、帰宅途中でじっくりと読んで映画を噛みしめました。
これはもう一度、もう二度見てもまだまだ映画の深みにハマる気がしました。
また、2014年に公開された『MUD』という、、マシュー・マコノヒー主演の少し設定の似た映画を思い出しました。(当時この映画にもいたく感動しました)
ちょっとエキセントリックなタイトルからは全く想像できない、こんなに美しく深層のあるドラマが描かれていたとは(墓場まで持って行く秘密はともかく)、原作にもそれを映像化したプロデューサーのR・ウィーザースプーンと制作チームにも、ただただ脱帽です。
ラストは、流れから「もしかして」と思ったらその通りでした。だからこそ、自然(とそれを体現した主人公)への畏敬がもう一つのテーマになっていると感じました。
主人公のmarsh girlは、荒ぶる自然そのものだった…ということが、映画の最後でわかるのです。
良い映画でした。語りたいです。
原作を読んでとても素敵で美しい作品だと思ったので映画も見た。 映画...
原作を読んでとても素敵で美しい作品だと思ったので映画も見た。
映画のロケ地はノースカロライナではなくルイジアナ州だそうだけど、小説を読みながら想像していた、カイアが生まれ育った湿地帯の美しい姿を映像で見られてとてもよかった。
この小説には様々な要素があって、素晴らしいミステリとしても有名だけど、貧困や差別を描いた社会派文学性もあり、親に捨てられた少女カイアが美しく聡明に成長する姿を描く成長譚でもある。
映画ではその要素が広く浅く取り入れられていて、カイアと恋人たちの恋愛シーンとミステリ要素を主軸にしている。あの濃厚な小説を2時間の映画にするために、やはりいろいろな要素が細切れにされていて、目まぐるしくいろいろな事が起こる。拘置所のサンディ・ジャスティスを映像に詰め込んでくれたのは良かった。
この小説で一番心に残ったのはカイアの成長譚としての要素で、一人の少女が差別や貧困に苦しみながらも賢明に生き、よい人達に出会いながら美しく育ち、そして秘密を残しながら去ってゆくところまでを丁寧に描いていて、それが最後に余韻となって響いていたと思う。
なのでその過程を丁寧に描いている小説のほうが最後の余韻も深く感じた。
あと自然は映像化してもその美しさは変わらないが、人物については映像化するとイメージが固定化してしまうので、文章で読んでいる方が想像力が良い方に働いて自由に読むことができ楽しく感じると思った。
原作を読みたくなる
美しい湿地帯
沼地とドラマ
IMdbが7.1。
RottenTomatoesが34%と96%。
批評家評が異常に低かったが、なにが悪いのか解らなかった。
なにが悪いのか解らなかっただけでなく、RottenTomatoesの批評家がどんなことをダメだと言っているのか想像がつかなかった。
なので批評家の言い分を興味をもって読んだ。
①メロドラマ②原作にくらべて浅い③脚本がよくない──という三つの主張が多かった。が、いずれにしても34%は低すぎて納得できなかった。
そこであっちの批評家評の低さを考察してみた。
おそらく②のことは大きいだろう。
Delia OwensのWhere the Crawdads Singはあっちで1,500万部売れたベストセラーだそうだ。すごく売れた本の映画化なので、精度の高い変換値が要求された結果、拒絶されてしまった感じ。日本で例えるならアニメの実写化で引き起こされたアニメファンの悲鳴のようなもの。ソースが愛されているばあい、総じてソースの愛好者から嫌われる。
また批評家の言説を読み解いていくと原作のWhere the Crawdads Singはもっと性的で禍々しいミステリーを提供していたようだ。marshという環境も含め、もっと沼地と血汗の匂い立つ気配が小説にはあった。(のではなかろうか。)それが綺麗な画に収まってしまったことへの不満が多く、インスタ的(映え狙い)という声も幾つかあった。
②と③は連鎖して、脚本家Lucy Alibarも槍玉にあげられ、何人かがto kill a mockingbird(アラバマ物語)、テネシーウィリアムズ、ニコラススパークスを引き合いにして、それらに比べて浅いと述べていた。
さらに多数の批評家がこれをメロドラマだと指摘しているがメロドラマの定義がアメリカとこちらではちがうので①の指摘がまるでピンとこなかった。
われわれ日本人がメロドラマを感じるのは(たとえば)おしんや渡る世間は鬼ばかりや昼ドラ。演歌のように悲哀を背負って泥臭く辛苦がするのがメロドラマ。対してアメリカではなんらかの障害によって結ばれない恋愛話をメロドラマと言うようだ。ウィキペディアの「メロドラマ」に代表的なメロドラマ映画として嵐が丘風と共に去りぬブロークバックマウンテン逢びき哀愁フィラデルフィアマディソン郡の橋若草の頃私の秘密の花悲しみは空の彼方に、などが挙がっていた。
たしかに尽くしてくれた善人テイトと結ばれず金持ちのぼんぼんで女たらしのチェイスと結ばれてしまうのはメロドラマ的だった。最愛の人がいるのに茨の道をいく──そういうのをメロドラマと言うようだ。
ただしRottenTomatoesの批評家の中には絶賛している人もいた。
以前からRottenTomatoesのトマトメーターに思うことだが、批評家にはひねくれた奴が多い。日本もそうだから驚きはしないが、これが34%ってそりゃねえわ。原作と比べてどうのこうのあるにしても、とりあえず演出技量で測っていいとしたら、本作の演出は手堅いし、撮影も良かった。評点が半分以下というのはあり得ない。
(ただしこれはミステリーというよりファンタジーだった。そこに焦慮している意見が多かった──のは感じた。)
デイジーエドガージョーンズはダコタジョンソンに似ていた。それにともなってぜんぜんちがう話/映画なんだがピーナッツバターファルコンを思わせた。個人的にはそれくらいいい映画だった。
ところで他の人のレビューにもあったのだが、映画のセールストークが本作の価値を貶めているという指摘があった。
どういうことかというとトレーラのキャッチコピーに「最後まで推理が止まらない」とか「結末は正真正銘の衝撃」とかの文言があり、それらを期待して見るとフーダニット映画じゃないから肩すかしを食らうということ。
そのとおりだと思う。
これは謂わばbayouのムードをたのしむ映画であり、カイヤがチェイスをやったんかやってないんかということはどうでもよかった。
カイヤは悲劇的な境遇を背負っているが、攻撃性向のある女でもあるだろう。過酷な家庭環境を生き延びる過程で、相手をやっつける狡賢さも学んだにちがいない。
ただしその非情や心理や推理や衝撃をOlivia Newman監督は、翻案の最前線にポジションさせていない。
沼地の自然で育った少女が人間社会と出会うという話。
だから謎解きというよりピーナッツバターファルコンに近いっていうわたしの感想にご同意いただける方もきっといるにちがいない。
ザリガニって英語でcrawdadって言うんだね
多様性のひとつの形
この物語のバックボーンはタイトルに象徴される湿地帯の自然である。主人公はそこで家族から取り残され一人孤独に、しかし自力で生きていく。やがて、若い男の遺体が発見され、「湿地の女」として蔑まれてきた主人公が犯人とされる。主人公が弁護士にその来歴を語る形で物語は展開し、観客は主人公に感情移入しながら、主人公の生をともに生きていく。テイトとやり取りする鳥の羽や主人公の描く昆虫たちの細密画なども含め、豊かな水の自然は繊細で十分にエモーショナルであり、観客の共感を引き出す。だから私たちは結末を穏やかな気持ちで受け入れることができる。
昨今流行りのダイバーシティという言葉がある。多様性を意味するこの言葉は「みんなちがって、みんないい」(金子みすゞ)というように肯定的なものとして捉えられがちである。しかし、生物の多様性という概念は人間だけでなく自然、ひいては地球環境全体を指すべきものであるし、善や悪という概念を超えたものである。湿地帯の自然とともに生きた主人公は人間の矮小さ、邪悪な性質を退け、観るものにカタルシスと癒しをもたらすのだ。
湿地は全てを飲み込む
ノースカロライナに広がる湿地で1人の青年が死体で見つかった。
容疑をかけられたのはこの湿地で1人生き抜いてきた少女。
裁判を通して明かされる少女の人生と湿地の絆と事件の真相に心が動かされた。
本作は何と言っても画面いっぱいに広がる湿地の美しさ、自然の隅々まで細かく描く繊細さで自分が湿地に存在するかのように圧倒的没入感が凄まじかった。
自然描写だけでなく、人と人との温かい交流、線が引かれる緊張感のあるやり取り、複雑な人間の関わりが本作にドラマ性を加え、事件に引きつけられるミステリー要素もあり、見入ってしまった。
カイアのロマンス、神秘性、ミステリアスの要素が複雑に絡み合い、観た者がずっと考え込んでしまうほど魅力に溢れていた。
湿地は観た者の感情さえも全てを飲み込んだ。
湿地の娘の数奇な運命
この映画(原作未読)は、裁判の場面と弁護人が主人公カイアと会話する拘置所の場面が現在進行形で描かれ、主人公の幼少期から事件前までが自分語りで振り返えられる。
我々は数奇な生い立ちの主人公に感情移入せざるを得ない。
湿地帯の一軒家に取り残され一人で生活する彼女に、町の人々は好奇の目を向けるのだから、可哀想でならない。
自給自足を余儀なくされた少女を、雑貨店を営む黒人夫婦だけが優しく見まもっていた。
この夫婦も、この町で商売を始めた頃は差別の壁にぶつかったのかもしれない。あるいは、子供がいないようなので擬似我が子のように感じていたのかもしれない。
だが、そんな彼らにも本当に彼女を護ることはできないのが現実だ。
もう一人、幼い頃に川で出会った少年テイト(青年期:テイラー・ジョン・スミス)が唯一の友人としてカイアの味方だった。成長して再会したこの青年から、カイアは文字を習い、彼女が湿地帯の生物を観察したスケッチが本になるとヒントを貰う。
ただ、カイアの運命を変えた最大の要因がこの青年でもあるのだ。
湿地帯の風景を捉えた映像、特に若い男女を自然の中心に置いたいくつものシーンの映像美は特筆すべきだ。
併せて、カイア役のデイジー・エドガー=ジョーンズが本作の価値だと言える。
自然に囲まれて一人で生活する逞しさと、他人を警戒する臆病さが同居した少女を繊細に演じていて、遂に暴力に屈しないと誓ってからの強い眼差しが印象的だ。
湿地帯の一軒家で一人で生きていくには、映画で見られる自給自足の苦労だけではなく、自然の驚異があるはずだ。周囲にいる野生動物たちの中には危険なものもいるだろう。
だが、映画で見る限りそれはなく、カイア自身が湿地帯の自然の一部なのだと思わせる。
古い話だが、「ジャングル・パトロール」(だったかな?)という湿原を警備する保安官とその家族を描いたテレビドラマがあった。モノクロだったと思う。内容は全く覚えていないが、ホバーボート(というのかどうかは知らないが、スクリューではなくプロペラで進むボート)で川も沼も(たしか陸地も)走り回っていたのを覚えている。
この映画の舞台とは異なるのかもしれないが、時代背景は近いと思うので、あんなパトロールボートが出てこないか、少し期待してしまった。
さて、法廷サスペンス映画としては、大きな欠点があると思う。
検察側の公訴事実の立証が不明確なところだ。
弁護側を主体とする物語なら、絶対不利な証拠で追い詰められてこそサスペンスが生まれる。
弁護人の台詞で追い詰められた状況だと説明されるが、その一方で状況証拠や証言をあっさり駆逐してみせる。
この展開だから、最後のどんでん返しは想像できてしまうのだ。
差別意識によってバイアスがかけられた裁判だと言わんばかりでリアリティを感じないのだが、時代背景的に『アラバマ物語』('62)と近いことを思えば、未成熟な田舎町の裁判なら、そんな起訴もあり得るのかとも思ったりする。
原作は、アメリカでは2年連続のベストセラー、日本でも本屋大賞を得たというから、恐らく小説ではこの辺りのサスペンスがうまく表現されているのだろう。読んでいないのが恥ずかしくなってきた…😅
ところで、ザリガニは鳴かないのだから、母親が言う「ザリガニが鳴くところ」は存在しない場所だと思う。あるいは、主人公を一人残して最後に逃げ出そうとしている兄からの伝聞だから、母親の言葉ではないかもしれない。兄はザリガニが鳴かないことを知っていて、妹を連れては行けないが、せめて安心はさせようと発した言葉だったのかもしれない。
湿地帯全体を「ザリガニの鳴くところ」と称しているという見方もあるが、父親から逃げる先を指して言われたのだから、違うのではないか。
(鳴かないが、ザリガニが何らかの音を発することはあるみたいだ)
裁判を終えた後日譚では、年老いたカイアと夫が湿地帯で暮らしている。
この裁判を経て、町に変化があったのかは分からない。
湿地帯に暮らし、自らも湿地帯の生態系に身を委ねた"湿地の女"の物語... 魔女裁判の如き法廷で少女が愛と死と憎悪の渦巻く半生を訴える青春映画!!
1950年代のノースカロライナ州の閉鎖的な海辺の田舎街、隣接する湿地帯で街の人気者の青年が遺体で発見され、その湿地帯にただ一人で暮らす年若い変わり者の女性が容疑者として逮捕され、偏見だらけの住民で構成された陪審員たちを向こうに、現役を退いた老弁護士と無罪を訴えて孤軍奮闘する法廷ミステリー。
しかしその一方で、ヒッピーの如き奔放な両親の家庭で育った主人子の少女が周囲からの侮蔑に見舞われながらも学を身に着け、限られた人間関係の中で二人の青年と恋に落ちそして…という青春映画としての側面も色濃いです。
そして何より、そこからのハートフルなエンディングに差し掛かったところでの冷や水を浴びせかけられるようなどんでん返し・・・"自然と生きるには何よりも生物として強かでなくてはならないのか"と嘆息するような余韻も有ります。
ミステリー映画はスッキリ胸が晴れる結末か、それともやがて来る暗雲を予期させる鬱な幕切れのどちらかに振り切った作品が最近とみに多いように感じますが、本作のそのグラデーションぶりはなんとも言えない味わいでした。
ただ、生きるために。
小説未読、前情報は予告のみ。
昨今流行りの「驚愕のラスト!!」と意外な結末を売りにした予告が印象的で、どんなサスペンスドラマなのかと楽しみに鑑賞。「グリーンナイト」後のハシゴ鑑賞だったからなのか、話が染み入る染み入る…笑
個人が感じる映画の善し悪しは、好きな監督や俳優、世界観などで多少なりとも甘くなりがちだと思っている。また、いかにその映画に共感し、自己投影、陶酔、感情移入できたかは、かなり大きな作用になると思う。
この作品は特に、いわゆる「女性的」な感覚が強く、男性よりも女性の方が好む映画ではなかろうか…。
(2つの性別でお話することを不快な方がおられましたら申し訳ありません)
動植物に強い愛情を持ち、救われる日々。一方、属する人間界の理不尽さに怯え、静かに耐え忍ぶ日々。ただ、生きる為に必要な事を選択し、多くを望まずささやかな日々。貧困、家庭不和、嫉妬や疑念に身を焦がしながらも、それでもいつかは…と甘い幸せを願う日々。図らずしも強くなり、前を向き、手に入れたはずの幸せは束の間…消えてゆく。
私はこの映画の冒頭から最後まで涙が止まらず大号泣、翌朝まで目の腫れは引かなかった。 自分と重なる自然界への強い愛情と敬意。そして生育期のバックグラウンドによる苦悩、情熱、そして失望。
「共感」してしまったからだ。
しかしこれはあくまでも「私」だから。
他の誰でもがそう感じるとは全く思わない。
作中何度も出てくる鳥の羽が意味する愛のメッセージも、チーム繊細さんには「なんて素敵なの!!」と胸きゅんでも、動植物に興味の無い方には全く別の印象だろう。また、主人公の「唯一の救い」である自然界への執着に関しても共感が出来ず、「いやさっさと街に越せよ」などと、本末転倒、入り込めないかも知れない。
サスペンスの仕上がりとしては、普通かなと思います。極上サスペンスとか、この結末がスゴイという程でもないかなと思います。ただ、ある意味怖さはあります。感じる方は。
勿論原作は映画に盛り込めてない部分もしっかりと描かれていると思うので別のお話。あくまでも映画「ザリガニの鳴くところ」の印象。
自然界は善悪の概念で生きていない。
生に対して貪欲なものだけが生き延びられる。
ただ、生きるために、生き続ける。
私はこの作品、好きです。
美しい映像と強い覚悟
上映終了間近で原作を読破して鑑賞した。
原作は去年か一昨年のミステリ小説部門で上位にランクされていた。上映終了が間近に迫っていて、大慌てで原作を読んだ。原作は家族、世間から疎外され、一人で生き抜いていく少女の孤独な魂を描いていて、その心情に感動した。少女の心を癒やすのは沼地の自然だ。小説ではその場面がよく描かれて感心した。但し、沼地の環境が私にはよく想像できない。鳥や生物の名が書かれていてもどんな姿・形をしているかよくわからない。映画であれば当然スクリーンに映写されるので理解できる。だから、どうしても上映終了前に鑑賞したかった。
映画は原作小説をはしょった物で、これは仕方がないだろう。上映時間の制約がある。原作を読んだ感想は、殺人事件を絡ませる必要があるのだろうかとの想いだ。まあ、それでは娯楽小説にならず、全世界で一千万部も売り上げはできないだろう。
さりげない伏線の配置
伏線回収がたまらなく好きだ。だからミステリーが好きだと言っても過言ではない。これ見よがしに伏線を陳列するよりも、さりげなくちりばめてくる方が好きだったりする。そういう意味でこの映画の伏線のちりばめ方は素晴らしい塩梅。観終わってから、あのシーンとかあのセリフとかも伏線だったかーなんて余韻を楽しむことができる。ちなみに原作は未読。
最後の展開は少し予感していたから驚きはなかった。でも、そこに至るカイアの壮絶で、でも優しさに満ちた人生を感じ取ることができたから問題ない。いやー、カイアの伝記のような話だった(実在してはいないけど)。こんな重厚なミステリーは意外と埋もれがちだが、公開から結構たってるのにそれなりにお客さんが入っていたから口コミで人気が高まったのかもしれない。
でも、タイトルの意味が未だにちゃんと理解できないでいる。原作を読めばもっとわかる類のことなんだろうか。
全296件中、101~120件目を表示