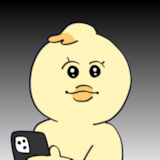シン・仮面ライダーのレビュー・感想・評価
全912件中、241~260件目を表示
ついに見ました!
シン・仮面ライダー!
オープニングの曲で胸が踊りました!
斎藤工さんのかっこよさ。浜辺美波さんのかわいらしさ。素晴らしかったですね。
あと、仮面ライダーの首や髪の毛が見えてるところや英語を変な発音でするところや怪人の造形や音響と音楽、言葉に頼る脚本や、そもそもの設定などが変わればもっとよかったと思います。
最後のバイクシーンはとてもかっこいいのですが、向かって行く先が、行き止まりの島だったのがおもしろかったです。
あと、これは大切なことだと思うのですが、ほんとは監督はあまり元々の仮面ライダーが好きではなかったのかもしれないと思いました。
お金も人もかけているのにもったいない
仮面ライダーは事前に1話だけ観て、本作を鑑賞。
ウルトラマンは昔よく観ていたが、仮面ライダーはあまり興味はなかった。
なるほど、冒頭はなかなかに楽しめた。原作を踏襲しつつ、新しく生まれ変わった印象をうける。バイクアクションは音響も相まって迫力ある。
作品通じて、シナリオ自体は、目立ったところなく...普通である。
そのうえで、つなぎや、一つ一つのエピソードの深掘り、アクションシーンの密度など、もっと作り込めたんじゃないかとは思ってしまう。
ウルトラマンも駆け足だったが、更に駆け足になって、中途半端感は否めない。
また、俳優陣も下手ではないのだが、合ってはいない。藤岡弘、とは違う意図はあったのだろうが、池松くんはヒーローというより、悩める現代の青年である。
浜辺美波も好きではあったのだが、ちょっと抜けたくらいの役がいい。
とはいえ、独特のカメラワーク、特撮要素はワクワクしたし、他作品と一線を画してはいる。
お金も人もかけているのに、なんとももったいない作品である。
2023年劇場鑑賞61本目
初代をちゃんと観てから鑑賞した方がいいかと
シン・ゴジラとシン・ウルトラマンは両方観ました。
ウルトラマンや仮面ライダーの知識はほとんど無いですが、庵野作品という理由だけで観に行った、にわか中のにわかです。
鑑賞後の感想としては、特にアクションシーンについては、あれ?こんなもん?と思ってしまったのが正直なところ…。
ゴジラやウルトラマンでセリフや設定が自分の様な素人には難しい事は承知してたので、そこは納得できます。しかし、マトリックスで受けた衝撃やトムクルーズが自ら体を張ったアクションに衝撃を受けた身としては、監督が拘ったとされるアクションシーンにイマイチ感を感じてしまった。
往年のファンからすれば自分の様な目線で見るのは「違う」となるとは思いますが。
自分は観る前にドキュメンタリー等を観ていたから「ドキュメンタリーで庵野が言っていたのはこういう事かな?」と納得できますが、ホントに何も知らない人が観たら評判通り賛否分かれて当然だと思います。
なので、余計に初代仮面ライダーをちゃんと観て、アクションも含め仮面ライダーとは何ぞやと前知識を入れてから観る事をオススメします。
アクションはカットが切り替わったら前のカットとの整合性がないと成立しないし、繋がらないから「?」となってしまい置いてけぼり感になるとずっと思ってましたが、仮面ライダーはそういうものと初めて知りました。
そういう意味でも初代を観ておいた方がいいと思いました。
※邦画が洋画に(時代劇を除いて)殺陣でどうしても見劣りしてしまうのは様々な要因があると思うので仕方ないとは思いますが、個人的には庵野の嫌う段取りでもいいのでもっとスケール感の大きいアクションを見せて欲しいと思いました。
※バイク乗りの身としてはバイクのシーン良かったです。
あとバイクについて語るセリフは心に沁みます。
いつもの表現を既視感ととるか作風ととるか
オリジナルを想起させるポイントが多く、TV版「仮面ライダー」履修済みの自分としては十分楽しめた。
いわゆる熱血&痛快な「ヒーロー映画」ではないが、「仮面ライダー1号と2号の物語」としてはオリジナルや石ノ森ワールドを逸脱しない正統派の作りだと思う。そのため、新規性が無いと感じたり、監督の定番の表現が多用されるのを既視感・食傷と評する人がいるのは仕方ないかも知れない。
特撮やスーツアクトのテイストを大事にし、造形に現代風のセンスやテクスチャを入れ込んだのは見事だった。むしろあそこまで拘るなら、ところどころのCG丸出し感を抑えて騙しきってほしかったと、観客として欲が出る。
今後も「仮面ライダー1号と2号」の世界は様々なメディアで続くだろうから、バットマンやスパイダーマンのユニバースのように、次の50年後には本作が「仮面ライダー1号と2号なら○○版が好き」と言われる作品群の一つになっている可能性もある。
ちゃんと仮面ライダーでした、凄い好きです。
もう感謝の言葉しかありません、有難うございます観たかったモノを観せてもらいました。賛否両論激しい中で私もこの映画を手放しで称賛はしません。普通の2時間1分の映画を期待して起承転結と登場人物それぞれの掘り下げを求めるならば他の映画を観て下さい。この作品は仮面ライダー1号と2号の物語を昭和/平成/令和の「仮面ライダー」の書式を用いずにアップデートさせたモノだと私は感じました。NHKのドキュメンタリーを視聴した方からパワハラとか今の時代にはそぐわない手法だとか騒がれていますが、作劇におけるインプロビゼーションやアドリブはそれこそ芸能の世界ではあるある話です。この映画を作る事に参加した人、特に画/演技に関わる人達に「あなたの仮面ライダーをギリギリまで見せてくれ。」と監督は要求し続けました。「相手を殺したいと思いながらの格闘は殺陣の様な様式美では無い筈。」妥協しなかった/出来なかった部分なのだろうと私は解釈します。東映のヤクザ映画へのオマージュまで盛り込んで庵野氏のサービス精神にはもう脱帽しかない。個人的に拭えない気持ちは『「シン・ウルトラマン」よりも前に公開されていたら違う評価だったろうな。』です。巨大で絶対的な強者を思わせながらも人としての弱さ/生き方を肯定してくれた異星人も尊いけれど、理不尽に力を持つことを強制され苦悩しながらも自分しか受け継げない思い/自分しか止める事の出来ない危機に立ち向かう等身大の人間・・・駄目だなぁ、仮面ライダーが大好きだ。20230417追記、熱が冷めないというのかレビューを書いてもまだおさまらない。庵野氏が「シン・ゴジラ」では総監督で「シン・ウルトラマン」では脚本/編集であったのに、何故「シン・仮面ライダー」では監督なのか?極論、統括責任者やスタッフのポジションでは無く現場に密着して自分が全てに関わることを望んだとしか思えない。NHKのドキュメンタリーも「シン・エヴァ」と「シン・仮面ライダー」しか無い。東宝が宣伝としての庵野氏の露出を許可しなかった可能性は大いにあるとしても。「シン・エヴァ」のドキュメンタリーの時に庵野氏は言った「宣伝ですよ。」、「シン・仮面ライダー」はあのドキュメンタリーも重要な要素なのだ。イチ観客でしか無い私が泣きたくなるくらい「仮面ライダー」が好きで、そして庵野氏は遥かな差を持ってこの比では無いのだ。半世紀以上も続くIPの解体/再構築などという試練を誰が面白半分なだけで引き受けられるものか?!庵野氏の作家人生?として今後何に取り組んで下さるのかをものすごく期待はするものの、情熱を注げるものがまだ残っているのだろうか?余計な事だとは思うが心配になってしまう。自分の熱が沈静化することを願いながら最後に、東映は今後の仮面ライダーシリーズにおいて「シン・仮面ライダー」を汚すなよと書き残す。変な客演とか趣旨を曲げた続編を作ったら生涯恨んでやる。私にとって池松壮亮氏と柄本佑氏は仮面ライダー第1号と第2号として刻まれたから。拙いレビューに共感をして下さった方々に感謝を。
悪い意味で…
全編悪い意味で
同人映画っぽかった…
特に気になったところは
・戦闘シーンガチャガチャして気持ち悪い
・CGが稚拙(コウモリ男の飛ぶとこひどい)
・脚本が悪い意味で童貞っぽく恥ずかしい
・説明少ないのに変なとこに時間かける
・浜辺美波、ルリ子役合わなくない?
・ルリ子刺された時手を挙げてあいつら呼べよ
・ルリ子の遺言シーン、特に恥ずかしい
・Kはロボット刑事?なに?
・トンネルのシーン暗闇で突然爆発するんで目が疲れる
・シンシリーズと俳優が同じなのはスターシステム?世界観繋げるなら繋げりゃいいのに…立花と滝だった!という事のミスリードなのかもしらんけど
・長澤まさみをこんな贅沢に使ってまんねん!…そういうのいいから…
なんか全編退屈だなーと思って観てました。
で、最後、橋を2号が渡ってる時
(頼むぞ、庵野!ここが最後の挽回のチャンスだぞ!
ここで「レッツゴー!ライダーキック」か「仮面ライダーのうた」だぞ!頼むぞ!)
と思ってたらほんわかした曲流しやがった…
挽回のチャンス与えてやったのに…
もう庵野に物申せる人いないのかな…
エヴァは庵野がはじめた物語なんでどういう結末でも受け入れざるをえなかったけど、仮面ライダーは違うじゃん?
庵野がやりたい事と客のニーズがズレてないかな?
シンウルトラの時は樋口監督がバランスとってたのかも…。
1.5点はティザーの時のOPオマージュ映像の衝撃との高低差もあって厳しくつけたかもという反省もありだけど、1点でもいいかな…くらいの印象
まあ、良かったです。
良かったのですが、簡単に死なせすぎ。音楽の古さと映像が合わない。これはシンウルトラマンも同じ感想でした。あと、サソリオーグの頭でクルクル回るやつ、あれはウケ狙いだったのだろうか? 庵野さん、あれはOKなのですか?
と、思いました。
PG12の必要があったのか?
なぜPG12なのか、あの血飛沫のせいだろうか。そもそもあの血飛沫は本作のアクションシーンで必要だったのか、あれでなにかリアリティーを出したかったのか。
正直、最近鑑賞したやたらと血飛沫は多いがアクションや脚本はダメダメな韓国映画みたいで本作もどうしようもない代物だった。当然あの血飛沫もとてもアクションを際立たせる効果はないし、主人公が人の命を奪うことに対する葛藤を表現するためだったとしてもさほど効果的とも思えなかった。あの血飛沫表現ぐらいで人の命の重みなど表現できていないということだ。
また、内容的に大人向けなどと聞いていたがあの血飛沫がそうなのか、あるいはいろいろとこねくりまわして一見複雑そうにみせている設定がそうなのか、最後まで大人向けの意味もわからなかった。
元々子供向けのヒーローものを設定を小難しくして一見知的なセリフを並べることで大人向けのヒーローものをやってる気でいたんだろうか。
正直、観客にとってはそんなことはどうでもいい。要は楽しませてくれればいいだけである。
ヒーローもので重要なのは観客がいかにそのファンタジーを楽しめるかである。そして娯楽作品で必須なのは観客がいかに登場人物に感情移入できるかである。本作はそこがまるでなっていない。
まず主人公をはじめとする主要人物たちの行動原理が全く理解できない。とりあえず家族を無残に殺されたという設定はあるけど、そこからなぜ人類を滅ぼそうとなるのか、また逆になぜ命をかけて人類を守ろうとするのか。それら動機にも納得できないし、また簡単に改心してしまう点も。彼らが命を落とす場面でも少しも悲しいと思えなかった。これは正直娯楽作品では致命的だ。
また映像も予算がないのは仕方ないとしても、有能な作り手は予算がなければないなりにチープに見えないよう絵作りを工夫するものだ。現在のハリウッド大作を手掛けている監督たちも初めは低予算から始めてその実力を認められたのだから。
そういう点でも本作はやっつけ仕事なのかあるいは開き直ってるのか、絵作りを工夫しようという努力は一切感じられない。CGなんかはとても映画館で見せられる代物ではなかった。
ウルトラマン同様、子供の頃テレビで見ていたので鑑賞中本作のいいところを何とか探しだす努力をしたが、結局無駄だった。
考えられた作品
まるで昔のままのオープニング。
懐かしい。 しかし、しっかり違う。 冒頭での血が飛び散る戦闘シーンは思わず目を背けそう。
ストーリーはなかなか新鮮で楽しめた。 「バイクは孤独を楽しめるから好きだ。」元バイク乗りは思わずうなづいてしまう。実家にあるRZ250にまた乗りたいな。
他にも当時の流行語を混ぜていたりと元少年は懐かしく楽しんだ。 一番の違いはこれまでの仮面ライダーと違い、必ずしもイケメンではなかったこと。
普通の男でも仮面ライダーになれるっていうところがヒーローが身近に感じられる。 悩める本郷猛、悲しき本郷猛はこれまでにない視点だ。 ルリ子も本郷も消えてしまったが、桜が散っていくような日本のはかなさを感じさせてくれた。
考えに考えられた作品と感じた。
もっと良くできたとは思う映画
原作はかいつまんで見たことがある程度です。
映画を見終わっての感想は"中弛みはするけど、大筋は面白かった"だったのですが、完全に原作パワーですね。
やはり庵野監督の絵はあまり好きじゃないですね。無駄に寄りすぎ、アングルが悪い。会話のシーンで真正面から撮り続けてることが多々ありますが、ズームの塩梅が微妙、完全など正面、尺が長いで昔風を謳ってますがなんか違う。スクリーンが横長だから隙間が生まれるのも原因かな。
戦闘シーンもかっこいいのだけど、絵がわかりづらくてせっかくのアクションが分かりづらくなってる場面もありました。
画面の色調は好きでした。
デザインはエヴァンゲリオンナイズされてるといった雰囲気。でもかっこよかった。クモかっこいい。
でも1号のはみ出た襟足は僕は嫌です。
演者?そんなん言わなくてもよかったのわかるでしょ笑
アツいシーンも結構あったし、庵野作品の中では好きな方です。
てか長澤まさみなんでもやるな…
赤いマフラーはマスト
ネット上では何かと賛否があるなか、映画館での予告を初めて見たときから必ず観ると決めていたので他人のレビュー、感想は全く見ずに劇場へ。
テレビシリーズは子供の頃に夢中で見てて遊ぶのも仮面ライダーごっこのドンピシャ世代で期待しかなく観た感想は予想以上に良かったしテレビシリーズへのリスペクト、それを現代においてリメイクするのに難しさもあるなかVFX,CG を上手く融合して昔のテイストを残してというか融合、表現されていてファンとしては堪らなく子供の頃に格好いいと思ったのと同様に格好いいと思わせてくれた。
シンウルトラマンと比較すると断然こちらの方にすべてにおいて軍配をあげます。
わたしのような子供の頃に夢中で見てた者が大人になった今、ショッカーとライダーの生い立ち、バックボーンを大人向けに仕上げていて少しの子供だましな部分とメッセージ性のあるシナリオが相まってファンには堪らない映画になっていました。
若い世代、夢中になったことの無い世代にはアクションシーン等、海外映画のヒーローアクションもののCG,VFX に慣れた人には物足りなさを感じるであろうが、効果音や劇中音楽など昔のままのテイストでエンドロールまで最高でした。
サイクロン号がとにかく格好いい、マスク、スーツも。俳優陣もよく出てくれました。
本郷猛が池松壮亮で良かったし
やっぱりヒーロー、ライダーには赤いマフラーがよく合うね。
令和の仮面ライダー
仮面ライダーを知らなくても楽しめたが、正直物足りなさを感じる
今まで仮面ライダーに触れたことがなく、「藤岡弘、さんが演じる本郷猛が、黒タイツのショッカーなる悪の軍団にバッタの改造人間として改造されるも、離反し悪の怪人を倒していく特撮。現在に渡るまで様々なシリーズが作られている」といったくらいの、およそ大半の方が持っている知識しかなく、なんでバッタなのか、なんで離反したのか等全然分からないレベル。おそらく1作品も見たことがない。
見るきっかけとなったのは、所謂「シン」シリーズである「シン・エヴァンゲリオン」「シン・ゴジラ」「シン・ウルトラマン」を見てきたため、「シン・仮面ライダーはどんなもんかな」くらいの感覚が視聴の理由である。正直、特に庵野監督のファンというわけでもない。
ストーリーとしては、概ね私が持っていた知識と相違ない感じ(「イ~」と叫ぶ黒タイツの戦闘員?は出てこなかったが)。仮面ライダーを全然知らない私にとって一番良かったなと感じたのがバリバリのCGによる戦闘シーンや、おそらく当時の仮面ライダー(1号、2号?)たちがとっていたであろうポーズ等は素直にカッコよく表現されていたと思う。次点としては役者さん達の演技。主人公、ヒロインともに、序盤は「棒のような演技だなぁ」と思っていたが、これは「改造されたため」(ヒロインがどうなのかは読み取り不足で確信がないが)あえて感情や抑揚のない話し方などを終始行っていたのか、と考えると良い演技だったと私は感じた。
逆に上記以外はちょっと微妙だったかな、というのが個人的に正直な感想。何故肉弾戦?いちいち宙返りをする必要は?などの無粋なことは言わない。元が特撮な訳で「こっちの方がカッコいいだろ?」の一言で済むからだ。その通りだと思う。
それは分かるが、淡々と処理されていく各怪人たちや、最後のボス?との戦闘がいささか味気なく感じたのと、おそらく役者たちのセリフも、こだわりの末マスクを着けて発声しているのか、若干聞き取りにくかったのが残念。あと、これは至極個人的な嗜好であるが、上手く表現できなくて申し訳ないが、庵野監督っぽい演出等も過去の「シンシリーズ」に比べるとかなり抑えられていたのではないかとも感じた。
結論からすると、仮面ライダーを知らない人間が見ても十分ストーリー等を理解し楽しむことはできるし、CGを使った戦闘シーンは見ごたえがあったが、尖った言い方をすると「ちょっと物足りないなぁ」という感想。ただ、重複するがこれはあくまで「仮面ライダーを知らない人間」の感想であり、当時のリアルタイム世代や仮面ライダーファンから見たら、私が気が付かなかった魅力があるのではないかと思う。
あ、一つ言えるのが「PG12」の作品のため、特撮好きのお子様向けの作品ではないのは確か(暴力・流血表現もあるので)。そう考えるとやはりファンムービー的な作品なのかなとも考える。逆に当時のリアルタイム世代の方達には刺さるかも、なので、私としては少し低い評価となってしまったが、是非ご自身の目でお確かめいただきたい。
血シブキのバイオレンスには唖然としたが、庵野秀明のアレンジは流石だと言いたい。
浜辺美波のルックスは綾波レイだった…。
池松壮亮のキャスティングは、藤岡弘からの180度転換を意図しているようだ。
ゴジラやウルトラマンに比べると、仮面ライダーは平成→令和とシリーズを重ねるほどに原点からの解離が大きくなっており(と、思う)、それが現代には受け入れられている。そんな背景からかどうかは分からないが、本作はあまり客足が伸びていないようだ。
お陰で、大きな劇場で他人を気にすることなく鑑賞できた。
仮面ライダーに、石森章太郎(敢えて、石ノ森ではなく)の原作マンガというものは存在しない。
テレビ放映にあわせて、原作者(設定やキャラクターを考えた人)がマンガ化した作品を雑誌に連載するコラボレーション企画だった訳で、そのマンガ作品をテレビ化したのではない。他の石森原作の特撮テレビシリーズの多くが同様で、アニメだが永井豪の「デビルマン」や松本零士の「宇宙戦艦ヤマト」なども似たような関係だ。
と、いうことで、〝原作〟ではなく〝原作者によるマンガ作品〟と言うのが正しいと思う。
何が言いたいかというと、よく言われる「原作と違う」とか、「原作だと本当はこうなる」は、当たっておらず、テレビとマンガは全く別の作品だということだ。
とはいえ、原作者によるマンガ作品には、創造主の思想・嗜好がより強く表れているのは当然である。
石森章太郎も永井豪も(二人は師弟の関係)、テレビの企画段階から原作を担当した最初の作品「仮面ライダー」「デビルマン」で、“テレビではできないこと”を敢えて自らのマンガ化作品に投入している。
この『シン・仮面ライダー』には、テレビの初期シリーズと石森章太郎によるマンガ作品のみならず、石森原作の「人造人間キカキダー」「イナズマン」「ロボット刑事」および、それらの原作者によるマンガ作品からエッセンスが引用されていて、石森章太郎ファンとしては心揺さぶられるものがある。
庵野秀明というオタクの帝王は、観客に媚びることなく自身の拘りを貫いている。
だがそれは「分かる人だけ分かれば良い」という独善的な思考ではなく、「オレの拘りは凄いだろう、見て見て」的な子供っぽさだ。
そして、それが極めてマニアックだから、結局分かる人にしか分からない。そこがオタクの帝王なのだ。
本作には『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』からの流れを期待しがちだが、『キュティーハニー』('04)の方がテイストは近いように感じた。
ウルトラマンを完全CGで描いたことに対して、仮面ライダーおよび怪人(オーグ)たちは完全スーツアクションで、変身前を演じる役者にスーツを着せる伝統を踏襲している。
『キュティーハニー』で試した実写コマ撮りに本作でも挑戦していて、これも庵野の強い拘りだろう。何でもCGが当たり前の今、これが下手なCGに見えてしまったなら残念だ。
ショッカーを世界征服をたくらむ悪の軍団ではなく、〝救済〟の〝計画〟を実行しようとしている〝非合法組織〟にアレンジしているのは、庵野の庵野秀明らしさだ。
恐らく、石森章太郎のマンガに基づき、本郷猛が死ぬことは初期から決めていただろう。
サスガに脳だけ生かして一文字隼人に指示を出すことまではなぞらなかったが、あのラストシーンは一文字だけが本郷と通じあえていることを匂わせている。
シークレットキャストが話題になっているが、ロボット刑事Kならぬロボット執事ケイの声の主は分からなかった。
残念だったのは、美脚女優のサソリ女が仮面ライダーと戦わなかったこと。
特撮って感じ
まず、箇条書きで感想を。
・結構血が出るのね、、、
・演技が感情が出てこない設定かと思ったら、感情むき出すとこもあるし、、、
・カメラワークが独特すぎて見づらいとこあり
・ジャンプシーンが見所だとは思うけれど、さすがに多い
・思ったより敵出てくるのね、、、
仮面ライダー全然詳しくなかったけど、所々に説明があったおかげで分かりやすかった。
ただ、淡々と話すからそこがなんだかなぁって思う。ストーリーの展開はそこまで嫌いじゃないが、バトルシーンがやけに血が出るのと、敵多すぎてサクサク進むのが何とも言えない感じ。それぞれの感情や葛藤があるんだろうけど、色々詰めすぎてて淡く感じてしまう、、、
ジャンプのシーンやたら多いし、、、
色々良いとこはあれど、惜しい感じ。映画の最後の方は結構良かったです!でも、テレビでいいかな、、、
応援上映は本郷を推せる!
仮面ライダーは1971年から続く特撮アクションシリーズで、初代「仮面ライダー」も2年間放送しているため放送中も作風が変化している。今回の「シン〜」は藤岡弘が怪我で降板するまでのいわゆる旧1号編(1話〜13話)を意識したリメイクで、TV番組と同時連載された石ノ森章太郎のマンガ版の影響も大きい。
初回鑑賞時、4体目の怪人・ハチオーグ戦までは楽しめたがアクションエンタメとしては満足できなかった。特にイチローによる「ハビタット計画」でどんな被害が起こるか、ハビタットの中はどんな世界かが描かれないことで、カタルシスが結実しにくいと思われる。
またSHOCKERの本体であるAIのシンギュラリティについてもっと踏み込みがあれば、更に今日性を獲得できただろう。
さて初見では不満だったが、ドキュメンタリー番組を見て、応援上映(字幕付き)に参加してみると見方が変わり、求められる「仮面ライダー」像の1つを実現したのではないかと思うようになった。
新たに気づいたのは、ほとんどのシーンで仮面ライダーの中に俳優の池松本人が入ってアクションしていること、戦い終わったら必ずマスクを脱ぐこと、敵に黙祷を行うこと、そして応援上映で「泣かないで」「がんばって」とさかんに声援が入ることだ。
自らの悲しみを抱えながら他者のために闘う姿は初代「仮面ライダー」のテーマの一つで、石ノ森のマンガ版でも強調されている。また、変身後も本人が演じるのも旧1号編の特徴だ。
池松本人が変身前〜変身後を通して演じることで、ライダーの姿に悲しみと苦悩が乗り、それでも闘う意志や信念を感じることができる。
このヒーロー像はTVでは実現しにくいもので、仮面ライダー/本郷猛(池松)の悲しみと優しさが観客に伝わったのなら、「仮面ライダー」の原点回帰として役割を果たしているのではないか。
ドキュメンタリーでは、決められた見栄えのするアクションを作ってきたアクション監督の田渕氏と、不確実性や身体性を求めた監督が対立的に描かれていたが、仮面ライダーの身体性や感情、ドラマのためにそれが必要だったことがわかる(ただより多くの予算とスケジュールがあれば、テスト撮影と検証が行われると良かったとは思う)。
本編で語られなかったSHOCKER側の論理や設定は、前日譚マンガ「真の安らぎはこの世になく」に期待したい。
大人のための仮面ライダー
自分の幼少期、ゴジラとウルトラマンまでは、ドはまりした世代だが、仮面ライダーは、リアルタイムで観た覚えはなく、自分達より一世代後のヒーローの為、観ようか迷っていた作品。それでも庵野さんのシン・シリーズとしての敬意を表して、遅ればせながら鑑賞。
これまでのシン・シリーズと違い、等身大のヒーローとなる為、どうしても着ぐるみ感は否めない。ハリウッドのVFXを駆使したアクション・ヒーローを見慣れてきている分、リアルな臨場感やスペクタクル戦闘シーンといったものは、見劣りしてしまう。だが、日本の仮面ライダーだからこそ、そんなアナログで、ノスタルジックな映像でもいいのかもしれない…。
本作は、子供のヒーロー・仮面ライダーというよりは、人造人間となった苦悩を前面に押し出した、大人向けの作品となっている。初っ端から、グロい撃退シーンを見せつけ、R12指定となっていたのも納得。また、仮面ライダーの性能やショッカーの目的等、よく分からない科学的なウンチクをたれるシーンも、庵野作品らしさと言える。そして、舞台やシーンが整合性や繋がりも無く、急展開していくので、ついていくのも大変でもあった。
物語は、仮面ライダーとなった本郷猛が、仮面ライターの生みの親の娘・緑川ルリ子と協力しショッカーの野望を砕くため立ち上がる。そこに、仮面ライダー2号も味方となって、無敵のライダー・キックを武器に、昆虫と人間の力をミックスした怪人オーグ達に立ち向かう。そしてクライマックスには、ラス・ボスとの死闘を繰り広げるというストーリー。
仮面ライダー・本郷猛には、池松壮亮が演じ、嘗ての藤岡弘に比べて、やや線が細いと思ったが、内容や人間味ある役柄から鑑みた場合、適役だったかもしれない。そしてヒロイン緑川ルリ子には、渡辺美波、ライダー2号・一文字隼人には、柄本佑が演じていた。
しかし、その脇を固めていたのが豪華絢爛。竹野内豊をはじめとして、斎藤工、仲村トオル、大森南朋、森山未來、そして、長澤まさみや西野七瀬は、なんと着ぐるみ姿で、ショッカーの怪人を演じ、松坂桃李も声の出演をしており、庵野ファミリーの総出演の作品だった。
主人公がカッコよかった。
庵野監督のプロダクトアウトの作品だと思いました。好きなものを好きなように作りたい、というのを100%重視して作ったような気がしました。みんなMCUみたいなユニバース作品を楽しみにしているなか、「そんな大衆ウケに全振りした作品は作らないぞ」という信念を感じました。
なにせ、客層はどこを狙ってるの?と思ってしまいます。映画館に来ている人から見て、それはおじさんだと分かります。キッズ、Z世代、カップルとかはガン無視、原作へのオマージュ、原作勢への目配せが多く、ノスタルジーに溢れる作品。MCUでもそういった目配せは多いけど、大金が注ぎ込まれてる違いもあるかもしれないですが、全方位的な作品作りが徹底されています。
庵野さんの個人的な思い出作りとしては素晴らしいデキだったのではないかと思いました。
再会に感謝します「仮面ライダー1号・2号」
全912件中、241~260件目を表示