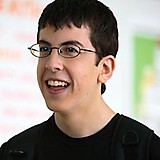ノマドランドのレビュー・感想・評価
全426件中、241~260件目を表示
「邂逅」という言葉を表すとしたら
きっとこうなるであろう、と思った。
日本では「ノマドワーク」くらいでしか聞いたことのなかった"NOMAD"という語。
根無草のように転々と生活していく生き方を、望んで選んだ者もいれば、そうせざるを得なかった者も居る。
劇中に何度か出てくる「石」がポイントだったのかもしれない。
地面を転がりつつもその地に佇むその様は、転々とするノマドランドの人間たちでもあり、かつて石灰の採掘の街で夫やその記憶と共に留まっていたファーンでもあるように思う。
国立公園では砂の粒が幾重にも重なって見事な岩肌の景色を作っていた。(岩に乗っかった2人の視線が一瞬交錯し、片方は慕う気持ちを滲ませたのも、もう片方はさっと前を向いて降りていくのも、凄く良かった)
積もれば長く残るものと化すこともある。そういえば、昔生きていた恐竜の等身大の像の前で写真を撮るシーンもあった。
例え移ろいながら生きていても心の中に拠り所となる家を持つことはできること、亡くした者も記憶の中に生き続けることの象徴みたいに思える。
ラストで火に石を投げて弔いとするその炎が立ち上がる先を、空に向かって辿っていく画の美しさと、ハッとさせられたような感覚が印象的だった。
このように石と言えども、様々なイメージを重ねることができる。
腰を据えることも、転がりゆくことも、どちらも美しく肯定するかのように。
カメラも地にしっかり据えるように空と地を捉えた引きの画が多かったようにも思った。
ファーンの他人との距離感の取り方も好きだった。ノマドランドの人々は皆そうなのかもしれないけれど、交流を持ちつつも、関わりすぎない。出会っては過ぎ去ってゆくのをただ受け入れる。さよならは言わずに、またどこかでの邂逅を願って別れの挨拶とする。
旅をしながら生きる目的や入口は様々でも、最終的に皆、どこかに定住するにしても旅を続けるにしても、自らの意思を持って人生を決め、進み、生きては死んでゆく。その様が本当にどこか潔かった。
淡々とした表現の中に、圧倒的にこれぞ人生なのだと滲み出る実感で包まれる感覚だった。
実際に旅をしながら生活している人々は高齢者が多いとのことだが、人生の酸いも甘いも知り、後悔も絶望も抱えながら長らく生きている人ほど、響く作品のように思う。
前作『ザ・ライダー』に続く秀作、この監督は期待大。
ファーン(ノマド)の暮らし方は季節労働で車で移動しながらというものだけれど、それは人々の人生そのものなのかもしれない。決して多くないセリフがしみじみと心に響き、俳優たちの無言の演技と目線が胸に迫る。
撮影は監督の前作『ザ・ライダー』と同じくジョシュア・ジェームズ・リチャーズ。荒野を引きで捉え明け方や焚火の光などを美しく生かす。『ゴッズ・オウン・カントリー』でもその力量はかなりのものだったが、見捨てられたような土地にそれでもなんとか生き抜く人間を対比させる映しとる。
それは全裸のあおむけで水に浮かぶマクドーマンド、真冬のフロントガラス、RVキャンプの駐車場などで生かされ、一方で、広大なアマゾンの倉庫や狭いバンの中での機能的/機械的な人工物との対比も良い。
ノマドたちに金銭的な不安はあるだろうが、すでにどん底を味わった強さも感じさせる。 なんらかの事情を抱えてここにたどり着いた人々の顔のシワや古びた持ち物。さりげなく助け合い共感しあい信頼し合う。
しかし(おそらく)キリスト教にのっとった共感や赦しと徹底した個人主義が、「人は皆一人で死んでゆく」という強さでもありはかなさでもあるのだろう。
漂流なのか、自由なのか
主人公は夫を亡くし、家を失くし、多分年金もほぼ無く、子供のいない高齢者だ。短期労働をしながらキャンピングカーで点々と放浪の旅を続けている。驚いたのは、定年後の第二の人生を楽しむ為にではなく、生活をする為に、終の棲家をキャンピングカーとしている高齢者が多いということ。アメリカの美しくも荒涼とした冬の砂漠が、主人公の不安をよりいっそう強く感じさせる。決して孤独ではないので、あんなに寂しさを強調した演出でなくても良いのでは?とも思う。彼女は亡き夫の想い出を失いたくないからと、その土地を追い出されても、尚もそこにいようとする。その呪縛から解かれるときが、真の漂流になるのか、真の自由になるのかよく分からないが、ラストの清々しい表情を観ながら空想に浸っていたら終わってしまってエッとなった。歳を取ったら、何か喪失感と向き合う時があったら、また観てもいいかもしれない。ベネチア金獅子賞も納得で、アカデミー作品賞も取るだろうと思った。
またどこかの旅先で
旅をしながら、土地土地で仕事をする。そのたびに新しい人と出会う。その繰り返し。
観ながら、大前研一の言葉が浮かんできた。人が変わるには3つの方法があって、それは、時間配分を変える、住む場所を変える、付き合う人を変えることだ、という言葉だ。(ついでに言うと"決意を新たにする"は意味がないらしい) ファーンは、そのうち"場所"と"人"の2つの条件は確実に満たしているし、"時間"もそうかもしれない。そうか、ファーンは自分を変えたかったのか、と思った。
じゃあ、何を?
その疑問が付きまとう。だけど、それは不満にはならない。むしろ、どこかいたわってあげたくなる気分になってくる。常識はあるし、人付き合いはできるし、仕事もしっかりとこなす。なのに、何が彼女を"高齢漂流労働者"にしてしまうのか。美しい自然美は、その哀愁を際立たせている。
ノマド提唱者(?)ボブが言う。「この生き方が好きなのは、サヨナラがないから。またいつか会えると思っているから。」と。そこで気付いて想像したのだ、亡くなった夫が彼女にとってどれほど心の拠り所だったのだろうと。すると、彼女の生き方がまるで、亡くした者(失くした物でも)にもう一度出会うために、自らが成仏できない精霊となって彷徨っているように見えてきた。だから、たとえ相手が快く迎えてくれようとも、ひとつの場所に留まることなんてできないのだ。
そしてまた、"またどこかの旅先で"出会えると信じながら旅を続けていく。そうやって新しい年を何度も迎えながら、これからもずっと彼女は生きていくのだろう。
人生の選択肢は無限にあると思える
自由とか、経済とか、色んな事を教えてくれるロードムービー
それでも生きていかなきゃならないから。
何を言いたかったのか、わかりづらい
I love マクドーマンド!
彼女を観たい!それが理由で鑑賞。
前作のスリービルボードで大ファンになりこの作品が待ち遠しかった!今作品の彼女も前作以上に最高でした。
ほぼすっぴんと思わせる超ナチュラルメイクにショートヘアーが最高の美しい姿だ。まさにノマドにぴったりの彼女!内から湧き出る大人の女性のたくましい姿、時折見せるお茶目な表情や遠くを見つめる色気のある瞳にただただ彼女に釘付けでした。ドキュメンタリーを見せられてるかの様な自然体の演技が素晴らしいです!
季節労働を転々としながらノマドとして生きていく彼女だか、仕事を変える度に変わるユニホーム姿の彼女がまた素敵過ぎて、、、、
作品としての評価は今回はしません、彼女の魅力を伝えたくての投稿でした!
この社会の片側より
今感じる不自由さと向き合って
特段の知識もなく所謂洋画を観たくてさほどの期待もなく観た作品でした。
出演者のほとんどがリアルホームレス、いやハウスレスという事実を知りドキュメンタリーかと思った理由に納得した。
マクドーマンド演じるファーンも他のありのままに演じている出演者?もありのままに存在しファーンと対話している場面は自然そのものに感じた、アメリカ社会ならではの車中生活、ましてほぼ全員が高齢者、日本では考えられない逞しさと自由な生き方が許される社会を垣間見た、日本では年齢の壁の向こう側の寂しさや1人で生きる難しさを体感している年代の人達である、車を使いスマホを使いGPSを使い時にはコミュニティを作り自分で車を改造しながら旅を続け高齢者、そしてそれでも雇ってくれる仕事場もある。
ただその中には一人ひとり切実な事情がありその思い出を捨てきれず現代のノマドに身を投じているような気もする
リーマンショックという大波に揉まれ失くしてしまった生活の思い出と亡き夫の記憶が、出会いがあり定住を誘われても意思が揺らぐ事がない、彼女に放浪を続けさせる大きな理由でありさまざまな束縛からの開放感があるのかも知れない。
アメリカ社会でも西部の荒野や大自然の中と東部や大都会の中とはまた違うだろう、この作品に衝撃を受け共感し今の自分に向き合う事が出来た気がした、ノマドの人達があまりにも自然に存在し自分の言葉で語ってたから。
あまり良さが分からない
「生きる」意味を問いかけてくる映画です。
アクションもうるさい音楽も、美男美女も美しい夜景もない。
静かに流れる映画時間の中で、私は自分自身と対話をしていました。
自分の感情や想いより、安定・安全な暮らしを優先したいの?
何を一番、大切にして生きていきたい?
「普通」でなくなることは、すごく怖い。
でも、「普通」でいるために、自分の本音を見ないようにしていると感じる時があります。
学歴、性別、出身地・国籍や既婚・未婚など、仕事と直接関係ないことを問わない流れになってきた今、住民登録の有無も関係なくなる日も近いかもしれません。
遊牧民のように、キャンピングカーで移動しながら暮らす人たちが社会的に認知される日が来て欲しいです。
主人公が言うように、ある程度の年になったら貯金をはたき多額の借金をして家を買うという社会規範を疑ってもいいかもしれません。
日本は地震大国なので自宅壊滅の危機もありうるし、アメリカでも昨今住宅ローン破綻が問題になっていました。
自分の頭と心で生き方を選択することはできます。
この映画は、ノマドをその選択肢のひとつとして提示してくれた気がします(*^-^*)
人間らしい"美しさ"
"放浪人" ノマド。広大な砂漠という大自然の中で自由な暮らしを追求する人々の姿を、スクリーンを通してストレートに体感できる貴重な映画でした。
"映像"と"音"という、映画が持つ最大の特権をフルに活用して、砂漠を照らす太陽の光や月明かり、雨風の音や人間の呼吸、土を踏む足音まで、挿入される音楽を極力なくすことでありのままの"空気感"をダイレクトに感じることができました。息を飲む圧倒的な映像の美しさも見応えたっぷりですが、じっくりと映し通される放浪生活を追体験することで、主人公と同じように人生観を深く考え、濃密な時間を過ごしたかのような錯覚を味わうことができます。キャンピングカーライフを送るほとんどの人々が高齢者だというのも、作品をより一層味わい深いものにしていると思いました。大切な人を失ったり、仕事に追われる日々を過ごし心身ともに疲弊した人々が、自由と癒しを求めて放浪の旅に出、お互いに助け合って生きていく様は、本来の人間らしい生き方なのではないでしょうか。美しいのはなにも自然だけではなく、そうやって生きていくノマド達の姿かもしれません。
この映画がアメリカンドリームを体現している、というのを耳にしましたが、あながち間違ってはいないのかもしれませんね。(自由を求めてやってきた移民たちの理想形) 。ただ、アメリカでホントにこんな風な車上生活を過ごしていけるのか少々疑問で、あまりにも理想的に映し出しすぎているかのようにも思いますが、そんなことを言ってもしょうがないので、受け入れます。
自分には彼女達のような放浪生活を送る胆力は到底ありませんが、日常とかけ離れた人生をこの映画を通してほんの少しだけでも体感できたように感じます。たったの100分程度なのに、こんなに濃密な体験ができる"映画"の素晴らしさを改めて実感した作品でした。
See you down the road,
Proレビュアーの方々の神々しい高評価は、too muchな気もするし、かと言って、「共感できない」一点張りの酷評も、私には当てはまらず。ただ、この暮らしを選んだ人たち、選ばざるを得ない人たちの実際を淡々と追う、それ以上でも以下でもない作品。共感なんてしなくてよい。ただ、映像は美しい。同情ではなく、旅情を誘う。
狭い我が国でバン暮らしは考えられないけど、ネットカフェやとある地区の安宿に置き換えれば、そんなに遠くない話。
今すぐ仕事が必要、年金じゃ足りない、しかし貴方の年齢では、、、という冒頭の会話は、遠く見えて実はそんなに遠くない自分たちの未来を見せつけられているようでした。
違いと言えば、別の部分。車上暮らしでも、依存症やPTSDに悩まされても、体験や情報を共有できるコミュニティが充実している社会。悲壮感は薄い。
屋根のある家に暮らしていても孤独な人たちは、我が国の方がずっと多く深刻な気がします。
ベリーショートと、スウェットと、マウンテンパーカのフードが、似合いすぎる60代、排泄シーンも軽々こなすマクドーマンド。彼女以外にこの役にハマる人が考えつきません。そして、彼女以外のほぼ全キャスト、実名出演なのも、なんだか心を掴まれました。
タイトルなし
コーエン兄弟作品でお馴染みで、近年では「スリー・ビルボード」で強烈な存在感を見せつけた名女優フランシス・マクドーマンドが原作本に惚れ込み、映画化が実現した本作。
マクドーマンドは主演も勤めているのだが、全編通してすっぴんで、ノマドの役に説得力を出すために実際に車上生活をしたり、日雇いの仕事にも従事したというのだから、その本気度が窺える。
マクドーマンド以外の殆どの出演者は実際に車上生活を送る人々で、役名も本名である。
始終静かに淡々と進んでいく展開だが、そこには家を持たない者たちの様々な思いが溢れていて、退屈することなく見いってしまう。
ノマドの人たちをただ社会的弱者と決めつけるのではなく、自らが選択し社会のシステムに組み込まれないで生きる人として描いているのが良かった。不幸な目に遭って放浪をしている人もいるだろうが、自分の意思で生きている人たち。マクドーマンド演じるファーンも含め、彼女たちの前には日々困難が立ちはだかり、悩んだり葛藤するが、自然を側で感じ、仲間との交流を大切にする。それが本来生きるということである。それを知っている人たち。
ノマドたちの世界では、さよならがない。一ヶ月後か一年後か、いつになるかはわからないがいつかどこかで再開できる。大切な何か、誰かを密かに夢見て彼らは今日も車を荒野に走らせる。
傑作だと思うが、オスカー取るぞ!という勢いを凄く感じてしまったので、4.5
全426件中、241~260件目を表示