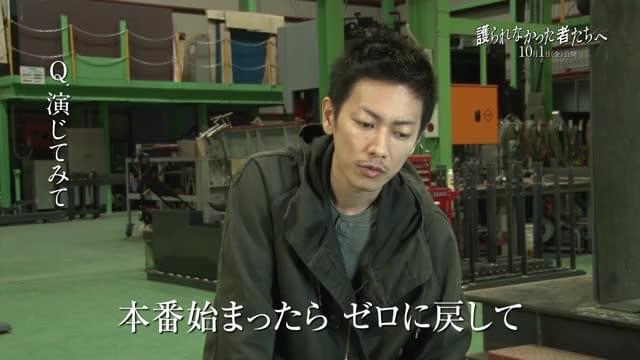護られなかった者たちへのレビュー・感想・評価
全464件中、41~60件目を表示
プロフェッショナルな人たち
弦楽器のBGMが凄く良い。
映像はアングル、構図がとても良い。
林遣都さんと阿部寛さんの刑事コンビが好き。
プロの刑事を感じた。
生活保護のシステムや携わる職員の仕事について考えさせられた。
終盤の「護られなかった人たちへ」と題されたSNS投稿の内容に感動。
ラスト、黄色いパーカーの子どもの話と海の波の音からのエンディングテーマ。その流れが好き。
劇中のプロの仕事だけでなく、原作者にも、監督にも、役者にも、歌手の歌声にも高い技術を感じた。
それは無理がないか?
理解できなかった者たちへ
ちょっとストーリーに無理矢理感があり過ぎました。本作の見どころは、それぞれの俳優さんたちの名演技、好演技。重いテーマの作品にある緊張感を途切れることなく、維持させています。
とは言え、利根くんやカンちゃんがあのような行為に至ってしまう動機が弱いというか無理矢理というか、個人的には理解できませんでした。不正や杜撰な対応に我慢出来ず、義憤に駆られ犯罪に至る、というのは分かるのですが、あんなに猟奇的でまるでSAWの病的な殺人鬼のような行為に至るって…、本当に理解できませんでした。
震災後のあらゆるトラウマや生活保護、不正受給、そんな重いテーマを真剣に考えさせるためには、ここまでのストーリーにしないと、みんな気づいてくれない、考えてくれない、そんな想いがあったのかもしれません。
原作とは「同名」の完全別作品です。
決して他人事では無い、重厚なテーマ。アカデミー賞を受賞しても全くおかしくない。
第45回日本アカデミー賞作品賞ノミネート作品。
ドライブマイカーという素晴らしい作品の陰に隠れてしまったかもしれないが、アカデミー賞を受賞しても全く不思議ではない作品。
「人としての生き方とは何か」生活保護という最後のセーフティーネットを通してその意義を問いかけた佳作!
骨太な作品。フィクションでありながらそのテーマはドキュメンタリーなヒューマンミステリドラマ(と言ってもミステリ要素は話を進める要素に過ぎない)。
東日本大震災という未曾有の災害から生き残ったが、時が経ち生活保護を受けなければ餓死をしてしまうまで追い込まれた・時。
そんなギリギリの状況に手を差し伸べた人たちの気持ち、それはごく当たり前の人としての”正義“だった。そして
それは”愛情”でもあった、しかし・・・。
その”正義”は差し伸べられた相手にとって本当の愛情だったのだろうか?
それよりも、たとえ飢えの苦しみがあったとしても生活保護を受けないことに本当の幸せを感じてしまう人もいる、
”矛盾”・”すれ違い”
もどかしくもありその先にあるそれぞれの人たちの愛情のすれ違いに、<しあわせとは、そして人として健康的で文化的最低限の生活とは何なのか>を今一度考えさせられる。そんな作品だった。
生活保護は解決では無い、本来なら少しでも生活保護を必要としない社会になれば良い事だ。しかし、21世紀になってこの20年あまりひたすら右肩上がりを続け増加している生活保護受給世帯の数・・・これは紛れもない社会の悲鳴の数だ、そしてその様な社会の悲鳴の先に何か光明はあるのだろうか。東日本大震災からの復興五輪も終わったが果たして日本は復興できたのか、そう思ってる日本人が多いとは思えない
平均賃金はこの20年ほぼ横ばいなのに手取りは下がり続け暮らしは一向に楽になどならない。超高齢化社会、年金問題、格差社会の増大「日本は素晴らしい国だ」と言う言葉の幻想ばかりが先行している。幻想ではあってもこの国を少しでも「素晴らしい国」と思って人々は救いを求めてる。戦後復興を果たし世界有数の経済大国になったが今置かれている状況はこの国自身餓死する瀬戸際なのでは無いだろうか、20年後に今を振り返りあの時こうしておけば、そんな風にならなければ良いのだが・・・。
映画を観て、何か他人事では無いざわざわした気持ちになった。
そして、佐藤健があまりにも凄い!天皇の料理番で見せた完全な料理人とはひと味どころか全く違う繊細ながらも切れ味鋭い役どころを見事に演じて見せた。
2021/10/14 22:48
震災、生活保護に言及した社会派ドラマ
震災で生き残るってことは
東日本大震災の被災者でバラバラになった被災者が片寄せ合って生活していたのに、生活保護が受けられずに、恩人が亡くなったのを端緒に生じた殺人事件。初視聴だが何故か感動も、共感もできなかった。自分は岩手の内陸に在住で、多少は被災地のことを知っているが。
違和感の大きな理由は、被災で生き延びた人は、人を殺したりできないと感じたからだ。被災するか否かは、たまたま、その時間に沿岸にいたかいなかったの運にも左右される。一つ間違えば、誰でも津波にさらわれていたのだ。いただいた命だから、悩みつつも、亡くなっていった人たちのためにも、命を大切にして生きようとする。まして、他人の命を奪うなどなおさらだ。けいに守られて、疑似でも家族として生き始めていただけに、譬え生活保護の受給問題により困窮して亡くなったとしても、制度や役人を恨んで殺人をするようにはならないと思う。
サスペンス要素が多い刑事物だから、こういうストーリーになるのも仕方がないのだろうが、震災で生き残るとはそういうものではない。洋画で「インポッシブル」というスマトラ島沖地震の被災映画があるが、助かっただけで感謝したくなるものなのだと思う。良い俳優が揃っているだけに、ちょっと残念であった。
公務員の人に一見はしてほしい。
ストーリーなどは他の方のレビューがわかりやすいので割愛します。
私は生活保護担当ではないですが、生活に困窮する市民に対応する課に属する公務員です。
本作品を鑑賞する前は、自分の職種への意識などありませんでしたが、ストーリーが進むにあたり、その意識はより強く考えさせられるものへと変わりました。
本作品で出てくる行政業務における原理原則という考え方。これは、公平公正な行政を行うには特に重要な考え方だと思っています。不明確であったり臨機応変であれば、それはかえって、混乱や不平等を生みます。
そして、この考えに従った判断により、対象から外れることもあります。
本作品は、この対象から外れた人達に対して、原理原則だから仕方ないと終わるのか、それとも、終わらすべきではないとするのか、私自身もこの葛藤は業務の中であるので、凄く意味を持った映画となりました。
生活保護制度を通し、本作品のメインとなる対象者以外に、不埒な対象者、同情はできるがルールを破る対象者なども描かれ、原理原則の是非について考えさせられる作品でした。
最後に、終盤に犯人がSNSであげるメッセージがあります。これは本当に重要なことだと思います。
共感できない。公助は崩壊していないでしょ。
まずもって、けいさんは現役時代(理髪店をしているとき)に年金を納めていない。
「そんな余裕なかったよ」で、そのこと(納付)についてなにも触れていない。
サラリーマンは強制的に、そんな余裕があろうとなかろうと徴収されている。
自営業者それぞれの考えのもと、納めないこともできる現制度がそもそも間違いだが、それはさて置き、
サラリーマンが毎月数万円、強制徴収されているお金を、けいさんはその当時に使っていたわけだ。
緒形直人が「きみたちの境遇には理由がある」と言っていたけど、ただただその通りでは?
けれども、その上で、現在困窮状態にあるならば、きちんと申請すれば、生活保護を受け取ることができるのが日本。
公助は崩壊していない。
震災と関連づけているので、琴線に触れたという人がいるのかもしれないけれど、根本、ソコにまったく共感できず。
難しいテーマ 善悪とは?
登場人物、全員が『善人』である。(?)
Amazonプライムで視聴。
お勧めいただき、早速観てみました!
間違いなくいえるのは、良い作品でした!
役者陣がGOOD!
佐藤健、阿部寛は安定の…!ってところです(^^)
この作品は観る人によって解釈が違うと思います。
何が善で、何が悪か?
殺害される人も『善人』で、殺害する人も『善人』でした(?)
この『善人』の基準とは何か。
『この人は良い人、悪い人』の基準は人によって違う。
利害によって違う。
距離感で違う。
主観、客観で違う。
人•時•所で違う。
シチュエーションで違う。
そして、みんながみんな、自分の考えこそが『正義』だと思っている。無意識に。潜在的に。
『弱者は見捨てて構わない』と思う人もいる。
一方で『弱者を虐める、権力者からは搾取しても構わない』と思う人もいる。
さらに、『弱者を虐める者は殺しても構わない』と思う人もいる。
どれも間違いである。
いずれも、ここに欠如しているのは『愛』である。
お互いを『思いやる気持ち』。
本作の登場人物たちも、それぞれが『思いやる気持ち』がある『善人』達である。
しかし、立場によって、利害によって、『憎しみ』が生まれる。
本当に難しい問題だ。
この問題が、民族規模、国家規模の憎しみになると『戦争』になる。
この世界から『憎しみ』が無くなる日を願うばかりです。 『憎悪』を捨てて、『愛』や『許し』に変わる日まで。
映画最高!
阿部寛濃い演技はノーサンキュー
東日本大震災×生活保護
がどんな化学反応起こすのかなと思っていたが
拙的には落ち着いた感じがして
響かなかった良質な作品。
佐藤健もなんかすごくなったね。
うんうん
お前は父親か
60点
イオンシネマ草津 20211016
重いテーマだけど、キャストも素晴らしく良質な映画
3.38良作
小説原作、全体的に良作な映画でした。
日本人だから共感できるような生活保護や震災を話題としており、事件はおまけみたいなものです。
この映画を見て思うのは、優しい人間は公務員に向かないのだろうということ。世間は生活保護はもっと削減しろといい。明日は我が身になったら絶望する。昨今では、「生活保護を受けるのは恥ずかしい」という考え方よりも「当然の権利である」という権利論者が増えているので、より条件は厳格化していくことでしょう。
もうこういった判断は人間には酷なので、AI行政にお任せになるのも遠くはないような気がしました。優しい人間はNPOや起業をしたほうがより自分の思うがままに救いやすいのでは、と。
震災の悲劇の根深さと社会の闇の根深さ。
生きるって大変で尊い
アマプラにて。
最初は3.11の映画かな?と思ったが、そこから発展し、被災者が被災者を相手する限界ギリギリの精神のなか生活保護を承認する側と申請する側の心情、そして殺人事件。
震災で前を向いていける人は本当に強い。
生きるって難しいし、大変。
夫と3.11の時のことを話した。
人ごとでは済まないし、忘れてはいけないできごと。
もう12年か。。
佐藤健の外見は強がっているが、中身は脆く弱く優しさに満ちている演技が素晴らしかった。
生活保護…
不正受給の問題は時々メディアに取り上げられるが、実際の申請→審査→承認までの実情はどうなっているのだろう。原理原則通りだと思うが、特殊なケースの場合、事務所の裁量はあるのだろうか。映画のように助からないと分かって措置しない行為が果たしてあるのだろうか。映画は震災という重しが根底にあり、加害者、被害者のみならず刑事も心に傷を負っている。家族を失った者同士が生きるために寄り添い、助け合う。それさえ失ったのならば。。復讐の仕方が凄く、真犯人は何となく分かってしまった。ラストの刑事の息子を助けられなかったくだりはちょっとやり過ぎな感じがして、不要だったと思う。
全464件中、41~60件目を表示