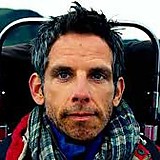クワイエット・プレイス 破られた沈黙のレビュー・感想・評価
全260件中、61~80件目を表示
音を立てない
それだけで観てる方もハラハラ感が倍増。
聴覚に障害がある娘のため、家族は手話を使う。
よく考えたね〜と感心。
音を立てずに移動する。
しかも裸足…怪我してるのに。痛々しい。(靴探そうよ、傷が悪化するよ〜)
終始緊張するが、ちょいちょい息抜きが出来るシーンはある。(酸欠防止のため、時間が決まっている)
わかりづらかったのは、島へ渡ろうとした時に襲ってきた人々。
エイリアンに一致団結してるわけではなさそうで。
いつと時代にもどんな状況でも人間は対立してしまうのか。
前作の続きではあるが、子供達の成長も感じられる。
ビビりっぱなしのマーカスも、なぜか赤ちゃんを放っぽり出してあちこち探るシーンもあったけど(なんでそんなことする〜?)、最後にはお母さんと赤ちゃんを守るべく敵を倒してくれたし。
最後は感動の再会などもなく不気味に終わる。
まだ続くのか…
モンスターパニックのルール
前作クワイエット・プレイス(2018)は手放しの絶賛で批評家に受け容れられました。
じぶんはしばしば映画の評価をIMDBやrottentomatoesでかくにんします。
クワイエット・プレイスのトマトメーター(批評家評)は96%でモンスターパニック映画として異例の高さだっただけでなく、数百人もの批評家間でネガティブ評がほとんどないほどの熱賛でした。
たしかにすぐれたホラー映画であり絶賛に異論はありませんが、批評家たちの異様な高い評価が気になりました。
ホラー映画、パニック映画などのジャンルでは、ここまで圧倒的多数の(批評家の)高評を得ることは稀だからです。
IMDBやrottentomatoesの評価は、おおむね腑に落ちるものです。ただ、自分の予測と微妙な違いがあったばあいに、それが何故なのかを、わたしは知りたくなります。
繰り返しますがクワイエット・プレイスはいい映画でした。だけど批評家評が異様なほど高かったのです。その理由を知りたいと思ったのでした。
調べた結果、なにか核心めいたことが解ったわけではありません。
ただいくつか理由(と思えること)を見つけたので、その考察を書いておきます。
まず個人的には驚いたことですが──多くの海外の批評家たちがクワイエット・プレイスのアイデアを絶対的に独創的とはみなしていませんでした。
クワイエット・プレイスは、そもそも音にはんのうするモンスターあってこそのものですが、多くの批評家がそれをさほど感心していませんでした。
ただし、ほとんどの批評家がアイデアを効果的に運用していることを指摘していました。つまり音にはんのうするモンスターを造形し、それに合わせた世界観を、徹底的に造りあげていたことを称讃していました。
世界を徹底的につくる──とは、まずクラシンスキーとブラントはじっさいの夫婦です。おそらくふたりのリアルな結束がクワイエット・プレイスの成功要因のひとつだと思います。
娘役Millicent Simmondsも「世界観の徹底」のひとりだと思います。彼女は現実に聴覚障害者です。
『生後12か月になる前に、シモンズは薬物の過剰摂取のために聴力を失いました。』
(Millicent Simmondsのウィキ(英語版)より)
『テレビや映画で耳が聞こえない人を見たことがないまま育った私は女優になることを考えたことはありませんでした。私はそれが可能だとは思いませんでした。』
(本人の述懐)
コーダあいのうた(2021)に出演した聴覚障害者のマーリー・マトリンはシアン・ヘダー監督のオファーにたいして、相手役となる夫をじっさいのろう役者から選ばなければわたしは出演しないと突っぱねたそうです。その要求が飲まれTroy Kotsurがえらばれ(男性の)ろう者として初めてオスカー候補になった──のだそうです。
これはたんじゅんな真理──ほんとのろうが演じなきゃリアルじゃない、ということだと思います。
人物のリアルに加え世界のリアルがありました。かれらがなぜそうやって生きているのかを映像で語っていたからです。
『日本の映画監督清水崇は、冒頭10分で引き込まれたと述べ、本作がホラー描写だけでなく家族の関係性もリアルに描かれていると評価した。また、彼はエヴリン役のエミリー・ブラントとリーガン役のミリセント・シモンズの演技も高く評価したほか、世界設定を細かく言葉で説明せず劇中の行動で観客に悟らせている点も絶賛した。』
(ウィキペディア、クワイエット・プレイスより)
『世界設定を細かく言葉で説明せずに劇中の行動で観客に悟らせている点』とありますが、それって映像作品の基本的な使命ではないでしょうか。また、解っているなら清水監督もやったらどうか──とも思いましたが、いずれにしても、世界を徹底的に造りあげたからこそ──『世界設定を細かく言葉で説明せずに劇中の行動で観客に悟らせ』ることができたのでしょう。
クワイエット・プレイスの高評価は、それら(夫婦・聾・世界)のリアリティがもたらしたものだと思います。
高い評価をうけたクワイエットプレイスおよびこのパート2を見て、モンスターパニック映画三つの重要課題を発見したので、それを書いておきます。(発見つっても、たんに素人の自己満にすぎません。)
①それが蔓延または恒常化している人間の習慣をていねいに描くこと。
その(モンスターまたはゾンビの)出現が既に日常となって久しい人間の生活習慣を克明に描く──。これがいちばん大事だと思います。
だめなパニック映画は、モンスターが現れた→びっくり→たいへんだ→いろいろわかんないぞ──を描いてしまいます。
が、観衆はモンスターが現れてびっくりしたり怖がったり、どんなモンスターなのか説明している描写に冗長を感じるのです。
ロメロがナイトオブ~をつくったのは1968年です。クリエイターに人並みの羞恥心があるなら君と世界が終わる日にのようなのはつくるべきではありません。
現れたから(→びっくり→たいへんだ→)いろいろわかんない──まで、ぜんぶ不要であり、現れて数年経っている、慣れている、あるていど退屈な作業感、(新種以外)ぜんぶ知っている──そんな人間側を描くことで、わくわくする導入を達成できます。
②対処措置を三段階くらい用意すること。
モンスターに攻められたときの対処方法(武器や仕掛けなど)を、雑魚と中堅とラスボスで三~五段階に用意しておきます。
雑魚をやっつけるのは習慣・恒常化しているゆえ、だれでもサクッと処置できます。中堅モンスターは主人公を脇役がたすけて「あぶなかったぞいまの」風のヒヤリ感を醸します。ラスボスは「しかたないあれをつかおう」「え、だってあれは・・・」感でやきもきさせます。その上にさらに隠しボスや隠し武器も設定してもいいでしょう。
人間側の対策が、敵の強さに合わせて段階的になっていることで、盛り上がりを演出できるとともに、モンスターが日常化しているディストピアにリアリティを付与します。=すなわち①にも貢献します。
③人道と効率のジレンマを設定すること。
誰か(大切な仲間や家族)を守ることと敵をたおすことの両立ができない状況をつくります。
序~中盤では、誰かを救出するために、あるいは過失のために、やられそうになる、終局では、主役格の犠牲をもって、ラスボスを倒す──のような対価の設定が躍動につながります。
ただしエモーショナルにしてはだめ。感傷をさらりとやらないと、ただの日本映画になってしまうでしょう。
④今までになかったモンスターを創造する。
①②③を使ってモンスターパニック映画をつくるのは④を創造してから。なのでいちばん大事かもしれませんが、おそらくクワイエットプレイスを見た人の何人かは、音にはんのうするモンスターに絶対的な独創性(唯一無二のキャラクタライズ)を感じなかったと思います。
なんかどっかで見たぞ的な印象もあったに違いありません。ただし、音にはんのうするモンスターを徹底的に突き詰めた映画はクワイエットプレイスしかありません。それは正にコロンブスの卵です。
おそらくモンスターのアイデアは完全に独創的である──ことよりは、実現可能な限りで徹底的に突き詰めることができるもの──であることのほうが大事なのだ、と思った次第です。
さらに次回への含みややり残しを残せばなおいいでしょう。
クワイエットプレイスおよびパート2はそれらの課題の手本のような映画だと思った──という話。因みに個人的には初作のほうがいいです。
結局、目新しさはないエイリアンもの
登場人物だったら即死
危険は続く
音に反応して襲ってくるモンスター。 弱点が分かって人間が反撃に転じ...
面白くなっちゃってる!
1はもう突っ込まずにはいられない!と言うような
僕の中ではなんじゃこりゃ作品だったのに、
続編は面白くなっちゃってました。
嬉しいはずなのに何故か寂しい気もしてしまいました。
ただ、あの化け物は何をしようとしてるんだろ?
地球を乗っとろうって魂胆なのかな?
食うでもなくただ殺すだけってのは。
口と口が開いたら鼓膜?が見えるビジュアルは
とても良いなと思いました。
前作は子どもが足手まといと言うか、
逃げるのに子どもが足枷になると言う構図だったと
思うのだけど、
今回は子どもが独り立ちし、皆を守ると言う話だった
のが続編の意味だったのかなと思います。
怖くてドキドキ出来たし面白かったです。
しかし、耳が頼りの化け物なんだから眼前に迫った時
向こうのほうに何かしら投げりゃ時間稼ぎ出来るんじゃ
なかろうか?
と突っ込み待ちしながら観てたので、そこだけは
思ってしまいました。
ポップコーンも食えない笑
エミリー・ブラントがニコラス・ケイジに見える
まあまあだったかな。
子どもたちが主役の成長物語風。
風というのはイマイチ描ききれていないので。
面白かったけど地味な感じだった。
1作目を見てからだいぶ経ってたので冒頭で前回のシーンの
名残が出てきたんだけど結構忘れてて、微妙に入り込めなかったなー。
ハウリング音が嫌いというのも忘れてた😵
母親のチームと娘のチームで別々に戦ってるんだけど
いちいちシンクロさせるシーンがちょっとわざとらしい演出で
ウザかった。最後にやっつけるとこだけシンクロさせれば十分。
どちらのチームでも怪物は各1匹だけでの戦いで
ピンチに継ぐピンチという感じではなかったので
続編にしては盛り上がりがイマイチだったかな。
静かな盛り上がりというか。。。
多分パート3を視野に入れてるんであろう。
中だるみ感があったかな。2になっても怪物がどこからやってきて
何なのかなどや、人間の反撃などもうひと盛り上がりがありそうな感じだった。
赤ちゃんの存在や喋れない、耳が悪いなどの設定をもう少し
上手くいかせるべきだったかな。せいぜい補聴器が
武器になる程度なのが残念。
もっと怪物がいっぱい出てきてバトルがないと
カタルシスがえられないね。
もう音を立てずには生き残れない
原題
A Quiet Place Part II
感想
音を立てたら即死で話題をさらったサバイバルホラーの最新作!!
本作は導入部で始まりの日が描かれていたので分かりやすかったです。リーもボーも生きてますね。
そして前作よりも格段に緊張感、面白さがパワーアップしてます。
赤ちゃん関係なく前作より緊張感が倍増です。
相変わらずの裸足は痛々しいです。
もう主人公はイヴリンから娘のリーガンになりましたね笑
子供たちの成長がすごい感じられました。
エメットが素晴らしくリーガンとエメットの関係性はラスアスのジョエルとエリーを見てる感覚でした。
荒廃した世界、荒くれ者とラスアスですね。
ラストはさぁ人類の反撃だ!って感じでした。
今年の映画見納めは今作でよかったと思います。
※Byond The Sea
相変わらず静かな作品
現代版の地球上バトルでの台詞少なめ“ALIEN”
冒頭の前作未鑑賞の人の為のプロローグはすぐく良かったと思います!
この設定、ジャンルは大好物なのですが、
最近の映画の作り方は80、90年代頃と違い(当たり前だ!)スピード感があるがストーリーに引き込まれる力が弱く感じてしまう……(歳を取ったからか)
昔の映画は、事件が起こる前からストーリーが始まっていたが、最近は事件が起きてからこうなってたよという作品が多く感じる。時代の流れだからか。簡単になんでもできてしまう、便利な時代だし。映画の作り方も変化してきているのかな……(すべてではないが。)
ライトで見やすくなったぶん重みがないような気がしてしまう。
映画は映画館で見なくては駄目ですね(前作は映画館で見ましたが(^_^;))
ウォーキングデッド+ジェラシックパーク新鮮味あまりなし
このシリーズの第一作では非日常+非日常(無音の出産)や非日常と日常の無情な対比(おもちゃの音による末っ子の喪失)等、新鮮な驚きがあった。
だが第二作になると話の焦点が家族の維持と、家族それぞれの成長に移り、新鮮味が薄れたような気がする。家族の生存の為の戦いには、ウォーキングデットやジェラシックパークで見た既視感を感じる。
この映画の取り上げるべき点とは、破壊された世界における、人物それぞれの選択と行動、そしてその結果だと思う。母親の我が子を第一に思い、取る選択と行動、どんな異常な世界でも、母親の愛は変わらず強いのだ、と描いている。
特筆すべきはろうあ者の長女の成長だ。前作でも彼女はそれなりに活躍したが、今作では彼女を中心に焦点をあてている。彼女の選択と行動が家族を救い、世界を救うきっかけになるのだ。肢体不自由者が世界を救う、人間の可能性は実は無限なのだと、映画はおしえてくれる。
ウォーキングデットでも感じたが選択と行動がすべてを決めるのだ、例えそれが最悪の結果になろうとも、選択と行動をしないことの方が最悪なのだと訴えている。それが実にアメリカ的だと私は感じる。
絶望の中に希望(=子供たち)は立ち上がる
絶対に笑ってはいけない! 笑ったら、即尻バット!…は毎年大晦日の恒例だけど(今年はやらないみたいだけど)、
絶対に音を立ててはいけない! 音を立てたら、即死…。
斬新で緊迫感ある設定が話題を呼び、大ヒットしたSFサバイバル・スリラーの続編。
コロナで1年公開が延期になったが、コロナ禍の全米で初の1億ドル突破となり、意義ある大ヒットとなった。
今回まず見せ場は、OP。
のどかな田舎町。子供たちが草野球に興じ、それを応援する親たち。
まだ平和だった頃…。
前作は“何か”に支配され荒廃した世界のみで話が展開していったが(それはそれで引き込まれた)、今回は事の始まり=“DAY1”も描かれる。
突然の隕石飛来。その直後、音や音を立てた人々を“何か”が次々に襲撃…。
息つく暇も無いあっという間の衝撃の出来事に、ただ恐怖し、逃げ惑うしかない人々…。
その中で、徐々に気付く。“音”を立ててはいけない、と…。
それでも一人、また一人と犠牲になっていく…。
アボット一家は辛うじて危機を脱していく。
このOPシーンで秀逸なのは、長回しを多用。臨場感や緊迫感を高めている。
そして、“DAY474”。いよいよ前作の続き…。
家族を救う為犠牲となり、大黒柱のリーを失ったアボット一家。
家を出、安住の地を求めて危険ながらも旅に出た母エヴリン、長女リーガン、長男マーカス、産まれたばかりの赤ん坊。
道中、マーカスが怪我をする。前作のエヴリンが釘を踏む描写も痛々しかったが、今回もOUCH! 声を上げずにはいられない。
“何か”襲撃。廃工場へ逃げ込む。そこで一家を助けたのは、エメット。死んだリーの友人。
助けたのは助けたが、旅をする一家の手助けはせず、廃工場から出ようとはしない。
廃工場には密閉すれば音が外に漏れない焼却炉がある。万一の時はここに逃げ込めば“何か”に襲われる事はないが、密閉空間になる為酸欠状態に…。(←勿論後々そういう危機になるという事)
前作ではほぼ一家のみだった登場人物。
今回は謎の人物エメットの他にも、生存者が居そうな…?
と言うのも、リーが遺したラジオ。それから流れる音楽『ビヨンド・ザ・シー』。
一家は知らなかったが、4ヶ月ずっと同じ音楽が流れている。
ラジオの故障ならまだしも、ひょっとしたらこれは合図…? 誰かが意図的に…?
流れている場所は廃工場から一日もかからない距離にある島。
曲の意味は、“海の彼方へ”。
リーガンは家族の制止を振り切り、行動に出る。発信源の島目指して旅へ…。
家に立て籠るだけのシチュエーション的だった前作と違い、いつ襲われるか分からない外の世界でさらにサバイバルのスリルは増し、目的の場所を目指すロードムービー要素もプラス。
やはり今回も“音”の演出が素晴らしい。
森の中、落ち葉を踏む音でさえドキドキ…。
ある罠や鳥の羽音/鳴き声にビクッ!
音の演出で見事だったのは、リーガン。ご存知のようにリーガンは、難聴。時折無音になる。
道中、必要なものを調達しようとする。が、耳が聞こえない故、どれくらいの音を立てているか本人は全く知らない。
本人は音を立ててないつもりが、気付いた時、“何か”がもうすぐそこに…!
天晴れな恐怖演出!
そこを救ったのは、エメット。
2人で発信源の島目指して旅を続ける事になるのだが…。
ある朝起きると、エメットの姿は無く、補聴器も無い。騙されていたのか…? 疑心暗鬼。
ある港。ここで彼らを待ち受けていたのは、言うまでもない。滅びた世界、得体の知れないものと同等に恐ろしいのはモラルが崩壊した人そのもの…。
一方のエヴリン、マーカス、赤ん坊は廃工場に留まる。
エヴリンが必要品を調達に行っている時、ついついマーカスが音を立ててしまい…!
襲撃する“何か”。エヴリンは子供たちを救う為、機転を利かせて対決する。
この2つのエピソードが交錯して展開。
一緒に居た家族が途中から別れ、下手すりゃスリルが分散してしまいがちだが、これが呼応するくらい相乗し合っている。
例えば…
港でのリーガンとエメットの危機と、廃工場でのエヴリンとマーカスの危機。
島に辿り着いたリーガンとエメット。“何か”は水が苦手で海を渡る事が出来ず、生き残った人々は島で平和に暮らしていたが、渡ってきた船に“何か”が…。
“何か”による島襲撃とリーガンらの決死の闘いと、同じくエヴリンらの決死の闘い。
これら全くの別場所で繰り広げられるのに、そのあたかも繋がっているような巧みな編集の妙!
OPの見せ方も巧いし、“DAY1”から“DAY474”への繋ぎ方も絶妙。
今回も相変わらずツッコミ所はあり。
音立てるなよ!音立てるなよ!絶対に音立てるなよ!…と言ってる割りに、ちょいちょい音を立ててる皆さん…。ダチョウ倶楽部か!
あっという間に世界や人類を滅亡させたのにも関わらず、鉄砲であっさり退治も出来る。脅威なんだか弱いんだか分からない“何か”。
廃工場や島の暮らしを脅かした張本人は…、まあこの辺で。
しかし、この斬新な設定やスリルはますます冴え渡り、OPやクライマックスのパニック演出や“何か”とのバトルなどスケール面もアップ。
上々の続編。ジョン・クラシンスキーのチャレンジ精神は止まらない。
続投のエミリー・ブラント、初参加のキリアン・マーフィ、ジャイモン・フンスーはさすがの熱演だが、今回はあくまでサポート側。今回の実質主役は、子供たち。
リーガン=ミリセント・シモンズ、マーカス=ノア・ジュブ。
シモンズの熱演、ジュブの成長。
彼らの逞しさを見よ!
絶望的な世界のサバイバルSFスリラーだが、僅かな希望を失わない、一種のジュブナイル映画にも最後は感じた。
全260件中、61~80件目を表示