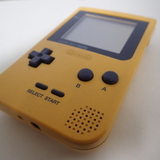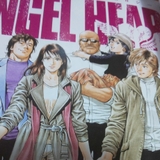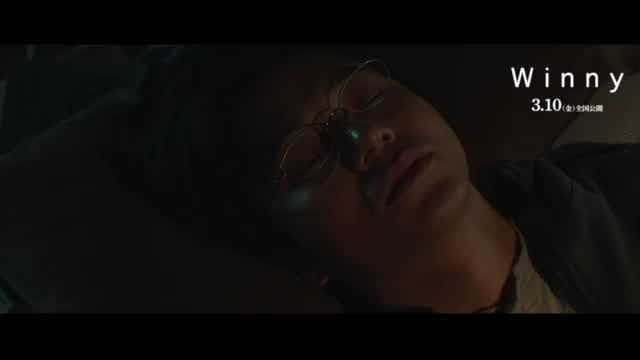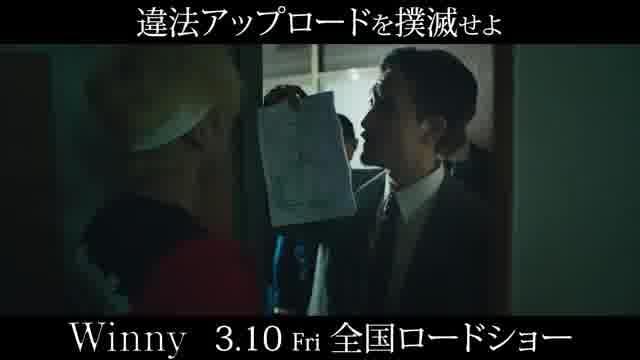Winnyのレビュー・感想・評価
全302件中、261~280件目を表示
二本立てで見たかった
この事件があった当時
そこまでパソコンに詳しいわけじゃなかったけど
あちこちで流出騒動があったのは記憶してる。
巻き込まれた人々も多かったでしょうね。
可能なら、Winnyの開発者の話と、愛媛県警の不正問題の話
ちょっとずつ絡みながらも
それぞれの作品として見たかった。
一本でまとめるのが勿体無い。
古く浅い。
Fly Away
10日公開は個人的に魅力的な作品が少ない週…。消去法で今作を選びましたが、これがまぁ傑作でした。マジで舐めててすいませんでしたとしか言いようがないです。
パソコンで立ち上げたサイトが悪用されて、そのサイトを作った開発者が不当逮捕されてしまい、その開発者の無罪を証明するために戦う弁護士と開発者との物語になっています。
日本の警察描写は基本的に間抜けなことが多いんですが、今作はとにかく悪どい奴らが多いので、腑抜けに感じるシーンはあまりありませんでした。とにかく権力で抑えつようとする感じ、裏工作を仕掛けて事を収めようとする感じ、年代は違えど悪い警察はとことん悪い、それを体現するメリハリの付け方はとても良かったと思います。
役者陣の入り込みも素晴らしく、東出くんのひょうきんさとダークさが絡み合った濃厚な演技、三浦さんの真摯に事件と向き合う弁護士の鏡の様な生き様の演技、渡辺いっけいさんと吹越満さんの裁判シーンでのバチバチの演技、吉岡さんの警察の裏を暴露する強い姿勢を見せる演技、邦画の中でもトップクラスの演技合戦が観れて最高でした。最初から最後まで隙のないものになっており、エンドロール後に流れるこの作品のモデルにもなった金子勇さんの映像を見ると、東出くんが完全に重なっており、憑依力がエグいと思いました。
リアルな裁判シーンでこんなにもカッコいいと思えたのは初めてで、僅かな隙を見つけてボロを出させて、一気に証拠をたたみかけるという頭脳戦で圧倒する面白さを邦画で体験できたことがとても嬉しかったです。これからの邦画の裁判シーンはこの作品と比較されていく気がします。
淡々と進むドラマに緊張感が直走り、その中で解決へのピースが埋まっていく瞬間、最高に気持ちいいです。ぜひ劇場へ。
鑑賞日 3/10
鑑賞時間 12:10〜14:30
座席 F-14
正義ってなんだ?
Youtubeが普及する前に一人の天才プログラマーが開発した「Winny」の事件を映画化したノンフィクションリーガル作品。弁護士・壇さんと無邪気な天才プログラマー金子さんが「著作権侵害」をめぐる裁判を繰り広げる傍ら、愛媛県警の巡査部長・仙波さんが県警内で裏金作りが行われているのを告発する。「著作権侵害」と「裏金作り」一見関係なさそうに見えるが「Winny」をきっかけに国家の闇を暴く、という濃ゆい内容で脳みそが満腹になりました。
一言でいえば暴露映画だと認識しました。警察・検察・裁判所の面子を潰す場面が多く、「公権力の信憑性」を今一度見直す良い映画でした。
また、この映画を今の10代に観てほしい気持ちになりました。プログラマーの苦悩や弁護士の仕事がこの映画で細かく描かれているので、プログラマーや弁護士の仕事に興味ある人は必見だと感じました。
おふざけ一切ないですが、無駄な場面がなく充実した時間でした。
20年前も今も日本の組織は何も変わっていない
《2ちゃんねる》や《Winny》が何かを知らなくても、社会人であれば何となく自分との共通項を見出せる作品。
かく言う自分も、Winnyのことはほとんど知りません。
ただ、上司からの指示が社会通念上あり得ないものだったり、実際にことが起きた時に指示役の上司が責任を取らなかったという経験。社長クラスでない限りは、ほぼ全ての社会人なら(公的機関に勤めている人も含め)何かしら経験していると思います。
自分も覚えがあります。
20年前の事件を扱っている作品ですが、日本の組織の仕組みとしては、今も昔も何も変わっていないんじゃないかと思いました。
これは別に警察組織という場に限らず、一般企業にも当てはまりますが。
映画自体の出来は素晴らしかったですが、社会人的には観終わった後、すこぶる嫌な気分になりました。
まあ、でも何にしろアレですね。
自分と共通言語で話せる仲間の存在(今作では壇弁護士)は、精神的にも社会的にも大きな存在なんだなと。
もっと広い視野で描いてほしかった
かつて話題となったソフト「Winny」を題材としているところに興味をひかれて鑑賞してきました。他にも、作中にソフト「Napster」や雑誌「ネットランナー」等が登場していて懐かしかったです。思えば、この頃から情報漏洩や著作権といったものが、自分にとって身近になってきたように感じます。
ストーリーは、ファイル共有ソフト「Winny」による著作権侵害が社会問題となる中、開発者である金子勇を著作権法違反幇助の罪に問おうとする警察と、無罪を主張する弁護士・壇俊光たちとの裁判での攻防を描くというもの。実話をもとにしているため、ドラマチックな見せ場はないですが、当時の記憶がある方には興味深く鑑賞できるのではないかと思います。
Winny開発者の刑事責任の有無を問うという単純なストーリーですが、Winnyの使用経験のない方には少々イメージしにくいかもしれません。とはいえ、その仕組みや違法性について単純化して噛み砕いて描いているので、ネットワークの基礎知識がなくても内容は理解できると思います。また、裁判での争点や駆け引きもなかなかおもしろかったです。
これと同時進行で愛媛県警内部の裏金問題が、メインストーリーとは絡まないながらも、間接的にWinnyの援護射撃をするかのような形で描かれます。全編通して、警察の悪意ある捜査、隠蔽体質、組織の腐敗などを糾弾するスタンスを感じます。開発者の金子勇氏が優れた技術者であり、彼に犯罪目的は微塵もなかった、そんな彼の名誉を守るために、本作は作られたのではないかと思います。もちろんこれはこれでおもしろいのですが、著作権保護の立場からWinnyの存在を苦々しく思っていた人には、作為的な描き方と受け取られるかもしれません。
エンドロールで、金子氏が「誰かのせいにすればいいというわけではない」とコメントしたVTRが流れるのですが、まさにそのとおりだと感じました。とかくこの国は何かが起こると誰かに責任を押し付けて叩いて、ことを収めようとしているように感じます。しかし、警察が全て悪いと言わんばかりの本作も同じではないでしょうか。なぜ警察が開発者の責任にあそこまでこだわり、あのような捜査や尋問をしたのか、その真意はどこにあったのか、軽い気持ちでWinnyを悪用した人間がどれほど多く、著作権者にどれほどの被害や迷惑があったのか、コンテンツクリエーターたちはどう感じていたのか等、愛媛県警の件よりこっちをもっと広く描いてほしかったです。そして、それぞれの立場や思いを感じ取らせ、観客が自身の行動を振り返るような描き方にしてもよかったのではないかと思いました。警察VS弁護団という小さな構図にしてしまうのは、ちょっともったいなく感じました。
キャストは、金子役に東出昌大さん、壇役に三浦貴大さんで、どちらも上手くハマっていました。脇を固めるのは、皆川猿時さん,吹越満さん、吉岡秀隆さん、渡辺いっけいさんらで、ベテランらしい安定の演技で作品を支えます。
良かったです。
20年立ちました
この映画の述べたいであろう「真の趣旨」は別のところにあるのでは?
今年77本目(合計729本目/今月(2023年3月度)12本目)。
1時間差でみた今週の本命作であろう本映画です。
WinnyはIT技術者であればもちろん、当時は社会をにぎわした事件であるので、知っている方も多いのではないか、と思います。
「表向き」はタイトルがそもそもWinnyですし、Winnyを扱っている部分もありますが、個人的には「第二、第三の論点が見え隠れしているが、(大人の事情で)表向きに出せなかった」のではないか、換言すれば、「この映画の主義主張は他のところにあるのではないか」と思えます。
採点としては特に差し引く要素までは見当たりません。
多くの方が書かれている通り、第一審(地方裁判所)しか描かれていないのも、下記に述べる「この映画の真の論点」に焦点をあてたという解釈をすれば至極当然の話であるからです。
なお、以下は、行政書士合格者レベルでの理解と採点、ほか補足説明や私見によるものです(反対意見ほか大歓迎です)。
(減点なし/参考/「ほう助」について法律事務所で聞いているシーン)
・ 日本には「刑法」という法律があり、学説をとく本では「刑法総論」と「刑法各論」の2部構成(あるいは2冊)になっていることが多いです。前者は「どのようなときに罰せられるのか、罰するべきものは何か、あるいは「ほう助」とは何か「共犯」とは何か」といった総論的なもの、後者は「個々の刑罰(例えば、殺人罪や傷害罪ほか)について各種の展開をしていく」という構成になっているのが日本の伝統です(ただ、本格的にこれを学習するのは、司法試験(予備・本試験)以外ありません)。
しかし、「ほう助とは何か」は映画内でも示されている通り、学説上の対立が非常に激しく、また判例も一貫していない部分があります(具体的な事件ごとにコロコロ変わっている)。この「ほう助」については学説の対立があり、「理解の難しいところ」であるのは確かです。
(減点なし/参考/「判例を調べる」の部分)
・ 日本の裁判制度では「判例」といった場合、最高裁判例を指すのが普通です(これに対し、高等裁判所以下のそれを「裁判例」といって使い分けるのが普通です)。
-----------------------------
▼ この映画が真に伝えたかったことは何なのか
もちろん私は映画監督ではないので、一人の資格持ち、あるいは一人の鑑賞者としての意見になります。
本映画でWinnyが題材にはなっていますが、Winny「それ自体」の技術的な論点ほかはほとんど映画内では前提になっていません。むしろ、「特定の警察組織」に関することばかりが多く取り上げられています(ネタバレ回避でぼかしています)。
翻って日本を見ると、現在においても、「法の解釈を誤った間違った逮捕・拘留」といったものはある程度見られます。それは人がやることなので「ある程度は」仕方がないところです(だからといって、警察官が怠けてよいという理由にもならない)。
しかしこの映画の「とある警察組織」のように、「そもそも根底論から無茶苦茶な警察組織」ではまともな裁判は展開できません。この映画は固有名詞が出るように、その大筋において史実と同じです(正直、国民目線からすればあきれるレベルでしかない)。「単なる誤認や勘違い」と「警察の支離滅裂な公権力の行使」は分けて考える必要があります。この映画はもっぱら後者を問題視したもので、ほか、リアル日本で「多くの人がこれは変だろう」と思えたであろう「無茶苦茶な事件」としては、「鹿児島県警の「踏み字」事件」などがあげられます(詳しくはネット参照。あまりにも無茶苦茶すぎて地裁で警察内部が裁判官から論破されて地裁で確定している)。
この映画は、そのような「あまりにも支離滅裂、やる気もなければ不正行為もモラルのかけらもないやる気ゼロ」の警察組織に対するメッセージではなかろうか、というのが個人的な意見です。
そしてそのような批判は、「常識的な範囲であり誹謗中傷等にあたらない限りにおいて」は日本では言論の自由で保障されますし、映画での上映においても同じです。また、映画内で出る「プログラム作成を通した自己表現の自由」や「報復を恐れる意味での匿名性を維持したソフトの開発」も、結局は「言論の自由」に帰着されます(「匿名性の確保」をどう考えるかは難しいですが、匿名性を盾にとって誹謗中傷を繰り返す類型と、匿名性を担保したうえで内部告発等を行う類型は、明確に区別する必要があります。今でも報復を恐れて内部告発ができないケースはあるからです。そして後者には「ある程度の妥当性」が認められるべきものです)。
要は、この映画はタイトルこそ「Winny」であるものの、結局のところ「あまりにも支離滅裂がおかしい警察組織へのメッセージ」、あるいは、「表現・言論の自由は「基本的人権の王様」と呼ばれるように最大限尊重されるべき」という立場で作られたものなのだろう、というところです(もしこれが気に入らないなら、その映画内で参照されている「特定の都道府県の県警」が抗議などしていると思うので)。
-----------------------------
長くなりましたが、この映画の「真のテーマ」はこのように別のところにあり、Winnyというタイトルは「ひとつの出来事のひとつにすぎないのではないか」というのが個人的な見方です。このように解すれば、「ストーリーが妙なところで終わってしまう」等も理解ができるので、個人的にはこの立場です。
司法が潰した画期的な新技術
東出クン、開眼したんじゃないの。プログラミングのこととなると無邪気で話が止まらなくなる。刑事や検事の強面に臆してしまう。そんな金子さんの人となりがスクリーンを通して伝わってくる。
東出クンを応援する気はさらさらないが、彼が出演する作品は見たくなるね。
当時、金子さんの逮捕に驚いた。いくら悪用されているソフトの開発者とはいえ、無理筋にも程がある。
京都府警の警察官がWinnyに生息するウイルスに引っかかって、捜査資料もろともPCの中身を晒された。京都府警のメンツは丸潰れで、著作権保護を大義名分にして金子さんを潰そうとしたのは間違いない。
さらにもっと問題なのは、司法が機能しなかったことだ。作品中でも描かれているが、ソフトウェアが何たるかを理解できない裁判官が事件を担当している。京都地方裁判所の、いや日本の司法の無知蒙昧を全世界に知らしめてしまった。これは、恥ずかしい。
愛媛県警の裏金問題をwinny事件に絡めて差し込んだのは、余計だった。金子さんは反権力を志向していなかったし、本人が語っているように「そこに山があるから登った」でしかないと思う。ちょっと焦点がぼやけたかも。
全体から見ると、ちょっとしたマイナスでしかなく、それを上回る法廷シーンの面白さがある。弁護側が、京都府警の刑事の嘘を引っ剥がし、矛盾を突かれて歯軋りする刑事の顔には、胸がスッとしますよ。
ビットコインの創始者のサトシ・ナカモトが金子勇氏であるとの都市伝説がある。拘置所でブロックチェーンのアイデアが浮かび、それを実現して換金せずにこの世を去ったとしたら。
革命を起こして世を去ったと信じたい。
水は方円の器に随う。それは人とモノの両方に言えること
今となっては死人に口なし、
『金子勇』が「Winny」を開発した時に
どのような思いであったのかは
しかとは判らない。
が、今回の映画版では
少なくとも悪意は無かった
との前提に立っているよう。
もっとも、そうした旗色を鮮明にしないと
ストーリーは創り辛いのだな、とも思う。
コンテンツを作る側は
違法動画のアップロードと日々闘っている。
承認欲求が満たされ、
オマケに報酬が得られる行為は
一つBANしても、
直ぐに異なるアカウントで復活する鼬ごっこ。
それでも、野放しにするわけにはいかず、
サイトをクロールしピックアップ、
弁護士からの要請で処理。
削除対応の速度はサイトによって様々も、
概ね以前よりもスピード感は上がっているとも。
とは言え、動画サイトそのものを悪としているわけでは勿論なく。
いみじくも本作でも語られているように、
道具は使い方によって善にも悪にも染まる。
あくまでも相対する側の人間性が現れるとの理解。
本作での『金子勇(東出昌大)』は
無垢というよりも世間常識がかなり欠落している人間との描写。
実際の当人の人となりは知る由もないが、
周囲にサポートする人間は存在しなかったのかと悲しくもあり。
海外でのそうした天才には
多くが伯楽の存在があり、
上手くサポートしている印象なのだが。
事件を通して知り合った弁護士が、
それに近い存在になるのは何とも皮肉。
主人公の描き方の偏りに加え、
法廷での幾つものシーンにも迫力が感じられぬのも不満。
また、最後まで警察が起訴した理由が明確に提示されぬことも
消化不良の要因。
中途挿入される「愛媛県警の裏金事件」も実際に有ったこと。
警察の暗部と、一方で中には正義の人も存在することの対比の妙はありつつ
「Winny」の功罪と併せて語るのはズレている気もする。
官の側は、先進の技術開発を可能な限りサポートすべきであり、
この国にありがちな、率先して枠を嵌めてしまう行為への反意は激しく頷ける。
もっとも、本作では先にも挙げた多くの要素を盛り込んだため、
ややピントがぼやけてしまった印象を受けるのだが。
警察と検察の阿吽の呼吸で
宥めすかし、知識が無さそうなの良いことに
騙すのに近い手法で誘導、罪を膨らませるやり口は
〔99.9〕や〔イチケイのカラス〕等のドラマを生む下地として
日本的なあるあると義憤も感じる。
自分が同じ立場になったら、と
空恐ろしくもあり。
エンドロールを見れば、制作に当たっての
公的機関の協力は当然のように一切無く(笑)。
弁護団の各員や『仙波敏郎』等の個人名に止まるのは
思わず笑ってしまった。
事実を‼️真実を‼️究極までに再現した‼️歴史的‼️❓ドキュメンタリー的‼️❓最高映画‼️
見て楽しいと思う作品ではないです
起起承承転結転結結のストーリー構成
Winnyの実話としての物語性は素晴らしいものです。そのために本作の題材は悪くはありません。
しかし、監督が金子勇さんという人物を理解しようと努力して、敬意を払い、観客に伝えようという意思は全く感じられませんでした。
本作は金子さんを逮捕した警察の裏の意図を観客に伝える役割として、仙波敏郎さんという実在の方を用いていますが、“観客にそのことを伝える実力が監督には無く”、作品の中に金子さんを主人公とする物語と仙波さんを主人公とする物語の2つが、重なることなくそれぞれ独立して存在します。
そのために起承転結が2つ存在し、合間に挟まる仙波さんの物語が、金子さんの物語に集中しようとしたときのノイズにしかなっていません。
また金子さんの物語の「転」の後、急に時間が飛び別の1つの「結」が現れます。
さらに最高裁の判決という本作の本来の「結」の部分を過程を省略して表現していて、さらに非常に簡素であり、なんの感慨も生まれません。
そのためにタイトルのような起起承承転結転結結のストーリー構成になってしまっています。
結論としては、この作品は監督の描写、脚本によって表現したいことを観客に伝える能力が求められる能力に達していないことによる力不足と、過去に実際に起こったWinny事件を理解しようと努力しない怠慢による金子さんへの冒涜です。
しっかりとした捜査・裁判映画 プログラム知識は不要 ただし観客は選び抜かれた精鋭❗️テンポ良し❗️
捜査とか裁判の映画、テレビドラマは
そもそも、法曹、裁判所事務官、警察の経験のない作家、大学の法学部すら出ていない作家原作だから
幻滅する作品ばかり
犯罪立件で重要な【故意】すらわかってない原作者、脚本家が多い。
その点、この作品は 現実の捜査・裁判に基づいているから骨格がしっかりしているし
多くの弁護士が制作に噛んでいる模様だから・・突拍子もない飛躍は無くて安心。
愛媛県警だかの吉岡秀隆演ずる55歳巡査部長の話も【一瞬間チカラ技】に見えたが
事実であるか否か【有料パンフは一応見ましたが・・】にかかわらず
【本件の本質】をついている。【も一回パンフ見たら事実の模様】
ウイニー今も健在の模様で【有料パンフ受け売り】安心した。
確かに【悪用される恐れ】に関してはウイキペディアのとおり認識あったと思う。
ただ、それをもってして罪に問うのは法律ど素人
ワシもウイニー誕生当時、週刊アスキー【仕事の関係で】隅から隅まで熟読してて
ウイニーは結構馴染み、アップロードは一切してないよ念のため。
ただか著作権=犯罪の匂いがしたから、使ったのは数回のみ
偉大なるパイオニア金子勇さんはただ純粋に【そこに山が⛰あるから】ということだと思う。
そうだよ80年代後半以降【マイコン】だったのだよ一部のマニアのみ
Windows95の効果が出たのは1999〜2000年。そのパソコン💻黎明期に一石を投じた
金子勇さん
弁護士の 壇俊光【すごい名前だなぁ】さん に敬意を表したい。
体重を増量した東出昌大、いい意味で老けたなぁ、山口百恵の息子の三浦貴大も好演
イヤイヤパソコンは💻実は一般レベルでは普及して20年と少し
映像配信、SNS 等 隔世の感ですよ。
比較的長い作品なのだが、構成の巧さ、テンポの良さで飽きることは無い人間と進歩を考える作品
ただ、上映回数が少ないのは疑問 前列含め、ほぼ満員だった
こういう作品故か【予告編、着席段階から、声どころか咳ひとつない】選ばれた精鋭たち
が集う観客席であった。
淡々と進んでいく感じにハマりました
難しいテーマだと思った
実話ベースの作品で、淡々とストーリーが進むが当時のことを知らなかったので楽しめた。
得体の知れないものは怖いと言うが、当時のwinnyはそういうものだったのだろう。
無罪が勝利と軸になっているが、著作権侵害によって被害受けてる人もいることは事実なので、その人たちから見たらハラワタ煮えくりかえってることは間違いない。
そこがこのテーマで作品を作る難しさだと思った。
劇中で検察官が「マスコミがリークしたことなので関係ない、分からない」と言っていて、お前たちが有罪にしようとしてることはそういうことなんだよとツッコミたかったし、渡辺いっけいの悪おじさんがギャフンとなるところは最高。
裁判の傍聴席に阿蘇山大噴火さんがいるディティールには笑った。
最後のエンドロールまで見て、現代にまだこの天才が存命であったらどういったネット革命が起こってたのか、とても気になった。
別の視点から P2Pはそれ自体が革新的なのではない
インターネットは本来P2Pが簡単に行えるものです。
しかし、32bitという制限とそれを前提としたルーターやLANの存在がP2Pの壁となり、少しそれを行い辛い環境が広まってしまいました。
その壁を超える手段は割りと簡単なのですが、万人が使える形でソフトウェアにするという人は当時あまり存在しませんでした。
技術革新という言葉が先行しすぎていますが、それを加味しても金子さんが実装力のある天才である事実は変わりません。
そして、京都府警が行った違法取り調べの事実も変わりません。
この問題の本質は、取り調べと司法判断の違法性と不条理です。
3月の春風と共に青春が戻ってきたかのような映画です。
日本人にしかわからないでしょう。
全302件中、261~280件目を表示