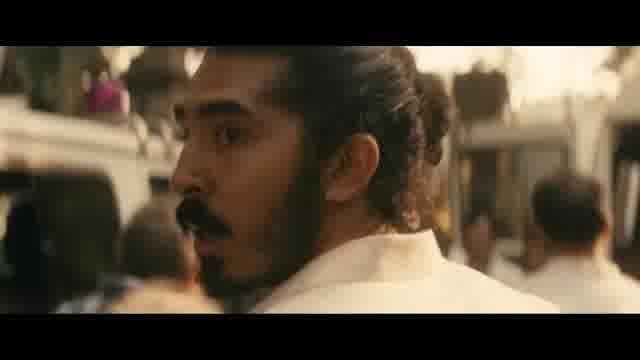ホテル・ムンバイのレビュー・感想・評価
全257件中、201~220件目を表示
正義の意味
インドのテロをやはり、記憶にありません、実話に忠実に作られたとある。子供を使って影で操る奴らをどうか捕まえて。どこのテロも爆発犯は利用されてる。
宗教の名の元に
正義をかざし、貧困を他人のせいにする。
苦しいだろう、這い上がるのは。テロリストが海から上がる、波打ち際には大量のゴミ。
混雑の電車、その実情を垣間見ただけでも、この場で幸せを願うのはきびしい。
だから、彼が映画で世界的に成ることが奇跡であり、彼がライオンから更に飛躍しつつ、
インドを捨ててない。
ハリウッドに染まらず。劇中でも、ターバンの説明はとてもグッときた。
理不尽な攻撃はいつの世も怒りを呼ぶ。
ずっと手を握りしめていた…
予測不能です
祈りこそ全ての元凶
初めから終わりまで手に汗を握りながらの鑑賞
なんとも・・・
作品としては満足。ただし複雑な気持ち
恥ずかしながらこの出来事は知らなかった。
その為この映画でこの出来事を知ることになった為、率直な感想としてはとても複雑な気持ちである。
映画作品としては素晴らしいものだろう。知らない僕にとっても2時間あっという間に時間が過ぎ見入る事ができたからだ。
ただノンフィクションという事もあってどうしても被害者感情が強く出てしまう。
ノンフィクションが故にテロリストの背景などは一切描かれる事はないので、やはりどうしても怒りだけが湧いてしまう。未熟ながらその怒りの矛先がどうしても、地元警察や警備隊に向いてしまった。
彼らもまた被害者であり、計画的なテロのためきちんと機能させないように阻んだんだろうと思うが、やはり被害者感情が強く湧いてしまう。まだまだ僕は理解が追いつかない未熟さを痛感させられた。
やはりこういったノンフィクション作品だとこの作品を通じて何か学んだ、育んだということは難しいが、窮地に立たされた時に団結し時には自分が犠牲になってでも他者を守るといった正義心には心打たれた。(ただしこれもまた本当に正解なのかはわからない)
中々難しい理解になるが、確実に言えることはどんな理由、価値観があろうともテロリストを断じて許してはいけない。そしてホテルムンバイの従業員達を心から讃えたいと思った。
もう一つ何かが足りない…
「ダイ・ハード」ではない。
引き込まれました
終始緊迫感が収まりませんでした。
実際にあった事件だから
尚更恐ろしい。
実行犯が時折見せる純粋さが
一層リアル感を引き立てました。
久々に素晴らしい映画に
出会えました。
とても満足です。
心が掴まれる感覚
2008年インドのムンバイで起こった同時多発テロを
題材にタージマハルホテルを占拠された事件を描く。
史実に基づいているので過度な脚色は出来ない分
映画としての描き方は限定的となる。
現在においてはホテルムンバイは再度
運営を再開しているものの、いざ海外のホテルに
宿泊してこんな事件が起こったらと思うと
圧倒的な恐怖に支配される。
この事件の背景には印パ対立問題や
宗教問題など複雑な糸が絡みつく。
印パ対立の根元には米ソの問題も絡むし
テロの少年達が白人達を人質にするのも
そういった問題があるからであり、
歴史の陰の部分が祖父以前の代からの
因縁を持たせ若い人間たちを不幸に陥れていく。
これは舞台の印パだけでなく、我が国に関しても
決して外れていないのだと思う。
この映画において最もピュアな存在の人間が
これからの未来において、どう感じて生きるのか。
製作陣の希望を担っているように感じた。
印パ対立において希望を描いた「バジュランギおじさんと小さな迷子」を
鑑賞しておくとズシンと来た心を救ってくれると思う。
準備するものしないもの
ホテルマン(サービスマン)の矜持なんてものは見えないに越した事はないし、見せない。それでも気が付くものはあるのだが、ほとんど触れない部分。それが危機管理であり、対処訓練である。自分もサービスマンであるが故に、事件の当時からソコを想像して震えたものだ。勿論、怖いからではなく。
さて、この映画。「危機管理」の明暗と、暗い人間を纏める難しさが溢れていて、ドラマとしては苛々したりもするが、それもリアルだったと感じた。主人公とあの女性の行動が正に明暗。それらを感じとるだけでも観て良いのではないのだろうか。個人的には粛々と職務を遂行していている料理長と、緩急で煽られる恐怖が素晴らしかった。
日本は宗教的に偏りが少ないので起こる可能性は低いのだが、何も揉め事は宗教だけではない。明日は我が身である。
すごい迫力と緊張感
犠牲者も可哀想だがテロリストの青年たちも哀れ
パニックもの x テロ x オーストラリア映画 = 駄作
時間とお金の、全くの無駄だった。
インドが舞台なので観に行ったのだが、実は、オーストラリア・アメリカ合作であることに、早く気付くべきだった。
一皮むけば、ただのバイオレンス系ドラマであり、「インドにおけるテロ」を真面目に扱った映画かと思って観に行った自分が馬鹿だった。
重要な役の多くが“白人”か、そのパートナー。(つまり、明白に“白人”目線の映画。)
“白人”につくして、命まで捧げる(!)、“インド人”スタッフ。(主役には、貧困階級のインド人らしさが全くないという、嘘くささ。)
狂信的で残虐なテロリストで、最後は射殺される“イスラム教徒”。(ピザのシーンでは侮辱的な描写がなされる。本当に史実に基づいているのか?)
「実話を元に」という触れ込みだが、“西側陣営”の白人本位のステレオ・タイプな設定である。(東側の“ロシア人”の描き方に注目。)
しょせん想像を膨らまして、虚構をたっぷり交えて作ったエンタメにすぎないわりには、見所のないガンファイト。
ダラダラと長いだけの、閉じ込めパニック。(昔から使い古されてきた衣装戸棚のシーンは、長すぎてうんざり。)
音響効果を期待して劇場に行ったのだが、自動小銃がウルサいだけで、期待外れ。
ただもう、呆れた。
「豚肉のピザなんて食うな!」「ピザじゃありません。ピッツァです!」
2008年にインド、ムンバイで起こった同時多発テロ。若きテロリストたちは5つ星ホテルのタージマハル・ホテルを占拠するのだが、そこにはヒーローなんていない。ビルでのテロと言えば真っ先に『ダイハード』を思い浮かべるのですが、そこにはマクレーン刑事がいるわけでもなく、「お客様は神様です」という信念を持ったホテルマンたちが必死で客を避難させるだけなのです。
洗脳されたイスラム原理主義と思われる若きテロリスト。ことあるごとに「神は偉大なり」と唱えるところなんかは皮肉にも対照的だ。彼らにとってはアラーと先輩たちだけが拠り所であり、人の痛みなんて解らず、他宗教者、欧米人を虫けらの如く殺しまくる。
特殊部隊は1200キロ離れたデリーにしかいないため、到着するまで何とか隠れて持たさなければならない。緊迫感ある展開と臨場感が半端ないため、最後の脱出シーンで失禁しそうになるくらい背筋が凍りつく思いになるかもしれません。『ユナイテッド93』でも経験した緊張感と、自分まで死んでしまうかのような絶望感。もう涙無しでは見れなくなる!
「テロには屈しない」という言葉は、為政者が発言するのと民間人が言うのでは意味、重みが違うと思います。この作品ではまさしく民間レベルでの抵抗劇。個々の命の重みを理解出来るからこそ行動出来たものなのだろう。
まるでドキュメンタリー
まるで、ドキュメンタリー。11年前、こんな事件があったような…なかったような…。記憶も曖昧で、完全に、平和ボケです。
テロの話なので、無惨な殺害シーンが続きます。そんな中、誇りを持って働いている従業員の姿は、感動しました。「お客さまは神様です。」って、日本の言葉だと思ってましたが、違うんですね。
首謀者は、まだ、捕まっていないとのこと。人の命を粗末に扱ったテロリストは許せないけど、彼らも、ある意味、被害者。彼らも、きちんと教育をうけていたら、命を落とさずに済んだはずなのに…。
犠牲者の方のことを考えると、悼まれないです。自然災害ならまだしも、テロを防げる世の中になってほしいですね。いろいろ考えてしまいました。
全257件中、201~220件目を表示