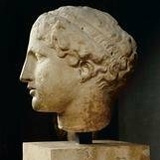浅田家!のレビュー・感想・評価
全350件中、101~120件目を表示
写真が持つ力。改めて教えてくれる、家族の温かさ。
【賛否両論チェック】
賛:“家族写真を撮ること”を通して、家族だからこそ感じられる温かさやぬくもりを教えてくれるよう。1枚の写真が持つ力のスゴさを、改めて実感出来る。
否:どうしても感動的な演出へと持っていく感じは出てしまうので、その辺りの誘導が、人によっては少し苦手かも。
類まれな独特のセンスを持った主人公が、「“家族写真”を“撮る”」という一連の作業を通して、その一家族一家族の思い出やぬくもりを大切に形にしていく姿に、観ていて心が温かくなるようです。そして後半では、東日本大震災の被災地で、“写真を洗って返却する”という活動の中で、主人公が改めて“写真”という存在の持つ意義を再認識していく様子に、思わず考えさせられます。
そんな作品を通して実感させられるのは、1枚の写真が持つ力のスゴさです。詳しくは是非実際にご覧になっていただきたいのですが、その1枚の写真だけで、叶えられなかった夢が叶えられたり、会えなかった人に会えたり、行きたかったところへ行けたりしてしまうのが、本当にステキだなと思いました。
どうしても自伝的な部分だったり、感動的に演出している部分はあるかと思いますが、それでも“写真”というものを通して、家族や人間そのものの温かさを感じさせてくれるような、そんな作品です。是非チェックしてみて下さい。
前半が三重映画でびっくりした。
浅田家!は中野量太監督作であること、二宮和也と妻夫木聡が出演することだけを前情報として鑑賞しました。
見始めてびっくりしたのは、浅田家は津の人達なので、津がめっちゃ写っていたこと。
津新町の駅とか、めっちゃ懐かしい…三重大の最寄駅やんなー。
私は津ではないが三重県出身で、津とか鈴鹿とかあの辺の方言が懐かしかったです。
伊勢弁ともいうらしいが、私はいせことばと思っているあの方言。
そやもんで、とか、~するんさ、とか、友達が話していたことを思い出して懐かしくなりました。
が!!~やに、って誰も映画の中でゆってへんかったけど、あの辺の人らは毎日やにやにゆうんやで?
なんなら私は、~やにだけは、職場が津市なのでやにやにゆってた父の言葉がうつって、三重をはなれたいまでも時々~やにってゆうんやに(~やに、は、ほかの関西弁でいうところの~やで、とか、~やろ?に相当)。
映画でも聞きたかったなー。と、どうでもいいことを思いました。
これまで映画・ドラマの関西弁ポリスとしてしゃしゃり出ていた私ですが、ポリスは引退しました。
そもそも、その地域だからといって全員がおなじ方言を話すわけでもないです。
自分を省みても三重→大阪→和歌山→奈良→京都と転居し、関西系方言が独自のブレンドをなし、どこの方言しゃべってんのか自分でもわかりません。
もはやいずれの地域にいても「純粋な」〇〇弁話者でないです。
そもそも関西にいる関西出身者だけど基本は標準語を話す人もいます。
おうちでは両親の方言を、そとではその地域の方言を使い分ける方言バイリンガルもたくさん知っています。
言葉は道具であって、道具で人を規定するのはおかしいです。
なので、役者が慣れない方言を使い、その習熟度が物足りなかったとして(思うのは自由ですが)やいやいいうのはせんほうがええやろな、と思うようになったのです。ほめるのはいいと思うけどね。
さて、浅田家!ですが、前半と後半で全く違う話みたいな構成でした。
前半は主人公政志が写真家になるまでのクロニクルです。
印象的だったのは、次男でまさしっていうのが、わが弟2と同じ…というのと、
お兄ちゃんが「お母さんは(まさしを)心配している」といい、
お父さんも「お母さんが心配している」といい、
お母さんも「お父さんが心配している」という、
「心配をかける家族に対し、別の家族を引き合いに出してたしなめる話法」が多用されていたことです。
この「心配をかける家族に対し、別の家族を引き合いに出してたしなめる話法」は、私の母が多用する話法で、彼女の場合は自分の意見を言えないので別の家族を引き合いに出して私(や弟妹)を叱る・諭すというもので(私はそう思ってる)、実際の「別の家族(我が家の場合ここには父が入る)」は母に心配とかの意見を伝えていない(両親は意思疎通不全40年)ので、母による願望・想像なんです。
なので、私と母の間では、母に「お父さんもあんたのことを心配してた」と言われると、また出た、父はそんなことほんまにゆうたか?あんたが言いたいことを人に代弁させずにあんたがあんたの意見として言え!とキレ返す、という流れになります。私のキレに対して、母は言い返せないので、図星なのだろうと踏んで生きてきました。
が、映画の中で、何度も出てきたため、他の家庭でも「心配をかける家族に対し、別の家族を引き合いに出してたしなめる話法」が多用されているんだな、もしかしたら三重あるある?やろか、いやごく一般的なんかな?、いずれにしても浅田家での「心配をかける家族に対し、別の家族を引き合いに出してたしなめる話法」は、嫌な感じがしないな…と思いました。
でも更に考えると、相手をたしなめるときに自分の側にインビジブル味方をたたせるっていうのは、やっぱ数に物言わせようとしていて卑怯な感じがするな…私は使わない話法だな…というところに行き着きました。浅田家の人達が使う場合、嫌な感じがしないのは、発言者をいい人だと私が思っているバイアスのせいなのかな?というか、私は自分の母を思考停止した卑怯者と思っているので、そっちのバイアスのせいで母の発言を反射的にはねのけるんかなと思いました。
あかん、作品自体についての感想が遠い…
全体的に面白かったです。いそいそコスプレするおとうちゃんとおかあちゃんは可愛いですし、つんつんの若菜ちゃんもかわいいし、工業高校卒で学校推薦で手堅い地元企業に入社した(←私の予想)であろう「The 地方都市の長男」・妻夫木お兄ちゃんもよかったですし、もちろんまさしもよかったですし。
二宮さんはヒゲと長髪がびっくりするほど似合わないのには、笑いました。
後半の東北パートもね、写真に写ってないお父さんは、写ってないけど撮影してた、インビジブル出演してるって思えた。
よかったねって思いました。
もう会えない誰かと写真の中で再会できる。流された過去の欠片が手元にある。絶望の中で、かき集めた希望。
いけめんオーラを消して登場する菅田将暉もよかったです。
死期が迫る息子との家族写真を撮ろうとする一家のエピソードは、特に切なかったです。
演技力に脱帽です。
写真って愛。
こういうゆる〜い感動が良い
母親の厳しさに感動
家族写真を
家族写真っていいな
二宮くん、はまり過ぎ
二宮くんじゃなきゃこれできなかったでしょうね。
それくらい、合ってた。
コミカルで、自分勝手で、アイデア豊富で
ちょっとだらしなくてヘタレ男で、憎めなくて
でも、すごく優しくて、相手が喜ぶことが一番嬉しくて。
写真家にもいろいろあるけど
趣味だとカメラのことなんか語って、自己満足の人も多いのに
どこまでも人が喜ぶ写真を撮りたくて
あったかい優しい目線
家族って人の帰るところだしね。
鬼滅もそうだけどそれぞれの生い立ち
核となる家族
そこが何より大切だと
いうことをつくづく思わされる。
家族が優しい世の中は平和だよね。
身近な人を受け止め大切にすることって
一番難しいことで
取り替えがきかないからきついけど
だからこそ逃げずに自分が一番受け止めるべき運命なんだろうと思う。
受け止め方はそれぞれだと思いますけどね。
必ずしも仲良くしなきゃ、一緒にいなきゃいけないということではないし
自分は個人的に
自分の得意なこと、出来ることで人を喜ばしていくことだなあと改めて思いました。
あったかい映画でした。
さっすが、中野監督!
笑わせて、泣かせる。「湯を沸かすほどの熱い愛」と同様に、前半は微笑ましいエピソードの連続から、後半は怒涛の涙というパターンに、気持ちよく翻弄された。
各エピソードが繋がっているような繋がっていないような不安定感も、相変わらず健在でした。
笑わせると書いたが、いずれも「変わった人」エピソードであり、自分には素直に笑えない。これも、前作と同じ。だから、前半は、俺にとっては、爽快に楽しいわけではなく、もやもやした感じと言った方が、あってる。
ただ、それが後半の涙と繋がっていることも、またたしかなんだよなぁ。前半がなくて、後半だけでは、おそらくこれだけの涙は来ないような気がする。中野監督の不思議なところは、ここなんだと、俺は勝手に思い込んでいるわけだが、今回も、そんな小難しいことは横に置いておいて、とにかく泣けました。
二宮さんも上手いが、今回の出色は、妻夫木さんと黒木さん、そして菅田さんかな。
写真は家族そのものを写すんですね。
ちょっとレビューためてしまったので短めで連投します。
「湯を沸かすほどの熱い愛」がとても良かったので中野量太監督に期待して鑑賞。
やはり中野監督の描く家族は良い。
ちょっとタメが多いかな、と感じる部分があったのと、いきなりのタトゥーに何か説明がほしかったのがやや引っ掛かったけど作中何度も涙を流してました。
役者さんたちも皆素晴らしかったです。
前半と後半で大きく場面が変わるのも違和感は全く無かったです。ただ被災地の描写はもう少しリアルでも良かったのかも。あんなもんじゃないでしょ、と誰もが思ってしまったのでは?
映画を観ていて思い出したこと…
赤ん坊の頃の私の写真(白黒!)は全部カメラ目線で笑顔。母親に抱っこされててもベビーチェアに座って食事してても座布団に寝転がってても。
大人になってカメラ目線笑顔の理由にハッと気づきました。
赤ちゃんの私はカメラを見ていたのではなく大好きなパパを目で追ってニコニコしてたんだなぁって。
物心つく前だけど当時の写真を見ればあの頃の両親の会話が聴こえてくるようです。
一生懸命カメラを構えて撮ってくれていたであろう亡父母に感謝。
全350件中、101~120件目を表示