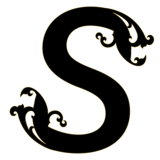日日是好日のレビュー・感想・評価
全311件中、1~20件目を表示
雨の日は雨を聴く。雪の日は雪を見る。夏には夏の暑さを。冬は身の切れるような寒さを。
「先生の所作はどこかに丸みがあった。山の湧き水のように、すーっと体に染み込んでいく。心地よく、頭の中がさっぱりした。」
「リスみたいに軽くてあたたかい。」
「文字を頭で読まないで、絵のように眺めればいいんだ、、。すごい。掛け軸って!」
「今日は暑いから、つくばいの水を少し多めにしましたよ。」
「ある日、かすかな音の違いに気づいた。お湯の音。水の音、、、。」
「雨の日は雨を聴く。五感を使って全身でその瞬間を味わう。雪の日は雪を見て。夏には夏の暑さを。冬は身の切れるような寒さを。 そういうことだったのか。」
お茶の世界の真髄が一瞬みえたような気がした。この世界をぜひ自分も味わいたいと思った。
(掛け軸の面白さも!)
「世の中にはすぐ解るものと、すぐ解らないものの2種類がある。すぐに解らないものは長い時間をかけて少しづつ解ってくる。」
これほんと、年齢を重ねてくるとよくわかるわ。
典子が自分の居場所がないと落ち込んでいるとき、武田先生はいろんなものを使って励ましてくれていた。
・庭の万作の木 「1年のうちに一番寒いときに咲く花もあるのねえ。」
・掛け軸 「今日は節分だし明日は立春でしょ。これから春に向かうのよ。」
・お菓子 「銘は下萌え。冬枯れの地面からこう草が芽吹く様子を表現してるの。」
で、ぽつっと。 「いつ辞めてもいいじゃない。ただ美味しいお茶を飲みにくればいいじゃないの。」
やさしい。。
※ちょっと違和感あったところも。
・亡くなったお父さんを想って浜辺で「ありがとうございます。」と叫ぶところ。
・最後の方の細胞?の描写
樹木希林から黒木華へ日本的美意識の継承
多くの映画ファンにとって心の母、心の祖母であった樹木希林。昭和顔で親しまれ高い演技力が内外で評価される黒木華。この二人が茶道を介して対峙する。なんとも贅沢な企画ではないか。茶道の先生から決まりごとと所作を教わる長い年月の中で主人公が人生の大切なことを学ぶという物語だが、撮影現場での演技のやり取りを通じて、樹木から黒木へ、女優としての矜持、いち人間としてのあり方が伝授されたようにも見えた。それはきっと、茶道の根本にある日本的な美意識とも相通じるものだ。
大森立嗣監督は、過去作と照らして考えると、初めて「美」に真正面から取り組んだように感じた。俳優たちの所作はもちろん、茶の道具、和菓子、和服、庭の自然などをとらえた映像もみずみずしく、ため息が出るほど美しい。大森監督の新境地であり、将来のスケールの大きな傑作につながるステップとしても位置付けられそうだ。
画面一杯を使って、科白なしで表現に昇華させ、作品として成立させられる俳優はそうはいない
真面目で、理屈っぽくて、おっちょこちょい。そんな典子(黒木華)は、いとこの美智子(多部未華子)とともに「タダモノじ ゃない」と噂の武田先生(樹木希林)のもとで“お茶”を習う事になった。細い路地の先にある瓦屋根の一軒家。武田先生は挨 拶も程々に稽古をはじめるが、意味も理由もわからない所作にただ戸惑うふたり。「お茶はまず『形』から。先に『形』を作っ ておいて、後から『心』が入るものなの。」と武田先生は言うが――。青春の機敏、就職の挫折、そして大切な人との別れ。人 生の居場所が見つからない典子だが、毎週お茶に通い続けることで、何かが変わっていった……(Amazon Primeより)。
茶道、華道、書道を伝統芸能の「三道」というが、これ以外にも剣道、柔道、弓道、合気道などの武道も含め、とにかく日本人は「道」が好きなわけだが、いずれの「道」には事細かな「型」がある。型はある意味で不変である。その型通りに事が進まないのは、実存であるわたしや環境、あるいは道具に何かしらの不具合が生じている可能性が高い。逆に言うと、わたしたちは不変な型と対照しないと、生来、変化に気づきにくい気質なのかもしれない。風を感じ、雨の音を聞き、水の滴りの気づくことができるのは、不変であり、常に立ち戻ることができる型があってこそである。武田先生が言う「後から心が入る」ことの本質はそこにあるし、道とは、この型を継承していくための文化的形態である。
それにしても樹木希林の佇まい、所作の美しさは凄まじい。画面一杯を使って、科白なしで表現に昇華させ、作品として成立させられる俳優はそうはいない。黒木華の普通の女性像も良かった。10歳の子にフェデリコ・フェリーニ「道」を、しかもたぶん劇場で、ということはつまり、名画座で見せる親は存在するだろうか、とはちょっと思った。
風変わりな映画
多部未華子かわいい
頭で考えるのではなく、自然と体が動く事が大事なのよ
昨日「1ST KISS」を映画館で一人で観たので、今日はNHK-BSで録画してあった未見の「日日是好日」を家内と二人で一緒に観賞。森下典子の原作エッセイは未読。
茶道教室でお茶に触れる典子の物語はいきなりフェデリコ・フェリーニの「道」から始まる。小さい時に父親に連れて行かれて解らなかった映画として。
20歳の春、大学生だった典子(黒木華)は母親の勧めで武田先生(樹木希林)の茶道教室に通い始める。気が進まなかった典子だが、いとこの美智子(多部未華子)が一緒に行くというので教室通いが始まる。性格等は対照的な典子と美智子だが仲良く教室に通う。
観た事も無い道具や作法(決まり事)だらけのお茶の世界に触れ、戸惑いながらも魅了されて行く典子。
「頭で考えるのではなく、自然と体が動く事が大事なのよ」
お茶を入れる時に流れるように体が動いた時の典子の歓び。教室通いは何年も続く。
茶室の掛け軸。和菓子。庭の花、木々。自然の音。
典子は美智子に言う「小さい時に父親に連れて行かれて解らなかった「道」という映画を最近観たら素晴らしかったのよ」
それは、彼女にとって最初は未知と戸惑いだった「茶の道」が長年通う事によって彼女の中で素晴らしいものとして理解されたのと同様だという暗喩か。
父親(鶴見辰吾)を失った時に彼女は海岸で号泣する。映画「道」でジェルソミーナの死を知ったザンパーノが海岸で慟哭したように。
ラスト、25年経った教室で武田先生と45歳の典子は空を見上げる。桜の花びらが舞い散っていた。(樹木希林さんは、この映画が公開される前の月に亡くなった)
「今日みたいな日に観るのに良い静かな映画だったね」と家内が言った。
メッセージが素晴らしい
タイトルなし(ネタバレ)
悪くない。悪いところはないけど、眠くなる。
原作の本を持ってて読んだときは、なんとなく良かったって感想だったと思う。
この映画は感じることができないととても退屈かもしれない。
主人公の典子や従姉妹の美智子などは実際にやってるけど(しかも長い年月を)、やってる人を見ているだけの視聴者はやっぱ感動が少ない。
じんわり響いてくるような、積み重ねが効いてくる気づきをこちらが受け取るのは、まぁできるけど静か過ぎて難しい。
この映画に参加した役者たちは本の作者の体験には劣るけど感じるものが多かったかも。
見てるだけの視聴者は所詮見てるだけの範囲で感じられるものが少ない。
本では淡々と所作が書かれていてその静かさが合っていたが、映画では眠くなってしまった。
でも茶道の手順を映像で見せてくれるのは映画の良さだと思った。
ゆく河の流れは絶えずして・・・
お茶(茶道)を習い始めた主人公が、人生におこる様々な出来事と茶道をリンクさせながら過ごした日々を淡々と描いた作品。
原作のエッセイは未読だが、かなり原作に寄せて作られた映画ではないだろうか。二十四節気を区切りに短い物語が繋がれていくように、静かに月日が流れていく。エッセイの1章毎に区切られているように思える。
大学生から中年になるまでの主人公典子を黒木華が演じているが、年齢を重ねていく様子をとても上手く演じている。和服が似合う顔立ち。
樹木希林は、どの映画に出ても「樹木希林」でしかない。しかしいつも素のような演技で画になる女優なんだ、やっぱり。存在感が違う。
100分という短い尺なので、主人公が遭遇する人生の悲喜交々の描き方はあっさりしているし、ずっと静かにときが流れていく。正直言って、退屈な映画である。
茶室の掛け軸や、何度も繰り返し挿入される水や川の流れ、玄関の履き物の映像に、禅の言葉が想起される。どれもタイトルの「日日是好日」に相通ずる言葉。
巡る季節の映像は、少しずつ視点を変えて映し出される。
夏の建具(引き戸)のしつらえが、センスがあってよかった。
世界観は好きだけど、映画としては、退屈。映像ももうちょっと工夫ができたのでは?タイトルの意味をわかってください、と言われているような感じが終始漂っておりました。
映画ってこれでいいよね、と心よりそう思う
あまり本作の評判は聞き覚えなかったが、私の母が長年お茶の教室をやっているので今回偶然目に留まり、何気なく鑑賞。
これはピュア、何という良作だ。
自身は茶道のことは全くわからないのに、何気ない日常と四季の繰り返しを通して茶道にぐいぐいと引き込まれていく。
「五感を使って全身でその瞬間を味わう」わかるようなわからなような感覚なのだが、明らかにその世界を垣間観れた気がしてくる。
そして、ストーリー的にはお涙頂戴系作品ではないのに、様々なシーンでなぜか泣けてくる。特にだるまの掛軸のシーンは印象的。「必勝・七転び八起きとも言うけどね」温かい涙が止まらない。
本作は何が凝っているという訳でもないのだが、映画ってこれでいいよね、と心よりそう思える作品だ。心がスッキリと洗われて、映画感が少し変わった気がする。
「季節のように生きる」「毎日が良い日」今後はぜひそういう想いで日々を過ごしていけたらなと思う。
晴れでも雨でも、毎日が好日。
世の中には、すぐわかるものとすぐわからないものの二種類がある
女優 樹木希林さんを懐かしく思い久しぶりに映画「日日是好日」を観ました。茶道が理解出来無くても日本的美意識に心を動かされるのではないでしょうか。出演者が黒木華さんを筆頭に多部未華子さん 鶴田真由さんなど凛としている方々で固められているので何気ない所作の一つでも思わず見入ってしまいます。 この作品は2018年公開ですから6年経ちますが今尚色褪せることがないです。黒木華さんとの共演は樹木希林さんの要望によるもの この作品に対して思い入れが深かったのだと窺い知れます。 『私のあとを継いでくれる、芯のある女優さんだと信じている」 茶室という厳かな雰囲気の中での撮影 演じる事以上に何かを呼び起こしていたのでしょう。黒木華さん・多部未華子さんは最も現代的にかかわらず何処と無く昭和っぽい?そこが大きな魅力でもあります。 常に自然体で役者のあるべき姿を具現化していると評される黒木華さん これからも注目していきたいです。 樹木希林さんは「あん」以降も記憶に残る作品に出演していきます。「モリのいる場所」「万引き家族」 どれも輝きを放っています。これからもScreenの中で永遠に存在し続けるのでしょうね。
ゆっくりとした静かな日常の物語
この作品の起承転結とは永い人生の物語。
同じ場所で同じ仲間が集まっても、同じものなど決してない。
武士道と同じ。「武士道とは死ぬことと覚えたり」
だからこそ、この二度とない今この瞬間を精一杯五感で感じようではないか。
日本のすべての教えのジャンルの中にある考え方であり精神文化であり、奥義。
しかし、いい話を聞いたと思っても、それを実行に移すことができない難しさ。
日常の習慣化された生活や、ルーティーンやタスク管理社会。
忘れてしまうのか、思い出せないのか、とにかく必要な瞬間にそれが出てこないほど、主人公にとって茶道が身に付いていないのだ。
ある日突然割り込んでくる些細な出来事はいつも「次回」に先送られる。
そしておそらく、前触れは必ず起きる。
試されている。私たちは常に「試されている」のだ。
頭の奥で感じる違和感。
気になるが、もうどうしようもない。
そしてそれは的中する。
後悔、慚愧の念。
もう一度出直さなければならない。
主人公のノリコにとって、お茶は人生を考えるためのアイテムだ。
彼女の人生の軸だ。
ノリコはそこまで認識していないが、頭の中がすっきりすることでお茶を続けている。
悩むときにはまたそこに戻ってくることで気分がリフレッシュされるが、さすがに婚約者の浮気と破断から立ち直るには時間がかかった。
しかしやがてまた新しい出会いがあった。
日日是好日
最後にノリコは「毎日がいい日」と心の底からそう思えた。
私はその解釈を「あるがまま」と捉えた。つまり、「何があっても大丈夫」という心構え。
ノリコとの比較でミチコが登場するが、ノリコはミチコと比較してしまうことで自己否定感を覚えるが、人生の長い時間の中でそれは解消されていくのだろう。
物語として、これといった出来事もないまま、この作品は終了するが、最後に24年後となる。
あの犬の茶碗。12年に一度しか使わない茶碗。先生が次回遣うときは100歳。
「次回このお茶碗を使える時、どんな世の中になっているのかしら?」
どうしても思い出さずにはいられない「JIN-仁」の武田鉄矢さんのセリフ「南方先生のいた世界は、太平の世ですか?」
思わずこみ上げるものがある。
そして二度とない今この瞬間を、毎年同じことのように繰り返すことのできる幸せ。
受け継がれていく精神。
少し敷居の高い世界であるかのようなお茶を、入門したての失敗を交えてコミカルに描いている。
茶道は、
ノリコの人生の中心軸。
自分軸。
そこに戻ってくるための手段がお茶。
それがやがて身に付き、どんな出来事があっても「大丈夫」になって行くのだろう。
樹木希林さんの遺作になったことで話題にもなったが、共演者たちは彼女のセリフがそのまま現実化したことに驚愕しただろう。
樹木希林さんとの共演は二度とないだけに、作品への想いも一入だろう。
二度と見ることのない樹木希林さんを偲びながら見させていただいた。
やわらかく優しい良い作品だった。
本筋と違うかもしれないけど
典子の若干ふがいない人生
とってもとっても美しい映画
BSプレミアムにて鑑賞。
お茶の世界を通しながら、四季二十四節気の移り変わりを、登場人物たちの日々の暮らしと重ねつつ味わう、とってもとっても美しい映画。
原作は未読なのだが、プロデューサーや大森監督が心からこの原作に惚れ込んで、大切に脚本を書き、映画化したのだろうということがあふれ出ている。
観ているうちに、映画の向こう側に、原作者の森下典子さんそのものの姿が立ち上がってくる感覚を覚えた。
それにしても、黒木華、多部未華子、樹木希林の表情や立ち居振る舞いを観ているだけで、自然と涙が滲んできてしまったのは、自分でも驚いた。
形の美しさが、こんなにもこちらの心を動かしてくるとは…。
この映画で何よりも大切にされているのは、観客の五感が最大限に働くようにすること。特に音を本当に大切にされているところが素晴らしく、自分も記憶を揺さぶられた。
公開時に、タイミングが合わず鑑賞機会を逃していたので、今日こうして出会えたことにも感謝。
これもまた、大切な一期一会。
<追記>
妻が原作を持っていたので、早速読了。
原作も間違いなく素晴らしかったし、今度は、黒木華と多部未華子と樹木希林と…というように、映画の登場人物たちの声と姿が浮かび上がってきた。
森下さんの文は、すうっと心に入り込んでくる。
原作未読の方は、是非。
全311件中、1~20件目を表示