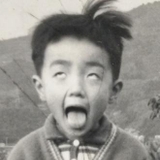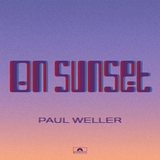ウインド・リバーのレビュー・感想・評価
全290件中、221~240件目を表示
殺人さえも日常
アメリカ的な内容
2人のカップルが殺されたことに対する刑事の復習劇だが、そのために銃撃戦で双方10人以上死ぬと言う効率の悪い展開に、銃社会の恐ろしさを感じた。
ストーリーも終始暗く良い所を見出せなかった。
たしかに西部劇
まさに「見ごたえ」の映画
物語、キャラクター、音楽…すごく好きな映画。
アメリカが歴史的に抱える社会的な闇や、ドラッグや性暴力、銃社会の問題など。
主人公のコリーが最後に言う。
「ここにいる人達には、前に進むか諦めるかしかない」
確かに、よそ者であるFBI捜査官のジェーン
は当初から「運」という言葉をよく使っていた。しかし運の良し悪しなんてものは、生きる上での選択肢が多い人だけに与えられたものである、と。
何もない辺境のこの地で人々が死に物狂いで生きていく姿に、恵まれた我々の尺度で形式的な正義を本当に押し付けていいのだろうか。
ラスト以外にも作品のあちらこちらに「名言」が散りばめられている。
見終わった後、身体も心もズッシリくる。
これが映画体験だ!という見本の様な作品。
西部劇
ワイオミング州ウィンドリバー。人里離れた酷寒の地は、インディアン居留地でもある。そこで起きた若い娘の死亡事件。先住民を追いやったアメリカの歴史を背景に、事件を追う物語。
主人公のハンター、コリー・ランバート(ジェレミー・レナー)は、家畜を荒らすコヨーテ狩りの際に、雪の中に若い娘の遺体を見つける。そこへ派遣されて来たFBI女性捜査官のジェーン・バナー(エリザベス・オルセン)。この地の状況を把握しないまま現地入りし、コリーに協力を仰ぎ、共に捜査をする事に。
しかし、酷寒の僻地は、厳しい自然が生活に困難さを与えるだけでなく、社会から隔離され、人間の精神を容赦なく蝕んでいて、都会の常識が通用しない。この広くて狭い社会で、法や正義をかざしても、誰も振り向かない。
コリーは自らのやり方で捜査を進め、バナー捜査官も戸惑いながらも、そのやり方を徐々に理解していく。その過程で、捜査に協力するコリーの思いが、彼の過去とともに明かされていく。
ジェレミー・レナーの悲哀を抱えた、強い男の渋さが光り、エリザベス・オルセンの現実主義的な捜査官ぶりがうまく絡みあって、よいテンポで物語を先に運ぶ。酷い現実と厳しい自然が、これでもかと人間を痛めつける様はサディスティックだ。それに加えて暴力とドラッグで、人々は互いに痛めつけ合う。それが淡々として描かれていて、物悲しく見える。夏だから良いものの、これを冬の雨の日に見たらメンタルやられそうな勢いだ。
社会問題を背景としているが、単品のサスペンスとしても楽しめる、出来の良い作品だ。
最後まで静かな緊迫感に包まれた
緊迫感
鹿が襲われるのは運が悪いからじゃない、弱いからだ。
とても面白かった
猛暑の夏に心が凍るピッタリな作品!
ピューマの親子
クソ暑いこの季節に映画館は涼めるが本作を大画面で観ると涼しさが増しキンキンな気分に!?
常に緊張感が張り詰めて不穏な音楽に終始ドキドキで先が読めない展開に渋味のある主人公とW・デフォーの「ハンター」をチョット思い出したり!?
J・レナーは渋くて格好良かったがT・ハーディが適役だったと勝手に思ったり犯人がピューマに食われる最後を勝手に想像してみたり。
嫌ぁなレイプシーンがリアルで犯人に対して観ている側も腹が立ち憎しみの感情が生まれ間髪入れず怒涛の銃撃シーンが圧巻で盾になるような身を守る物が無い怖さが伝わる。
不穏な雰囲気の音楽にピリピリと張り詰められた緊迫感に渋い男同士の葛藤など脚本家として本作の監督デビュー作と一貫して手腕を発揮するT・シェリダンには今後も期待するベシ!!
復讐劇なの?
痛みと向き合う事で一緒にいられるのだ
米国闇部を白い雪原で描いたクライム佳作
アメリカ中西部ワイオミング州、冬。
吹雪があり、雪に一面閉ざされたある日、ネイティブアメリカンの保留地ウインド・リバーでひとりの若い女性死体が発見される。
発見したのは、近隣の家畜がコヨーテに食い荒らされていることの通報を受け、駆除に出ていたハンターのコリー(ジェレミー・レナー)。
彼も四年前に娘を亡くしており、情況が似ている・・・
といったところからはじまる物語で、すぐにコリーはネイティブアメリカン女性と結婚しており、亡くした娘は彼女との間にできた子どもだったということがわかる。
映画はその後、FBIから派遣されてきたバナー女性捜査官(エリザベス・オルセン)が加わり、犯人究明に乗り出すが、常に行く先々は雪に覆われている・・・と展開する。
直前に観た『ノクターナル・アニマルズ』の劇中小説の冬版・保留地版という趣が強く、知られざる米国の一面をあぶりだす迫力は相当なもの。
興味深いのは、ネイティブアメリカンの保留地の扱いで、英語では「reservation」、かれらにとって用意された土地という意味で、歴史的なことを反故にしたような押しつけがましい響きがある(つまり「囲い込み」にもかかわらず、という意味である)。
で、その保留地の自治は、彼らネイティブたちにまかせっきりで、殺人事件と明白でないと、全米警察機構のFBIは関与できない。
(BIAという組織に捜査は委譲され、当地のBIAの警察組織は6人しかいない、つまり、解決はほとんどなされない)
発見された女性の死体は、レイプ痕跡はあるものの、犯人からの逃走中に、極寒の中で肺出血を起こし、結果、窒息死したことが判明する・・・
というあたりかなり興味深く、バナー捜査官が本来は捜査権がないコリーを相棒をして捜査を進めていくまで、近年まれにみる雪中行で、撮影のベン・リチャードソンも含め、テイラー・シェリダンの演出は迫力がある。
そして、事件の真相がわかり・・・
というあたり、さて、このタイミングで事件の真相を語るべきだったのかどうか、少し疑問が残る。
捜査する側は、真相については薄々でしかわからないなかでのクライマックス前の真相バラシ・・・
後の、クライマックスの銃撃戦からはショッキングな編集なのだけれど、ここでいいのかしらん、少々説明が長い、と感じました。
ここは、もう少し前段階で、怪しいと感じて合同捜査に出る前あたりが、観る側にはわかりやすく、ハラハラするような語りになったのではありますまいか(って、個人的は『めまい』のネタバレ的位置が最適と思うのだが)。
というのも、この映画では、事件の真相(だれが、どんな目的で、被害者女性に害を及ぼしたか)がカタルシスにつながるわけでもなく、かといって、ここを描かないと米国の闇(最後の字幕説明されるネイティブアメリカンの失踪事件についての説明)に焦点が当たらないので、なんとももどかしいのだけれど。
というわけだが、本作、米国の闇を扱った映画としては、かなり上位に属すると思います。
(安易に、コリーの娘の死に直結しないあたりが、その闇を深く描いていると思いました)
社会問題を投げかける硬派なサスペンス
全290件中、221~240件目を表示