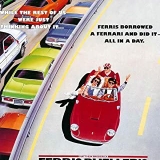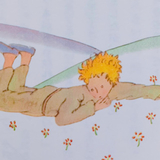チョコレートドーナツのレビュー・感想・評価
全244件中、41~60件目を表示
2 Thumbs up great movie, but very sad
2 thumbs up , very sad movie.
The time has come now for “any day now”.
If he was alive today, he could live with two daddies.
子供は親の人生の延長線上にいるわけじゃない。
無償の愛
舞台延期でこちらを鑑賞
まずは今回のコロナ禍で、予定されていた舞台「チョコレートドーナツ」の12月7~19日の舞台は中止、21日が初演となった。
私は12日のチケットを購入していたので涙をのんだ。「せめて映画を」と、舞台の隣の映画館で原作を鑑賞。
舞台化されるほどだから、人の心を揺さぶるに充分な作品なのだろうとは覚悟の上。
それでもやられてしまった…
マルコの笑顔を思い出すと、まだ悔し涙が…。
40年前ってまだこんなに頑なな差別があったんだ。
今の時代、私の所感としては
最初の裁判官が言ったような
「同性愛が普通と思ってしまう」
なんてセリフは陳腐で
「同性愛も普通」な世の中と感じている。
ゲイカップルが里親になったなんてニュースは最近ではいくつもある。
でもここまで来るのに、長い戦いだったんだろう。自然と法律が改正されはしない。
悪法(とまでは言えなくとも)に涙をのみ、裁判で戦ったり、まわりにうったえたりしたルディやポールのようなや人たちが開拓した現代の生活なのだ。
チョコレートドーナツって甘いタイトルからはもっとホンワカした内容かと思っていたが…、この映画を見てチョコレートドーナツがとっても切ないものに変わってしまった!
ルディ役の俳優ものすごく好きだわ!男も女も一目惚れするね、これは!歌の表現力が凄い。
これを東山紀之が演じるのを見たかったよ。
【ハッピーエンドの話が聞きたい】
この日本語タイトル「チョコレートドーナツ」は、オリジナル・タイトルより、なんか好きだ。
僕も、マルコのように、ハッピーエンドの話が聞きたい。
マルコが求めていたのは、何も世界最高のハッピーではなくて、チョコレートドーナツを食べた時に感じるような幸せであったはずだ。
僕もドーナツが好きだ。
このリバイバルを観た後も、実は、クリスピークリームのプレーンのドーナツを食べた。
おいしい。やっぱり、ハッピーな気になる。
でも、今の世界は、ちょっとやっかいだ。
LGBTQに対する理解が進み、窮屈にカテゴリー化するのを見直して、呼び方をSOGI(=セクシャル・オリエンテーション&ジェンダー・アイデンティティ)に替えるような動きがある一方、ダウン症の人が映画作品に出たりすると、感動ポルノだといって批判を浴びたりもする。
そして、批判の先鋒に立つ人に限って、実は差別を助長するようなことを言う人だったりする。
なかなかコミュニケーションが簡単ではないダウン症のはずなのに、この作品のマルコは、心の動きがとても豊かだ。
演技だといえば、それまでだが、よく考えてみたら、ダウン症の人だって、みんなの心に訴える演技が出来るし、実は、みんな同じなのではないのかと思う。
そして、世界でもうひとつやっかいなのは、ゲイが親になろうとするストーリーに出会うと、ゲイにも母性本能とかいう上から目線の括り方をする人が結構いることだ。
人が、大人になって、子供の成長を育み、助け、そして、見守りたいと考えるのは、ジェンダレスな親でありたいという気持ちや行為のはずだ。
母性や父性という考え方も実は過去のものにしなくてはならない時が来ているのだ。
少し手間でも、ニュアンスがどうだとか、こうだとか言い訳をする前に、僕達は考え続けなくてはならない。
実話をベースにした物語だ。
このカップルは、ずっと、自分達のこと、マルコのこと、そして、社会のこと、社会システムのことを考え続けるだろう。
悪法も法だと言った古代ギリシャの哲学者もいた、
でも、もうソクラテスの時代ではない。
選択的夫婦別姓すらまともに議論できない、この国の暗い部分には辟易とするが、ずっと声をあげ続けることに意味はあるはずだ。
僕達だって、常に頭の隅に置いて、気をつけるぐらいは出来るだろう。
ハッピーエンドの話が聞きたい。
ささやかなセリフだが、これほど、優しくて温かい、そして、自分もこの話聞いてみたい、そんな気にさせてくれた映画は、かつてなかった気がする。
ゲイだとか障碍者だとか、そんな括りには当てはまらない普遍的なテーマだと思う。
そして、きっと色褪せず長く愛される作品だと思う。
この作品が世界の人々の心を揺さぶる。
世の中は、まだ、捨てたもんじゃない。
そんな気がする。
泣けた!
「人は最終的には血筋を優先するのだろう…」
と(記憶は定かではないけど)
誰かがコメントしてるのを見た事ある
確かにそうなるだろう
と、しみじみ思った
血が繋がってるのが本当の親子だ!と。
子供の前で薬物をしてても
育児放棄してても
虐待してても
目の前で苦しんでても
他にも(これ以上言えない事も)……
しかし人は血の繋がってない人と
人生を誓う
沢山の人の前で
手間暇かけて
金かけて着飾って
涙を流しながら
唇を潤わせて
瞳を輝かせて
約束する
貴方しかいない
と。
不思議だ
っつか、
面白い
わかってても
幾万年も くり返してる
そして言う
「気持ち悪い」
「あり得ない」
「本物じゃない」
そうやって区別して
共感し合う人達と
差別し群がり
優越感を感じる
………
マルコは
三日三晩
自分の帰る場所を探して
橋の下で息を途絶えて亡くなる
きっと
彼の
シンプルで優しい彼の
行くつく場所は
自分を受け入れてくれる
「居場所」。
たとえそこが
ゲイの人だろうが
異人種だろうが
異国籍だろうが
異文化だろうが
関係なく
ハッピーエンドを求めてて
マルコはマルコなりに
探して
彷徨ってたんだよな?
な?マルコ。
違うかい?
三日三晩
飲まず食わずで
苦しくなかったかい?
辛くなかったかい?
っつか、オイっ、マルコ
平和ボケした俺より
感受性あって
お前スゲ〜じゃん!
普通にそんな事しきらんしよ?
お前
最強っ!!
でも
マルコは本当に安らげる
居場所求めて
彷徨ってるって
おそれおおくて
参りましたm(_ _)m
最後の歌うシーン
本当に泣けたよ
自分の汚れさ
と
気づきに。
世間は何も分かっちゃいない
映画好きの友人から強くオススメされたので鑑賞。
前情報は全くなしです。
こりゃ、ホントにいい映画だな...。
笑えて、嬉しくなり、辛く、胸が痛む。
主人公と同じ感情をいつの間にか抱いている
同性愛に強い偏見と差別があったアメリカ1970年代。ゲイバーでダンスを披露している主人公のルディは、とある日毎日大きな音を鳴らす隣の部屋で捨てられた子供を見つける。
3人の演技が素晴らしい
特に実際にダウン症を患っているマルコの演技がとてつもなく染みる。染みる。染みるんだよ...。(涙)
マルコはもちろんのことだが、同性愛の2人が成長する様も非情に上手く描けている。
マルコは2人によって、ルディはマルコとポールによって、ポールはルディとマルコによって。お互いに支え合って共に成長し生きていく。
音楽とテンポが非常にいい。
ルディの歌声がホントに綺麗。心を掴まれる。
短いながらにして、内容は濃ゆいし、テンポも良いので見応えバッチグー。映画館で見たかったなぁ...
ぼそっと呟く言葉も胸に響く。
最近になり「差別」がようやく問題視されるようになったが、50年近く前はここまで酷かったのかと改めて感じさせられる。この世界に住む全ての人にこの映画を見て欲しいくらい、刺さりますよ。
欠点としては、1年間の思い出がサラッとしすぎていたかな。ハロウィンもクリスマスもビデオ越しではなく、実際の様子が見たかった。
あと、ラストもサラッとし過ぎていたんじゃないかなと。しっかりと落としてくれないとね。
法律が正しい?
家族が正しい?
同性愛や障害者が間違っている?
なんて理不尽な世の中なんだ。
世間は何も分かっちゃいない。同性愛者にも男女カップルと同じような愛を持っているんだから。
私は障害者という言葉が嫌いだ。
それと同時に24時間テレビが嫌いだ。
障害者は特別ではない。特別扱いをすることそのものが間違っている。それこそ差別なのだ
最高の映画でした。
これからオススメの海外映画はと聞かれたら迷わずこの映画を挙げることにします。
絶対に見るべき1作
薬物依存の母親から育児放棄された、
ダウン症の少年マルコ。
ゲイカップルであるルディとポールは、彼を引き取り、愛情をもって育てようとするが、世間はそれを許そうとしなかった…
まだ偏見の根強い1970年代のアメリカで実際に起きた話をベースにしてます。
・・・
「まとも」とは?と考えさせられる作品。
世間体、法律、権力…
「マルコの将来」という本質はないがしろにして、
型通りの正義を振りかざし、彼らを引き裂く大人たち。
でも、当時のアメリカ社会では、
多分これが「常識的な」結論だったのかとも思います。
社会的弱者の彼らがいくら声をあげようと届くことはない。
でも常識は、時代とともに変わります。
実際LGBTが受け入れられるような世の中になってきて、この作品の時代とはだいぶ異なってきてます。
必要なのは、法改正や制度と同時に、
個人の中にある偏見を取り除くことかと思います。
そういった意味でも、この作品は個人の視界を広めることのできるものだと思います。
あと、ラストのルディのショーのシーンは圧巻でした。
やるせなさ、悔しさ、無力さ。
力強いまっすぐな歌声に心打たれました。
こっちを先に見るべきだった、本家物
ゲイカップルが、隣人の子の面倒を見る話というのは
先日見てとても面白く感じた「彼らが本気で編むときは」の本筋と似ている。
「彼らが〜」の感想レビューの中にこの映画の事を言う人が多く見られたので、探して視聴。
だからと言って「彼ら〜」も全く遜色なく、視点は全く違うというのも見ればわかるが。
こちらは、同性愛者に対する徹底した差別が悲劇を産んだという一点のみのストーリー軸を
役者陣の圧倒的な演技で見せるもの。
Amazonプライムにて視聴したが
見始めたたのは一週間前。
三分の一程度を見て 残りを昨晩視聴し終えた。
この間に、先月から寝たきりで今月に入ってほとんど意識を失っていた夫の死と通夜と告別式を挟んだ。
寝たきりの夫を残して家をあけることができなかった数ヶ月、
配信される映画をうちで視聴する事がほとんどだった。
そしてこのサイトで感想を語り合う事で世の中と繋がっていたような気がする。
本来 こうやって見るべきものではない映画だったが
気持ちの中ではこれはこれで
私の中の軸を保つのに うってつけであったと言える。
人のためのレビューでなく
自分の忘備録として付け加えておく事にした。
We Shall be Released!!
勇気をもらえる映画だった。何か社会の理不尽/基本的人権が尊重されていないところを変えていこうとしたら、この二人のような努力がいる。極端に言ったらキング牧師やボビー ケネディーのように暗殺されてしまう。この映画でこの努力には特に大きな悲しみ(マルコのこと)があったが、ルーディー{Alan Cumming }が『 ふたりはいやされるだろう』と歌ってこの映画を締め括っている。二人が癒されるのには時がかかるが、これは人生において、この場合、この体験がルーディーとポールの絆、二人の生き方などにおいて貴重になっている。それがまた、社会に及ぼす影響力となると思う。
人権問題が希薄化している日本にもきっと、このように戦っている人がいると思う。でも、特に、政府や社会が『自己責任』を重視してくるとこの映画のような話題は困難化するだろうけど。
それに、この映画は当時、主に、米国のLGBTQ+の映画祭で賞を獲得している。公民権運動と同様、基本的人権を守るためのものなので、もっと、一般人に受け入れられる サンダンス映画祭(?)、トロント映画祭(TIFF)などや、米国のアカデミー賞のようなところで、ノミネートされる映画であって欲しかった。
この映画は1970年代の物語(事実も入っていると)らしいが、ニューヨーク州で、2003年に州法でLGBTQ+の雇用契約破棄などは禁止されたり、学校教育での差別の禁止されたり、結婚も可能になっている。私の職場でも、結婚している人たちや、子供を養子縁組している人たちは数えられないほどいる。でも、これらが認められていない州の方が多い。このところが大きいと思う。
最近のLGBTQ+の映画にはこの当たり前の権利(私見)が認められているかいないかより、二人の愛の葛藤について描いている映画が多いと思う。
この映画の良さは、基本的人権が認められていなかったニューヨーク州の問題を私たちに教訓にしている。それも、何十年もかかって、この法案が通ったわけだし。米国でまだまだ認められていない州が多いから、このような映画が繰り返し製作上映されることにより人々に『意識化』『気づき』が生まれ、結局は人間一人一人は同等の権利があり、大切なんだよと社会に認めさせることになる。
マルコの児童放棄や、母親がシングルマザーで障がい児を育てること、社会での職業の貴賎、LGTBQ+にたいする偏見などなど、たくさんのみなさんがここに感動したコメントを書いている。これが見せかけでなく社会を変えていく原動力になっていく。
私はこの映画で弁護士の職を解雇されたポールの目から、主に、この物語を観察していた。なぜかというと、現状で誰が私の個人の生活に近いかというと 三人の中でポールだと思う。彼はなぜ離婚をしてワシントン州のワラワラから、ロスに引っ越してきたかの理由を『世界を変えるため』と言った。そして、弁護士として働き始めて、『??社会正義のための良い戦いをしている???』とは思えないかと濁しているが否定してる。弁護士という勝負の世界で社会正義のための戦いをするには程遠いんだなと私は感じた。そして、ベッドでルーディーのことを『素晴らしい』というシーンがあるが、私はこの意味がよくわかる。自由奔放に生きて、怖いもの知らずに行動や言動できるが、それが、正義と善意と完全に結びつき自然な姿だからなのだ。その時、音楽が聞こえてくるそれが、『もしあなたが信じるように私も信じられれば。。。』この曲がポールの心情をよく表している。泣けるね。ポールは自分の思ったような人生を歩んでなかったんだよ。仕事を失った時、ルーディーが『自分に戻る時』だと言った。そして、ドアを蹴って叩き壊して世界を変えるために何かしろと。その時、ポールは初心にかえった。私もこの人生においてふと我に返ることがある。今まで何してきたのと。シングルマザーなって生活は人前にできるけど、え?と気づいた時があった。
ここからのポールは強くなっている。特に、公民権運動の弁護士と敗訴した法廷結果を話している時、この弁護士が、『あなたも、弁護士なら、弱いものや社会正義のために戦って裁判で負けてしまうことを知ってるだろう。それでも、挫けずに立ち上がるんだというようなこというシーンがある。この弁護士の言葉は彼に力を与えた。私も力をもらった。同じ弁護士が社会正義のため戦っている!ここから、もうポールは引きさがらなく、正義に向かってまっしぐら。自分を隠さず生きることが脆弱な人々を助けることにつながるから。その時、助けられなくても社会を変える一歩になっていくから。
ルーディーはステージで、ポールを見て、『私の愛する人よ、約束できるよ。私たちは癒される』ということを。『I 』じゃなくて
『We 』shall be released. でうったえて、締め括っている。
I Shall be Released.
https://www.youtube.com/watch?v=JUpOT4060AE アラン カミング
https://www.youtube.com/watch?v=E0pkHBVznLA ボブ ディラン
マルコのお父さんはどこに。
この終わり方でよかった、見た人にこの偏見と差別をドンと伝えてくれたと思います。
論点がズレますが
マルコのお母さんは、爆音で麻薬をし、釈放された後も男を連れ込んでマルコを放置。
たしかにひどいが、シングルマザーで子供を一人で育てることも大変なのに、さらに障害を持ってる子だという。
このお母さんを100%責めることも出来ない。
このお母さんにも支援は必要だった。
このお母さんがもっと幸せに、心に余裕があれば麻薬なんてやらなかったかもしれない、分からないです。
ゲイの差別もひどいし、シングルマザー、シングルファザー
子どもを育てるということはこんなに大変なんだ
そして、どんな影響があり、慎重にならなきゃならないことなのか
っていう命の重さを改めて感じるべきです。
この映画は、一見マルコのお母さんが悪者に見えるし
たしかに良くないけど
そもそもシングルマザーって時点でいろんな苦労があって
普通に頑張ってるシングルの親は、どれだけ頑張っている超人なのかというのをみんなに理解してもらえたらいいと思う。
邪魔な偏見。
同性愛に悩むパフォーマーと弁護士の二人と、母親が麻薬依存者でネグレクトされている子供の間に家族としての愛が芽生えるが、世間や常識がそれを許してくれない物語。
時代は1970年代のアメリカともあり偏見や差別が露骨に溢れている。裁判で「同性愛者は異常だ」と平気で発言し、特段問題ないような感じで裁判が続いている。
とはいえ現代でも性差別は無くなっていないし、なんなら自分だって気付いていないだけで差別をしているかもしれない。何十年後かに「こんな差別があったんだ」と思うような時代を生きているのかもしれない。
それでもその時の常識に囚われず、本当に大切なことを見極めなければいけない。難しいけど。
マルコの望んだハッピーエンドを目指して。
チョコレートドーナツを頬張るマルコの満面の笑み
ゲイのカップルがダウン症の子供を育てるという話。
可哀想だなぁなんてつい思ってしまいがちですが、普通と何も変わらない愛の物語です。
そもそも普通って?何?
ゲイのカップルなのに、まるで男女の恋愛を見ているかのようで、むしろ男女の恋愛以上に2人の強い愛を感じました。
そしてマルコの可愛いこと。
ダウン症の子ってなんか可愛いですよね。
アラン・カミングさんやギャレット・ディラハントさんの演技も素晴らしかったですが、マルコ役のアイザック・レイヴァさんも新人とは思えぬ演技力。
彼の他の作品も観てみたいと思いました。
普段、健常者として、性的マジョリティとして、生きている身としてはなかなか知れない彼らの悩みや苦しみを分かりやすく勉強することもできました。
ゲイだというだけで世間から冷たい視線を送られ、裁判でも不条理な証拠を作られてしまう。
ハロウィンは仮装だろ。
そもそも女装しようが、ゲイバーに行こうが何が悪い。
近年はようやくLGBTの考え方が浸透してきましたが、冒頭にも書いたように、最初は誰でも自分や周りと違う人を分けて考えてしまうと思います。
こういう映画がたくさん作られて(勿論、本人たちとの交流が1番ですが)、お互いをよく理解できるような社会になるといいんですが…
ラストは衝撃的でした。
マルコの好きなハッピーエンド。
現実が優しい世界になりますように。
家族の形は…
魔法が使える少年の話の続きは語られない。
全244件中、41~60件目を表示