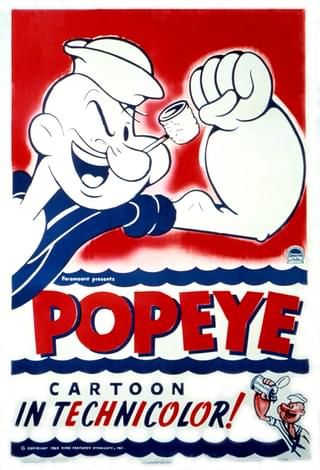マラヴィータ : 映画評論・批評
2013年11月12日更新
2013年11月15日よりTOHOシネマズ有楽座ほかにてロードショー
文化の違いに悩んだベッソンがフランスに逆輸入してみせたマフィア映画

夫が組織を裏切ったせいで古巣のニューヨーク・ブルックリンを追われて以降、フランス各地を転々としてきたストレスが、ミシェル・ファイファー演じる妻の瞼を余計に凹ませている。しかも、最後に流れ着いた先はフランスの突端、ノルマンディーの田舎町。地元のスーパーでピーナッツバターの所在を尋ねた彼女に対し、どうせフランス語は解さないだろうと踏んだ店主が「だからアメリカ人は肥るんだよ」とホザいた瞬間、妻の忍耐は限界に達し、直後に店を爆破。いくらマフィアの女房でも、ちょっとやり過ぎじゃないか?
いや、リュック・ベッソンならあり得る。イザベル・アジャーニを通じてウォーレン・ベイティが「グラン・ブルー」(1988)の製作に介在した際に、言語とシステムの壁に阻まれて主導権を横取りされそうになって以来、カルチャーギャップはベッソンにとって拭いきれないトラウマだったはず。久々の監督作では、すっかり得意分野になったバイオレンスシーンはいつものように快調なのに、それに対抗すべきユーモアが若干シュール過ぎて歪(いびつ)なのはそのためだ。
しかし、芸術ぶって弾け切れない母国映画に見切りを付け、愛憎相半ばするハリウッドでビジネスのノウハウを習得したベッソンの根回し力は、この「マラヴィータ」でも証明された。何しろ、1970年代以降のアメリカ映画を代表する名コンビ、マーティン・スコセッシ(製作総指揮)とロバート・デ・ニーロ(主演)を巧みに担ぎ出し、フランスに逆輸入してみせたのだから。代表作「グッドフェローズ」(1990)までフィーチャーすると聞いて、ここ数年、スター主導の大作に付き合わされてヘトヘトのスコセッシにとっては絶好の箸休めになったんじゃなかろうか。そんな画面の裏側が透けて見える、希代のネゴシエーター、リュック・ベッソンが面目躍如の最新作である。
(清藤秀人)