鬼畜
劇場公開日:1978年10月7日
解説
父を思い続ける息子と、環境に押し流されて正気を失う弱い父親、大人と子供の世界を較べながら、切っても切れない親子の絆を描く。松本清張の、昭和32年に事実をもとに書き下ろした原作の映画化。脚本は「ダイナマイトどんどん」の井手雅人、監督は「事件」の野村芳太郎、撮影は「事件」の川又昂がそれぞれ担当。
1978年製作/110分/日本
原題または英題:The Demon
配給:松竹
劇場公開日:1978年10月7日
あらすじ
竹下宗吉と妻、お梅は川越市で印刷屋を開いていた。宗吉は小金が貯ったところで、鳥料理屋の菊代を囲い七年間に三人の隠し子を作った。おりあしく、火事と大印刷店攻勢で商売は凋落した。手当を貰えなくなった菊代は、利一(六歳)良子(四歳〉庄二(一歳半)を連れて宗吉の家に怒鳴り込んだ。菊代はお梅と口論した挙句、三人を宗吉に押しつけて蒸発した。お梅は子供達と宗吉に当り散らし、地獄の日々が始まった。そして、末の庄二が栄養失調で衰弱した。ある日、寝ている庄二の顔の上にシートが故意か偶然か、被さって死んだ。シートのあった位置からお梅の仕業と思い乍ら宗吉は口に出せない。「あんたも一つ気が楽になったね」お梅の言葉にゾーッとする宗吉だが、心中、ひそかな安らぎをも覚えるのだ。その夜、二人は久しぶりに燃え、共通の罪悪感に余計、昂ぶった。その後、宗吉は良子を東京タワーへ連れて行き、置き去りにして逃げ帰った。長男の利一には「よそで預かって貰った」といい訳した。お梅は利一を一番嫌っている。兄弟思いで利口な利一の白目がちな目が、お梅夫婦のたくらみを見抜いているようだ。何日か後、宗吉は、こだま号によろこぶ利一をのせ、北陸海岸に連れて行った。断崖上の草原で蝶採りに遊び疲れ眠りこけた利一を宗吉は崖下に放り出した。翌朝、沖の船が絶壁の途中に引掛っている利一を発見、かすり傷程度で助けだした。警察の調べに利一は父親と遊びにきて、眠っているうちに落ちたと云い張った。名前、住所、親のことや身許の手がかりになることは一切いわなかった。しかし警察は利一の服のメーカーのマークが全部切りとられていたことから、事故ではなく、利一は突き落とした誰かをかばっていると判断した。利一の黙秘に警察はお手上げになった時、偶然、入ってきた名刺屋が、利一の持っていた小石に注目した。利一が“いしけりの石”と話すそれは、石版用の石で、インキをこすれば、消えた版が再現できるかもしれない。警察の捜査が開始された。移送されてきた宗吉が警察で親子の対面をした。「坊やのお父さんだね?」警官の問いに利一が激しく拒否した。「よその人だよ、知らないよ、父ちゃんじゃないよッ」手錠がかかった手を合掌するように上げて、涙を流して絶叫する宗吉の声が部屋いっぱいに響いた。「利一ッ……かんべんしてくれ!」








 秋刀魚の味 ニューデジタルリマスター
秋刀魚の味 ニューデジタルリマスター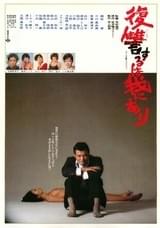 復讐するは我にあり
復讐するは我にあり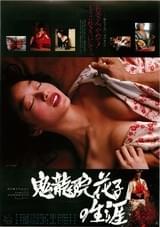 鬼龍院花子の生涯
鬼龍院花子の生涯 楢山節考
楢山節考 切腹
切腹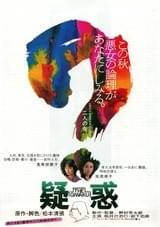 疑惑
疑惑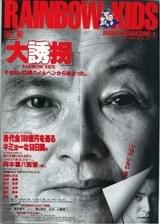 大誘拐 RAINBOW KIDS
大誘拐 RAINBOW KIDS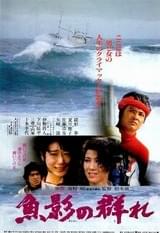 魚影の群れ
魚影の群れ 極道の妻たち
極道の妻たち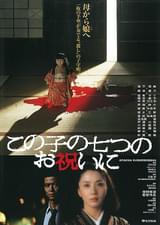 この子の七つのお祝いに
この子の七つのお祝いに








