アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督による2006年の映画「バベル」は、21世紀の映画史において「アンサンブル・ナラティブ」という手法を極限まで突き詰め、その形式を一神教的な運命論へと昇華させようとした野心作である。本作は、旧約聖書の「バベルの塔」の寓話を現代のグローバル社会に置き換え、言語や国境を越えた意思疎通の不可能性と、それゆえに生じる悲劇を描き出している。第79回アカデミー賞では作品賞、監督賞を含む7部門にノミネートされ、グスターボ・サンタオラヤが作曲賞を受賞。カンヌ国際映画祭でも監督賞を受賞するなど、当時の映画界に強烈なインパクトを与えた。
作品の完成度という観点において、本作は極めて高い技術水準にある。イニャリトゥと脚本家のギジェルモ・アリアガが「アモーレス・ペロス」「21グラム」を経て完成させた三部作の集大成であり、モロッコ、メキシコ、日本、アメリカという四つの舞台が、一発の銃弾という物理的現象を通じて有機的に、かつ残酷に結びついていく。この構造は単なるパズル的な面白さを狙ったものではなく、現代社会が抱える「繋がっているようでいて、決定的に断絶している」という矛盾を浮き彫りにするための形式である。全編を貫く緊張感、そして観客の感情を執拗に揺さぶる演出は、過剰とも言えるエネルギーに満ちており、映像体験としての強度は類を見ない。
キャスティングと演技においても、本作は世界各国の実力派と新人を巧みに配し、リアリティを追求している。
ブラッド・ピット(リチャード・ジョーンズ役)
本作におけるピットの演技は、彼が単なるスターではなく、実力派俳優であることを改めて世界に示した。モロッコを旅行中に妻が銃撃されるという不条理な極限状況に置かれた夫を演じ、無力感と焦燥、そして他者への不信感が混ざり合った複雑な心理状態を、その疲弊しきった表情一つで語っている。特に、劣悪な環境のなかで必死に本国へ救助を求める電話をかけるシーンでは、洗練された都会人が、文明の恩恵を受けられない場所で剥き出しの人間性を露わにする様を、説得力を持って体現した。彼の存在が物語の重力となり、観客をこの不条理な世界へと引き込む大きな要因となっている。
ケイト・ブランシェット(スーザン・ジョーンズ役)
リチャードの妻として、物語の悲劇の起点となる重要な役どころを担う。彼女は映画の大部分を負傷し、生死の境を彷徨う状態で過ごすことになるが、その限定された状況下での苦痛の表現、死を間近にした恐怖の演技は圧巻である。わずかなセリフと視線の動きだけで、夫との間にある冷え切った関係性が、死の淵で変容していく様を静かに、しかし力強く表現した。
ガエル・ガルシア・ベルナル(サンティアゴ役)
メキシコ編の中心人物として、物語に危ういエネルギーを注入している。リチャードたちの子供を預かる乳母の甥を演じ、国境を越える際の無謀さと、その結果として引き起こされる混乱を象徴する。彼の持つ若さと制御不能な熱情が、作品全体が孕む「予測不能な連鎖」にリアルな動悸を与えている。
菊地凛子(綿谷千恵子役)
聴覚障害を持つ女子高生という難役を演じ、本作で最も鮮烈な印象を残した。言葉を介さないコミュニケーションの葛藤、母を失った深い孤独を、身体を張った剥き出しの演技で表現している。劇中で描かれる彼女の過激な性的衝動は、他者との接触を渇望する魂の悲鳴として描かれているが、一方でその直接的な描写は、映画全体の「世界的暴力の連鎖」というテーマに歩調を合わせるための記号的な演出という側面が強い。アカデミー助演女優賞ノミネートという快挙を成し遂げた名演ではあるが、その過剰な身体表現は、日常的なリアリズムの範疇を超えた映画的装置としての役割を強く帯びており、表現としての妥当性には大きな疑問が残る。
役所広司(綿谷安二郎役)
クレジットの最後に名を連ねる重要人物として、千恵子の父であり、物語のすべての発端となる猟銃の持ち主を演じている。娘との深い断絶に悩みながらも、静かに寄り添おうとする父親の姿を、日本を代表する名優らしい重厚感と繊細さで演じきった。彼の静謐な演技が、激動する他国の物語との鮮やかな対比となり、作品に深い余韻と日本的な叙情をもたらしている。
脚本とストーリー構成については、時間軸を巧妙に操作しながらも、観客が迷うことのない骨組みを持っている。映像・美術・衣装は、それぞれの国の質感を極限まで引き出しており、モロッコの土埃、メキシコの原色、東京のネオンと無機質な空間が、視覚的なコントラストとして機能している。音楽はグスターボ・サンタオラヤが担当。主題歌はないものの、全編を貫く「Babel」や「Deportation」といった楽曲は、民族楽器ウードやギターを用いたミニマリズム的なアプローチでありながら、言葉にできない悲しみと祈りを体現している。
結論として「バベル」は、21世紀初頭のグローバリズムが生んだ歪みを、映画という言語で記述しようとした野心的な問題作である。しかし、世界規模の暴力という壮大なテーマを追求するあまり、個のリアリティ、特に日本編における少女の内面描写が「衝撃的な映像」という安易な手段に依存しすぎた点は批判を免れない。孤独の表現として性的衝動を直接的に描く手法は、狙いこそ明確だが、結果として表現の繊細さを欠き、日本というコンテクストにおけるリアリズムを損なう結果となっている。本作はパズルとしての完成度は高いが、そのピースを繋ぐために個人の心理的真実を犠牲にした、極めて歪な構造を持つ一作と言わざるを得ない。
作品[BABEL]
主演
評価対象: ブラッド・ピット
適用評価点: B8(8点) × 3 = 24点
助演
評価対象: ケイト・ブランシェット、ガエル・ガルシア・ベルナル、菊地凛子、役所広司
適用評価点: : B8(8点) × 1 = 8.点
脚本・ストーリー
評価対象: ギジェルモ・アリアガ
適用評価点: B6(6点) × 7 = 42点
撮影・映像
評価対象: ロドリゴ・プリエト
適用評価点: S10(10点) × 1 = 10点
美術・衣装
評価対象: ブリジット・ブロシュ
適用評価点: A9(9点) × 1 = 9点
音楽
評価対象: グスターボ・サンタオラヤ
適用評価点: S10(10点) × 1 = 10点
編集(加点減点)
評価対象: スティーヴン・ミリオン、ダグラス・クライズ
適用評価点: +1点
監督(最終評価)
評価対象: アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ
総合スコア:[74.4]













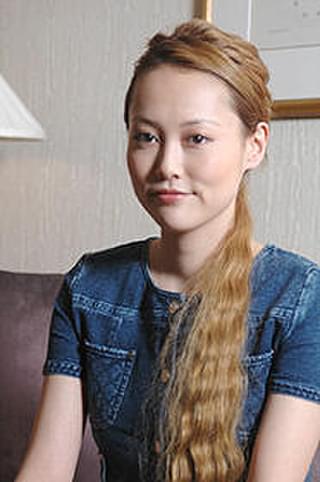
 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド オーシャンズ8
オーシャンズ8 ブレット・トレイン
ブレット・トレイン アド・アストラ
アド・アストラ セブン
セブン バビロン
バビロン キャロル
キャロル TAR/ター
TAR/ター ファイト・クラブ
ファイト・クラブ オーシャンズ11
オーシャンズ11

















