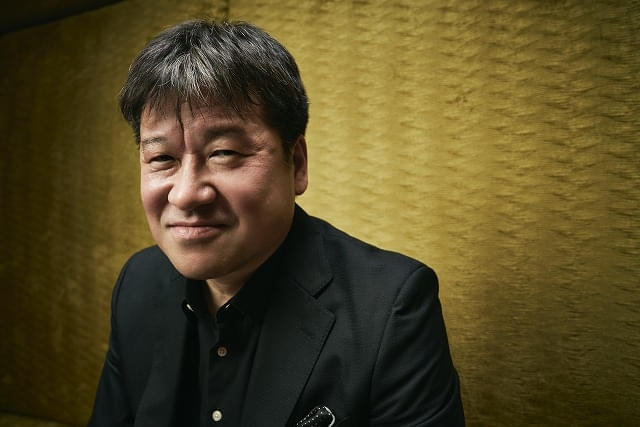スズキタゴサクと対峙し、彼の言葉を読み解き、事件の解決を目指すモジャモジャ頭のキレ者の刑事・類家を演じる山田裕貴 と、“怪演”という言葉がふさわしい圧巻の演技でスズキタゴサクを体現している佐藤二朗 が本作への思いを語った。(取材・文/黒豆直樹、撮影/江藤海彦)
――原作小説および脚本を読まれての印象を教えてください。
山田:まず、原作が本当に面白すぎて、これを映画にするのかと……。「これ、(映画にするなら)前後編ですよね?」と聞いた覚えがあります。類家という役柄に関して、僕自身のパブリックイメージとは全然違うと思いますが、実はマインドがめちゃくちゃ類家に似ていると思いました。それは、あんなに頭が良いということじゃなくて、僕はスズキタゴサクみたいな悪意を持った者が、なぜそうなってしまったのか?という気持ちがすごくよくわかる人間なんです。類家が世界や人間に対して悲観しているところを僕自身、人生の中で体感してきたところがあって、類家の気持ちでわからない部分がなかったんです。
岡田(翔太)プロデューサーとは「東京リベンジャーズ 」で一緒でしたけど「本当の山田くんはこっちだよね?」と言って提案してくれたのがこのお話だったので、「よく見抜いたな……」と思いました。類家は真心を持ったヒーローになりたかったけど、世界を見渡すといつでもどこでも人が死んでいて、それを全て助けることができない――だから、助けられる命は全力で助ける。でも人が死んでしまうというのは当たり前に起こっていることだから、とりあえず目の前のこの事件を解決して、腹いっぱい飯を食うっていうだけ。それが一番のキレイ事だと思っているという感覚です。
佐藤:僕は「
幼獣マメシバ 」シリーズを一緒にやった
永森裕二 というプロデューサーと飯を食って、いろんな話をしていた時に「いや二朗さん、ちょっとすごい小説があるよ。『
爆弾 』っていうんだけどね。このスズキタゴサクというのは、二朗さんがやると良いと思うんだよね」みたいなことを言われたんです。
山田:俺も思っていました。「タゴサクは
佐藤二朗 さんにやってほしい」って。
佐藤:その後に、このオファーが来たんです。読んでみたら、(タゴサクの設定が)小太りの中年で、どこにでもいそうな風貌で、もうその時点で僕はハードルをクリアしているんですよね(笑)。しかも「中日ドラゴンズファン」という。さらに、物語の舞台となっているのが野方警察署ですけど、僕は東京に出てきて初めて住んだのが野方なんですよ。読みながら「怖っ!」と思っていたら、オファーが来たので、もう「ようこそ」という気持ちでした(笑)。実際に読んでみたら、いやもう圧倒的ですよね。もう圧巻の面白さで、あんまり難しいことは言えないですけど、単純に面白さに圧倒されました。
(C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会 (C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会 ――撮影はほぼ取調室のセットで、ストーリーの流れと同じ順番で、
染谷将太 さん演じる所轄の刑事・等々力、
渡部篤郎 さん演じる警視庁捜査一課の刑事・清宮、そして山田さんが演じる類家と対峙されていったそうですね?
佐藤:ちょうど裕貴とも撮影中にそういう話をしたんですけど、俳優って、もちろん直感も大事だし、その場での反射神経も超大事だし、監督によっては「俳優は何も考えなくていい」という方もいますけど、この作品に関しては、知恵熱が出るぐらい考えないといけないなと思って臨みました。
染谷将太 、
渡部篤郎 、そして最後に
山田裕貴 が僕の前に来るわけですけど、この素晴らしい俳優たちが目の前に入れ替わり、立ち代わり来るって、そりゃ夢のように楽しかったです。いろいろと考えなくちゃいけないところもあるけど、そこはいったん全部忘れて対峙して……。
(シーンが)終わった後に裕貴に「いま、裕貴がこうしたから、俺もこうしたんだよ」みたいな話もよくしましたし、そういうセッションを山田裕貴 、染谷将太 、渡部篤郎 の全員とできて、もう毎日家に帰ったら妻に「おもしろいわ」「楽しいわ」って言ってましたね。
――類家とタゴサク、どちらもキャラクターが立っていて、一歩間違えれば漫画っぽくなってしまうところを、おふたりとも絶妙のラインでリアリティをもって演じられていました。小説という文字で書かれたキャラクターを映画として見せるためにどのようなことを大切にされたんでしょうか?
山田:「自分が類家だったらこういう話し方をするだろうな」という感覚でやっていましたね。撮影中に二朗さんがおっしゃったことが、僕の中で響いていて、一時期、波風立たせずにポロポロってセリフをしゃべるお芝居が流行った時期があったじゃないですか?
佐藤:“ナチュラル”なお芝居ね。
山田:二朗さんが「ナチュラルっていう言葉はあまり好きじゃない」とおっしゃっていて、「表現にする」ということをしっかりやらなきゃいけないと。僕自身は、すごくナチュラルというのを意識しようとしているんですが、(類家とタゴサクが)対峙している中で、心の中で「あ、いまこうやって動きたくなったかも……」と思ったところでポンッて跳ねさせるというイメージなんです。要はセッションで、ギターを弾いていたとして「いや、ちょっとアドリブでこの音を鳴らしたくなった」みたいな瞬間が訪れるんですよ、対峙していると。
佐藤:ちなみにいま裕貴が言った「アドリブ」というのは、決して台本にないセリフを言うってことじゃなくて、決められたセリフの中でということです。
山田:例えば原作には、もっとポップな感じで、類家とタゴサクの会話が進んでいったりする流れがあったんですが、この映画では全て(会話の内容が)事件のことになっているので、類家のファニーさ、ポップさみたいなのを、普段は猫かぶってる類家が実は伊達メガネをかけているというふうに遊んでみたり、タゴサクが笑ったから、自分もおかしくなっちゃって笑うとか、そういったところにキャラクターを込めるという感覚でしたね。だから自分がタゴサクと相対してみて、心の中の小さな爆発――感情の何かが動かない限り、ムダなことはしないでおこうというのはありましたね。
僕がとにかく守りたかったのは、このふたりが似た者同士だということです。(タゴサクは)一歩踏み込んじゃった人で、(類家は)「人を殺したい」とか「あいつマジでむかつく」とか思ったことはあるけど、割に合わないから(人を殺すということを)やっていないだけという。主題歌がエレカシ(エレファントカシマシ)の宮本(浩次)さんの「I AM HERO」だから、「自分はヒーローだ!」と思っていないとやっていられない人に見えればいいなという思いで演じていました。
佐藤:ちなみにさっき裕貴が言った「ナチュラルというのがあんまり好きじゃない」ということについてですが、ナチュラルなお芝居をすることは、もちろん俳優にとって相当必要なことです。僕の中で、例えば
高倉健 さん、
渥美清 さん、現代でもたくさんいるけど
浅野忠信 さんや
木村拓哉 さん……そういうナチュラルな芝居ができる人って、とんでもない熱量と技術があってそれをやっているわけです。それを見てくださる人が「あの俳優さん、ナチュラルでいいよねー」と言うのを聞くたびに、そういった実態と比べると、とても軽い感じがして、「好きじゃない」という話なんです。
――単に自然体で演じているのではなく、意図して“ナチュラル”な芝居を演じているということですね。スズキタゴサクは、考え抜き、作り込んだ上でできあがったキャラクターのように思えますが、どのようにつくり上げていったのでしょうか?
佐藤:僕が考えたのは、とにかくセリフの分量がすごいので、仮にこのセリフをずっと正面からお客さんに向かって、ずっと割り(※カット割り)がない状態で、僕の芝居だけを見ても、もつような芝居をしようということぐらいです。あとはもう、監督にお任せして、(カットを)割ったりするけれども、僕としては、とにかく長いセリフが多いけど、完全にフィックスで僕の芝居を見せても、客がもつような芝居をしようと。
(C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会 ――佇まいや話し方などに関して、別の映画の登場人物やキャラクターなどを参考にされた部分はありますか?
佐藤:具体的に「これを参考にした」というのはないです。ただ、僕はもう56年生きてきて、洋画も邦画も好きで、例えば「
ダークナイト 」も好きですし……もちろん(タゴサクは)ジョーカーとは絶対に違いますけど。自分でその時に意識していたわけではないですが、「いまのはあの映画のあのイメージだな」とか「松田優作さんのあの映画の……」とかいろいろあると思います。これまでにいろんなものを見てきて、その結果のアウトプットだと思います。
――改めて、取調室で類家とタゴサクが対峙するシーンの撮影について振り返っていただけますか?
佐藤:まずね、
山田裕貴 は大変だったと思いますよ。だって目の前で、(類家の前にタゴサクと対峙する清宮役の)
渡部篤郎 の長いシーンをずっとペン回しをしながら見ているわけですから。次に自分がそこに座るというのをわかった上で。プレッシャーもあっただろうしね。リハーサルは去年やりましたよね?
山田:1日だけでしたね。
佐藤:本読み1日。たぶんですけど、裕貴はもうちょっとやりたかったんじゃないかと……。
山田:そうです(笑)。
(C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会 佐藤:最初に本読みがあったんですけど、僕はそこでセリフを全部覚えて行ったんですよ。普段、本読みの段階でセリフを覚えるなんてことはしませんよ。ただ、今回は僕のプレゼンのつもりでね。要するに、監督もスタッフも共演者もいる中で「今回はこれぐらいの意気込みで行きますよ」というのをみんなにプレゼンするために、セリフを全部覚えて行ったというのがかなり大きくてね。
そうしたら、裕貴も「頑張ります!」って、その後のリハーサルの時にはもうセリフを覚えていて。本当はリハーサルの時だって、覚えていなくていいんですよ、まだ本番じゃないんだから。でも山田裕貴 は覚えてきて、類家のニュアンスでね、「いやぁ、これは素晴らしい!」と思って、だから、僕はちょっとこの若い俳優とのセッションを、もうこれ以上はリハーサルで決めずに当日楽しみたいなと思ったんですよね。それで「(リハーサルは)もういいんじゃない?」と言ったんです。ただ、裕貴としてはそこ(リハーサルでのやり取り)に宝石の鉱脈があるかもしれないからね。
(C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会 山田:いや、僕も本当はリハーサルが嫌いなタイプなんですけど、今回はもうこのセリフ量はやばいと思って……。量だけじゃなくて、類家がどんなキャラクターであれ、タゴサクを圧倒しなきゃいけないから、そこは本当に心配で、プレッシャーでしかなかったです(苦笑)。
佐藤:そりゃそうだよな(笑)。
山田:撮影中も、僕は類家っぽくなって、すごく頑固になっていて、監督から「タゴサクの周りを歩いてほしい」と言われたんですけど、僕は、席を立つことは、類家にとってはリングから降りる行為だと思っていて、ちゃんと目を合わせて、一瞬も見逃さないという状態で座っていたかったんです。でも、そうすると画変わりがしないから監督として悩みどころだったと思います。でも、僕は対面している時は絶対にここを動かないと思っていて、毎シーン「山田くん、ここ立ってくれないかな?」と言われても「嫌です」って。監督からは打ち上げで「お前が一番言うこと聞かなかった」「でも類家っぽいな」と言われました(苦笑)。
――サスペンスとしての面白さに加えて、現代社会の様々な様相が鋭く描写されているところもこの作品の魅力だと思います。“スズキタゴサク”はまさに、そうした現代の歪みみたいなものを背負った存在にも思えます。
山田:僕がタゴちゃん(※劇中、類家がスズキタゴサクを“タゴちゃん”と呼ぶ描写がある)について思っているのは、性善説・性悪説で言うと、タゴちゃんは決して生まれついての悪じゃなくて、誰にも相手にされなかったことでそうなったと思うんですよね。育ってきた環境、出会った人によって、こうなってしまったんだろうと。警察署の取調室にいる限り、自分は安全で、法律が自分の身を守ってくれるわけですけど、そういうことを考えられる頭の良さみたいなものも、おそらく生きていくために後天的に身に着けたんじゃないか? そうやってうまく生きていかないと心が耐えられなかったんじゃないかと。
自分が類家を演じたからなのかもしれませんが、恐ろしいことに映画の中で出てくる「殺します」という言葉が、どこか正しく聞こえてきちゃうようなところがあって、類家は自分ではやらないけど「タゴちゃんの気持ちはわからなくない」と思っているんだろうなというのが答えですかね?
佐藤:情報解禁された時に「謎の中年男・スズキタゴサクとは一体何者なのか?」という宣伝文が出ましたけど、僕自身、タゴサクを演じておきながら、最初にこのお話をいただいた時からいまに至るまで、いまだにスズキタゴサクが何者なのかわかっていないんですよね。わかってしまうのが怖いような、わかんないままの方が明日も穏やかに生活できるような……。それぐらいちょっと「わかっちゃいけない存在」というか。作品全体で善悪とか命の平等さとか、ある意味で答えの出ないものを描いている感じがあって、それが作品の魅力にも通じるものがあると思っています。
「爆弾 」は、10月31日から全国公開。



 (C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会
(C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会 (C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会
(C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会

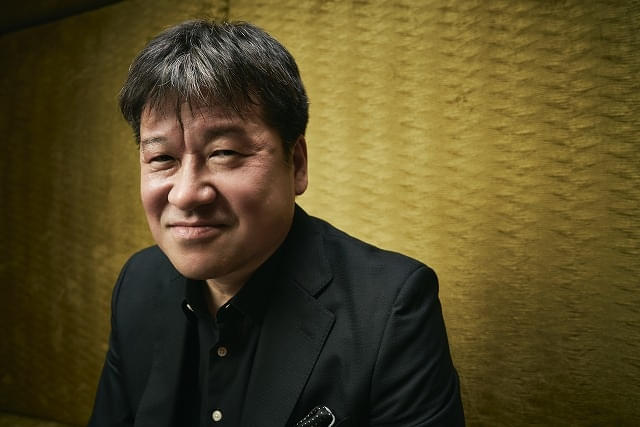

 (C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会
(C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会
 (C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会
(C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会 (C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会
(C)呉勝浩/講談社 2025映画「爆弾」製作委員会







 注目特集
注目特集  注目特集
注目特集  注目特集
注目特集  注目特集
注目特集  注目特集
注目特集  注目特集
注目特集  特別企画
特別企画