橋口亮輔監督、7年ぶり最新作は「恋人たち」が“救いになってくれたら”
2015年10月16日 14:20

[映画.com ニュース] 数多くの映画賞を受賞した「ぐるりのこと。」以来7年ぶりとなる、橋口亮輔監督のオリジナル脚本による長編最新作「恋人たち」が、11月14日からテアトル新宿ほかで全国公開される。7年の時を経て、橋口監督が「“今”を生きるすべての人に向けた絶望と再生の物語」に込めたものとは何なのか、映画を製作する意味などを含め、公開を前に橋口監督の現在の心情に迫った。
本作の主人公は、通り魔殺人事件によって妻を失い、橋梁点検の仕事をしながら裁判のため奔走する男アツシ、そりが合わない姑、自分に関心をもたない夫との平凡な暮らしに突如現れた男に心が揺れ動く主婦・瞳子、そして親友への思いを胸に秘める同性愛者で、完璧主義のエリート弁護士・四ノ宮という、心に傷を抱えながら幸せを求めて生きる3人の“恋人たち”。橋口監督のワークショップに参加しオーディションで選ばれた新人俳優の篠原篤、成嶋瞳子、池田良が抜てきされ、“作家主義×俳優発掘”を理念とする松竹ブロードキャスティングのオリジナル映画製作プロジェクト作品として製作。光石研、安藤玉恵ら実力派が脇を固めている。
前作公開後、東日本大震災などを経て出口の見えないトンネルに入ったという橋口監督は、2013年に全身タイツ(=ゼンタイ)を愛好する人々をテーマに、俳優たちのエチュード(即興演技)をもとにした中編のオムニバスコメディ「ゼンタイ」を撮り上げている。「同じようにワークショップ、エチュードで、『恋人たち』というタイトルを決め、恋愛オムニバスみたいなものが出来ないかと思ったのですが、なかなか上手くいかなかった」と振り返り、「ワークショップに参加する彼らはプロになりたい、世の中に出たいと思って来ているので、彼らの地を生かしながらも限界を超えてもらわないと注目は浴びません。それに長編でオリジナルという条件があったので、それなりの世界観を持っていないと映画としてもたない。だから、自分の中からモチーフを持ってきて、素人のレベルを全部底上げし、ある水準以上になるように整えながら描くストーリーを考えるのに時間がかかった」という。
メイン3人との出会いについては、「メンツが違ったら違う物語になったかもしれませんが、自分の思いはアツシに投影させています。なおかつ彼らの限界も超えていけるようにという配慮をしながら出来上がったという感じ。目標はワークショップに集まった人たちの中から1人でも2人でも世の中に出てくれるということが、僕に課せられた使命のひとつだったと思う」。さらに、「今の日本のねじれてしまった感じ、特に映像業界の自主規制みたいなものが厳しく、ものが言えなくなっている感じ、そういう空気みたいなものを盛り込みつつ作っていきました。ただし、嫌なものが後に残る映画は嫌いなので、きつい現実や理不尽なものに苦しむ人の気持ちを描き、それぞれ違うような感じで展開しながらも、1本の映画を見ているようなムードを心がけた」と説明。確かに、主人公たちの抱える問題を描きながらも、希望を感じさせる終わり方になっている印象が残る。

普通の商業映画であれば自主規制するようなテーマも扱っている本作だが、「皇族の話にしてもタブーですよね。どこもやろうとは思いませんが、なるべく今メジャー映画で避けて通るようなところをあえて拾っていったところはあります」。インディペンデント映画でも監督の撮りたいものを尊重した製作体制が難しい現状で「大手でさえ企画開発にお金をかけない。オリジナルを撮ろうと思ったら時間がかかりますが、企画開発にお金をかけていかないと人は育たない。この現状は日本映画界だけではないでしょうか」と問いかける。
「自主規制により家族の話とか、人って素晴らしい、絆って大切みたいな、本当に小さい話しかできない。こういうことをやっていたら、海外の作品と戦っていけない。言いたいことが言えなくなってきている空気を感じている人は多く、塚本晋也監督もそういった危機感を感じられて『野火』を作られたと思う。“今やらなきゃ!”ということを感じているのではないかと思いました。メジャー作品では描かない人たち、感情、日本の中にある様々な事柄について、やっぱりしっかりと描いていくことが大切」と吐露した。
では、この作品はどんな人へ向けて作られたのだろうか。「わかりやすく感情移入できる話ではないかもしれませんが、みんな『飲みこめない思いを飲みこみながら生きている』と思うんです。でも、殺すわけにもいかない、まして自分が死ぬことも出来ない。じゃあ、やっぱり生きていくしかないと生きている人たちって、特に震災以降、日本にはたくさんいらっしゃるんじゃないか。誰にも胸の内をわかってもらえなくて生きている人が、この世界にいるんだということをわかっている人がいて、こういう映画を作ったんだということを知るだけでも、その人の救いになる。そうなれば、この映画を作ったかいがあったと思う」と胸の奥にある熱い思いを語った。
橋口監督自身も今作を撮って救われた部分があったのだろうか。「自主映画みたいなのを作ろうと思ったんです。自主映画って表現がストレートです。未成熟かもしれないけど、そのストレートな表現の強さは絶対あると。だから、撮影中は(初の劇場公開映画)『二十才の微熱』(92)を撮っている時みたいな感覚でした。ちょっとリフレッシュという感じはありましたね」と、原点回帰した心情も明かした。
なお本作は、橋口監督の全国訪問と海外映画祭への出品費として、ネット経由で一般に資金提供を募るクラウドファンディングのプラットフォーム「モーションギャラリー」(http://eiga.com/official/motion-gallery/archive/)で、200万円を目標に支援金を11月6日まで募っている。
フォトギャラリー
関連ニュース



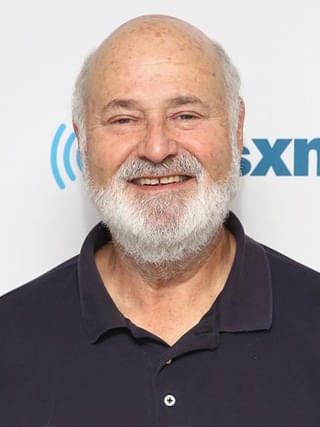


映画.com注目特集をチェック
 注目特集
注目特集 パンダプラン
【ジャッキー・チェンだよ全員集合!!】日本公開100本目 ワクワクして観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!
提供:ツイン
 注目特集
注目特集 神の雫 Drops of God
【辛口批評家100%高評価&世界最高峰の“絶品”】“知る人ぞ知る名作”ご紹介します。
提供:Hulu Japan
 注目特集
注目特集 配信を待つな!劇場で観ないと後悔する
【人間の脳をハッキング“レベルの違う”究極音響体感】戦場に放り込まれたと錯覚する没頭がすごすぎた
提供:ハピネットファントム・スタジオ
 注目特集
注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?
【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
 注目特集
注目特集 エグすんぎ…人の心はないんか…?
【とにかく早く語り合いたい】とにかく早く観て! そして早く話そうよ…!
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント












































