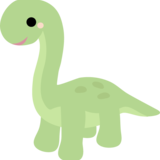1994年に発表された映画で3部作で構成され、上映時間は4時間を越えた。キリスト教が伝来した頃まで歴史は遡り、ソ連崩壊の混乱の最中にあった1994年頃までのジョージアの歴史を詰め込んでいて、これから同国について知ろうとするものには、間違いなく素晴らしい教材になる。
東と西の文明が交差する地域だからこそ育まれた文化特に美術や音楽、そして宗教観の紹介に多くの時間を割く。そこにあまり興味を持っていない自分は睡魔との戦いに追い込まれる。ジョージアは今も存在するが、この映画を制作したイオセリアーニ監督は祖国の消滅を危惧する切実さを持っていたことからこの映画が作られたということだから、ジョージアに素晴らしい文化があったことを記録に留めたいという気持ちが表現に現れる。
特に耳に残る音楽が混成合唱だ。異なる旋律が一つになって奏でる合唱は多様な文化が交差しつつもお互いに対立することなく、調和して紡いできた歴史と共にこの国があることを主張しているように映った。ここでは、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という対立は見えない。これを見ると、同じようにそれらの宗教が混在するエルサレムとは対照的である。だが、お互いの聖地だの居住地だのとより根源的な主張で対立する地域が同じようにできるだろうという主張であるとすれば、それは適切ではない。ジョージアを征服したのはペルシア、イスラム、オスマン朝、ロシアなどの大国だけではなく、幾度となく外敵の侵入や領土の分割を繰り返している。これらが無血で済んだはずがない。
それでもロシアに対する敵愾心は際立って伝わる。ロシアより100年早くアルメニアに続いて世界で2番目に早くジョージアがキリスト教を国教化したことに言及する。そのためか、アルメニアに対する一種の文明上の敬意をわずかに見せる一方でロシアに対しては一種の軽蔑を持っていることを感じさせる。そのロシアから支配され、宗教的にもロシア正教会に屈服したことへの屈辱感も感じる。その屈辱感を増幅させたのが、スターリン時代のソ連化だろう。そのスターリンの出身がジョージアというのも皮肉だ。そのスターリンから受けた仕打ちのうえに、その死後のフルシチョフのスターリン批判に対しては、スターリンを讃えて抗議、指導者に大国の指導者に振り回される姿を「小国の性(さが)」という言葉だけで済ましてしまうのは雑すぎる。
ジョージアはワインの原産地としても有名らしい。
今でもワインの産地であるが、かつては200以上のワインの原材料となる葡萄の品種があったのだが、共産主義の下、ワインの種類を限定するため栽培される葡萄の種類も限定されてしまったのだという。その限定されて作られたワインも集団生産の中、酷いものであったらしい。かつてのワインの復興を夢見て行動を起こす人がいるのだろうか。
失われたワインも大きな損失には違いないが、より大きな損失はソ連が植え付けた国内の分断なのだろう。圧政の下、密告を奨励したことで、人々の間で不信感を植え付け、他人との関係が疎遠になっていったという。そうした中で、必ず出てくるのがそうした外から支配に手を貸して協力する人も出てくる。こうして国民の心が分断された状態が解消されない中で、内戦が勃発すると大変なことになることをジョージアの歴史が語る。
ロシアは分断の種を植え付けたと主張する。周辺のロシアに従順な民族を入植させたというのである。それがアブハジア人やオセット人の国、アブハジアと南オセチアなのだという。そうした地域がソ連崩壊後の独立時に、ジョージアからの分離を求めることになったとこの映画では主張するが、これを鵜呑みにはできまい。だとしても、一つの国に住む異なる民族の対立は凄惨すぎる。昨日まで一緒に暮らしてきたはずなのに、多数派の民族の下で暮らす少数派への仕打ち、この映画では、アブハジアに住むジョージア人の悲劇だが、それが血で血を洗う報復合戦の様相を伝える。これは日本を同一国家同一民族の国というのは今では問題発言だが、国内で民族対立が皆無と言っていいほどの日本人では理解し得ない感覚だろう。
先の大戦で我が国は焦土と化したが、大戦の最中、思想的な意味で政治犯として敵を利しているとして捕らえられた人もいたが、少なくとも内戦のような要素は伝えられていない。(関東大震災の際には、在日朝鮮人の中にこうした被害があったことは忘れ去られてはいけない。)
この映画が制作された1994年は、アブハジア戦争は停戦が成立しているが、ジョージア人の難民問題が解決されていなかった。さらにジョージアは2000年代になるとカラー革命、ロシアの侵攻という事件が待っていた。
この映画は反ロシア的な主張で制作されており、ウクライナ侵攻を見ている今見るとその主張を鵜呑みにし易くなる。しかしながら、ジョージア人の中にも親ロシア的な人がいることを見過ごすわけには行かないだろう。2008年サーカシヴィリ大統領がウクライナとともに、NATOの加盟に動き出したとき、これをロシアは見逃さなかった。ロシアが後ろ盾となった南オセチアでの軍事衝突、名産のワインの輸出も停止され、窮地に陥った大統領に追い討ちをかけたのは自国内の親ロシア勢力であった。
兎にも角にも他民族国家の融和は難しい。ジョージアの場合にはその地理的な位置がそうした問題を呼び込んできた。ユーラシアで多様な文化が交わる地域はこの地域に限られるわけではない。パレスチナ問題やシリア問題等を抱える中東も然りである。かつて大きな帝国を築いたイスラム帝国やオスマン帝国、より過去に遡ればアケメネス朝ペルシャなども最盛期には、他民族を共存・共栄させるための寛容さがあったと言われる。しかし、そうした治世が長続きしなかったという事実もある。
ウクライナ紛争後、ロシアの勢力が後退することになれば、ジョージアのNATO加盟に向けた動きが再燃することは容易に想像できる。ウクライナ紛争はロシアというより、プーチン氏によるものという論調が多いように感じる。ただ、そもそもプーチン氏のような専制的な指導者によってこそ強いロシアが成立するとも言える。プーチン後のロシアを語るのは早いかもしれないが、ロシアが一旦衰退しても、大陸のハートランドで豊富な資源を有し、その寒さゆえ、ナポレオンやヒトラーの侵入を阻んできたロシアはいずれ強い国となって復活するのではないか。プーチン後の未来をロシアの周縁国はどのように描いているのか。中国や米国などの域外国の思惑にも左右されるだろう。ウクライナの復興だけではないこの地域の新たな混乱と秩序に向けた動きが既に動き出しているのではなかろうか。


 皆さま、ごきげんよう
皆さま、ごきげんよう 月曜日に乾杯!
月曜日に乾杯! 汽車はふたたび故郷へ
汽車はふたたび故郷へ 素敵な歌と舟はゆく
素敵な歌と舟はゆく そして光ありき
そして光ありき 月の寵児たち
月の寵児たち 歌うつぐみがおりました
歌うつぐみがおりました ここに幸あり
ここに幸あり トスカーナの小さな修道院
トスカーナの小さな修道院 落葉
落葉