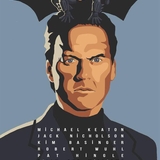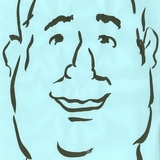怪物のレビュー・感想・評価
全1019件中、21~40件目を表示
怪物だーれだ
誰もが怪物
それぞれの視点から真実が浮かび上がるのが面白い
こういうのがわかってる人が高評価つける映画なんですね
存在
小学生の頃に気の合う友人ができると、狭いコミュニティの中では絶対的存在になりがちで、私の場合執着のある子であったと思う。
秘密の共有、気持ちを明かすこと、時間はその存在をより強くする。
大人には話せないことなんて子供の頃はたくさんあった。そして大人になった今、子供の頃の自分を思い出しては、あの頃の視野の狭さと、それによる間違いが何かあったのでは無いか、自分に非があるようなことが起きていたのでは無いかと日々考えることが多い。
でもそれは、自分だけのせいではなくて、それぞれが持つコミュニティから枝グラフのように繋がっていってしまっただけかもしれないと、この作品を見て改めて考えた。
大人が思っているより子供は脳を使って行動している。
純粋さが、それをたまによく無い方向へとも持っていく。
怪物探し・・・。そうなりましたね、監督の思惑通り(?)ハマりました。
辛気臭そうな映画だから、観るのを避けていたってのもありますが、AmazonPrimeで観れる内にみないと、せっかくの作品が有料になったら、また観る機会が遠のくかな、と鑑賞。
ボタンの掛け違いが、大きな歪になって悲劇になっていくというストーリー。監督の思惑通り(?)、2人目の目線が始まった段階で、怪物探しをしてしまっている自分がいる。ストーリーが進むにつれて、信じていたものが逆転して不信につながる。物事の見方によって正義が変わっていく、という戦争がなくならない理由を表しているような、そんな作品に感じました。
最後、あの二人は亡くなっちゃったんでしょうね・・・。僕はそう感じたのですが、いかがでしょう。そういう意味で、やっぱり辛気臭い映画だったと思います。説教がましい、というか。それでもいいのですよ、全然。でも、この手の映画は、心が強い時にみないと折れちゃいそうで。要注意、というか。
恐怖映画に勝るとも劣らない恐ろしさ
モンスターペアレント、学校の事なかれ主義、児童虐待、イジメ、同性愛、等々現代の小学校問題をこれでもかと詰め込んだ問題作です。
伏線がいろいろあって、ボーッとみていると理解が追い付かないです。
ただただ、人間の恐ろしさや愚かさをまざまざと見せつけられた気がします。
秘密基地の廃棄車両や廃線跡でのシーンがすごく印象的で、ラストシーンがとても美しくて救われた気がしました。
そこらへんのホラーより怖い
流石是枝監督
子供こえーーー
予備知識なしで鑑賞。
序盤の子供思いの母から始まりがなんとなく見方によって全員怪物という話しなんじゃないかと想定した。
湊くんが何考えているか分からない&何気ない母親の一言が
地雷になっていないかとザワザワ。
先生たちの棒読み不快感MAXなのにイライラ。
次の担任ターンの時に母親目線での「態度」だったんだなと把握。
担任も熱血まではいかないけどきちんとした子供思いの人だった。
にしても担任の先生は周りに恵まれてなさすぎて可哀想。
ここまで来て言葉足らずだったり1つの嘘で誰しも怪物扱いされるんだなーと。
そして途中から出てくる星川くんという存在。
仲の良い小学生同士ってこんなもんじゃないの?って思っていたら校長にはっきりと「好きな子」って伝えていた。
小学生って自認する勇気ないと思うけどそこはご愛嬌。星川くん可愛すぎる。
この話でのもっともな怪獣は星川父なんじゃないかと。
2人で仲良く走れて幸せだねーと思ってホカホカしてたら他の方のレビューで亡くなった説を見ていっきに切なくなる(´・_・`)
正直、やっぱ子供って怖いなーという思いが1番。
怪物に集約された形
黒川想矢さんを応援しているため、怪物を観ました。
3回目の鑑賞です。
子供からみた大人は自分を押さえつけて理不尽に支配する怪物に見えるし、大人からみた子供は理解できない存在として怪物に見える。だとしたら、誰にでも怪物と思える存在がいて、でも誰かが怪物だと思ってるその人にとっては純粋な行動で。
怪物の最後のシーンは、誰かからしたら怪物的な行動(常識的でない行動)だけど、2人からしたら純粋で美しい自由な選択なんだと思います。「怪物だーれだ?」という言葉が何度も繰り返されるのも、自分にとっての怪物を問うきっかけを与えているのかな、と。
人によって怪物と捉える対象が違うから、あなたにとっての怪物の解釈について問いたくてこのタイトルにした。
また、そこから派生して、そうやって人のことを怪物と決めつけてしまうわたしたちこそが真の怪物なのではないかということ。
「自分にとっての怪物」を解釈していくと、そこに辿り着く。そのためのタイトル。
わたしにとって怪物のタイトルは、この二重構造だと思います。
いや、もしかしたら多重構造かもしれません!
例えば、言葉が怪物であること。
怪物の映画の中で大きな役割を果たしているのは、嘘や誤解だと思います。
誰かが口にした小さな誤解や嘘が、どんどん膨らんで人を傷つけていきます。
そう考えると「怪物」とは人間じゃなくて、言葉そのものが怪物化することを指しているのかもしれないな、と。
次は社会に潜む怪物です。
学校の規律、保護者の目線、地域社会の監視などみんな「正しいこと」を守ろうとするけど、それが子どもたちを縛って追い詰めていきます。つまり「怪物」とは個人じゃなく、子どもを押しつぶす社会の仕組みそのものなんじゃないかっていう解釈です。
その次は愛の形が怪物化すること。
親の愛、教師の責任感、子ども同士の友情や恋心など全部愛であるはずなのにすれ違いや歪みで相手を苦しめる存在になってしまう。
つまり、純粋な愛情がゆがむと怪物になるっていう見方です。
最後にそもそも怪物はいないという解釈です。
ラストシーンはとても幻想的で現実離れしていたと思います。
そこで示されてるのは「本当は怪物なんていなくて、ただ純粋な子どもたちの世界があるだけ」なのかもしれません。
だから「怪物」というタイトル自体が観客の先入観を揺さぶるトリックになってるのかもな〜と思いました。
高校生の稚拙な解釈かもしれませんが、まとめると世の中にはいろんな形があって、それが全て「怪物」という言葉に集約されている、ということなのかなと思いました。
2人の子役が素晴らしい
敷居高そうだったから見るの敬遠してたけど、結構シンプルな構成で面白かった。
最初はいじめの訴えを学校側が無視して逃げる感じで物語が進められていくのかと思いましたが、中盤からキャラ視点が変わって物語通して様々な視点でストーリーが進む映画だったので、あのシーンこういう理由かみたいな感じで飽きなかったのとテーマが怪物だったので何が誰が怪物なのだろうかと見ながら探していてキャラの言動や行動の意味を理解しようとしたので個人的には物語に惹き込まれました。あと個人的にはテーマの怪物って意味は主人公たちが豚の脳と揶揄されるので、テーマを怪物にしたのかと思いましたが、どちらかというと片方の視点から見た相手の行動、言動を切り取って見て異物感を感じるいわゆる相手が怪物っぽく見えてしまう、見てしまうのが物語を通してあったと思うので、そういう意味でテーマが怪物になったんじゃないかと個人的に思っています。
フィクションと分かっていても嫌やわぁ〜🤢
見ていて思ったエトセトラ
◯いろいろな視点から物事を捉えて
描いてゆきましょう。
そうしたら、いろいろな事情がだんだん
ぼんやり見えてきました。
なるほどねぇ〜
◯自分がもしあのような親の立場なら
やっぱり学校へ乗り込んで行くと思います。😤
短絡的ですみません。🙇
自分もある意味カイブツ?
◯小さい頃はノーマルじゃないことにも
もちろん悩み苦しむんだろうなぁ。
◯あんな密かな場所や秘密基地(遊び場)があるといいなぁ〜 うらやましぃ〜
◯それにしても、教室でクラスの子たちが
あんなことを特定の子に平気でしてたらたまりませんわ。😱
見終わってすぐ、子供に学校でおかしなこと変なことが起こっていないか聞いてみました。
フィクションと分かっていても、嫌やわぁ〜🤢
◯『誰も知らない』もきつかったけど、
本作もなかなかきつかったぁ〜〜😨
◯ちなみに、是枝監督の以下作品はスキです。
『歩いても 歩いても』
『そして父になる』
『海街diary』
『万引き家族』
※一部修正済 2025.8.17
世界はそれをLGBTとゆうんだぜて話
中、高と自分に置き換えてもそれらしき同級生はいたなあと。
個性なのか、病気なのか
作品では怪物と表現され
私としては病気
だからこそ向き合っていかなあかんのでは無いかと感じた。
切なくて美しい話でした
主人公二人の笑顔に胸が締め付けられました。私にも、子どもが二人いますが、ただただ自由に生きて、幸せになって欲しいと思いました。
ラストシーンは映画史に残る美しさを感じました。主人公二人が、幸せに生きて行ける世界に変わったと信じたいです。
素晴らしい映画でした。
怪物=思い込み
安藤サクラ演じる、夫と死別したシングルマザーは、お母さんになんでも言わなくなってきた小5の息子の湊と全身全霊向き合って生きている。
その湊に不可解な鼻血や怪我や物の紛失などなどが起こりはじめ、母は学校での先生からのいじめを疑う。
状況から、まぁわかる気もするけれど、
児童がいる=先生が授業をされている時間帯に何度も通い詰め、口調も教師を信用できないのはわかるが、タメ語。非常によろしくない。なぜ、先生が意味もなく体罰をするはずがないので、まずうちの子がどんな言動をしたからなんだろう?という発想にならないのか見ていて非常に不可解だった。
信任教師の保利先生もまた、作内では噂で先に、火事があって全焼した建物に入っていたガールズバーに保利先生がいたという先行情報を基に保利先生が登場するため、母親は一層保利先生への先入観不信感を強めて接し、保利先生が息子に暴力をふるったに違いないと断定的に罵倒する。
ミスリード役、湊と同級生の母親役野呂佳代に、どこからそれ聞いたの?と聞かない母親がまた、不可解。
それでも、安藤サクラのクリーニング店員役は万引き家族でも非常に板についていたし、ラグビー選手だった夫に顔向けできるように息子を真剣に育てようとクリーニングの仕事を夕方までこなしながら育児に奮闘している姿は応援したくなる。
その応援に含まれた、
「湊が普通に結婚して子供を持つまではお母さん頑張るってお父さんと約束してるんだ」
が、湊の苦しみの元凶だとは。
息子湊はチャッカマンを部屋に持っていたり、山に入ったり、車から転がり落ちて耳を怪我したり、様々おかしな行動を見せ、それは先生のせいだとは思えないものの、実は保利先生が勘違いしていたように湊がいじめっ子側なのか?チャッカマンで放火までしているのか?豚の脳と人間の脳の入れ替えと称して猫殺しまでしているのか?なんせ表題が怪物なものだから、頑張ってるお母さんの心子知らずで、実は息子は少年Aのような闇を抱えてしまっているのかと考えながら見進めていく時間には脅かされた。
どうか母親の知る湊像と著しく乖離、逸脱した本性ではありませんようにと願う。
それでも、湊から、凶悪な感じはしてこない。
真相はなんなのか?
学級内には、鏡文字を書く、おそらく発達障害の依里くんがいた。依里くんはいつもにこにこしていて感じの良い優しい子だが女の子にも見間違うかもしれないくらいあどけない可愛い雰囲気。
しかし、中村獅童演じる父親は酒にだらしなく、実は母親は依里を置いて出て行っており、父親は依里は豚の脳だと担任の保利先生にも言うほど息子を人間の脳にしなければなどと傷つける発言をするだけでなく、依里に激しいDVをしている。
息子は浴びた言葉を素直に信じて自分はそういうものだと思い、クラスの中ではエイリアンなどと呼ばれいじめを受けているが、笑って対応していた。
湊はそのいじめにできるだけ加担したくないと感じていた。学校の中で依里と仲良くすると、キスキスなどと囃し立てられて自分もいじめの対象になるから学校では依里に話しかけないでなどと子供ゆえの残酷すぎるお願いをしたりするが、実は下校後お互い親の帰りが遅いため、2人で仲良く遊んでいて、おそらく3.11で土砂崩れにより使われなくなったと思われる旧列車を秘密基地のようにして、「怪物だーれだ」の合言葉で人狼ゲームをしたり、列車を宇宙に飾り付けたり、2人だけの世界で将来の夢を話したり、友情を育んでいた。
湊は学校では依里へのいじめを止めるために、他の子達の防災頭巾を散らかして暴れたり、感情コントロールが効かない素振りを見せるが、優しく止めようとした保利先生の手がたまたま当たって鼻血が出ただけで、湊も誰もいじめていないし、保利先生も誰にも体罰をしていないのが実態だった。
湊の怪我は全て、依里くんを公に守りたいのにそれはできない葛藤と、なぜできないかというと依里くんに恋愛感情が芽生えている自覚があり、同性愛では子を持てないとわかるので、母親が軽く発した結婚や家庭を持つまで湊のために頑張るという言葉から、自らを幸せになれない存在と思い、悩んでいた。
学校では、母親の言葉を発端に保利先生が体罰教師として謝罪して新聞に載り辞職、校長先生その他先生は母親を刺激しないようとにかく本質よりも謝罪を繰り返す対応に走る大事態となっていたが、5年生の湊には保利先生が全てをかぶり湊の将来を思い周りの思惑通りに謝罪し仕事を失い、記者に追われ、結婚したい彼女にも逃げられている深刻さを知らない。
それでも保利先生が悪いと嘘をついてしまった罪悪感はあり、校長先生に打ち明けた。
校長先生もまた、孫を亡くした経緯を、実は校長が轢いた等と噂されて先入観のもと教師達から見られたりしていたが、幸せになれないと話す湊に答えをくれる。
「誰かにしか手に入らないものは幸せとは言わない。みんなが手にできるものが幸せ。」
抱えていることは楽器を吹いて吹き飛ばしてしまいなさいと助言してくれる。
ある日暗くなるまで秘密基地に依里といた湊には、血相を変えて母親が車で迎えに来たが、依里を心配し助けに行くべきと車から転がり落ちて怪我していた。
その後依里を心配して家に行くと、依里の父親は依里に、「祖父母のもとに好きな子がいるから転校するので今まで遊んでくれてありがとう」と玄関先で嘘をつかせるが、もう一度出てきて、「実は嘘!」と話した依里が家に引き摺り込まれお仕置きの暴行を加えられている声を耳にする。
嵐の前の日には、家では母親と窓に段ボールを貼ったり準備が進むが、依里を心配して家に行くと、依里は全身に暴力を振るわれ浴槽でぐったりとしていた。
助け出して2人で山に向かい、列車内に台風が近づくのを、生まれ変わりへの出発だ!と称して遊んでいた。
豚の脳と親に言われクラスでも虐められる依里も、植物好きなため品種改良の夢を持ちながらも、死んだら生まれ変わる輪廻転生に希望を感じていた。
父親を亡くし、母親を心配させたくないが、同性愛の悩みを抱えた湊もまた、輪廻転生に希望を感じていた。
猫の死体を学校で見つけた時も、依里から場所を教えて貰い見ていた湊を、女子は目撃して保利先生に報告しているが、その後依里と湊は猫の死体を山に運び、生まれ変われるように依里の持っていたチャッカマンで燃やして、山火事にならないように湊が水筒の水を川から運び火消していた。
チャッカマンはおそらく、依里が父親に火傷の虐待をされた時に手に入れたと思われる。
駅前の建物の火事は、父親がガールズバーに通うのをよく思わない依里が、知的判断がつかずにチャッカマンで放火した模様。
提出した将来の夢の作文を休職中に添削した保利先生が、2人の作文にある横文字、みなととよりに気が付き、過去に依里やみなとに、男らしくないなどと軽く発した言葉など全てに気がついて湊の家に台風の中謝罪に来た時、母親は怒っていたが不在の湊を探しに行くところだった。
保利先生と母親が山にたどり着くと、土砂崩れは既に起きて封鎖されていたが、無理やり中に入り列車に湊と依里がいるか探しに行く2人。
泥まみれの窓からなんとか中を覗くと、2人の姿はないが、2人の着ていたレインコートが見えた。
作中では、2人は列車の車体の下の線路の下に潜り込んで雨風を凌ぎ、生まれ変わりなんてないと湊は言いつつも、台風一過後、転生完了として2人で晴れてから山を駆け回る描写がある。
果たして湊も依里も本当に助かったのかはわからない。発達障害や同性愛の自我を受け入れて、子供達だけの世界の一瞬だけを切り取って判断するしかない先生や親が真相に気付いたとしても、依里の父親は変わらないだろうし湊の母子家庭も変わらない。
子供達は時に親に気を遣いながら、大人の言葉や環境で浴びる辛辣な言葉ひとつひとつを、大人が思うよりはるかに真剣に心に溜めて、傷付き悩んでいる。
5年生の、親とは異なる自我の尊重を求め秘密を持ったりもする月齢への接し方の親の揺れ、
親ではなく断片的に子供を見て責務に支障がないようにするのが仕事の教師、
親の言葉の影響を受けてものの見方が変わってしまう子供達、
その全てに居場所を見出せない時、子供の毎日は地獄である。
子供が話してくれる大人で居続けるためにも、先入観で話をしたり広めたりしないこと、それをよくわかっているからこそ、校長はスーパーで躾なき親が店内を走り回らせている子供の足を引っ掛け転ばせたのかもしれない。
是枝監督の、子供が大人に理路整然とは説明できないが日々感じている心情や時系列で出来事と整理すると子供が日々起こる事象に対して大人や周囲の影響を受けながら思考し判断し行動している様子の描き方がとても丁寧でリアルで好きだ。
作文のとこ
先生が作文の横文字で2人が仲が良かった事に気付いたとされるシーン。
あれ見てる側置いてけぼりで展開早すぎて意味不明でした。
観客に理解してもらうつもりならもぅ少しゆっくりのコマ回しかセリフが欲しかった。
女生徒が猫に対して先生からの再確認では知らないと言い張った所ももぅ少し分かりやすく伝えて欲しかったなぁ。
先生のセリフは猫を殺しただとかの言い回しに対して女生徒は猫をいじってただと言っただけだったので先生の言う殺した、とは言ってないと言った形だったらしい。
後はまぁラストはそれぞれ2パターンで観客の好きな方を選べばそれぞれに値する作品には仕上がってたと思う。
私は2人ともダメだったんだと解釈しましたが。
何を伝えたいかはそれぞれの視点で理解はしたけど先生ターンの時に飴を舐めたシーンは取り入れるべきだったとは思う。
既に彼女が落ち着くために飴をって伏線も張ったんだからと。
まぁそんな感じで私は生徒2人の気持ちには遠い昔すぎて感情移入も出来なかったのでイマイチな感じになりました。
全1019件中、21~40件目を表示