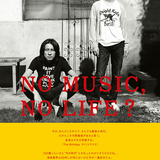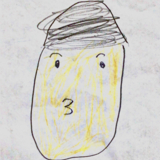怪物のレビュー・感想・評価
全1025件中、1~20件目を表示
ビッグバウンス宇宙と怪物
どうしてこうなってしまったのだろう。
昨日観終えた直後は、軽やかな疾走感と美しい緑、そして心に沁み入る音楽に包まれ、不穏な2時間を経て穏やかな気持ちになれた。けれども、一日経って日常の中で思い返すと、子どもたちは行ってしまい、大人たちは置いてけぼりにされたという思いが、じわじわと迫ってくる。朝ごはんを食べながら、小学生ふたりに尋ねてみたら、「…やっぱり、−−ということだと思う。」という返事。あまりにもあっさり反応が返ってきて、少し愕然とした。大人になってしまった私は、決定的な何かを見落したのかもしれない。
母親、先生、子ども。それぞれの視点で物語が語り直されるたびに、印象が反転する。後からは何とでも言えるのは承知だけれど、母親は押しすぎ、先生は流されすぎた、のかもしれない。とはいえ、その時々の焦りや軽々しさは誰にでもある。母親は、学校に行くために何度も仕事の折り合いを付け、深夜の通院の翌朝も日課をこなしたのだと思うと、何ともやり切れない。さらには、序盤では怒りさえ感じた校長先生に、終盤に至って救われる気持ちになるとは、思いもよらなかった。
誰かが意図したわけでもないのに、事態が絡まり悪化した大きな要因は、いくつもの噂や、無関心の連なりだろう。そして決定的な打撃になったのは、幾度となく繰り返された、手近な材料での辻褄合わせだ。彼らは、もっと何かあるかもしれない、何かを見落としているかもしれないと考えるのをやめ、あっさりと結論を下してしまった。すぐそこに待つ不吉な予感にさえ、目をつむって。
湖そばの公園の塔で、子どもたちがビッグバウンス宇宙について話すシーンが美しく、忘れ難い。宇宙が閉じた場であれば、いつしか宇宙は膨張から収縮に転じ、時間は逆戻りするという。創造と破壊が繰り返され、大きく循環するなかで、わずかなゆらぎから、銀河のもとととなる突起も無数に生まれ得る。ならば、映画に描かれた人びとの世界が、本作を観る私たちの世界と反転するのは、良くも悪くも、ごく当たり前のことなのかもしれない。そして、怪物もまた、自在に姿を変えながら跋扈し続けるだろう。
帰り道、「親に気を遣って大変だねー」「大変だよ、自覚しなよ」と子とやり取りできたのが、ちょっとした救いだった。
怪物という蜃気楼
ガールズバーの入ったビルの火災を起点に、教室での子供の喧嘩、子供による教師の暴力の証言、学校の謝罪、そして嵐の日に2人の子供がいなくなるまでを、3つの視点から描く作品。
最初の母親視点のパートでは、学校関係者の態度が絵に描いたようにひどく見える。あまりにテンプレ的な描写なので、これは何か物語としての意図があるんだろうということは察せられる。
一方、序盤こそ母親の早織に同調しつつ見ていて、教師たちに対し言葉が荒くなるところくらいまではこんな教師相手ならしょうがないと思っていたものの、取り上げたファイルを投げつけるあたりでちょっと気持ちが引いて、彼女が受難の親とモンスターペアレントの境界線にいるように見えた。教師たちの姿は、早織の主観が入った描写なのかもしれないと思えてくる。
湊との会話の場面で彼女が言った、「湊が普通に結婚して子供をつくるまでは……」という言葉の、聞く人によっては引っかかるであろうかすかな無神経さも、下味のように効いている。
ちなみに、早織のこの言葉が早々に心に引っかかったのは、本作がカンヌでクィア・パルム賞を受賞したことを映画.comの紹介文で読んでいたからだ(クィア=既存の性のカテゴリーに当てはまらない人々の総称)。このことに関しては最後に余談を追記する。
次の、教師の保利視点のパート(何の説明もそれらしい区切りもなく火事があった日に戻るので、ちょっとわかりづらかった)から、早織パートで点々と撒かれた謎が少しずつ明かされてゆく。早織を通した視界で一面に立ち込めていた靄が徐々に晴れていくような、ミステリにも似たエンタメ感があった。
実は保利先生は、最初の印象よりは熱心なよい先生で、そんな彼が周囲の嘘により追い詰められていった、ということなのだが、それがわかってもちょっと危なっかしくて怪しげな雰囲気が残るのは、永山瑛太の演技の絶妙さだ。
ただ、本質的にそこまで真面目なら、最初の母親との面談がいくら不本意だとしても、その場で飴をなめるか?そこはちょっとキャラのブレを感じた。それ以外の挙動も早織のパートとは若干印象のずれがあったが、それは早織から見た保利と保利自身の視点からの描写という違いのせいなのかもしれない。
女児が猫の死体について嘘をついたのはどういう動機だったんだろう?それだけがわからなかった。
最後は、湊のパートだ。ここで、細かい謎は概ね明らかになる。水筒の泥水や、片方だけのスニーカーから、それまで学校の場面で遠くに響いていた管楽器の音まで。
是枝監督はやはり子供の撮り方が上手い。今回は、従来のような現場で口伝えに台詞を伝える方法ではなく、事前に子役に台本を渡して覚えてもらったそうだが、子供たちの自然な姿を捉えていることに変わりはなかった。
廃電車の中で依里の転校の話をする場面などは、あの年代特有の色気まで感じた。
このパートでは、校長の善性も垣間見える。早織の目を通した校長の姿も、管楽器を介して湊を慰めた校長の姿も、同じ人間の一面だ。
最後に2人が楽しく駆けてゆくシーンは、どこかこの世ならぬ雰囲気もあった。彼らは嵐で命を落としたのかもしれない。
人間には多くの側面があり、そこには必ず善も悪もある。そしてその側面を見る者の置かれた状況によって、見え方も変わる。誰が怪物なのか、そもそも怪物は本当にいるのか、自分の主観だけでは真実が見えないことの方が、想像よりはるかに多いのだろう。
誰かの人間性を安易に決めつけること、自分から見える風景だけで善悪を断定することの危うさを思った。私たちが誰かを疑う時、卑近な例ではネットで炎上するような事案に遭遇した時、自分から見えているものが全てだと、つい信じたくなる。
その時立ち止まって、他の立場からの見え方を想像する。そうすることで初めて、この物語のように少しずつ、物事の本当に正確な姿が見えてくるのではないか。そんなことを考えた。
余談:
映画ライターの児玉美月氏のツイートによると、試写会の時の資料に「(クィアの要素がある作品であることは)ネタバレなので触れないでほしい」といったことが書いてあったそうだ。
一方、是枝監督は会見で、「性的少数者に特化した作品ではなく、少年の内的葛藤の話」と言っている。なので試写会資料の注意文はちょっと謎だが、クィア・パルム賞を受賞したことで、注意文を入れた製作サイドからしたら受賞の報道自体がネタバレのようになった形だ。
ただ個人的には、クィア要素があると事前に聞いていても物語の感動はきちんとあり、知ってがっかりするようなネタバレとは思わなかった。なお、児玉氏はクィア要素をネタバレ禁止のネタにすることを批判している。当事者性の高い観客への配慮に欠けるから、とのこと。
試写会資料の是非は置いておいて、やはりマイノリティ要素があると受け止められた作品は海外で賞を取りやすいという面があるのかな、とひねくれた私は思った。最近そういう作品が本当に多い(否定ではない)。
Japan's Burning Tire Pit of Adolescence
Just what Japan needs: another film to show the hardship of raising a child as a single-mother. Koreeda as one of Japan's best auteurs of the moment shows a perceptible disparagement to public education admins, perhaps something audiences understand all too well. The strongest point is the emotionally hypnotic soundtrack by Ryuichi Sakamoto, his final before his death prior to the film's release.
人の目線には死角がある
長野の諏訪市を舞台にしているのだが、真ん中に湖のあるのがいい。特に夜、俯瞰で街の全景を何度か見せているが、夜には湖がぽっかりと開いた黒い大穴のように見えて、その闇に吸い込まれそうな気分になる。あの闇には何があるのかと考えたくなる。
「怪物、だーれだ」という問いかけがなされるこの映画は、誰かを怪物と思いたくなってしまうその心象こそが怪物であり、街にぽっかりと開いた闇のようなものだと、そう問いかけられているような気がした。
同じ事件を3つの視点から描き直すこの映画を観ると、一度信じたものを崩され、どんな人にも見えない死角があることを自覚させられる。視覚効果による表現である映画は、カメラの向きは一方向を向くので、どれだけ真実を透明に映し出しているように見えても死角が存在する。これは、その映画の弱点に自覚的だから作れる作品だと思う。あの街の真ん中の闇のように見ようとしてもなかなか見えないものが、社会にも人間関係にも必ずある。そのことを忘れずに世の中を見つめることの大切さと難しさが見事に表現されている。
是枝裕和監督と同時代に生き、作品に触れられる僥倖
坂元裕二氏が脚本を手掛けているだとか、今回は子役に脚本を渡して撮影に臨んでいるだとか、そういった部分はきちんと取材をしたインタビューをご覧ください。
ここでは多少の主観も交えながら……。これはいつからだったか、是枝監督と同時代に生き、作品に触れられる幸せというものを、噛み締めるようになりました。
黒澤、小津、溝口など、日本映画界に燦然と輝く名匠たちの作品にも数多く触れてきましたが、やはり同時代を生き、時には撮影現場で取材をしながら息をのむ瞬間を目の当たりにすることが出来るのは、幸せなことだと再認識しなければなりません。
ほかにもシンパシーを感じる同年代の監督たちとの出会いも含めて。
是枝監督は、「これが是枝監督の集大成」みたいな表現を嫌がります。当然ですよね。監督ご本人が「これが僕の集大成」と発言するのならばともかく、他者が決めつけることではありません。今回も「集大成」ではなく、是枝裕和という映画監督の通過点であると考えるべきです。この先、もっともっと世界中の映画ファンを楽しませてくれることを切に願いながら。
それにしても、田中裕子さんの演技にはたまげました。
是枝組の常連であった樹木希林さんとは対極の位置から仕掛けてくるアプローチに仰天させられます。安藤サクラ、永山瑛太の芝居も、堪能してください。
怪しくて やがて哀しき 藪の中
安藤サクラが演じるシングルマザー・早織が、小学生の息子・湊が担任の保利(永山瑛太)からモラハラと暴行を受けていると確信し学校側へ説明と謝罪を求める序盤のかなり早い段階から、心臓のあたりがぞわぞわするような、なんとも不安で不快な気分が長い時間続いた。
坂元裕二による脚本がカンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞したことを報じる記事などで言及されていたように、本作の物語構成は、芥川龍之介の小説「藪の中」、またその映画化である黒澤明監督作「羅生門」に似て、真相がわからない一連の出来事を複数の当事者の視点から語り直す手法が採用されている。この「怪物」においては、主に早織、保利、湊の視点の順で(ほかに田中裕子が演じる校長の視点も少し入るが)、学校での数日間に起きたことや、湊と同級生の依里(より)とのかかわり、台風の一夜の出来事が多面的に語られ、当初は不明だった事実が徐々に明かされていく。
だが、坂元の脚本と是枝裕和監督の演出は、“たった一つの真実”が存在しそれを明らかにしようとするのではなく、むしろ各人の考え方感じ方や立場によって事象のとらえ方が変わってくる、言い換えるなら“認知のゆがみ”が生じうることを示唆しているのではないか。たとえば序盤、早織に感情移入して観るなら校長や教員らの心のこもらない釈明や謝罪は役人の答弁のようで腹立たしいことこの上ないが、保利先生ら学校側から語り直すパートでは早織がモンスターペアレントのように映る。
得体の知れない存在や体験したことのない状況を怪しむ、恐怖する感覚は太古から受け継がれてきた自衛本能だ。自分の命やアイデンティティー、家族やパートナー、よりどころになる家庭や職業・職場が何ものかによっておびやかされると感じた時、その何ものかが“怪物”として映り、自衛のため必死に抗おうとする。だがそうして抗う自分もまた、自分のことをよく知らない相手から“怪物”に見えているのかもしれない。
認知のゆがみが「事実でないことを私たちに見せる可能性がある」という理解に基づくなら、ラストシーンも見た目通りのとらえ方とは別に、180度異なる解釈もありうるのではないか。その解釈に思い至ったとき、改めて坂元裕二脚本の深遠さに震えた。
是枝裕和監督作品の中で「テンポ」は最も速い。「深さ」についての感じ方は人それぞれか?
是枝裕和監督作品と言えば、大きな特徴として「何気ない日常を切り取る」というのがあります。
そのため、物語はゆったりと流れていくような傾向がありますが、本作では矢継ぎ早に物事が動いていきます。これは、デビュー作以外では監督自身で手掛けてきた脚本を、「花束みたいな恋をした」などで知られる坂元裕二に任せた面が大きいと思います。
もしかしたら、これまでの「是枝裕和監督作品を見る」という姿勢でいると違和感を持つかもしれません。
それは、何の予備知識もなく作品の世界に身を置くという姿勢でいると、珍しく「時系列」が行ったり来たりするため頭が混乱するからです。
親切な作品であれば「(安藤サクラが演じる)母親目線の場合」「(永山瑛太が演じる)担任教師目線の場合」といった切り替えのタイミングを明示してくれますが、本作では似たトーンで映像が続いていきます。
要は「コンフィデンスマンJP 英雄編」などと似た構造にあり、様々な視点から眺めると物事の見え方が変化していくといった手法で、私たちに「種明かし」をしていきます。
「今は誰の目線で、どの時間を描いているのか」を的確に探り当てる、シーンの切れ目を自分で見つける必要があります。
これのヒントの1つはビルの火事でしょうか。
近頃ニュースでは似たようなビル火災が続きますが、本作では「ビルの火事は1回の出来事」なのがポイントです。
さて、そのような映像上のトリックを見極めた後は「結局、どのような全容なのか」を把握するために、組合せを頭の中で行う必要があります。
その結果、どんな物語が見えてくるのか?
私は、結局のところ「是枝裕和作品」という印象でした。
ただ、本作では「理由のない嘘」が少なくなく、これを連発すると「真相は藪の中」となり、やや気になる点でした。
良い点は、クセの強い人物が多く登場し、「この人物はどういう人なのだろうか?」と気になる独自性があり、その優れた「人物像構築」などで第76回カンヌ国際映画祭で「脚本賞」を受賞したのは納得できます。
怪物だーれだ
感想
『万引き家族』でカンヌ国際映画祭最高賞パルム・ドールに輝いた是枝裕和監督が、『花束みたいな恋をした』やTVドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」などで圧倒的な人気を博す脚本家の坂元裕二と初タッグ。
また音楽は、『ラストエンペラー』や、『レヴェナント:蘇えりし者』など、海外でも第一線で活躍した坂本龍一。映画史上、最も心を躍らせ揺さぶる奇跡のコラボレーションが実現した。
いったい「怪物」とは何か。登場人物それぞれの視線を通した「怪物」探しの果てに、私たちは何を見るのか。その結末に心揺さぶられる、圧巻のヒューマンドラマ。
先に「でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男」を観てしまい、見る順番間違えたなと…笑
シングルマザーの麦野沙織、先生の保利、麦野湊の3つの視点から描かれていて話が進むにつれ不可解な点が明確になっていく構成は良く出来ていました!
沙織視点では保利先生の態度は悪く、校長、教頭もやる気がなく酷い人間たちでしたね。
保利視点では優しい先生でしたが湊の嘘の証言によって人生転落で報われないです。
湊視点では小学生とは思えない大きい問題を抱えていて苦悩している。
LGBTが絡む話だったのはビックリしました。
俳優陣が素晴らしかったです、安藤サクラは安定感ありますね。湊と依里の子役も抜群でした!
ラスト、湊と依里が笑顔で山を走ってるのは希望なのではないでしょうか。
本作が遺作となった坂本龍一さん、ご冥福をお祈りします。
思い込みで誰しも怪物になりえると思います。
※インディアンポーカー
※ビックランチ
※誰でも手に入るものを幸せって言うの
繰り返し見たくなる
『怪物』ってタイトル
昨今の邦画から『怪物』というタイトルは
『悪人』や『正体』、『告白』などの映画の影響のせいか、
どんな怪物が出てくるのかと身構えて観てしまった。
でも実際は誰も恐ろしくない、淡々とした物静かなストーリー。
『スタンドバイミー』や『E.T.』、『エクスプローラーズ』のような
子供たちが主人公の名作も感じたし、
ある個所『ムーンライト』とまでは言い過ぎかな。
管弦楽器は『スウィングガールズ』まで思い出した(笑)
どきどきさせながらラストまで余韻を残す映画でした。
坂本龍一さんの遺作でしたか。
子供の頃、YMO時代に渋谷の東急ハンズで買い物途中に
握手してもらった経験も忘れられません。
時は過ぎるものですね。
地球もいつ滅びるものやら。
重いけど人生にとって観てよかった映画
最初は母親の視点
次は教師の視点
子供たちの視点
と
視点が変わることによって、誰にも「真の悪意」があるわけではないことがわかる
学校の腑抜けた対応に憤りと不信感を募らす母親
学校のことなかれ主義に失望し、誤解を生む態度をとってしまう教師
大人に本心を言えない子供たちの世界
物事の一面だけを見て、叩くのはたやすい
何かを守りたいからこそついてしまう嘘が誰かを貶める
この音楽知ってると思ったら、坂本龍一のピアノだったんだ
それぞれが抱える辛さも、いつか晴れるように
やさしい音色がそっとかさなる
怪物は何処へ
途中までは展開が読めなくて楽しかった
ずっと、「怪物」というタイトルに引っ張られて誰かが怪物のようにおかしくなるのか!?と思って見ていた。
みんな無意識に怪物だった。
クラスメイトの「ドッキリだから!ノリ悪!」と言ってた男子が私的には1番の怪物。
それぞれの視点が見れて、そういう事かぁ〜と色々な点で納得できて楽しめた。
ただ、最後が子どもの視点のま終わってしまったのが残念だった。
2人は亡くなってしまったんだろうけど、最後は母親や先生から見た視点というか、客観的に物語の終わりを見たかった。
さすが三人トリオ
是枝、坂元、坂本の作品。さすが
一部は母親目線 二部は保利の目線、三部は湊の目線。母親目線では演出がそうなっているからか学校の教師たちの理不尽、不誠実な態度に怒りしかもママ友からの言葉「保利先生のガールズバー通い」を聞くから尚更疑心暗鬼が募る。二部では保利の誤植探しの趣味が依里の作文から謎解きのキッカケを見つける、彼女の資本主義的思考につられる未熟さも三部では湊たちが死に興味をもち始めるまた性の目覚めなど洋画「禁じられた遊び」を思い出させる最後思春期の一段を乗り越えたあとの爽やかさ大人に一歩近づいた感じは洋画「スタンドバイミー」を彷彿とさせるラスト鉄橋のバリケードが消えていたことも印象的。
全体からはまず子どもは親の都合で生活しなければならないことと子どもは親のことを常に気にかけている親が喜ぶように悲しまないように冷静にみている何故靴の片方が強調されるのかシングルマザーシングルファザーを意識させるため、うなり笛は自分をもっとみてくれの合図トロンボーンとホルンの音色は真実を話したいの意味か。などまだまだ深く考えさせられることがたくさん詰まった作品。もう一度観なくてはと思わせるいい作品。
今日改めて感じたことを追記します
子どもに対する接し方に母親、父親、教師でそれぞれ温度差がある、その事を理解した方が子育てしやすいし子どもも窮屈にならなくていいよ。と伝えているのかも知れない。私の子育て観は 来るものは拒まず去る者は追わず なのですが。
全1025件中、1~20件目を表示