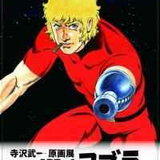TAR ターのレビュー・感想・評価
全361件中、281~300件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
映画史上最も衝撃的なラストって?
ケイト・ブランシェットの演技は圧巻
エンドロールみたいなのが最初から流れる
いかにも何かが起こりそう、個々のエピソードも詳しく語られる事は無く...
チェリストさんち誰も住んでなさそうだしまさかの夢落ち?かと思ったのですが、冒頭の飛行機のシーンは誰かにはめられたってこと?結局よく分かりませんでした
武装音楽祭
この映画はトッドとケイトから世界中の観客に投げかけられたメッセージだ。
人類史の黎明期から人間が直面してきた「権力」というテーマについて今こそ思索し、大いに語り合いましょう!
という投げかけだ。
物語の舞台をクラシックオーケストラ、主役をベルリンフィル主席指揮者としたのは世界を牽引する「最高権威」の象徴であり「権力の行使」などを画面の雰囲気や空気感といった感覚的なものでも伝えやすいからだと思う。
権威ある立場というのは気楽なものではない。バッシング対象になりやすいし、延焼速度は一般人より遥かに速い。
だから権威の座に立つ者は、常に己のパブリックイメージをコントロールする必要がある。
リディア・ターはそのコントロール能力に長けていた。さながら鎧を纏って武装するが如くだ。
しかし、風の噂にリディアが怖いとか職権濫用だとか聞いたのでよほど傲慢で気の強い棘のある人物かと思ったらかなり違うではないか。
悪意の編集でリディアを陥れたジュリアードの授業は客観的に見ると非常に親切な教師だと思う。
曲がりなりにも米国最高峰の音楽大学に指揮を学びにきていて、音楽とまったく関係ない理由から頑なにバッハを学ぼうとしない男子学生だ。嫌な教師ならばこんな不心得者はまともに相手にしない。しかしリディアは「指揮を学ぶならバッハにも向き合う方がよい」と辛抱強く諭す。
男子学生が性癖に対する偏見でバッハを否定するから「あなたが同様の理由であなたの音楽性を公正に評価されなかったらどうか?」と考えさせたのではないか。
子供のイジメの件だってそうだ。
相手の親や教師に言いつけてイジメ相手を追い詰めたりはせず、まずは
「もう二度とやらないように。今度やったら、わかるね?」と釘を刺しただけじゃないか。脅しちゃいるが、関係者を増やすよりは非常に優しい対応だと思うが。イジメっ子も親には知られたくないはずだ。
クリスタの件は「過去の過ち」だとしても「実際にはどこまでの事があったのか、或いはなかったのか」「どこまでがクリスタの勝手な解釈」なのかは不明である。
仕事に私情を挟んでいるのはリディアではなく周囲だと感じる。
副指揮者セバスチャンの更迭は、彼がその任に相応しい能力をすでに失っていたからだ。
市井のアットホームな楽団ならば温情優先だろうけど、世界最高峰のベルリンフィルですよ?
伝える言葉には配慮と労わりがあったしね。
リディアがフランチェスカを副指揮者に選ばなかったのは、彼女とフランチェスカの「仲」を疑う噂が楽団に蔓延していたからであり、リスクを避ける為であった。(実際シャロンの前に「関係」はあったようだし)
その点は可哀想だがフランチェスカだって「副指揮者になれたのはリディアの情婦だからだ」などとスキャンダラスなデマが蔓延ったなら未来は暗かったはずだ。
リディアを信じてもう少し待てばベルリンフィルのトップに立てただろうに、リディアに不利な情報をリークしたのは残念だ。
オルガの抜擢だって筋を通した根回しはしている。演者が誰かわからない公正なブラインドオーディションにて満場一致で彼女の技術が証明されたじゃないか。
トップチェリストの彼女だけがおかしな逆恨みはせずに大人の対応をしてくれて助かった。面子を潰されてショックではあっただろうけど、カラヤンでもバーンスタインでもない新しいベルリン・フィルをクリエイトするのが「仕事」なんだからさぁ。
1番哀しく思ったのはシャロンの言動だ。元々情緒不安定ではあるが、猜疑心から「嫉妬」にかられ、悪意の罠でボロボロのリディアから最後の救い(ペトラ)まで奪りあげて。
リディアが危機を相談しなかったのは心理的負荷が心臓などの変調を招くシャロンへの配慮もあっただろう。
打算が強かったのはリディアよりもシャロンやフランチェスカの方だ。シャロンはコンマス、フランチェスカは副指揮者の座を得る為に「権力者」と特別な関係になる事を受け入れた。
リディアは奔放な恋愛を楽しんだかもしれないが強要ではない。リディアだけが責められるべきではないと思う。
(5番4楽章はオルガをビョルン・アンドレセンになぞらえた隠喩だとは思いたくない。監督は「クラシックの中ではマーラー5番4楽章が1番好き」だそうなので、ヴィスコンティの事は「本当に気にしないで欲しい。本作とは関係ない」というメッセージな気がする)
トップに立つ者は常に孤独である。パートナーや家族、慕ってくれる仲間でさえも、その重責の凄まじさは決して理解出来はしない。
「権威」の椅子がいかに脆弱なものかを、本作は教えてくれる。
「悪意の捏造動画」や流言飛語一つで瞬く間に転落する砂上の楼閣なのだ。
攻撃のツールがSNSなど非常に現代的なのが観客の危機意識を喚起してくれる。
ラストは「落ちぶれた絶望」ではなく「次なる階梯に進んだ希望」だ。
「権力の楔」から解放されたリディアはもう重すぎる鎧をまとう必要はない。
「過去の音楽」ではなく「生の活気に躍動するこれからの時代の音楽」が彼女を迎え入れてくれた。元々、アフリカの音楽にもヨーロッパの古典音楽にも等しく価値を見いだすリディアだ。
登り詰めた者だからこそ見える次の草原が、彼女の前に広がっていることだろう。
監督はアジアやゲーム音楽を「田舎」「格調低いもの」だとは一切捉えていない。むしろクラシックという「権威の象徴たる過去の亡霊」に対し「今を生きる人達が作り上げる情熱的音楽」と見做している。コスプレは「音楽の為にわざわざ着替える(ドレスアップする)ほどの熱量を持って、音楽に向き合っている」という解釈だ。監督自身がそう語っている。
(モンハンが大好きで、その音楽にも高い価値を見出しているらしい。サブカルを蔑視する傾向はむしろ日本人特有の偏見かもしれない)
ここに記した「テーマ」と「ラストシーン」の解釈は監督とケイト・ブランシェッドのインタビューを参考にしているので彼らが表現したかったものと乖離してはいないはずだ。
彼らがターを通して描きたかったのは傲慢な女性の転落劇ではなくて「権力というものの本質」だ。
さて、ここからはトッド&ケイトへの私なりの回答。
彼らと同様に私もここ数年は「権力」について思索してきた。
私は昔から「7つの大罪」や「マズローの欲求階層説」が「人間と動物を分けるもの」を見いだす鍵になっていると思っている。
原罪やマズローだと少なくとも社会的欲求辺りまでは生命の進化の過程において自己の命を守り、種を保存する種を次世代に残す為に必要な能力が本能的欲求という形でDNAに刻み込まれていると思う。
そこでぶつかったのが「権力・支配欲の謎」という壁だったのだ。
人間関係のトラブル原因は大半がこの「支配欲」ではないか?という気がする。大きいところでは戦争だの、組織だの、イジメだの、ボスだの部下だの奴隷だのって話で誰でも納得だと思うが、小さいところでは「他者に対して腹が立つ」「なんかムカつく」というのも実はこれだ。
「相手が、自分が正しいと思っている行動をとらないから腹が立つ」のだ。
親が子供を叱るのもそう。パートナーに不満が溜まるのもそう。大抵は
「どうしてこうしてくれないの!」という感情に起因するのではないだろうか。
「自分の規範に他者を従わせたい気持ち」それはすなわち小さな「支配欲」なのだ。
この「権力欲・支配欲」というものは、一体なぜ私たちのDNAに刻まれているのだろう?進化の過程で命を繋ぐためのどのような役割があったのだろう?必ず何か「必要」があったはずだ。
その謎を解き明かせた時、我々人類は「権力欲」という罪を克服する事が出来るのではないだろうか?
そうすれば戦争も小さな諍いもない、平和な世界を築けるんじゃないだろうか?
この映画が多様な解釈が可能というのは具体的な案件に関してだ。
「権力」というものをウイルスに置き換えるとジェンダーやら差別やらパワハラやらそんなものは「咳」「鼻水」「発疹」などの「症状」なのだ。
症状への療法については千差万別で多様な解釈や議論が可能だが、本当に重要なのはそこじゃないんだ。
大元の「権力・支配欲」そのものの構造について俯瞰し、大局からその真実を解き明かす為の議論を重ねたい。
トッドやケイトと語り明かしてみたいものである。
トッドは64年、ケイトは69年生まれ。円熟した技量と最高の熱量。
今後、知性、心、技術は更に高みに向かうだろうが、創作にここまでの凄まじい熱量を注ぐ事は次第に困難になってくるだろう。
本作は2人それぞれにとって、彼らの人生における最高傑作になる気がする。
【追記】
最高傑作と言えばヒドゥル・グドナドッティルがこんなに凄いとは驚かされた!ウン十年ぶりにサントラ買うことにする。クラシックではマーラーが1番好きだからターの振る5番が収録されているのも嬉しい♪
大テーマ以外の部分では冒頭からラストまで全編通してユーモアも含む知的小ネタが散りばめられており、興味深いトピック満載でとても面白かった!
「過去の相手」から送られてきたサックヴィル・ウェストの「change」。読んでみたいと思ったけど邦訳でてないや。
レズビアン嗜好は理解し難いがサックヴィル・ウェストとヴァージニア・ウルフは読もうと思った。まぁ、愛の前に性別は些細なことなのかもしれんしなぁ、、、。
ケイト・ブランシェッドの【完璧】な仕事ぶりは驚愕した。生半可なプロ意識では出来るもんじゃない。
私もまだまだ頑張らねば、、、と喝を入れてもらった。うん、がんばろーっとw
ちなみに日本のモンハンコンサート「狩猟音楽祭」にてタクトを取るのは第1回シベリウス国際指揮者コンクールの最高位に輝く栗田博文。演奏は東京フィルハーモニー(大阪公演は大阪交響楽団)
(レビュータイトルは、これと個人的に好きな野阿梓の小説を絡めたものですw)
頂点から転げ落ちる
トップに上りつめた指揮者リディア・ターの栄枯盛衰を描いた、ヒューマンドラマ。
冒頭、いきなりエンドロールのように真っ黒のスクリーンに字幕、そして歌声。
上映ミスったのかと思った。
コロナの話もあるので、時代は現代。
頂点に上りつめた天才指揮者のター、セクハラ、パワハラ、そして告発されて・・・
3時間近い、長編の映画であったが、次から次へと展開され、
あわただしいけど、なんだかあまり理解もできず、
だんだん落ちぶれ、最期はアジアのどこぞへ。。。
途中で退屈になってしまった。
おまけに、英語の字幕は出ていたが、ドイツ語の字幕は少しで、結構省略され、
何を話しているのか、と気になった。
もっとクラシック音楽を聴きたかったかな、演奏しているシーンも。
観る前は、内容良ければ、サントラのCDでも買うか、と思っていたが、
買わずに退場となった。
ただ、これだけは言える。
主人公ターを演じたケイト・ブランシェット、演技はすごかった。
こればかりは拍手もの。
???
もっと指揮者の技術面を観たかった
リディア・ターのカリスマ性と作品の構造
「イン・ザ・ベッドルーム」「リトル・チルドレン」のトッド・フィールドが16年振りに監督した長編作品。
天才的才能を持つベルリン・フィルハーモニー管弦楽団初の女性主席指揮官リディア・ターの栄枯盛衰を、昨今のキャンセル・カルチャーを軸に、彼女が行使する権力とその結果を浮き彫りさせながら描かれる、いわゆるヒューマン・ドラマ、のはずなのだが…。
158分にも及ぶ、異色の長編。
一回の鑑賞では、散りばめられたあらゆる仕掛けに反応出来ないと思う。
冒頭、いきなり始まるエンドロールとバックで流れる謎の歌声。
誰が撮っているのか分からないリディア・ターの寝姿らしき映像とチャットの文字。
序盤に描かれる約8分にも及ぶリディア・ターのインタビューシーン。
そして、さらに彼女が教えるある講義の一部始終を描いている約10分を超えるワンカット長回しのシーン。
この冒頭のシーンはどれも作品の展開を示唆する重要なシーンである。
そして、それ以降も無駄なシーンは一切なく、すべて物語の展開に直結している。
この、本作の基軸リディア・ター役のケイト・ブランシェット。
「ブルー・ジャスミン」でのジャスミン役の印象は強烈だった。
本作はある意味近いキャラ設定ではあるが、そもそもトッド・フィールドはケイトを主役とすることを念頭に本作の脚本を書いており、またケイト自身もそれに応えるかの様に、ドイツ語、ピアノ、オーケストラの指揮者等のレッスンに励んでいる。
その結果、公開当初、本作のリディア・ターが実際の人物だと思われたらしいが、もちろん人物も話も架空である。
ケイト・ブランシェットの力量が遺憾無く発揮された本作の魅力は、話運びの方向性とミステリー的要素でもある。
ただし、劇中において謎は一切明かされない。
本作は2回、3回と観て理解を深めていくべきだろう。
また、遠慮なくネットやYouTubeの解説や動画を観て、劇中のミステリー部分を考察するべきだと思う。
そうすることで必ず2回目が観たくなる。
すると、散りばめられられた謎も少しづつ解けてくるはずだからである。
最後にある映画ライターの動画からの引用。
「TAR」と言う名前の由来を、トッド・フィールド監督は「アナグラム」であること以外ケイトには説明してなかった。
なので、ケイト自身は「TAR」を「RAT」のアナグラムだと思っていたらしいのだが、果たして真相とは…?
コレは難しくて,後から調べて行く内に…
あまりクラッシックのオーケストラ等の事は、人様に偉そうに語れる程詳しくは無い中&わりと話題になっていないかい?なんて安易な思いで鑑賞してみた。
一寸ケイト・ブランシェットの役の入り方には格好えぇんとちゃうの⁈と言いたくなる程…。
冒頭にも言った癖にと怒られそうだが,自分の為にも観た作品の内容云々を思い出す為にも記録させて頂こうかな?と…。
この手の作品は、交響曲5番とか云々を語れる程知り尽くしていないと語ってはいけない気もしたが…,
やっぱり気になった箇所を記録しちゃいます。
夜中に起きてしまっちゃう程,冷蔵庫の細かい音に迄敏感に反応してしまうのも職業柄仕方が無い事なのかもしれない。
結局の処、世の中の名だたる著名人は言い方非常に悪く言っちゃうが、一寸頭可笑しくて普通(って言う基準も良く分からん処だが…)では無い様な言動,行動を取ったりしていやしないかい⁈
ケイト・ブランシェットの魅力が見どころのすべて!
名女優ケイト・ブランシェット主演ということで注目してしていた本作。公開2日目の朝イチで鑑賞してきました。
ストーリーは、天才的能力と辣腕でドイツの有名オーケストラの主席指揮者となったリディア・ターが、公私共に多忙を極める中、かつて指導した若手指揮者の訃報が舞い込んだことをきっかけに、知らず知らずのうちに周囲の人間との間に生まれた軋轢や抱かせた不満が噴出し、しだいに追い詰められ、転落していくというもの。
言葉にすればこんな感じのストーリーだと思うのですが、映像からは細かい点が読み取れず、かなり難解な作品だと感じました。冒頭からいきなりクレジットが延々と流れるという挑戦的な構成で、その後の公開インタビューシーンでは音楽の解釈をめぐる抽象的なやりとりがこれまた延々と流れます。さらにスポンサーと思われる男性との会食シーンの会話へと続き、早くも脱落しそうでした。内容はまったく理解できませんでしたが、リディアが強い信念と絶対的な自信とプライドをもっていることは伝わってきました。
そんなリディアだからこそ、今の地位に上り詰めることができたのでしょう。しかし、一方で、考え方の合わない学生を否定、副指揮者を排斥、お気に入り奏者を重用、パートナーへ冷淡な態度、保身のために助手を冷遇と、高慢と専横の色を強めたリディアが転落していくのも、無理からぬことだったのだと感じます。
ただ、その観せ方がどれも断片的というか曖昧であったことや、登場人物が多くて相関をうまく整理できなかったことが、本作をやや難解にしていると感じました。中でも、転落のきっかけとなるクリスタやその過去、後半のキーマンであるオルガの背景などが、はっきり描かれず、観客の想像に委ねられているような気がしました。とはいえ、ラストはリディアのあくなき情熱と再生を感じさせる締め方で、悪くなかったです。
主演はケイト・ブラシェットで、本作の見どころのすべては彼女の魅力に尽きると言っても過言ではありません。まさに名女優の面目躍如です。他に、ノエミ・メルラン、マーク・ストロングらが脇をしっかり固めています。
理系(オタク)の私としては
答えはないけど
作中に明確な答えが示されていないので、考える余地が残された作品になっています。ただ、プログラムの監督インタビューを読む中で、この作品を作った意図は示されているので、気になる方は購入しても良いかと思います。
ネットでも様々な考察がされていますが、明確な誤りはあれど、どれが正解ということはないと思います。鑑賞終了後に、自分なりの解釈を人に話すところまでが、TARという作品の一部なのかなという気がしました。
観客もマエストロの掌で・・・
成功者、権力者の心の奥に潜む闇、ダークサイド、そして転落していく姿が、周囲の人々の憧れ、妬み、嫉妬などを絡めて描かれています。主人公が抱える罪悪感からくる悪夢の映像をはじめ、主人公が精神に異常をきたすサイコスリラーとしての面白さ、Metoo運動によって女性である主人公が失脚するという時事的な社会性、ケイトブランシェットの素晴らしい演技、クラシックな名曲の数々と、演奏シーンにおけるダイナミズムなど、エンタメとして非常に面白くできていると思います。世間ではケイトブランシェットの演技ばかり注目されているようですが、やはりリディア・ターというキャラクターと、この傑出した物語を創造した監督のトッド・フィールドこそ最高のマエストロです‼️
意思でなく才能が人生を選ぶ場合もあるのでは
◇ストイックという生き様
クラシック音楽の積み重ねられた歴史、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団という最も保守的で権威的な組織世界。実力と権力を手にした女性指揮者の姿を克明に彫刻するように描いた物語です。
音楽とは、微妙な音程、音色、テンポ、多彩な音の集合が配合されて、経過していく時間の芸術です。繰り返されることを大切な要素としている世界でもあります。演奏者は何度も何度も同じフレーズを練習し、聴き手は次に繰り返されるフレーズへの期待感とともに控えています。
そんな音楽、音そのものと人間の存在みたいな高尚なテーマから導かれていきます。主人公の指揮者リディア・ターにとっては、人間関係や世間の評判などは二次的なもので、自ら描く音楽の理想像の追求こそが自分の人生の本質なのです。
伝統を重んじる保守的なオーケストラの世界と対比して描かれる現代のSNS動画拡散と書き込みによるバッシング世界。あまりに、浮薄で移ろいやすい世間の評判が、無責任な匿名性を帯びてネットという仮想空間に不気味に漂います。
世間から見れば、薄情で自己本位とされる生き様かもしれません。一方で、主人公の過剰にストイックな生き様に惹きつけられて、同じ目線で音楽の世界の奥深く没入していく感覚が心地よいのです。その厳格な生き様が、女優ケイト・ブランシェットと重なり合って、ハーモニーを奏でます。
終章、観客席のコスプレイヤーたち。あれは、現代の聴衆たちのモンスター性とか、音楽を消費していく姿勢とかを象徴するものなのでしょうか。鑑賞しながら、自らにも問いかけさせるような仕組みを感じました。
ラストの気味悪さ
ラストの気味悪さが、あとをひく。
それでも指揮者としての立場を愛する世界観が不気味で、哀しく、観客に背を向けている彼女にはスコアと演奏者さえいればいいのだ。
前編のアカデミックな内容が続き、睡魔と闘わなければならないかと思ったが、特に説明のないまま話しは加速する。
ターのパワハラに対しての報復から、立場をおわれていく。
音楽は全編リハ風景のみだが、ダイナミズムを感じる部分を差し込んであって、鳥肌がたった。
私の理解力不足では謎が多く、もう一度観たいと思っている。
『リディア』、もっと音楽に没頭しなさい
『リディア・ター(ケイト・ブランシェット)』は時代が産んだマエストロ。
「ベルリン・フィル」初の女性首席指揮者であり
作曲もこなし、アマゾン原住民の音楽にも造詣が深い。
冒頭、対談形式のセッションでは
彼女の経歴が延々と語られ
『レナード・バーンスタイン』の弟子ともされている。
劇中名前が挙げられる多くの人物は実在。
それを巧く絡めているため、
架空の主人公があたかも現実に存在するように錯覚してしまう脚本の妙。
彼女の楽曲に対する解釈は
同業者が教えを乞うほど独創的。
自己プロデュースも完璧で、
自伝を出し、
出資を募り女性指揮者を育て上げるプロジェクトを立ち上げ、と
次第に自身の権威を高めて行く。
私生活ではレズビアンを公言。
現在のパートナーは楽団のコンサートミストレスであり
また、養女の溺愛ぶりも膏肓に入っている。
その一方で、得た権勢を自身の欲望の為に行使、
意にそぐわぬ時は容赦なく切り捨てる非情さを持つ。
そんな彼女が、
新曲の作曲の行き詰まりと、
〔マーラー 交響曲第5番〕のLIVE録音へのプレッシャーから精神の均衡を崩し、
加えて私生活の、とりわけ性的嗜好の絡むスキャンダルから次第に追い詰められていく。
嘗ての音楽家と「ナチス」との関係性が
『フルトヴェングラー』や『カラヤン』の名を示し語られる。
〔マーラー 交響曲第5番〕は〔ベニスに死す(1971年)〕でも使われ、
そこからは撮影時の『ルキノ・ヴィスコンティ』による男優の扱いを思い出させる。
力は「セクハラ」や「パワハラ」と
どれだけ結びつき易いかの暗喩が次々と提示され、
それは『ター』とて例外ではない。
権力者が次第に腐敗する世の常を非情な眼差しで描く。
『ター』が堕ちて行く過程は、
あくまでもスキャンダルによる部分が大きく、
〔ブラック・スワン(2010年)〕のように芸術に惑わされた末による純粋な悲劇とは異なり
もやもや感は残る。
また『ケイト・ブランシェット』からは
〔ブルージャスミン(2013年)〕での演技に通底するエキセントリックな印象を受け、
新たな境地とは言えぬうらみがあり。
その一方で、同作の監督『ウディ・アレン』による性的虐待を想起させる
副次効果もあるのだが。
男がふつーにやってる事をLGBTに変えただけ
よくわからず疲れた
名門オーケストラで、初の女性首席指揮者になったリディア・ターは、天才的な能力とプロデュース力を持ち、マーラーの交響曲第5番の演奏とその録音に向けての準備によるプレッシャーに苦しんでいた。レズを公言してた彼女は、ある時、かつて彼女が指導した若手指揮者が自殺し、その要因がターだと告発され・・・てな話。
ケイト・ブランシェットは長いセリフも流暢に話してて素晴らしかったが、いかんせん、ストーリーがわかりにくい。
どうなるのだろうと観てたら突然別カットになって、モヤモヤが続いた。
最後はどこ?アジアのどこかに招かれたんだろうけど・・・難しかった。
女性でも名門オーケストラの首席指揮者になれる、という事で素晴らしいオーケストラの演奏が聴けるのかと期待して観に行ったら肩透かしだった。
好きな女性をコロコロ変えて嫉妬されたって事?
顔を怪我したのは男に襲われたらしいがそのシーンは無し?
難しくて、ずっと???な作品で疲れた。
全361件中、281~300件目を表示