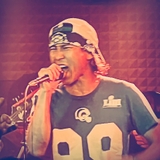マイスモールランドのレビュー・感想・評価
全122件中、61~80件目を表示
嵐莉菜さんに釘付けでした
とにかく今や日本の片隅に生きているだけで様々な問題が浮かび上がる破綻の国・日本。かつての繁栄もここ20年くらいで地の底に沈み、入管問題も今まさにそこにある危機的問題。
そんな中、ハーフモデルで充分な活躍ができそうな高校生の女の子が普通に進学に悩み、共同体で生き、恋をする。ただ彼女はクルド難民の子だった。
ごく普通の家族がなんの説明もなく、いわば日本のよくわからない「入管」に引き裂かれます。この映画はこの問題の「なぜ」に突っ込んではいきません。「クルド」もくどくど説明はしません。是枝作品と同じく、状況を、いわば普通の女の子の悩みとして捉えます。もうちっと弁護士がんばれ、と思わざるを得ませんが、まあそんなもんでしょう。しかし、いかんせん背負うものが大きい。
1時間くらいすると「誰も知らない」的な暮らしになり、逆に一瞬妹さんが少し解放されたかのような態度になるのだけど、本作品は割とその隔絶された世界での描写が是枝作品ほどあざとくなく、実直過ぎる感じがある。固い、というか。ただ、ぽっかり理不尽の中心にある「日本の入管」だけがブラックホールのように横たわる。そしてなんの確証もないが、父親が強制送還されればまるで恩赦のように子供にビザがでるという。。なんたる理不尽。しかしその理不尽に従わないと生きてはいけない。まるで現代の楢山節考。もっと問題になればいい。
ただ、一言だけ言えるのは、とにかく主演の嵐莉菜さんに釘付けだった、ということ。弱さと強さと大人と子どもの両方の魅力で、俯いた姿からのラストカットの眼差しは、予想を超える神々しさがありました。
高評価なのはわかる。でも私には、う〜ん⁉。
問題提議の映画だ。見てて辛かった。17歳の女子高校生に背負える問題ではない。名古屋の入管収容施設で、職員による虐待で女性が死亡した事件もあった。未だに我が日本政府は、難民に対し厳しい態度を崩さない。
難民解決の糸口が見えないので、物語の終わり方も宙ぶらりんとなる。落とし所が見つからないのだ。だから、問題提議で終わってしまう。そこが惜しい。日本人ならば、一家心中で結末をつける方法だってある。が、外国人には使えない。後味が良くないので、私はスッキリしたい。もやもやとして、記憶に残るのは主人公の思い詰めた顔だけだ。
私は難民受け入れに賛成派だ。日本は単一民族だなんてハナからでたらめだし、日本文化を興隆させるには他からの血を入れるのが一番だ。アメリカを見習って欲しい。二十世紀初頭、アメリカは文化後進国だった。移民、難民、亡命者を受け入れて文化先進国となった。日本の映画で、監督が外国人(在日朝鮮人は別にして)なのはあまり聞いたことがない。アメリカ製映画では当たり前の状況だ。
主人公を演じた女優は美人で、昔CMモデルで良く目にしたヒロコ グレースに似ている。
To the incompetent Japanese government
Do something for the refugees living in Japan who are suffering from living. Think of them as if they are yourself. This is what's happening to our family who really needs a help. Decide and do something by your own thoughts.
Ironically this movie is recommended by AGENCY FOR CULTURAL AFFAIRS ,Ministry of Education which is a part of Japanese government. They won’t do anything to refugees.
日本人全員が、この「ハッピーエンド」のない物語の共犯者である
ノンフィクションより強く訴える
日本の入管に杉原千畝はいないのだ
内容が今年(2022年)の2月に公開された映画「牛久」に直結していると感じた。「牛久」は茨城県の牛久市にある不法滞在者を収監する施設、東日本入国管理センターを描いた映画だ。
収監施設は閉鎖的な空間であり、必然的に職員も収容者もストレスが溜まる。そこで職員はストレスを収容者に対する暴力で解消している。ナチスのアウシュビッツ収容所と同じだ。つまり牛久の入国管理センターの実態は、強制収容所である。
牛久強制収容所の管轄は出入国在留管理局、つまり入管だ。入管は管理局であって援助局ではないから、滅多に難民認定しない。日本の難民認定率は0.4%で、欧米の15%〜50%に比べて極端に低い。ましてクルド人は国籍がまちまちだということもあってか、これまで一度も入管に難民認定されたことがない。2005年には国連難民高等弁務官事務所が難民と認めたクルド人親子が、入管によって強制送還された記録がある。
今年の5月13日、入管は前年2021年の難民認定者数を発表した。難民認定されたのは、2020年から27人増えて74人だった。それでも認定率は0.7%だ。難民認定外で在留を許可されたのは580人とのことだが、この数字は、6ヶ月しか滞在許可を与えられない緊急避難措置の対象者を含めた水増しではないかとの疑問がある。しかし入管は内訳を発表しない。
入管は難民に厳しい一方、技能実習生の受け入れについては甘い。アベシンゾウが人手不足という産業界の意向を受けて、入管法を変えたのだ。そして「技能実習生」という名の奴隷労働者が日本にやってきた。3年間の実習期間が終了したら、2年間は延長して働くことができるが、その期間が過ぎたら、自動的に不法滞在者となる。緊急避難措置の6ヶ月を過ぎても日本にいたら、見つかった場合に強制送還となる。
見つからなくても、日本国籍も住所もない外国人には仕事の機会はない。帰国するか、自殺するか、犯罪に走るかのどれかだ。実際に外国人による犯罪の半数以上は不法滞在者によるものである。こうなることは目に見えていながら、入管法を変えてしまったアベシンゾウの罪は大きい。多分バカだから何も考えていないのだろう。
本作品は深刻な難民問題を扱っていながらも、高校三年生の青春を明るく、しかし現実的に描いている。主演の嵐莉菜は初めて見たが、なかなかの演技力だ。美人すぎて当面は役柄が限られるかもしれないが、北川景子みたいにエキセントリックな役(「謎解きはディナーのあとで」「家売るオンナ」など)を演じて一皮むけることもある。美人に演じられない役はない。
冒頭の落書きみたいな線が埼玉県の形だとわかった人は沢山いたと思う。東京出入国管理局さいたま出張所はさいたま新都心駅から徒歩8分。さいたま第2法務総合庁舎内にある。働いている人は法務省の職員だから、基本的に解雇などはなく、給料が遅れたりすることもない。役人だから手当がたくさんつく。安全圏で暮らしている訳だ。職員から見たら難民の状況など対岸の火事である。毎日の職務さえこなして給料をもらって安全無事に生きられればそれでいい。強制送還された難民の運命など知ったこっちゃないのだ。大半の職員がそう考えているから、難民認定率が0.4%なのだろう。日本の入管に杉原千畝はいないのだ。
【観るべき映画】 難民認定の難しさ、そして理不尽さを知りました。
ドキュメンタリーではないことを強く意識して観るべき
日本に在留する外国籍の人はたくさんいるが、クルド人と接したことのある人は少ないはず。少なくとも私は話したことがない。そもそもクルドって国ではなく民族だから、その点でも実態がわかりづらいと言える。そして、日本での難民申請はものすごく通りづらいってこともとても重要なポイント。
そんなことを知っていたとしても、この映画で描かれる現実には驚かされる。いや、フィクションなんだけど、これが現実なんだろう。子どもが日本での大学進学まで考え、下の子は日本語しか理解できないという状況。それだけ日本で生活の基盤が築かれていることの描写がうまい。そんな状況で、親の難民申請が通らず、一家の在留資格が一気に危うくなるという展開。日本における外国籍の人間にとって在留資格ってものがどれだけ重要なのか改めて思い知られる。
それでもこれはドキュメンタリーではないので、ぼかすところはぼかした上で物語は進む。そういう意味であの家族が直面している問題が、わかりづらくなっている印象も受けた。裁判って何を争うの?とか、ビザがおりたとしてもその後は?とか。でもそれも仕方ない。難民問題や在日クルド人の問題をアピールする映画ではないから。そういう側面もあると思うが、描かれていたのはサーリャの青春だと感じた。恋もするし、バイトもするし、進学のことで悩んだりもする。そして、クルド人としてのアイデンティティに苦しむ姿も描かれる。
なんて過酷なんだ。心が折れるよ。他人に簡単に頑張れなんて言われたら、頑張ってます!って言い返したくなる気持ちもわかる。正直、あの子達に明るい未来が待ち受けているのかはわからない終わり方だったが、サーリャ役の嵐莉菜の表情を見ると希望は残っている気がした。そう信じたい(フィクションだってのに!)。
彼女の演技だけでも観る価値はあるかもしれない。キレイって表現を超える絶対的な魅力があった。今後が楽しみだ女優だ。というか女優を続けてほしい。
極悪人がいないのがかえって辛い
池脇千鶴、韓英恵、サヘル・ローズって、これで私が観に行かなかったらおかしい。キャスティングありがとう。奥平くんも素敵だったし、主演の嵐さんも学校のシーンとかすごく自然だった。
誰かものすごく邪悪な人がいるんじゃなくて、無関心だったり少しだけ偏見を持っていたりする人たちがいて(聡太母の反応の仕方、怖い)、これはかなりリアルな描き方なんじゃないかなと思った。難民問題のリアルを私が知っているわけじゃないけど。悪いのは特定の誰かではなく制度で、だから問題は根深く大きいのだということを理解させられる。
苦しい環境だからシンプルなガール・ミーツ・ボーイが輝くし、そこが輝くから苦しさもより伝わる。聡太のどうしようもないノンキさに少し腹立たしいような気持ちにもなるけど、そこに救われるサーリャもいたんだろうな。
マズルム父さんは、日本語を話すときのほうが、クルド語のときより高圧的でなく穏やかな気がした。“彼は日本での生活に自信がない”という演出意図だったかもしれないけど、私は日本語を高くて優しい声で話すときのお父さんのほうが好きだったな。
心に響きました。素晴らしい。
分福の新鋭、川和田恵真監督のデビュー作。難民認定されず、仮放免で理不尽に追い込まれる日本に滞在する外国人の問題は、昨年、入管で亡くなったスリランカ人のウイシュマさんの件でも記憶に新しい。映画「東京クルド」(必見の映画です)ではドキュメンタリーで窮状を訴えていたのに対し、本作「マイスモールランド」では、若い俳優たちの熱演による物語として描かれる。僕はどちらが良いというつもりは毛頭ないのだが、難民問題に関心がない人たちが足を運ぶ可能性を考えると本作に軍配を上げる。移民問題は、もはや日本社会の中心にあると言ってよいと思う。難民問題をはじめとし、外国人技能実習制度でも、様々な問題が起こっている。国のあり方として、また国民の意識としても、人権に対する関心の高まりは必要不可欠だと思う。そういう意味でもこういった映画がもっと多く出てこなくてはならないはずだ。
最後の眼差しが希望であり祈り
異質の他者を受け入れる
まず映画としての完成度の高さに驚かされる。伏線の張り方が見事である。都県境表示に二人で手形を残すシーンも、後の場面ではサーリャの今後を予感させる不穏な描写へと変化する。台詞や描写が説明的と言われる方もいらっしゃると思うが、私は一つひとつが丁寧に、複雑に絡み合ってストーリーが展開しているように感じた。これが商業映画デビュー作とは思えない、川和田監督の手腕が光る映画だ。また一つ大きな才能が日本映画界に生まれたことを大変喜ばしく思う。
この映画で描かれていることは「居場所」だ。国を持たない最大の民族と言われるクルド人はまさに「居場所のない存在」である。何らかの形で居場所を奪われた彼らに、我々日本人は居場所を与えることができるのか…。私も本作を見るまで、日本における難民を取り巻く問題にあまり関心がなく過ごしてきてしまった。これをきっかけに興味を持って調べてみたが、その不条理さ、問題の根の深さに無力感を覚えた。
川和田監督が各方面のインタビューで「知ってほしい、忘れないでほしい」と語っているのが印象的だった。知ることの積み重ねで何かが変わっていくと思う。しかし、それだけでは足りない。知ること、そして考えることは「祈り」に近いものだと思う。ラストカットにて、サーリャは祈ることを辞め、前を向いた。これは祈りを捨てることではない。祈りを胸に抱きながら、彼女は歩き出すのだろう。行動していくのだろう。だからは、私も行動しなければならない。
まず知ることから始めようと思う。そしてそれを伝えていこうと思う。本作のクルド監修であるワッカス・チョーリャク氏が営むクルド料理の店が十条にあるそうだ。ぜひ行ってみようと思う。
ドキュメントじゃないよ。
等身大のクルド人家族の物語が胸を打った。日本人全員が見るべき映画...
等身大のクルド人家族の物語が胸を打った。日本人全員が見るべき映画。
日本人は皆典型的で酷い。カラオケボックスでのパパ活男は本当に最低。そんな中、彼だけが素敵だ。
一生懸命生きている人をサポートできない日本という国。
不法就労に関してもおそらくヨーロッパならもっと寛容だ。
永作の振る舞いは、見た目、彼女に寄り添ってるだけ酷い。本当に日本的。
お父さん、面白い人だねという、彼のセリフが素敵。お父さんは味があって、娘を殴るのは許せないけど、いい人。ラストに繋がる石の話、ビズ、それと対照的なハグの話、ドイツのエピソード、ラーメン。忘れられない。
救いようの無い展開。 観ていて辛くなる映画、本年度ベスト級!
埼玉県に住むクルド人家族の苦悩を描いた作品。
長女の高校生サーリャを中心に進む展開。
サーリャ役の嵐莉菜さんが美しい。
日本とドイツのハーフのモデルの方だった。
勉強も出来て小学校の先生を目指すサーリャ。
コンビニでバイトして学費を稼ぐ中、家族が移民権を失いビザも失効される展開。
働く事も他県に移動する事も禁じられ八方塞がりな状況。
生活の為、働く父も違法で捕まり拘留されてしまう状況。
家賃も払えず最悪な状況が辛い。
そんな中、バイト仲間の崎山との恋愛ストーリーが同時進行。
辛い中、二人のちょっとした行動に心が休まった感じ。
家族の為に取った父親の選択が辛すぎた。
終盤、サーリャの弟がジオラマを作って遊ぶシーン。
石をそれぞれの家族に見立て、ジオラマに自分の好きな場所に石を置くシーンに泣かされた。
鑑賞前にクルドと移民の事を予習した方が良かったかも( ´∀`)
本作の良否を言うのは自分ではなく・・・
「難民」の問題も、ウクライナ「避難民」問題が生じため、今や新しいフェーズを迎えているが、政府はどういう詭弁で乗り切るつもりだろうか。
本作を見終わった後の第一印象は、問題点がシンプルに整理され提示されているようだが、劇映画としてはこれといったインパクトに欠ける、だった。
しかし、しばらくすると記憶の中で、妙にジワジワ味が出てくる。
電気代節約のため、冷房のスイッチを入れたり切ったりするシーン。
クルドの同胞男性を拒絶するシーン。
埼玉と東京の境を示す看板の手形は、問題の本質を一撃で表した、せつなくも特筆すべき名シーンだと思う。器物損壊を言うなら、人権損壊も見なければならないだろう。
彫りの深い顔立ちの嵐莉菜は、表情を作るのにやや時間がかかり、それが微妙な“間(ま)”になって、主人公の内面を暗示しているところが、本作のテーマに合致していて良かった。
初演技とは思えないほど器用で真実味があるし、この先おバカなトレンディー作品だけでなく、本格的な演技派でも売れて欲しい気がする。
とはいえ、本作の良否を言うのは自分ではないだろう。
日本の難民の人たちがどういう印象を持ったか、知りたいところである。
ノンフィクション
テーマや役者といった素材は良いのだが、、、、
在日クルド人の少女が、在留資格を失ったことをきっかけに自身の居場所に葛藤する姿を描いた社会派ドラマ。というのがあらすじの文句ですが、ストーリーはその通りです。
う〜ん、評価が高い作品ですが、好みではない。でも良い作品なので、なるべくネタバレ無しで。取り上げているテーマは良いし、役者も魅力的。映像の魅せ方としても楽しめるけど、、、映像としては文句なく良作だとおもいますが、エンタメ性が欠けています。
葛藤を描くならカタルシスがないと、みている側に届かない。アカデミー作品賞の「コーダ」に近いテーマで、なんとでも解決法を提示できるはず。それが作り物っぽくっても、逆手にビターなメッセージを入れることだってできる。
社会派ドラマとは初めから思えません。難民政策やらクルド問題なんてフレーバー的にしか語らず、美少女と安っぽい恋愛と青春ものでまとめていますしね〜。エンタメでも社会派でもないなら、何を創りたかったのでしょうか。
せっかく良い題材と魅力的なキャストに高い映像力があるのに勿体ない。例えが雑ですが、良い素材とシェフが見つかったので「あえて素材の味を」そのままで出された料理、って感じです。生食が好きな方には合うでしょうが、せめて「何味」が欲しかった。
まあ主演の女の子は可愛いし演技も上手いし、難民に日本は厳しいよね、って素材は分かるのですが、そこにどんな味付けするのが、伝わって来なかったです。
全122件中、61~80件目を表示