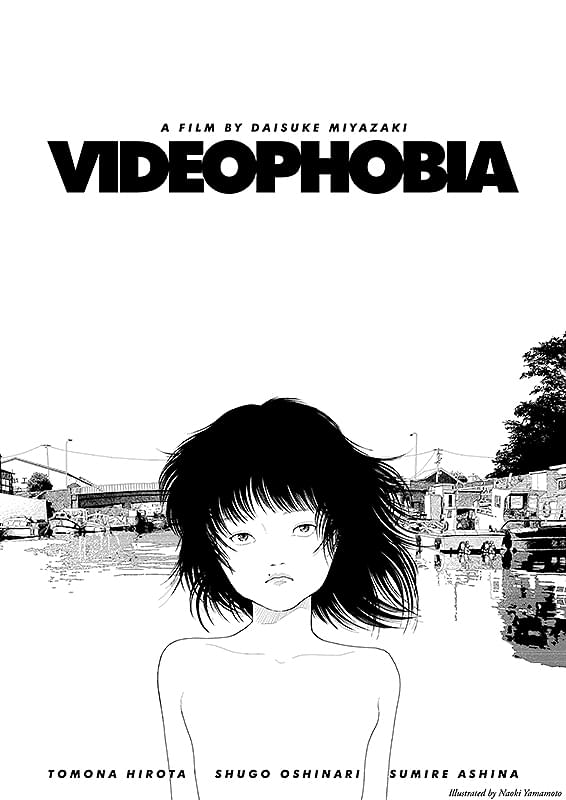ネタバレ! クリックして本文を読む
人間を見守る天使の瞳が、人々を監視するカメラアイとなって地上を覆うさまを、ヴィム・ヴェンダース監督は『ベルリン・天使の詩』から『エンド・オブ・バイオレンス』へのシフトで描いた。恋人が愛しているのは実際のところ自分の何なのか、と錯乱した女が整形を試みる姿をキム・ギドク監督は『絶対の愛』で描いた。そして、『VIDEOPHOBIA』になると、積極的にプライバシーを晒し、時にはプライバシーの切り売りが商売にさえなるネット社会で、不意にプライベートの情事をネットに晒された主人公が、最終的に整形で別人になる姿を描く。
監視を私たちは内面化した。内面化した末に順応し、見られることに無頓着になった。あるいは、快感になった。主人公の青山(朴)愛が、冒頭でPCの画面越しに肢体と自慰行為を見せるチャットレディのアルバイトをしているシーンがある。そして、行きずりの男との情事をネットのアダルトサイトにアップされ動揺する。ここには、パブリックとプライベートの揺らぎがある。ネット社会はその境界を曖昧にする。また、その動揺を抱えて参加した被害者同士のピア・カウンセリングの場で、リベンジポルノの定型的な被害体験を聞かされる。そしてまた、被害を訴えた警察には、ポルノ投稿サイトの年間総視聴時間が膨大であることを告げられる。そう、被害者当人にとって切実な問題が、社会から見ると「ごくありふれている」という残酷さ。
さて、主人公は女優の卵であり、演技のワークショップで別人を演じたり、アルバイトで着ぐるみを着て働いている。そしてこれは微妙なところだが、「在日」という属性を持つ。つまり、自分でない者になりたい、というアイデンティティの揺らぎがある、とも見える。そうした願望は、まさかではあるが、情事の動画を晒される、というトラウマティックな体験がきっかけで叶うことになる。強烈なアイロニーだ。
プライバシーとテクノロジーが交差する地点に「見られることへの恐怖」が生じる。しかしその「恐怖」がパッケージされて売られる社会のさらなる恐怖を私たちは知っている。
ところで、青山が自分だと思われる女が映っている動画を見返していると、明らかにアングルがおかしいのだ。とても盗撮で撮れるような映像ではない。彼女は何を見ていたのか。「真実」も「本質」も見たくない、刺激的な「虚像」だけを見せてくれ。ネット社会はそんなニーズに応え続ける。






 リリイ・シュシュのすべて
リリイ・シュシュのすべて サムライせんせい
サムライせんせい ひかりをあててしぼる
ひかりをあててしぼる アコークロー
アコークロー #ミトヤマネ
#ミトヤマネ TOURISM
TOURISM 大和(カリフォルニア)
大和(カリフォルニア) 5TO9 ファイブトゥナイン
5TO9 ファイブトゥナイン 夜が終わる場所
夜が終わる場所 ジョーカー
ジョーカー