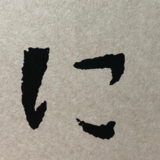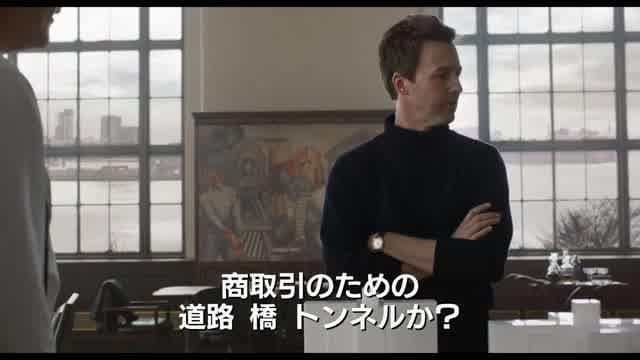マザーレス・ブルックリンのレビュー・感想・評価
全50件中、21~40件目を表示
私たちは毎日戦っていると。
ライオネル( Edward Norton)は母親に小さい頃死なれて、探偵事務所経営のフランクに拾われ親か友達にようにして育てられた。その、フランク(Bruce Willis)が殺され、そこで働く彼の謎解きが始まった。ライオルはトゥレット障害 Tourette’s syndorome(瞬き、顔しかめ、首ふり、肩すくめ、咳払い、鼻鳴らし、叫び声、汚言症) の障がいを抱えていて、それにOCDもあるから、物事に対して執着心があり、これらの才能でフランクの殺人事件を解決する。
ライオネルが人と話すと、相手は『なに言ってるんだよ』というから、よっぽど彼を理解してあげていないと付き合うのは難しい。だから本人はガールフレンドともうまくいかなかったと。かれのこの障がいを『人は毎日戦ってるのよ』だから、みんな同じそれぞれ違った問題(障がい)をかかえているのよというようなことをローラ(Gugu Mbatha-Raw)はいう。ーー人は皆同じだという意味のこのシーンが好き。
驚いたことに悪人役のモーゼス ランドフ(Alexander Rae Baldwin)にとってはすぐライオネル才能を見つけ出し、障がいに関して興味を示さずどうでもいいようである。人種差別はするが、障がいのある彼には弱みを握られているせいかどうかは知らないが、モーゼスはDeveloper (街や土地を開発する不動産会社)人の良さや才能をすぐ見つけ出す能力がある。一般論だが、障がいを持っているの人はどこか他のところに長けている。フランクがミーティングでライオネルに公衆電話の裏にいて影の存在になってもらうところがいい。ーーいいアイデアだね。
この映画を見始めて、20分で飽きてしまって、やめようかなと思った時、興味のある内容に入っていった。すべての映画が政治と結びつくと絶対飽きないで見られる。私にとって、出だしのスローな展開が辛かったけどこれは小説の映画化だからね。(これは90年代の小説を映画
の脚本にノートンが書き換えた)小説は読んでいないが、ノートンの脚本は小説のようで好き。内容が深くて言葉で表現する映画で、かれは才能あるね。
この映画の好きなところは:
50年代のニュヨーク開発(ブロンクスやブルックリンなど)で、橋や公園を作ったりしたのは低所得者の人の住まいが多いスラム街(?)の住民を強引に出させ、そこを取り除き、再開発したものだが、アクティビストやそこに住んでいる人々は、「我々はスラムに住んでいるんではなく,ここに住んでいるのは労働者だ」と。そうだと私も思う。下から上への動きでこういう草の根運動から私は力をもらう。
アクティビストは『ニグロ(1950年代の黒人はこう呼ばれていた)を撤去させてる」と憤慨。現実はローラ曰く、ニューヨークに公園は255あるが、ハーレムに公園は一つしかないと。
50年代のデベロッパー(不動産会社)は公園や橋を作ったが(ここから収益を上げるつもりで)、今の不動産会社は、低所得者の住んでいる地域を一掃して、住まいを増やしたり、企業や商店が入れるビルを作ったりしている。住まいは所得が高くないと入れないような高額な住まいやアパートだ。これは、「gentificationジェンティフィケーション」といって、低所得者、特にマイノリティーを追いやって、そこを再開発する現在の社会問題と似ている。追いやられた特にマイノリーティーは十分に生活できなく、他の州に引っ越して生活できればいいが、再開発によって生活できなくなった人々は車の中に住んだり、ホームレスになったり、遠距離に家を購入して、そこから例えば、月曜日の朝早く通って、どこかに車を止めて寝て、金曜日に遠距離に購入した家に帰っていく。50年代も今も同じなんだな!
当時のニューヨークのハーレムのジャズは最高だ。
トランペットのソロはWynton Marsalis. https://www.youtube.com/watch?v=ST5NgujQiMk
https://www.youtube.com/watch?v=P09T9JYvo2w
最後はThom Yorke https://www.youtube.com/watch?v=gFjep-baGuU
の曲でライオネルの障害があるための寂しさや孤独感をよく表しているとノートンかだれかが話していた。Frederick Law Olmsted (April 26, 1822 – August 28, 1903)の名前が出てくるが、かれはニューヨークのセントラルパークやナイアガラの滝の公園を造園した人。
Robert Moses, (December 18, 1888 – July 29, 1981) というデベロッパー(不動産業者)であり、政治的にもボスであった現実に存在した人がモーゼス ランドフに(アレック ボードウィン)に近い存在だと。
俳優エドワード ノートンが脚本、主演、監督を手掛けた映画で映画俳優や声優だから名前はしっているが、ここで彼の才能をまた開花させたと思う。収益をあげた映画ではなかったが、彼の場合、やりたいことをやるような人に見えるので、これが、いい足がかりになると思うが(?)かれは、日本に留学したこともあり、日本びいきで伊丹監督の『タンポポ』を好きな映画の一つにあげている。
じきに彼の声が聞こえるよ。「しっかりしろ。前を向け」って。
作品の持つ雰囲気がとてもよかった。
マザーレスはどこに…
エドワードノートンは好きだし 彼とニューヨークも好きだ jazzだし…好きな要素ありありだったけど なんか惜しい
トランペッターはとてもカッコいい 謂わばCOOLな役だけど それがカッコダサかった 特に最後トランペットで殴って 人倒せるかなぁ… その後のセリフもすべってる
そして、残念なのは 孤児四人の繋がりは特別なものなのに それが表れてない。
一人が裏切る?のもありだけど もっと4人のキャラや絡みがあっても題名からも思う。
あと 説明し過ぎなのが色々ないい要素を壊してしまっている気がした あの病気を絡めて起きる何かアイディアがあっても良いのに 「これは病気なんだ」っていちいち説明したりして…
ラストもなんか25時とかショーシャンクに似てるような…
けなしてばかりだが、それはエドワードノートンには期待してしまうからで…
終わって ストーリートミュージシャンの酷い演奏を耳にして 彼のように首を振りながら やり過ごした。すっかり影響されてる自分がいた。 チック症というのは 内外部からの不協和音に対する防御なのかも知れないなあ なんて思いながら…
中川家?
文句なしに面白い作品である。144分という長めの映画だが、あっという間に感じる。ウィレム・デフォーとアレック・ボールドウィンのランドルフ兄弟が悪役としてはややステレオタイプというきらいはあるものの、総じて気の抜けない作品だった。
レイモンド・チャンドラーのハードボイルド小説に雰囲気が似ていると思った。フィリップ・マーロウという探偵が主役の一連の小説だ。第二次大戦中から戦後にかけて書かれており、本作品と時代が近い。マーロウの台詞として有名なのが「男はタフでなければ生きていけない。優しくなければ生きる資格がない」という言葉である。森村誠一原作の角川映画「野性の証明」のプロモーションでも使われて有名になった台詞だ。
本作品の主人公ライオネル・エスログの雰囲気もどことなくフィリップ・マーロウを思わせる。頭の回転が速くていち早く真相に辿り着くが、俺が俺がと自己主張するタイプではなく、控えめで人にやさしい。好感の持てるキャラクターである。マーロウも銃を持っていたが滅多に撃たなかった。その点も似ている。
黒人差別、迫害、権力者の横暴、業者との癒着と、当時の政治社会問題を背景に、ボスが殺された事件の真相に迫っていくエスログ。ボスだからといって必ずしも絶対視も神聖視もしない。仲間だからといって全面的に信用するわけでもない。ひたすら事実だけを積み重ねて推理していく。エスログを敢えて精神障害者にしたのもいい。社会問題の場面では自然に被害者側の立場になる。
他の登場人物も魅力的で複雑なキャラクターである。単なる善人や単なる悪人というのは登場しない。それぞれの思惑が交錯して、主人公の行動を邪魔したり助けたりする。淡々とした描写もハードボイルドタッチである。BGMは当然ジャズだ。
息もつかせぬというほどではなく、適度にゆるいシーンもあるが、登場人物の人となりを紹介するのに必要なシーンでもあったと思う。緊迫のシーンと交互に見せることで観客の集中力を持続させる高等技術なのかもしれない。
それにしてもランドルフ兄弟が中川家に見えて仕方がなかったのは当方だけだろうか。
まったりとしたサスペンス
久々に映画らしい映画を見た!
入り口は音楽だったけれど、見応え強し
予告も観てなくてストーリーも全く 知らない状態でしたが エドワ...
予告も観てなくてストーリーも全く
知らない状態でしたが
エドワード・ノートンの監督作品なので
鑑賞が楽しみだった作品。
序盤は、エドワード・ノートン扮する、
主人公のライオネルのキャラの独特さと、セリフの多さに馴染めず、
エドワード・ノートンは凄く頭の切れる人というイメージがあり
その彼が脚本、製作も兼ねてるのだから
凄く複雑な作品で理解できる内容なのか
ちょっと不安に……。
主人公ライオネルはトゥレット症候群≒チック症なんですが、記憶力がとにかく凄い。
この2つの特徴を活かしながらどんどんとストーリーが展開してゆくのですが、
ライオネルと登場人物の関わり合いの
描き方がとても上手い。
ともすればマイナスなイメージに
なるかもしれない症状を語弊があるかもしれませんが、笑いに変えてしまう。
そのセリフは心の声となっていて観てる側をもほっこりさせてくれる。
おっぱい発言も全く嫌みがないんすよね。
知らず知らずのうちに序盤に感じていた
不安感は消えていて作品にのめりこんでしまう。
誰も信じられなくなって、
誰もが怪しく思えてしまうから不思議。
そこは脚本の良さかもしれません。
まぁそれでも登場人物の名前と関係がわからなくなりかけましたが…(笑)
この作品は音楽も良かった。
哀愁漂うトランペットの調べが
ライオネルや登場人物の哀しみを代弁しているかのようで。。
1950年代のニューヨークのハーレムにトリップさせてくれるJazzがこんなにも心に染みるなんて。
そしてエンドクレジットにトム・ヨークの名前がありビックリ!
どうやら、1曲だけサントラで曲を
提供していたみたいです👀
152分の長さのある作品ですけど
出演している役者さんも
皆さん素晴らしい演技でしたし
哀しみも温かみも感じられる内容で
鑑賞して良かった。
続編を作って欲しいなぁ。
上映館が少ないのはちょっと勿体ないくらいの良作ですね。
変化球のハードボイルド
発達障害を抱えた探偵を描いたハードボイルド。原作は未読。
記憶力や思考能力は高いがチック症のある主人公。奇声を上げたり、余計なことを言ってしまう症状はどうしても笑いを誘うシーンになりがちだ。原作がそうなのかもしれないが、この設定はいるのかな?と疑問に感じてしまった。
話としては上司であり友人でもあるフランクが殺された事件を追うというもの。設定の場所と時代がとてもいい。ドジャースがLAに移る前の話。色々と開発していこうとする話が絡んでいく。サスペンスとしてきちんとしていた。ただ全体的に渋い。渋すぎる。こんなハードボイルドが好きと思える人じゃないと途中は厳しいんじゃないかなと思う。眠気が襲ってきたのも確か。
それぞれが求めたもの
権力の沼
鋭い洞察力と推理力、及び、驚異的な記憶力を持つチックを抱えた探偵通称ブルックリンが、ボスであり恩人であり友人であるフランクが殺されることになった事件を追う話。
何を調べているのかを知らされないまま、目の前で銃撃されて死亡したボス。
ボスの死の真相を知る為に、復讐の為に、ボスの残した断片的なヒントを頼りにとNYの闇に触れて行くストーリー。
最初は頼りなさ気な主人公が身分を隠し調べあげていくけれど、かなりデカい話になっていって見応えたっぷりだし、主人公がどんどんイケメンに見えてくる。
鑑賞している側も、いったい何がと推理しながら見られる展開で、一部何故早くそこに気がつかないかなー?というものもあったけど、素晴らしいサスペンスだった。
ちょっとしか出てこないけど、スカーフェイスのラッパ吹きも痺れる渋さだった。
ハードボイルド
全50件中、21~40件目を表示