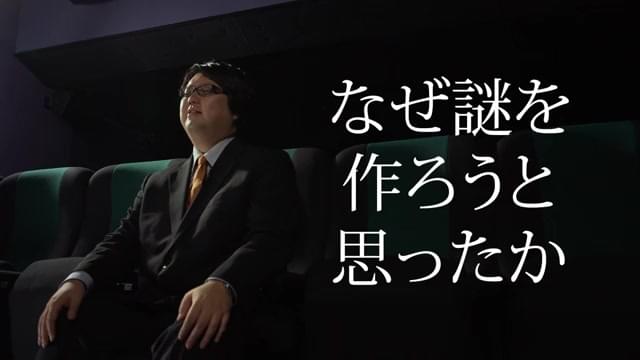9人の翻訳家 囚われたベストセラーのレビュー・感想・評価
全156件中、121~140件目を表示
迷っているなら断然コチラ!
名探偵と刃の館と どちらを観ようか迷っているならコチラが断然オススメです
好みにもよるんでしょうけど アチラは作り物の謎解きで コチラは血のかよった人が出ている謎解きです
アチラ星3つにしましたけど この星半分の差はけっこう大きいです
まぁ結局は好き嫌いの問題なんですけど
関心はするが、感動には至らない
知人がやたら推していたので見てきました。
前半がとにかく退屈でしたが、中盤からはそれなりに楽しめました
しかし最後まで見て、満足感が残ったかと言えば、そうでもなく。
いえね、ミステリーとしてよく考えられていると思います。
本編でもちらっと出てくるように、アガサ・クリスティー的でもあるし
前半の退屈さが後半で覆されるのは「カメラを止めるな」を想起させます。
2転3転する終盤の展開、言葉のレトリックのみで相手を破滅へと追い込んで行く手法などは、西尾維新の戯言シリーズ(「クビキリサイクル」「クビシメロマンチスト」等)を思い出しましたよ。いや、うまいです・・ほんと。
ただ・・「で?・・それで?」ていう感じなんですよね。
「ミステリーのいいアイディア考えついちゃった」と言う以上のもの・・言い換えれば、映画的魅力を本作からは感じなかったんですよね。シナリオで勝負するなら、序盤から謎とフックを散りばめて牽引するべきだし、後半のちゃぶ台返しで前半の退屈さの帳尻合わせをするなら、せめて登場人物たちのキャラクターで牽引したいところですが、どうにもキャラが弱い。9人の翻訳家も、彼らを集めた社長も、ちょっと魅力に乏しいなと感じました。
過度な期待をしなければ、見る価値は間違いなくあります。
2回見たら評価がまた変わりそうな映画ですが、2度みたいという気にならなかった時点で、わたしには合わなかったのだろう・・という事でこの点数でご勘弁を
タイトルなし
ミステリー作品なので何かは起きる
だろうとは思ってましたが
ぐぐぐぐっとのめり込ませてくれる
なかなか面白い作品でした。
世界的ベストセラー小説「デダリュス」
このミステリー小説を各言語に
翻訳するため9ヵ国から翻訳家が
集められるんですが、
翻訳を行うのに隔離され、
制約もあるっていうこの設定が面白かった。
観た後で知りましたけど、
「ダ・ヴィンチコード」で有名な
シリーズ小説の4作品目の翻訳の際に
各国の翻訳家を地下室に隔離して
翻訳をさせたっていう
事実をベースにした設定なんだそう。
出版前に内容が流出したら、
売上に打撃があるでしょうし
出版元としては色々大変なんですね~
まぁそんな状況下でお話しは
進む訳ですけど、これ本当に面白い
作品なのかなぁ?なぁんて思った
部分も正直あったんですが、
ミステリー性が展開しスリラーな部分も
含んで加速度的に進むあたりがどんどん
面白くなって目を離せなくなりました。
9人の翻訳家っていう位なので
様々な言語が入り乱れるシーンは
ドキドキ感とスピード感があって
見応えありました~。
知らない役者さんが多かったですが
「テリーギリアムのドンキホーテ」にも
出演していたオルガ・キュリレンコさん、本作でも美しかったです😍
楽しい終末世界へ。
質の良い推理小説を読んでいる時の感覚、あの快感を味わえる映画作品だった。
小説を書く者、翻訳する者、小説を売る者、登場人物の全員が本に関わり、物語の全てが本に関わっている。
読書が好きで好きでたまらなかったあの頃を思い出しながら観ていた。
ミステリーっていいな、と再確認。
「誰が、なぜ、どうやったのか」「一体何のために、何をしたのか」を少しずつ推し図りながら読み解いて鑑賞する楽しさと刺激。
私の考えなど簡単に外れ、物語が遥かに越えてくれる喜び。予想外の展開、ひっくり返る思考。
奥深い真実が示された時のどうしようもない切なさ。
美しく構成と鋭いストーリーの前にひれ伏すしかない。
文学への愛と執着、人間への愛と執着。
曲者キャラが揃う中、「原稿の流出」という事件はなんだか地味に感じてしまい、最初はローテンションだった。
しかし、「種明かし」が幾つも連なるごとに驚愕のテンションが重なり、後半はもう高まる一方。
行ったり来たりする舞台と時間の演出もお見事。
洒落にならない悲劇も起きていくけれど、振り返るとロマンに溢れた物語でもある。
謎に包まれた著者に会いたいと、最新作を一早く読みたいと、を素直に吐露した彼女。
アニシノバの狂信的で純粋なファン心理は非常に人間らしくて良い。
しかし「デダリュス」の表紙がかなりダサいのがずっと気になった。
もう少し品があってスタイリッシュなデザインにすればいいのに…と、本が映るたびに思ってしまう。
大学で研究されるほどのベストセラーなら尚更。
存在しない小説だとは知りつつ、デダリュスを読んでみたい気持ちは抑えられない。暗証番号は覚えた。
しっかりしたミステリー
ノレず…
もう一度観たくなる!芸術的で上質なミステリー
好みでした!
翻訳する人は複数の言語がそれなりにできるので、皆がそれぞれ色んな言語で言葉をかけあう場面にしびれました。その中で、フランス語しかできない彼が「フランス語話せ!」と言う箇所に、フランス語中心主義者め~!と思いました。が、この映画はフランス語だからこそと思います。
イギリスの作家デュ・モーリアの小説『レベッカ』は、映画(ヒッチコック)やミュージカル(ウィーン・ミュージカル)にもなっています。その作品がこの映画で意識されているのかは、私はわかりません。一方、彼らが翻訳する小説中の人物、レベッカは何度も言及されていました。デュ・モーリアのレベッカも、白いドレスを着ていて、水中での死を選んでいます。私の「レベッカ」愛ゆえ、プール=水の場面も気に入りました。だから、頭の中で色んな世界が混淆してあっちこっちに行けました。
リッカルドが翻訳家の役?と思いましたが、それなりに…。イタリア人、からかわれてちょっと可哀想だった。いいキャラクターの翻訳家が沢山いたので、彼らをもっと深く描いて欲しかったのは事実です。でも、見てよかった映画でした!
苦手なミステリーもの…
自分のものは、自分で守れ。
ミステリーとしてはちょい弱、でも…
『ダ・ヴィンチ・コード』、『インフェルノ』のどちらも未観賞だけど全く問題ナシ!
ミステリーの内容的には殆ど予想の範囲内だったのでそんなに目新しさは無いかと。事件が起きた経緯も至って普通、というか陳腐な理由。登場人物についてもちょっと無駄遣いしてるなー、と感じる部分があり、もぉ少し上手く活かしてくれたらより楽しめたのになと思う。
それでも自分の中での佳作となる3.5点以上を付けたのは過去の経験上フランス映画は大概睡魔に屈する場面があるのにこの映画では辛うじて睡魔に打ち勝てたから。なんだかんだストーリーと演者さん達に引き込まれていた自分が居たので良し♫
それにしても、世界9カ国同時翻訳ってなった時に日本語はギリシャ語に敵わないのが悲しかった^^;
密室劇なのかな?
うーん
ミステリーとしてそれなりに面白い
世界的なベストセラーの完結編の9ヶ国翻訳版を同時出版するために集められた翻訳家9人。地下に監禁された状態での翻訳活動だったが、完結編の冒頭10ページがネットに流出してしまった。誰が犯人なのか、そして厳しく監視されている中どうやって流出させたのか。
誰がやったのか、どうやったのか、そして犯行の目的は?3つの段階で真相が明らかになっていく脚本はなかなかよくできていた。ただ、過去と現在と未来、場面が3種類あるのだが、その切り替わりがわかりづらいときがあって戸惑ってしまった。
全体的には楽しめるミステリーにはなっていると思う。
ただ映画にするにはやや物足りない。舞台にすればもっと面白くなるかもと想像してみた。
面白かった!
全156件中、121~140件目を表示