赤い闇 スターリンの冷たい大地で
劇場公開日:2020年8月14日
- 予告編を見る
- U-NEXTで
本編を見るPR

解説・あらすじ
「太陽と月に背いて」「ソハの地下水道」で知られるポーランドのアグニェシュカ・ホランド監督が、スターリン体制のソ連という大国にひとり立ち向かったジャーナリストの実話をもとにした歴史ドラマ。1933年、ヒトラーへの取材経験を持つ若き英国人記者ガレス・ジョーンズは、世界中で恐慌の嵐が吹き荒れる中、ソビエト連邦だけがなぜ繁栄を続けているのか、疑問を抱いていた。ジョーンズはその謎を解くため、単身モスクワを訪れ、外国人記者を監視する当局の目をかいくぐり、疑問の答えが隠されているウクライナ行きの汽車に乗り込む。しかし、凍てつくウクライナの地でジョーンズが目にしたのは、想像を超えた悪夢としか形容できない光景だった。ジョーンズ役をドラマ「グランチェスター 牧師探偵シドニー・チェンバース」のジェームズ・ノートンが演じるほか、「ワイルド・スピード スーパーコンボ」のバネッサ・カービー、「ニュースの天才」のピーター・サースガードが顔をそろえる。2019年・第69回ベルリン国際映画祭コンペティション部門出品作品。
2019年製作/118分/PG12/ポーランド・イギリス・ウクライナ合作
原題または英題:Mr. Jones
配給:ハピネット
劇場公開日:2020年8月14日
スタッフ・キャスト
- 監督
- アグニエシュカ・ホランド
- 製作
- スタニスワフ・ジェジッチ
- アンドレア・ハウパ
- クラウディア・シュミエヤ
- 脚本
- アンドレア・ハウパ
- 撮影
- トマシュ・ナウミュク
- 美術
- グジェゴジュ・ピョントコフスキ
- 編集
- ミハウ・チャルネツキ
- 音楽
- アントニー・ラザルキービッツ
受賞歴
第69回 ベルリン国際映画祭(2019年)
出品
| コンペティション部門 出品作品 | アグニエシュカ・ホランド |
|---|










 いつかの君にもわかること
いつかの君にもわかること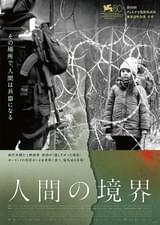 人間の境界
人間の境界 秘密の花園
秘密の花園 ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド ミッション:インポッシブル/フォールアウト
ミッション:インポッシブル/フォールアウト この世界の片隅に
この世界の片隅に





































