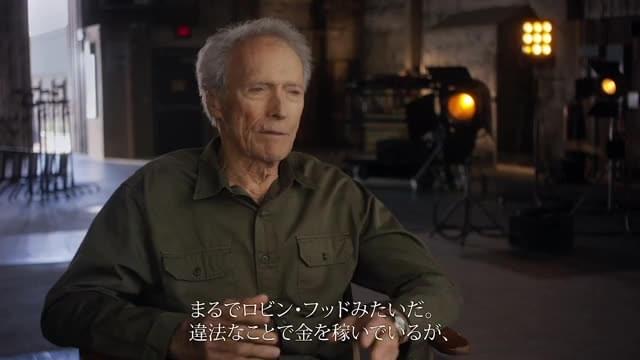運び屋 : 映画評論・批評
2019年3月5日更新
2019年3月8日より丸の内ピカデリーほかにてロードショー
強い米国の体現者イーストウッドの回顧と贖罪を忍ばせた、技あり脚本
クリント・イーストウッドが監督と主演を兼ねたのは、2008年の「グラン・トリノ」が最後だった。孤独で偏屈な退役軍人と移民の少年との風変わりな交流を描いた同作で、脚本家デビューしたのがニック・シェンクだ。フォードの工場で働いた経験もある苦労人シェンクの脚本を尊重し、ロケの都合で舞台を移した以外は一言一句変えなかったイーストウッドが、80代も半ばを過ぎて「運び屋」で監督兼主演の重労働に復帰したのには、信頼するシェンクの参加が決まっていたことも大きかっただろう。本作の主人公アールは実在の人物に基づくが、演じるイーストウッド自身の人生にも重なるキャラクター造形がなされている。
第二次大戦に従軍した退役軍人が、デイリリー(ユリ科の植物)の栽培でいったん成功するも時代の変化に取り残され没落、80過ぎでメキシコの麻薬カルテルから運び屋としてスカウトされる――という大筋はほぼ実話。シェンクはそこに、外面はいいものの家族を顧みず見放された男が、懸命に罪滅ぼしをして元妻や娘との絆を取り戻そうとするサイドストーリーを織り込んだ。30近くで人気スターになったイーストウッドは派手な私生活を送り、結婚歴は2回だが6人の女性との間に8人の子がいるとされる。最初の妻との間に生まれた実子アリソン・イーストウッドが本作でアールの娘アイリスを演じていて、父親に対する彼女の冷ややかで激しい態度には映画と現実の境界を歪ませるようなすごみがあるし、イーストウッドも作品を通じて家族への謝意を示しているように見える。

家族関係の失敗を償うかのように、運び屋稼業に関わるメキシコ人の若者に対し父親のように接して、真っ当に生きるよう諭すくだりは、「グラン・トリノ」におけるモン族の少年との関係性を反復する。モン族がベトナム戦争の影響で故郷を逃れてきたように、米国に暮らす少数民族の多くは、アメリカという大国が内外で正義と力を振りかざしてきた“副産物”として、かの地でマイノリティーとして生きざるを得なくなった。かつて無頼のガンマンとして、また「ダーティハリー」シリーズの暴力刑事として、世界の警察国家たるアメリカを体現したイーストウッドが、老いてそうした少数民族に手を差し伸べるとき、成熟した大国の反省と贖罪の意識もそこに重なってくる。
高齢の運び屋の実録を物語のエンジンとしながらも、イーストウッド個人とアメリカの回顧と贖罪をも積み込んで観客に届ける点が、脚本家シェンクの鮮やかな仕事ぶりと言えるだろう。
(高森郁哉)