パパが戦場に行った日
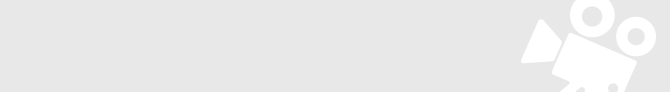
解説・あらすじ
「国連UNHCR難民映画祭2018」(18年9月7日~10月7日)上映作品。
2016年製作/90分/オランダ
原題または英題:Toen mijn vader een struik werd
スタッフ・キャスト
- 監督
- ニコル・バン・キルスドンク
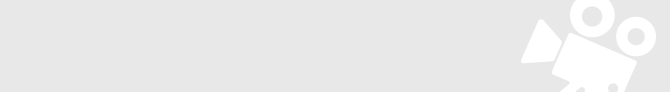
「国連UNHCR難民映画祭2018」(18年9月7日~10月7日)上映作品。
2016年製作/90分/オランダ
原題または英題:Toen mijn vader een struik werd
UNHCR難民映画祭2018にて鑑賞。
UNHCR難民映画祭2018のパンフレットより、以下転載。
「平和な日々の中でパン屋を営んでいた父娘に起きた物語。ある日紛争が勃発し、父娘は娘のトーダを祖母に託して兵士として戦地へ向かった。日に日に激化する戦闘。祖母はトーダの命を守るため、母親の住む隣国へ避難させる。母親を訪ねてたった一人の避難の旅。戦闘の光景を目の当たりにしながら、トーダは数々の試練を乗り越えてゆく。10歳の少女の目に大人たちの戦いはどう映ったのか―。紛争や迫害によって避難を余儀なくされる人々が急増する今、そこにある恐怖と苦悩を日本で暮らす私たちがどれだけ想像できるのか問いかけられている」
上記の作品解説って、UNHCR風にちょっとゆがめられているかな?
映画は、戦闘が激化して、娘トーダの身の安全を心配した祖母によって、別居して戦闘のない国に住んでいるトーダの実母の下へ送り届けてもらえるよう”他人”に託されたトーダの旅行記。
この手の物語によくあるように、簡単には母の下へ着かない。トーダの好奇心で待つと指示された場所からちょっと動いてしまって、置き去りにされることも含めて、アクシデント続き。”戦闘””難民”にまつわるさまざまな出来事をトーダが経験するが、トーダ自身が、「このように見えた」という感想を映画の中で述べることはない。トーダがはっきりと自分の気持ち・考えを言わないから、見る側の”想像”力が問われているのだと言われれば、確かにそうなんだけれど。
でも、戦争を起こすのは、その戦争をしている”大人”。この映画では戦争している理由にはふられていない。難民となっている悲劇よりも、難民を作り出さないことの方が大切だと思っているから、UNHCRの解説が陳腐に見えてしまう。
日本語の題名は『パパが戦場に行った日』だけれど、
英語の題名は『The Day My Father Became a Bush』
オランダ制作のオランダ語題名は『Toen mijn vader een struk werd』
予告にもちょっとだけ流れているが、ブッシュをヘルメットにたくさんつけて身を隠す方法を、父娘・祖母でいろいろと工夫している場面があり、トーダの願いがいっぱい詰まっている場面。
トーダの旅の途中で出会う、元将軍や兵士とのやりとり・顛末と併せて観れば、監督の言いたいところはこの題名に集約されているんじゃないかと思う。
トーダの言葉で印象に残っているもう一つは、「国境超えなんていうけれど、国境なんて線はなかった(思い出し引用)」という言葉。
漁業圏等、利権が絡むから、簡単に言えない。けれど、北方4島だって、元居た土地に住めて、お墓参りが自由にできれば、そこが日本だろうかロシアだろうか、住民には関係ないのじゃないかなんて、東京の空からは思ってしまう。アフリカやクルドの民が迷惑をこうむっているけれど、”国境”なんて、かってに当時の政治家が”利権”のためにひいた境界線だものなあ、なんてことを思い出してしまった。
”映画”としてはもう一歩。「子どもが戦争の犠牲になる」という思いを掻き立てられる名作はたくさんあるので。
でも、戦闘について考える一助にはなるかもしれない。
『アレッポ 最後の男たち』と併せて観ると良い。