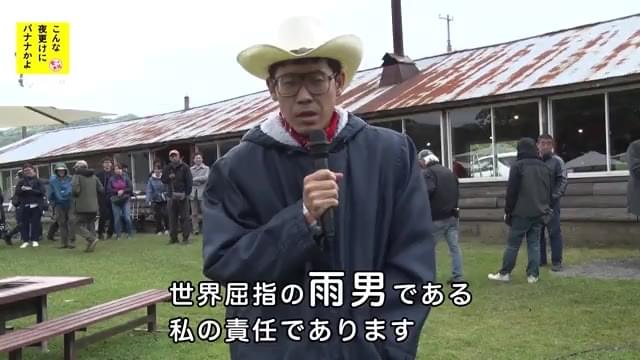こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話のレビュー・感想・評価
全331件中、221~240件目を表示
可もなく不可もなく
チョコポップコーン片手に一人鑑賞しましたが、どうにもお連れの方がいる人にとっては気恥ずかしくなる場面が少々見られました。
思っていたよりか恋愛色が強かったのが印象です。
また、実話である以上これはどうしようもないですが、登場人物の鹿野が頻繁に倒れたので、張り合いがなく、いまいち盛り上がりにかけました。どうせまた助かるんだろ、と。
ただ、映画としてはやはり流石の大泉といったところで、まるで本人が憑依しているかのようでした。
最後に余談ですが、途中のカップル間の関係がよじれるシーンでは、空気感がリアルすぎて端からカップルを指加えて眺めているぼくは手ぇたたいて喜びました
正直に生きることの大切さ
これは楽しかった〜
時に笑い、時には泣いて、主人公の鹿野さんから、自分に正直に生きることの大切さを教えられた作品だった
この作品では、筋ジストロフィーを患っている鹿野さん(大泉洋)と、彼を介助しているボランティアの人たちとの交流が描かれている
彼は、一人暮らしをしているが、ボランティアの介助なしでは、生活をしていくことができない
医学生の田中(三浦春馬)は鹿野さんの介助をしているボランティアの一人
田中を訪ねてきたガールフレンドの美咲(高畑充希)は、鹿野さんに気に入られ、美咲もボランティアの一員になっていく
そんな鹿野さんと美咲の交流を中心に、この物語は進んでいく
この鹿野さんが、とっても困った人で
タイトルにもある通り、夜中の2時に「バナナ食いたい。買ってきて」とか言ってしまう人
でも、そんな鹿野さんを観ているうちに、彼のワガママにも慣れてきて、次第に、そんな鹿野さんが、とても魅力的な人だと思うようになる
悪く言えばワガママだけど、よく言えば正直者
鹿野さんは、何でも言いたいこと、やりたいことを言って生活している
それが受け取る人によっては、ワガママに聞こえてしまうのだ
しかし、それぐらい、鹿野さんは、一瞬、一瞬に対して、とても真剣に生きているということなのだ
いつまで生きていられるかわからないから、やりたい時にやりたいことをやり、言いたいことを言う
そんな鹿野さんを観て、正直に生きるって大事だなぁと思った
人は夢がある時、叶えられるかどうかわからないから、なかなか口に出すことができない
でも、夢を正直に口にした瞬間、周りの人も巻き込み、その夢を聞いた人たちが手助けしてくれる
だから、正直に言ってしまった方が夢は叶えやすくなるし、時間も短縮できる
そして、夢に向かって一生懸命な姿は、周りに伝染するのだ
この映画は、そんな夢を見て、それを叶えるために必死に生きている鹿野さんに、周りの人たちが元気づけられる姿が描かれている
もちろん、それを観ている観客も元気づけられる
筋ジストロフィーの患者の話と聞くと、重い話とか、お涙ちょうだいモノだと思うかもしれないが
これはそうではなかった
正直で前向きに生きる鹿野さんから、健常者が元気をもらう作品なのだ
年の初めにこれを観たら
きっと「私もがんばろう!」と思えるに違いないので
凹んでたり、元気がない人にオススメの作品
図々しい人生
筋ジストロフィー患者がボランティアと共に人生を全うする話。
他人のお世話になりながら図々しく生きる。そんなことがあっていいのかと思い見に行ってしまった。
鹿野はなぜわがままに生きれたのか?彼の、周りの人に愛されるわがままは、僕たち健常者がよく想像する煩わしいわがままとなにが違うのか?
彼はわがままさによって、不自由な体のまま自由に生きることを獲得した。なぜなのか。
・ユーモア
彼と一緒にいることは、時にボランティアの労力を上回るほど、楽しいのだ。
・情熱
彼の心は「やりたいこと」で満ち溢れており、ゆるぎない目標を持っている。普段、そこまで強い情熱を抱いて生きることができない僕らは、より強い情熱を持つ人に際し、その他人の持つ情熱の実現のために動くことで、自分のために動くよりも、むしろ充実感ややりがいを感じられるものである。
・本音でぶつかり合える
鹿野は言いたいことをなんでも言う。それどころかボランティアに対してはあくまでも対等なスタンスを取り続けている。常に介助される状態にいながら、貸し借りの一切ない関係を貫くことで、遠慮なく自分の心が望む通りに生きることができる。
他人にわがままを言えるようになることは、確かに自分らしく生きるためのヒントな気がする。でも、現実には僕らがそのように生きるのは、やはりとても難しい。なぜなのか。
・本音と気遣いの両立
鹿野とボランティアの関係は、ボランティア自身が心から支えたいと思わねば成り立たない。そのためには、遠慮のない関係を築くため本音でぶつかると同時に、相手に好かれなければならない。本音をさらけ出すと同時に、周りの人間が自分のもとから離れていかないような言葉遣いや態度を持ち続けないといけないのだ。
・気持ちを曝け出すことの難しさ
僕らはついつい感情を押し殺してしまう。田中はデートの約束があったのに、わがままを言う鹿野に対しなにも言えないまましぶしぶ夜まで付き合った。鹿野に向かって、あなたの介助よりデートに行きたい、と本音はやっぱり言えないものだ。
・情熱的に生きることの難しさ
鹿野の病状は深刻である。きっと彼も怖くてたまらないに違いない。それでも、絶望的な気持ちを外に出してしまうと、忽ち対等な関係は崩れてしまうし、人を引き付ける強い情熱に影が差してしまう。これは僕たち健常者でも同じ。かつては常に高い目標を掲げ毎日情熱的に生きていた人でも、挫折を何度か味わったり、身の回りの出来事に対する感動がだんだんと薄まったり、目の前の仕事に追われて自分が本当にやりたいと思っていたことに意識を向けられなくなったりする。自分は情熱を持っていると堂々と言える人生を送ることの、いかに難しいことか。
わがままによって我が道を生きた鹿野に憧れる。でも現実に立ち返ってみると、やはり鹿野のように生きるのはとても難しい感じがしてしまう。それじゃあ僕らはどう生きるべきなのか。
・自立とは、「他人に迷惑をかけないこと」ではなく「自分が思うように生きること」である
僕たちはよく「人に迷惑をかけてはいけません」と教わって大人になってきた。でも、自分が幸せに生きることができる「自立」は、そうではなかった。
・与えられる人間になる
自分が思うように生きるためには、人から与えられることを厭う必要はないのだ。でも、人から与えられる人間になるには、人に与えられる人間になる必要があるのだ。鹿野にとってそれが、ユーモアであり情熱であり人生観であった。そして人に与えることは、自分にとっても幸せなことなのだ。
・自分の思いを大切にする
社会のしがらみの中で生きる僕たちは、自分が本当にやりたいと思っていたことがなんだったかを自覚することこそが、実は一番難しい。でも難しく考える必要はないのかもしれない。バナナ食べたい、アメリカに行きたい、デートしたい、みたいな普段ふっと思い浮かんでは消える色々なことに対して、物怖じせず口にでき、それに向けた行動を取れるかどうかではないだろうか。
おわりに
何事もとかく難しく考えてしまうけれども、今回も映画館の中では楽しく見れたのでよかった。
全くの健康体で大学院まで行って一部上場企業に勤める僕より筋ジストロフィー患者の方が幸せな生涯を送っている気がしたのはいかがなものか。
でも、それはちっとも不思議なことではないのだ。「キスしてほしい」で盛り上がれて、周りに与え与えられる人がいれば、人は例外なく幸せになれるのだ。きっと
こういう人に出会ったことある
大泉さんベストなキャスティングな気がします。
一見すると本当にわがままで、端からみると腹が立つ感じ。
でもなんか、この人のパワーに巻き込まれていっちゃう感じ。
そしてどんどん惹かれていく感じ。
弱っていくなんてとんでもない。
最期の直前まで命が燃え盛っていたんだろうなと。
原作があり、且つ実話に基づいてるなんていったら、二時間で描ききることは本当にもう至難の技なんだろうなと思う。
ここ半年で原作ありのヒューマンドラマ系を他に2本観たけど、一番良くできていると感じた。
ただ、回想シーンはまったく好みではなかった。
最後の両親のシーンもあんまり響かなかった。
その前に描ききれているから、観る側が読め切れるかわからなくても、大泉さんに読ませず手紙だけ何秒か写せばいいのにと思った。
主題歌目当てでいきました
タイトルの通りです。
ただキャストも良かったので、それもあって観たのもあるんですけど、微妙。
ここの場面はもう少し後半でもよかったのでは?と思うシーンが序盤で来るので、後半がグダグダしてるというか、緊張感もなくなんの面白みもない感じ。
大泉洋さんが役のために減量した点は天晴れですが、最後のシーンもあっけないというか、病と闘いながらも心は自由だった人の生涯を描いてる割にはテーマの重みが感じられず残念でした。
3人の主人公
違和感が、、
重病ものの実話だからもう頭痛くなる位泣けるんだろうとめちゃ期待したけど、期待を裏切り全く泣けない。
重病ものなのに明るく笑えて斬新なのだが、何故だろうか?どんどん病状が進んで行ってるはずの主人公が最初も最後も何も変わりがないように見えるこの違和感。
声帯切って人工呼吸器をつけながら、がんばって声を出せるようになった人
が喋ってる感がない違和感。
途中からその違和感と登場人物のドラマが薄いせいで映画に入り込めなくて退屈でまだ終わらないのかと、時計を見て1時間半過ぎあたりで20分ほど寝落ち。
もしかしてその20分とてつもない感動があったのか?
ちゃんと見ていた一時間半までは登場人物達のドラマの描き方が薄〜く感じたけど、寝てしまった時間にきっと丁寧なドラマがあったんだと思っておきましょう。
しかし最後まで車椅子に座っているちょっと元気ない大泉洋にしか見えなかったせいで全然話に入り込めなかったなー。
やはり私には大泉洋は向いてないようだ。
ごめんなさい。
役者良し、ロケ良し
昔の病院あるある
大泉洋が素晴らしかった
☆☆☆☆ 予告編を先に見て、次に原作を読んでいるからこそ合点がいく...
☆☆☆☆
予告編を先に見て、次に原作を読んでいるからこそ合点がいくのだが。原作だけ読んだのならば、「一体これが映画になるのか?」…と、思ってしまう事だろう。
ノベライズ版にて、数多く登場するボランティア達を。美咲と田中というカップルの目線から、鹿野という人物像を描く方法に切り替えた事で。読んでいても「あゝ!そう来たか!」…との思いを強く持った。
その要因として大きく感じたのが、主人公の鹿野を大泉洋が演じるという事。
この稀代の、弄られ・僻み・毒舌俳優が演じる事で。原作を読んだイメージ通りの鹿野像が、そっくりそのままスクリーンに映り込んでいるのだから。
そして、原作では数多くのボランティア達が登場するのだが。その中でも、鹿野との交流で印象深いボランティア男女の何人かをピックアップし。それを映画の中の、美咲と田中の性格に振り分けていた。
これで、原作だけだと単なる障害者を扱ったお涙映画になりそうなところが。若い2人の恋愛映画でもあり。鹿野を中心とした家族映画としても成立して来る。必ずしも傑作とは行かずとも、悪い作品にはならないだろう…との予想はついた。
それにしても、この主人公で障害者である鹿野は。その言動から、多くのボランティアを始めとする人達に数多くの毒舌を平気で吐くなど、実に強烈なキャラクターだ!
以前に私は、別の映画のレビューにてこう記した事がありました。
(※もしも人間1人1人に生きて行く人生の中で、我が儘を言える回数が決められていたとしたら…。
果たして使い切った方が得なのかどうか?
その結果として、最後に道端で野垂れ死んで行ったとしたら、その人の人生は悲しい最期だったのか?は解らない。
ひょっとしたら、多くの人に囲まれた幸せな最後であっても、死ぬまで我が儘を言わなかった事は、人生に於いて得だったのかどうか?…それも解らない。
全ては、神のみぞ知るところでしょう。※)
(『◯◯◯旅』のレビューより)
原作を読んだ時に思い出したレビューの様に。何故に鹿野はそこまで自我を剥き出しにし、毒舌や我が儘を言い続ける事が出来たのか?…を、原作を読んだ直後に考えさせられた。
鹿野のワガママに対しての最古参の鹿野ボランティアの言葉。
★「とらやにとって、寅さんというのはやっぱり〝ワガママなヤツ〟なんですよ。でも、みんなそのワガママに、ふと人生を感じちゃうというね…。逆にあのキャラクターが変わってしまったら、シカノさんの面白味の半分はなくなっちやうような気がするんだけど」
「もう1つ言うと、障害を抜きにすると、シカノさんのキャラクターもなくなっちゃうから難しいんですよね。障害がなきゃ、今のシカノさんじゃないだろうし、こういう言い方は語弊があるかもしれないけど、『障害あってのシカノさん』というところがありますからね」(★原作より転載)
↑この言葉を始めとして、原作の第6章「介助する女性たち」には。鹿野という人の人物像及び、何故に多くの人達が、彼の為に多くの時間を割いてまで尽力したのか?が説明されている。
彼は、ただ単に毒舌や我が儘を言い続けた訳ではなく。身動きが取れない自身の身体を受け止め、周りのボランティアの人達の、人となりを細かく観察し。自身での唯一の武器となる口からの言葉による手練手管を駆使しては【生き続ける】道を選択したのだった。
更に、同じく第6章には。社会で【健常者】と【障害者】が《共存》していく為の、意識の問題点と共に。双方が、今後に向けての【対話】と、立場の【対等】とゆう意識の変化が大事だと提示している。↓
★さらに社会的な場で「障害者」や「福祉」について語られる際に、つねに問題となってくることに、これまでも何度か挙げてきた「障害者の聖化」という問題がある。
健常者は、もっともっと障害者の痛みを知らなければならない。彼らはこれだけ大きなハンディを背負っているにもかかわらず、こんなに頑張って生きているのだから。悪いのは社会や健常者の側の不理解であり、彼ら自身はつねに正しい存在であるー
〜略〜
摩擦や対立は、なければないに越したことはないし、障害者と健常者がいつも穏やかに和気あいあいと過ごせるものなら、それに越したことはないのだが、「違うもの」どうしがつき合ってゆく場において、摩擦や対立は避けられないし、避けるべきものでもないという現実をもっとよく知るべきなのだろう。
〜略〜
「共に生きる」とは、つまりは、摩擦や対立を当然のごとく含み込んだ上での、「対話」を重視した双方向的な関係に他ならない。
それが「対等」ということの意味でもあるのだろう。
〜略〜
日本で障害者の自立生活や在宅福祉が立ち遅れているのは、なにも差別や偏見が根強いからではなく、むしろ相手に遠慮ばかりして、なかなか本音を語り合わない国民性、摩擦や対立を「対話」で乗り越えることに慣れていない、日本の風土とこそ関係があるのではないかと私は思うようになっている。(★原作より転載)
時には相手に不快な言葉を吐きつつも、直ぐにその相手に対して本音でぶつかって来る男。その思いを強く受け止めるボランティアの人達。
脚本に於いて、それを象徴する存在としての人物像が。おそらく美咲と田中の性格と行動で、表しているのだろうと思う。
初対面の時に美咲は、何の悪気も無しに「何様?」と本音で鹿野にぶつかって行く。
一方田中の方は、鹿野に対してなかなか本音でぶつかる事が出来ない。
全ての人がそうなる様に…とは必ずしも主張はしていないのだろうが。その様な〝対等〟な立場で【健常者】と【障害者】が向き合う社会で有って欲しいと願っての原作で有り、映画化でも有るのだろう。
ノベライズ版に於いて、最後に原作者は。鹿野本人が生きて来た人生で。彼が身を粉にして周りのボランティア達を始めとして、伝えて来た意味を語っている。↓
★それまで自立というのは、他人の助けを借りずに、自分で何でもできること(身辺自分という)、あるいは、自分で収入を得て自分で生きていくこと(経済的自立という)を意味していた。
しかし、そうではなく、自立というのは、自分でものごとを選択し、自分の人生をどうしたいかを自分で決めること(自己選択・自己決定という)、そのために他人や社会に堂々と助けを求めることである。そして、どんなに障害があっても、他人の助けを借りながら「自立」して暮らせる社会は、どんな人にとっても安心して生きられる社会のはずであるー。(★ノベライズ版の原作者あとがきを転載)
新年早々から良い映画が観られて本当に良かった。
サブタイトルに〝愛しき実話〟と付きつつも、肝心要なカップルの2人は。何人かのボランティアの人達を併せた、映画オリジナルによる人物像だったりするのだが。そんな事は映画製作に於いての批判にはあたらないだろうと思える。
何よりも高畑充希が最高に素晴らしかった!
出来る事ならおじさんにも触らせて欲しい(-.-;)ヽ(`ω´ )o
2019年1月5日 TOHOシネマズ市川コルトンプラザ/スクリーン7
正直に生きていきたい
真実は小説より奇なり
ボランティアとは
夢があるって素晴らしい!
前を向き続け、周りを巻き込みながらも
自分の信念を持って夢叶えようとしている人って
やっぱり魅力的に見えるよね♡
ミサキちゃんが恋心とボランティア精神を
錯覚してしまうのも分かる気がする
でも、それ位の愛情が無いと
あの鹿野さんのお世話はムリなのかな
少し前に観た「ブレス」っていう映画を
思い出しました
時代が全然違うけど、
どちらも車椅子で人工呼吸器付けて
自宅療養を希望して...
違うのは、鹿野さんは家族を遠ざけて頼らなかった
お母さんへの思いやり
不器用なやり方だけど、泣けました
大泉洋さん
身体の動きが制限ある分
顔の表情と言葉だけの演技でしたが
とても説得力がありました
三浦春馬さん
不甲斐ない医学生が似合ってましたね
高畑充希ちゃん
自由で開放的な感じが良く合ってました
感動はするけど、後味が良くないんだよね…。
主人公は、すごくバイタリティがあるんだと思う。だけど、皆が皆できないんだよね…。
たぶん。
だから、実話で、すごい!って感動もしたけど、他にもボランティアが必要な人が同じようなことができるの?って、聞かれると大いに疑問だし。
じゃあ、自分もボランティアに参加すれば良いじゃないか?と言われそうだけど、この作品を観て感動した人はボランティアになるのか?と聞かれるとそんな単純なことじゃないよね…。
社会保障が少しでも充実するように、せいぜいきっちり納税しますというのが、関の山か?
そう意味で対岸の火事になっちゃうんだよね…。
だから、ちょっと後味が悪い。もっとも、この主人公にしても同情が欲しい訳でもないんだろうけど…。
泣くよりも深く考えた事。 手助けを受ける側の本心と思える主人公のふ...
泣くよりも深く考えた事。
手助けを受ける側の本心と思える主人公のふるまいに、ボランティアを通して自分がなにをしようとしていたのか?と不甲斐なさ、おごりを再確認してしまう。意気揚々と志高く、自分も何か出来るなんて思っていればなおの事だ。
主人公とボランティアの関係に「人のために」の受け止め方が変わった、それだけで目の前の世界がガラッと変わる感じがした。
お互い立場は同じ。当たり前の事で分かっているのにうっかり抜け落ちる部分、自分を持っていないとグラグラするんだと思う。
そんな事をぐるぐると考えて、まだまだたどり着かない。
主人公も周りの人々も恋愛も歩むべき道も全部ひっくるめて良い描き方だった。
分け隔てなく物事を捉える、頭の片隅に備えて置こう。
全331件中、221~240件目を表示